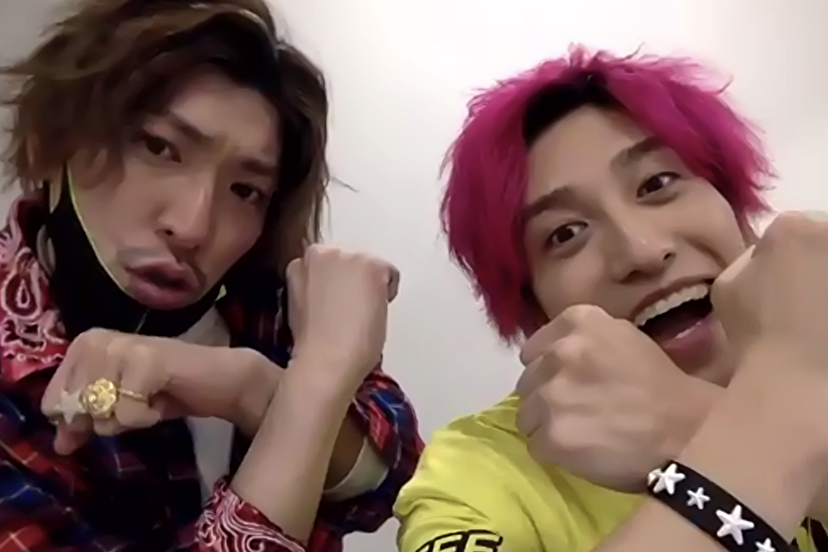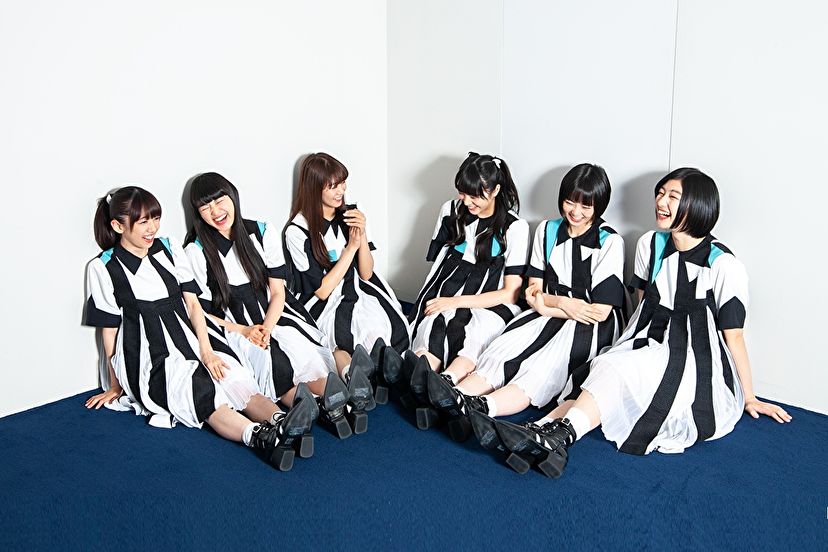言葉を慎重に選びながらも、何かを隠しているのではなく、確かめるようにゆっくりと言葉を繋いでいく。13歳のとき、ハリウッド映画『ラストサムライ』で映画初出演を果たし、26歳にして俳優のキャリアは14年を数える池松壮亮。20代半ばの若者とは思えない落ち着いたたたずまいで、取材中には心地いい緊張感が漂う。
当人も長いキャリアの中で、言葉については考えていた時期があり、「2年前なら、こんなにしゃべらなかった」のだと言う。
最果タヒの40篇以上の詩集を原作に、石井裕也監督が映画化した『夜空はいつでも最高密度の青色だ』に主演する池松。彼自身は、俳優として言葉というものをどうとらえているのだろうか。(取材・文=西森路代/写真=伊藤圭/Yahoo!ニュース 特集編集部)

映画には「言葉にするともったいない」ところがある
石井裕也監督とは、過去に映画『ぼくたちの家族』、『バンクーバーの朝日』、WOWOWのドラマ「エンドロール〜伝説の父〜」でともに仕事をしてきた間柄だ。映画『夜空はいつでも最高密度の青色だ』の始まりも、映画化するという説明もなしに、いきなり石井監督から詩集を手渡され、その2週間後に池松のもとに台本が届いたのだという。

(C)2017「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」製作委員会
「僕が詩集を読んだときはまさか映画化するつもりだったとは知らなかったんですけど、台本を読んだときと詩集を読んだときの感触が同じだったんですね。その上で、石井監督のフィルターを通して、現代社会につっこんだ物語になっていました。詩集を読んだときは、言葉の奥にある気分とかムードに触れることができて、そこが印象に残っています」
過去に一緒にやってきた石井監督と共有しているムードも変化しているのではないか、そのムードや感触とは何だろうと尋ねると、「言葉にすると“もったいない”というか、意味をなくしてしまう気がするけれど、石井監督の作品は、いつも人間賛歌なんです」という言葉が返ってきた。

映画というものに対して、この「言葉にするともったいない感じ」があったからこそ、「20代前半は(映画を)見てもらっただけで言いたいことは伝わると思っていたし、絶対しゃべるもんか」という気持ちが強かったのだという。
自分の語ったことが、人に読まれ、拡散されるうちに、違う何かに変化していき、一人歩きしてしまうことは確かにある。
「自分の発した意味みたいなものが、どんどん形を変えていくことが怖くて、だったらしゃべらないほうがいいと思っていたんです。映画って、言葉じゃないところで勝負しているところがあるので、自分がやったことをあれこれと説明することで作品を補うことは、正直なところ今でも避けたいと思っていますね」
また、一時は、「池松壮亮というキャラクターを作っていた」部分もあったと振り返る。
それが今では「言葉でつかんでいかなきゃ」と思い始めた。
「表に立っている以上は、ちゃんとしゃべらないといけないと思っています。ちゃんとしゃべろうと思ってから、まだ2年くらいしか経ってないので、それで何かが変わったっていう感触はわからないんです。今でも僕の言いたいことは映画の中にしかないと思ってはいるんですけど」

純粋さや誠実さは、社会にとって毒みたいに思われる
だからこそ正直に向き合い、言葉を尽くす。その姿は実直に映るが、それを不器用と受け取っていいのだろうか。『夜空はいつでも最高密度の青色だ』の原作の数十篇にも及ぶ詩では生きづらさを抱える都会で暮らす2人の恋物語を描く。不器用な人ばかりが出てくるが、そんな不器用な人たちと、池松壮亮本人というのは重なるところはあるのだろうか。
「答えになっているかわからないですけど、今の時代、純粋なままで生きるとか、誠実に生きるとかって、難しいじゃないですか。それが社会にとって毒みたいに思われることもある。この映画の主人公ふたりは、皆からは不器用って言われるだろうけど、そういう純粋なところが、まぶしくて仕方なかったです。それに、大げさじゃなくて、僕が演じた慎二という男は、世界一やさしい男だととらえて演じましたね」

対して、慎二が出会うヒロインの美香のことは、「この混沌とした世の中の暗部しか見ることができなくて、幸せになることを怖がっている人」だととらえたそうだ。そんな美香を見て「僕は慎二を通してあの人を救わないといけないと思いました」と語る。あくまでも自分の過去のデータではなく、慎二を演じて感じたことだ。
実際の池松壮亮に関しては、「30手前にして、戦略的にやってきたかというと、やってきてないです。でも、人としてあるべき姿を忘れてしまうと、“ずれ”が出てくるんじゃないかと思いながらやってはきました。僕は“器用”という言葉を悪い意味で使いますけど、僕は慎二や美香よりは器用だと思いますね。もうちょっと、なんとかしようと思うんじゃないですかね」と冷静に分析する。

「色気がある」という言葉は、軽くなった
ネットなどで、年上の女性との共演が多いとか、色気があると言われていることについてはどう思うのか、聞いた。
「僕は映画をパッケージだけで見てはいないので、その奥に潜んでいるものを見て魅力を感じてやってきただけなんです。でも、確かにやりすぎましたね。世間では濡れ場が多いと書かれることもありましたけど、パッケージだけを見れば僕だって多いなって思いますよ(笑)。でも、人がどう判断するのかはもういいかなと思っていて、自分の目の前にある、やるべきことをやっているだけなんです。それは自信をもって言えますね」
「僕が色気を売りにしているかと言ったらまったくそうではないですし、色気っていう言葉も語弊を恐れずにいうと、なんだか、軽くなりましたよね。『色気がある』という言葉は、褒め言葉としてものすごく大きなものとしてとらえてきました。たとえば僕が出会ってきた”映画人”と呼ばれるカッコいい不良のおじいちゃんたち。彼らと比べたら僕が色っぽいなんて、まだまだおこがましいと思ってます」

そんな池松が描く、自分の将来像というものはあるのだろうか。
「このご時世、明日何があるかわからないから、年をとったときのことを考える余裕がないんです。逆に、みんなの今の感覚を知りたいくらい。僕がやっている映画の世界っていうのは、ちょっと現実と距離があると思うんです。明日ごはんを食べるとかそういう切実さからの距離が。そんな中で身勝手にやってはきましたし、こんな僕みたいなのが言うことじゃないかもしれないけど、俳優だからとか俳優じゃないからとかは関係なしに、社会の一員であることを忘れずにやっていきたいなとは思っています」

編集協力:プレスラボ