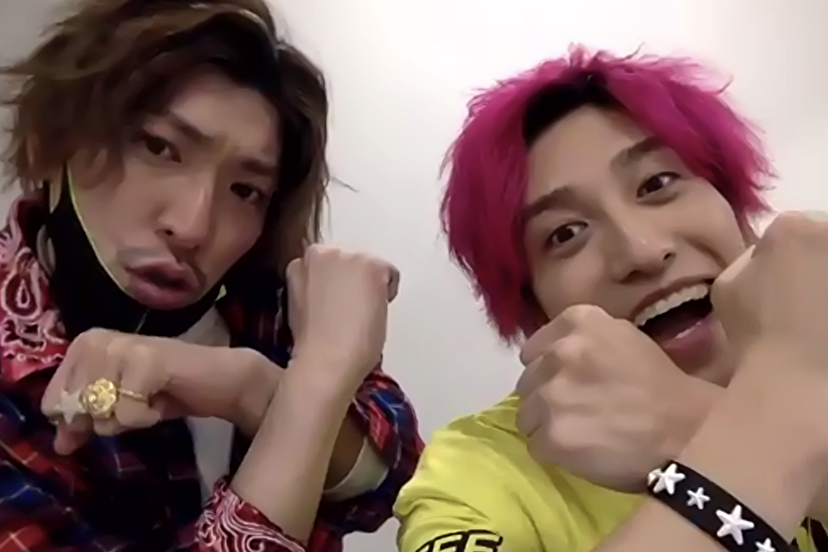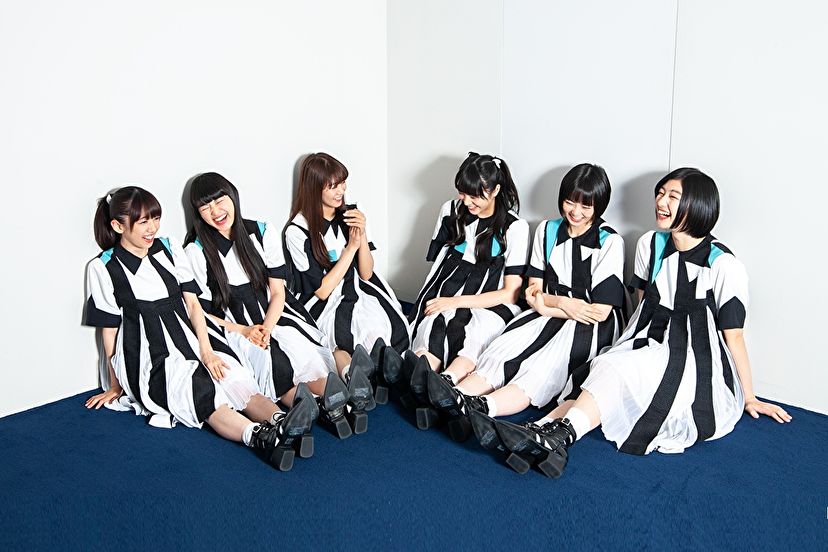「歌姫」という言葉が巷にあふれていた2001年、中島美嘉は私たちの前に現れた。
自身の歌手・女優デビュー作となったドラマ『傷だらけのラブソング』(フジテレビ系)。その劇中で歌った「AMAZING GRACE」がヒロインの未来を切り拓いたように、中島自身も瞬く間にスターダムに駆けのぼった。
あれから16年。彼女は唯一無二の立ち位置を築き、多くのファンを魅了している。激動の音楽業界の中にあって、彼女がそこに居つづけられるのは、自分を信じ抜く強さを手に入れたからだった。(ライター・大矢幸世 撮影・伊藤圭/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「歌手」という肩書に自信がなかった
デビュー15周年を初の海外ワンマン公演となる台北国際会議センターでのライブで締めくくった彼女は、2017年が明けて間もなく、再び台北の地にいた。旧暦の大晦日に6時間にわたって放送される『超級巨星紅白藝能大賞』の収録に臨むためだ。
会場となった台北アリーナには1万人を超える観客が詰めかける中、中島はただひとりステージに立った。『明日世界が終わるなら』を歌いはじめた彼女に、アクシデントが起こる。演奏と歌声をチェックするイヤーモニター(イヤモニ)が機能していなかったのだ。
「何も考えられない状態でしたけどね、耳栓してるような感じだったから」。けれども、彼女の歌声は揺らがない。すぐに左耳のイヤモニを外し、歌いきった。続く『ORION』では笑みさえ浮かべながら、観客に手を振る。そして、『雪の華』。憂いを帯びた胸声と、祈りにも似たファルセット。「謝謝」と一礼した彼女を、観客の大きな拍手と歓声が包んだ。「楽しかったですよ」と、中島は平然と振り返る。
前作から約4年ぶりとなるオリジナルアルバム『TOUGH』を3月22日にリリースしたばかり。デビューから16年の間には、耳の病気による音楽活動の休止と復帰、そして結婚と、さまざまな出来事があった。
「いいことも悪いこともいっぱいありましたけど、いい経験だったんじゃないかなと思えている自分がいるんです」
ステージに立つ以上はそこで表現するものがすべて、という思いがある。自ら詞を手がけた楽曲も、提供された楽曲も、「その曲の主人公になりきる」という意味で、差異はない。
「“歌手”と言われるとどうしても自信がなくて。これだけ歌っているのに、変な話なんですけど」。スタッフが声をかけるのもはばかられるくらい、ナーバスになることもあった。ライブに詰めかけたファンたちのまっすぐな眼差しが、歌うことが、怖くてたまらなかった。
「みんなキラキラした瞳で私を見つめていて……いったい、私に何を期待しているんだろうか。それに応えたい、と思うほど、空回りすることがたくさんあった。じゃあ、いっそ肩書を変えてみようかなと思ったら、気が楽になったんです」
万人に好かれなくてもいい。今、目の前にいる人たちの“代弁者”として、悲しみや苦しみ、怒り、あるいは喜びを歌う“表現者”として、ステージに立つ。

自分をだましてまで芸能界にいるつもりはなかった
18歳でドラマのヒロインとしてデビューしたとき、中島はまさか自分が“歌手”と呼ばれるようになるとは思っていなかった。モデルとして活動していた福岡で、知人に請われるがまま録った一本のデモテープがきっかけとなり、ドラマ『傷だらけのラブソング』のオーディションに参加することになる。
「その都度違うオーディションを受けているんだと思って、自分が勝ち抜いてると思ってなかったんです。でもなんか人数も少ないし、隣の子に『すみません……これ、何のオーディションですかね?』って聞いたら、『はぁーーっ!?』って驚かれてしまって(笑)」
演技をしても、レコーディングをしても、それがずっと仕事として続いていくとは思っていなかった。「ドラマが終わったら、バイト探さなきゃと思ってたんです。そう話したら社長に『おまえ、やる気ないのか?』って言われて(笑)。実際、仕事に関しては『これで家族を助けられるかな、ハッピーにできるかな』という気持ちだけでした」
何もわからないまま飛び込んだ世界だったものの、彼女は、ただ言われた通りにやるだけの操り人形ではなかった。「私、勘がめちゃくちゃ強くて、選択肢与えられたら迷わず『こっちだ』と思うことが多いんです。最初は、“歌って踊れるアイドル”になって欲しかったみたいですけど、ムリしてもどっかでボロが出るってわかってたから、できなくて」
ダンスレッスンはストレッチだけして、あとは先生とふたりでおしゃべり。ヘアメイクもファッションも、自分の思う通りに……「自分をだましてまで(芸能界に)いるつもりはなかった。自分らしさを認めてもらえないようなら、それは私の力不足だから、って思ってました」
トレンドにも左右されない。まるで役を演じ分けるように、さまざまに身に纏うスタイルは、彼女独自の美学をよく表している。その原点は、生まれ育った鹿児島にあった。

「小さい頃、世の中は美しいものであふれてるのが当たり前だと思って生きてたんです」。山あいの小さな集落。辺りには草花や木々が生い茂り、空には、手の届きそうな無数の星。月明かりだけが照らす夜の庭。「おねえちゃんと一緒に屋根に上って、『あれがさそり座……』って、指でたどって描いてた。あまりに故郷の空気が美しすぎて、今、東京でどんなものを見ても、『あれにはかなわないな』って思っちゃいますね」
かつて歌手を目指していた父は、中島が中学生の頃「モデルになりたい」と告げたとき、福岡にも系列のある事務所を探してきてくれた。母は日舞の師範として、彼女を厳しく、女性らしくしつけた。4つ上の姉は憧れの「一生かかっても超えられない」ほどの“スーパーヒーロー”。身近な家族が彼女にとっては尊敬すべき、学ぶべき人びとだった。

先駆者たちの姿を通して見つけた”居場所”
「やっとライブが楽しくなってきた」と話す彼女。怖くてたまらなかったそのステージは、今、彼女の居場所になっている。
「『これでいいんだ』って思えるようになったのは、ほんと最近で。背中押されても『いや、ちょっと疲れてるんだ』っていうような、弱ってる人たちのために生きるのもいいのかな。一緒に泣いて、隙間を埋めるアーティストって、そんなにいないのかもしれない。そう思ったときに、それが私の役目なんだ、って思えたんです」
そんな心境に至ったのは、ふたりのアーティストとの出会いがあったからだ。最新作にも収録されている『愛詞(あいことば)』を提供した中島みゆきと、『花束』を提供した玉置浩二だ。
「私はどこに属するつもりもなくて、その代わり、いろんな言葉を投げかけられることもある。きっと、おふたりも誤解されることがあるだろうと思うんです。でも、彼らの居場所は絶対に誰かに取って代わられようもない。自分たちの道を信じて、歩きつづけている姿を見たら、『あぁ、これでよかったんだ』って思えてきたんです」
30年、40年以上第一線で活躍しつづけるふたりから、中島美嘉のために贈られた楽曲たち。
「どこかで私のことを感じ取ってくださっているはずなんですよ。歌い方もそうだし、もがいてた日々だったり、避けてたことだったり……。初めて聴いたときには『恐ろしく難しい曲だな』と思いながらも、それを与えてくれたってことは、同じ土俵で『信じてるよ』って言われてる気がして。これを乗り越えたら、もしかして10年、20年後、彼らみたいになれるのかな……って、初めて欲が出たんです」
デビューからの歳月が、彼女に与えたのはなんだろうか。
「今までのことが全部積み重なって、なんだか“岩”みたいになっていて。昔はまだ弱かったり、迷ったりしてたんだけど、今はもう、もの投げられても、何をされても動かない。もちろん、感情はあるけどね(笑)。自分の信念や、周りの人たちが信じてくれていることを、疑いもなく、そこから一歩も動かずにいられるんです」。
でもその“岩”は頑なに閉じているのではなく、さまざまな変化や化学反応をも受け入れるしなやかさを持つ。
「自分がいちばんわからないんです。これからどうなるのか。それも含めて、楽しみです」
編集協力:プレスラボ