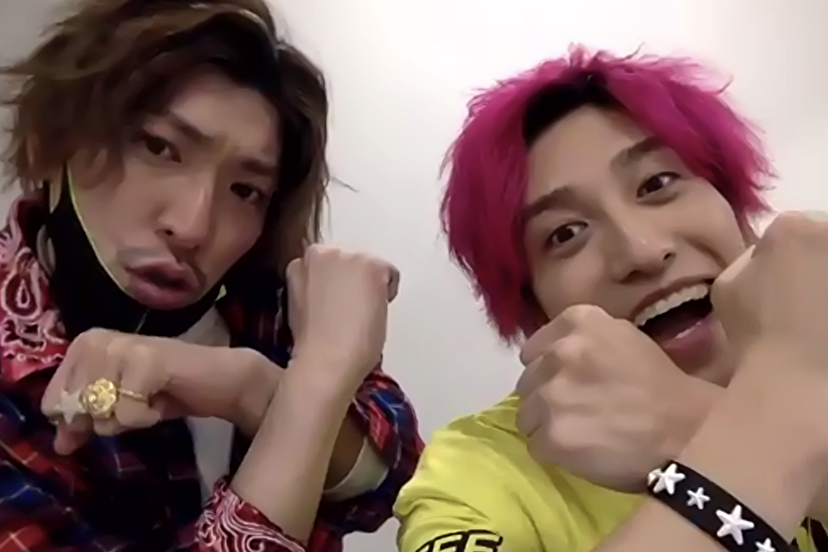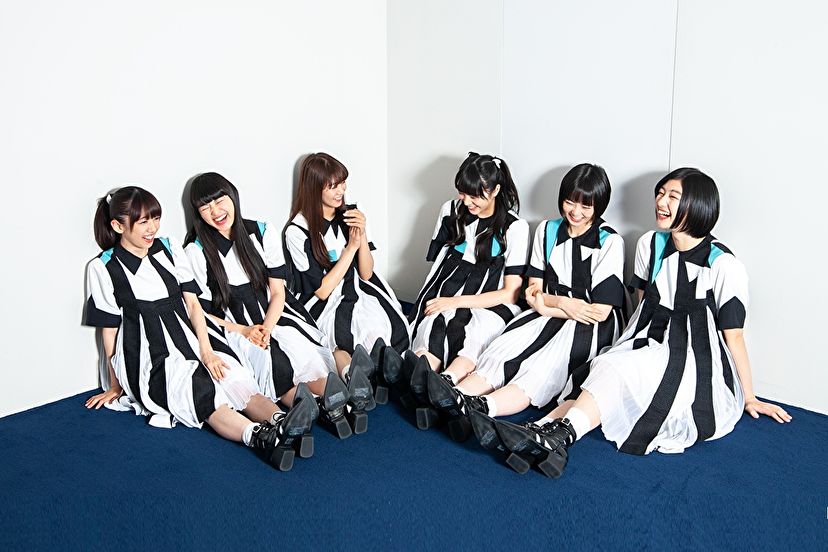「相談に乗ってくれる人が身近にいて、協力態勢があるのは本当に恵まれていると思います」。柄本佑、32歳。俳優一家に生まれ、幼いころから映画を見て育った。2018年の出演作で、キネマ旬報ベスト・テンの主演賞を妻の安藤サクラと同時に受賞。今、俳優業と育児に向き合う日々だ。夢は監督として長編映画を撮ることだという。(取材・文:関容子/撮影:野村佐紀子/Yahoo!ニュース 特集編集部)
(文中敬称略)
恥ずかしさと、落胆と

「家ではとにかく、映画の話しか話題がありませんでした。親父もかあちゃんも、学校の成績なんか全く関心がない。ところが見てきた映画のことを話すと、すぐ食いついてくるわけですよ。それが家族の会話でした」
父は俳優の柄本明、母は女優の角替和枝(2018年病没)、弟に柄本時生がいる。役者一家の長男だ。幼いころから自然と映画を見て育ったが、俳優志望ではなかった。
「小学校3、4年のころ、うちに『座頭市』のビデオがあって見たんですね。そしたら勝新(太郎)がすげえかっこよくて。でも、勝新が勝手に動いてるわけじゃなくて、監督が作ってるんだ、ということは漠然と分かってました。演出なんて言葉も知りませんでしたけど。監督がトップで、主役や周りの人を動かして、こんなにかっこよくさせてるんだ。絶対、勝新よりかっこいいじゃん、って」

中学3年のときにオーディションで選ばれ、2003年公開の『美しい夏キリシマ』(黒木和雄監督)に主演。いきなりキネマ旬報ベスト・テンの新人男優賞に輝いた。
オーディションに応募するきっかけを作ったのは、母・角替のマネージャーだった。
「マネージャーさんがやめることになって、最後の仕事として、『このオーディションに佑が合うと思うんですけど、書類出していいですか?』って、うちの親父とかあちゃんに聞いたらしいんです。それで、『佑がいいって言やあいいよ』となった」
「写真選考に通って、2次審査が監督面接でした。俳優の仕事には興味がなかったんですけど、かあちゃんが『あんたさ、どうせ落ちるよ、でも面接行ったら映画監督というものを見られるよ』って言ったんです。生で映画監督を見てみたいな、と」

それまで演技の経験は全くなかった。
「オーディションで『他の子と組んで、これやってみてください』って言われて、うわ、恥ずかしい……って。恥ずかしさを通り越して、もう俺笑っちゃって。よく受かったな、と思います」
『美しい夏キリシマ』には原田芳雄、石田えり、香川照之などが出演。錚々たる俳優たちのなかで、主役を演じた。
「自分の姿をスクリーンで見て、ものすごく落ち込みましたね。自分だけその映画の中になじめてない感じがして。撮影から16年経って、(ロケ地の)宮崎県えびの市に行ったんです。上映会があって、トークを頼まれて。駅の周辺で、『あ、ここ砂利だったのにコンクリになったんですね』って言ったら、『違うよ、あのとき4トントラック6台分の砂利を敷いたんだよ』って。俺、ものすごい大作に主演させていただいたんだなと思いました。16年ぶりに見るんだから、さすがに自分を客観的に見られるだろうと思ったけど、やっぱり全然がっかりでしたね。もう恥ずかしくって」

初めての映画の現場では、「ホームシックになって泣いた」という。一方でこのとき、ものづくりの楽しさを知ることになる。
「大人たちに囲まれて、みんなで同じ方向を向いて一つのものを作っていく、その楽しさをくらっちゃいました。しかも2カ月という長い期間。学校生活に戻ると、決まった時間に学校と家を往復する毎日が、つまらなくて仕方がなかった。同級生もなんだか子どもに見えてしまって」
「『またあそこ(撮影現場)に戻りたい』と思いました。撮影部でも照明部でも、まず技術を学ばなきゃならない。監督なら、仲間を集めたりしなくちゃならない。真っ先に戻れるとしたら俳優しかないと思って、父に相談しました。そしたら、今の事務所に話を通してくれて。高校に行きながら、いろいろな監督にお見合いみたいに会いに行って。仕事が決まると俳優さんと現場でご一緒できて、俺、ミーハーだから幸せな気分でした」
「地に足のついた生活」がしたい

高校卒業後は、早稲田大学芸術学校空間映像科に進学。いよいよ俳優一本で行くというころ、心境の変化があった。
「学生という本分があったから楽しんでいた仕事も、本分がなくなると、フワフワして社会とのつながりがないように思えてくる。極端な話、俳優の仕事って、社会にとってはなくてもいいのかな、みたいな気がしてくる。同級生に会うとスーツなんか着てるけど、自分は1カ月半も仕事がなくて、Tシャツに短パン、サンダル履きだったりして。自分って何者なんだろう、と思えてくるんですね」
そのとき、「地に足のついた生活」をしたいと思った。
「高校を卒業してから、一人暮らしをしていました。両親の家にほど近いところでしたけど。とりあえず、地に足がついてる生活というのをするために、だらしない生活を改善しよう、と。日常を生きたうえで、俳優の仕事をやる。地盤づくりのために、まずは台所に食器をためない、洗濯物はきちんと畳む、布団は起きたら干す。掃除とか、そういうことから始めました。そうすることで、社会の中に自分もいる、と感じられる。日常でちゃんとした生活をしていなければ、この仕事はできないと思ったんです」

尊敬している落語家・柳家小三治師匠の言葉が、心に響いたという。
「『芸なんてできる限りのことしかできません。あとは人間です』って小三治さんがおっしゃっているんです。これにすごく納得して。芸なんて表面的なもので、結局見られてるのは人間だもんな、と」
「だから開店休業のときも、店の商品にホコリはためず、毎日ハタキぐらいかけておこうよ、と思って。あと、映画を見ることは絶やさない。空いてる時間の過ごし方が、むしろ重要なんじゃないかな。それが人間としての仕込みの時間なんだと思いますね」
家族と芝居を磨いてきた

このころにもう一つ、地盤をつくった。弟・時生との二人芝居だ。
2008年に、2人のイニシャルにちなんだ演劇ユニット「ET×2」を結成。小劇場で公演を重ねている。2017年には、フランスの劇作家サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』を父の演出で上演し、父から子へ芸を伝承する様子が『柄本家のゴドー』というドキュメンタリー映画にもなった。
「父の主宰する劇団東京乾電池の制作を叔母がやってるんです。俺がまだほとんど何の仕事もなかったころ、俺と時生が叔母の家で飯食ってたら、(ハンガリー出身の作家)アゴタ・クリストフの『ジョンとジョー』を渡されて。『これ二人芝居だから、あなたたちでやってみたら』って。じゃあやってみようかって。後から考えると、自分たちの地盤というか、帰れる家みたいなものが欲しかったんだと思う。父で言えば、それが東京乾電池。親父も暇さえあれば、一人芝居を自分ちの地下のホールでやってる。それが精神的所属なんだと思う」
「乾電池には劇団員の人たちが70人弱いるんですけど、その人たちが、『お、芝居やんの? じゃ、手伝うよ』って。俺と時生でゼロから始めようとしても、ノウハウが分かんなかったら、実現しなかった気がするんですよ。すぐに相談に乗ってくれる人が身近にいて、協力態勢があるのは本当に恵まれていると思いました」

兄弟2人で演じるのは、どんなものだろう。
「兄の責任感、弟の無責任というか(笑)。『俺がしっかりしなきゃ』と思うんですよね。芝居をしていて、ぱっと時生のほうを見ると……なんかぼーっとしてる。『俺、頑張ってんだけどな』って。それで時生が『やっぱり兄ちゃん、すげえ』とか言っていて、『ふざけんなよ、このやろう』みたいな。まぁ楽しいですけど」
家族は2人の芝居をどう見ているのか。
「2作目をやったとき、『ちょっと佑』って親父に呼ばれて。『お前、時生と芝居やってたら確実に損するよ』って。『あいつはただの石だから、そこに石が転がっていたら、お前がやっぱり何かする羽目になっちゃうだろう』って。つまり、舞台に石と俺だけが立っていたら、見られるものにしなきゃと、兄として一生懸命になる。自分がピエロみたいになって、石が褒められることになる。親父は『転がっている石を、ただ見られるようになればいい』って言ってました。それにはまだ長い時間がかかりそうです。映画の製作の仕事してる姉貴が言うには、『時生は天才だよ。親父と佑はただの努力家だね』って」

父の助言はいつも、「『声探せ』とか『耳使え』とか、禅問答みたい」だという。
「かあちゃんには、『腐るなよ』って言われたことがありました。何かを見て、そう感じたみたいで。たぶんよくなかったんじゃないですかね、俺の芝居が。『もうちょっと詳しく言ってくんねえかな』と思いましたけど」
家族と共に芝居を磨いてきた。2012年には女優の安藤サクラと結婚。義父母は俳優の奥田瑛二、エッセイストの安藤和津、義姉に映画監督の安藤桃子、いよいよアーティスト一家になった。
「(安藤サクラとは)似たような境遇で育ったことで、お互い感じてきたことが似ていたりする。分かり合えるし、まどろっこしくない。お互いの芝居や演技については、あんまりしゃべらないかな。普通の夫婦ですよ」

2017年に娘が誕生。2018年から翌年にかけて、安藤サクラは、NHK連続テレビ小説『まんぷく』のヒロインを演じた。乳児を抱えたヒロインは、朝ドラ初だ。オファーを受けるにあたっては、夫や一家のサポートがあった。
そして2018年に出演した映画で、キネマ旬報ベスト・テンの主演賞を夫婦で同時に受賞する。佑は『きみの鳥はうたえる』『素敵なダイナマイトスキャンダル』『ポルトの恋人たち 時の記憶』の3作、サクラは『万引き家族』での受賞だ。そのほかにも、複数の賞を受賞した。
「今は子どもが2歳になって、やっぱり忙しい。いろんなことに意識が散漫になって、椅子に座ってちゃんとご飯を食べる時間が少なくて。ご飯は食べたいけど、アンパンマンのおもちゃで遊びたい、とか。ご飯に集中させるのに頭抱えてます。世のお母さん方はすげえなって思いながら。仕事は書いてあることを言うから線路が敷いてあるようなものだけど、子どものことは分かんない。どうしたらいいんだ、と」

育児に奮闘しながら、数多くの映画、ドラマに出演する。高い評価を受ける今も、自分の出演作を見るとがっかりするという。
「次こそはと頑張って、今回は行けたかもしれないと思って、できあがって見てみたら、またがっかり。あるときかあちゃんに、『俺、本当に落ち込んじゃって』と言ったら、『何言ってんのよ。俳優は待つのとがっかりに慣れるのが仕事じゃないの』って。和枝ちゃんみたいな大先輩が言うんだからそうだよな、と。褒められる自分が映ってたらいいな、と期待するんですが、いまだにがっかりしてますね。でも、がっかりしなくなっちゃったらおしまいかな」
少年時代から追いかける夢

最新主演映画は『火口のふたり』。キャストは、柄本佑・瀧内公美の2人きりだ。結婚式を間近に控えた女と、初めての恋人だった男が再会し、激しく肉体を求め合う。原作は白石一文、監督・脚本は、脚本の名手として知られる荒井晴彦。『身も心も』『この国の空』に続く3作目の監督作品だ。
「荒井さんには、5歳のときから知られてます。荒井さんの脚本の作品に一度は出てみたいという憧れがあったけど、まさか監督作品に出られるとは」

©2019「火口のふたり」製作委員会
荒井の脚本には、一挙手一投足が書かれている。
「男と女が久しぶりに会って初めて交わるとき、どう過激になっていくのか、具体的に書いてあります。ただ、激しく求め合う、なんて書かない。体位だとか、キスして、愛撫して、とかちゃんと書いてある。現場に投げるんじゃなくて、全部ト書きで演出が書かれているんです。荒井さんは、『脚本家は気持ちを書いちゃいけない。悲しそうな顔をした、ではなく、悲しくなった男はどういう行動をしたのかを書く』とおっしゃっていたのが印象的でしたね」
「初めての荒井組だったので、自分なりに何かできないかなって思っていたんです。でも、脚本に『勝手に動いてくれるなよ』っていうくらい全部書いてある。それでも5歳からのお付き合いという甘えもあって、自分から動けそうなところは動いてみました。勝手にやって、だいたい『それやめて』って言われるんですけど。採用になったところもあります」

『火口のふたり』完成披露試写会での舞台挨拶を前に、瀧内公美(左)、荒井晴彦(中央)と談笑する
憧れの荒井の脚本で、せりふの難しさと面白さを実感したという。
「年齢的には僕より少し上の感じのせりふで。それを自分の体を通して出すのは苦しかったけど、楽しかったですね。面白いのが、原作通りのせりふなのに、荒井さんの体を一回通して出てくると、荒井さんのせりふになる。不思議なんです。荒井さんは『原作がある場合、脚本家は一回原作の中に入っていかなきゃいけない』とおっしゃっていて。原作を自分に寄せるんじゃなくて、原作に浸かって、そこから作り上げていく、と」

デビューのころと同じように、現場でものづくりの面白さに魅せられている。
無類の映画ファンであることも変わらない。学生のころから、年間200本以上の作品を映画館で見てきた。仕事や育児で忙しいなか、昨年も120本くらい映画館で見たという。
自身で短編の自主製作映画を手掛けてもいる。少年時代からずっと、映画の夢を追いかけてきた。
「やっぱり長編映画を撮ってみたいですね。サスペンスがかった心理ドラマとか。そのためにも映画をよく見ているんです。いつか、というよりなるべく近い将来、監督になる夢を実現したいなと思っています」

柄本 佑(えもと・たすく)
1986年生まれ、東京都出身。2003年、『美しい夏キリシマ』で俳優デビュー。最近の主な主演作は、『素敵なダイナマイトスキャンダル』『きみの鳥はうたえる』『ポルトの恋人たち 時の記憶』。2019年公開の映画に『ねことじいちゃん』『居眠り磐音』『アルキメデスの大戦』などがある。NHK大河ドラマ『いだてん』に出演中。『火口のふたり』は8月23日公開。
関 容子(せき・ようこ)
エッセイスト。『日本の鶯 堀口大学聞書き』で日本エッセイスト・クラブ賞、角川短歌愛読者賞受賞。『花の脇役』で講談社エッセイ賞、『芸づくし忠臣蔵』で読売文学賞、芸術選奨文部大臣賞を受賞。『舞台の神に愛される男たち』『勘三郎伝説』『客席から見染めたひと』など著書多数