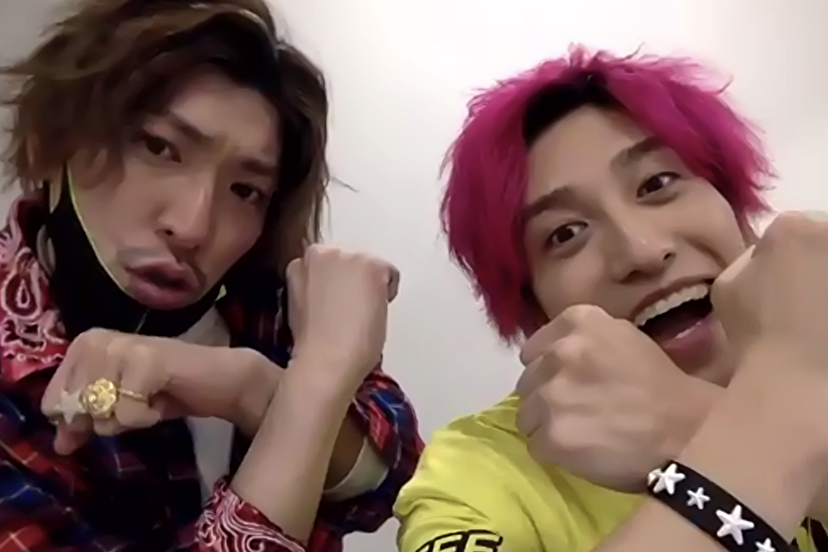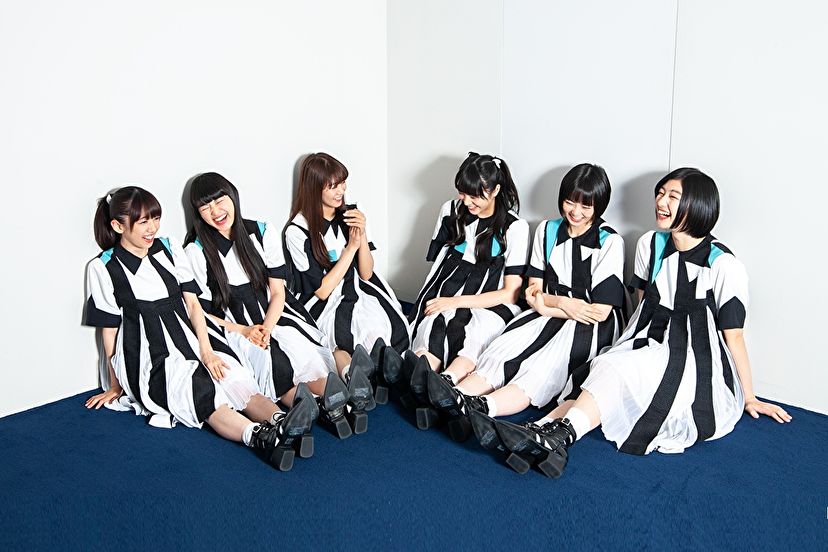主演ドラマはたびたびシリーズ化され、映画でも鮮烈な印象を残す阿部寛。「役に対して欲張り」と語る裏には、若き日の苦悩がある。「せっかく俳優という職業に就いたのに、このまま終わりたくなかった」。転機となった“一行”とは。(取材・文:水田静子/撮影:岡本隆史/Yahoo!ニュース 特集編集部)
(文中敬称略)

恵まれたデビューがコンプレックスに
「役者として、いったい何をどうすればいいのか分からずに、ずっと迷っていました」
渋い刑事や寡黙な武士、熱血漢の町工場社長、離婚されたうだつの上がらない作家、はたまた古代ローマ人……まで、ありとあらゆる役を演じる阿部寛。今やこの国のドラマ、映画界を牽引する。
だが、ふと漏らしたこの言葉には、20代から30代にかけての意外な苦悩、逡巡があった。

阿部は大学時代に、男性ファッション誌『メンズノンノ』の初代表紙モデルに選ばれ、華々しく活躍するなか、23歳の時に俳優としてデビューした。順調な滑り出し。しかし爽やかなモデルのイメージに近い青年役ばかりがきた。次第にオファーも減っていった。
「1、2年経つと新しい俳優が出てきて、すぐに過去の存在になる。あれ? 俺って何だったんだろうって。取り残されていく感覚が僕にもありました。モデルとしてある種、“蝶よ花よ”の扱いを受けていたから、余計にそう感じたんでしょうね。恵まれたデビューの仕方が、逆にコンプレックスになっていったんです」
「いろいろな役をやれるようになって実績を上げないと、この世界では通用しない」。そう気付いた。だが、来るオファーは相変わらずルックス重視のこれまでと変わらない役ばかりで、そこからどう抜け出していけばいいのかわからず、当時はずいぶん苦しい思いもした。

多数あったCMも激減。さらに週刊誌の「あの人は今⁉」という企画の取材対象にさえなった。
「仕事が減ることで過去の人になってしまうという不安感や経済的問題もあって、これはなんとかしなくてはと。ただ、役者以外の仕事はしたくないと思ったんです。役者一本にこだわりたかった」
「あの一行が僕の人生を変えてくれた」

苦境は6年ほど続いた。だが阿部はあきらめなかった。
「せっかく俳優という職業に就いたのに、このまま終わりたくなかったし、やめたくはなかった。あの時もしくじけたら、あそこで終わっていたな」
幼少期から負けん気が強かったという。ある日、突破口が見つかった。
「『リング・リング・リング』という映画で、ご一緒させていただいた演出家のつかこうへいさんから、次の自分の舞台のオーディションを『受けろ』と言われたんです」
作品は、つかの代表作の一つとして語り継がれる『熱海殺人事件~モンテカルロ・イリュージョン』である。ゲイの部長刑事という役。脚本には「きゃー、やめて」といった台詞があふれていた。

「これはとても自分にはできない、この台詞は断ろう、こんなことはやりたくない。明日こそ、つか先生に言おう。ずっとその繰り返しでした。仕事がどれだけ減っていても、きっとまだどこかで、それまでの自分のイメージを保ちたかったんでしょうね」
しかし毎日の稽古で、つかに激しく叱咤され、変わっていった。背水の陣であったのだろう、派手なメイクとドレス姿で本番に臨み、恥ずかしい台詞も次々に絶叫した。鎧が脱げた瞬間だった。
「大ウケして嘘だろうって思いました。ある週刊誌が『この舞台に出ている阿部寛を評価しないわけにはいかない』と書いてくれて、ものすごくうれしかった。それまで一度も褒められたことがなかったですから。あの一行が僕の人生を変えてくれたんです」
すでに29歳になっていた。この舞台を経て怖いものがなくなった。つかはまだ何者でもなかった自分を掘り起こして世に出してくれた恩人、と阿部は言う。

「もう一歩も引けないと覚悟しました。いただいたこのチャンスをものにして、映像の世界でも評価されていきたいと」
それが、つかに報いることだと思った。
Vシネマの悪役で爪痕を残して
オファーのあったVシネマにも次々に挑戦。『悪党図鑑』ではチンピラ役、『凶銃ルガーP08』では復讐に燃える狂気に満ちた男を演じ、好評を得た。『凶銃ルガーP08』は映画館でも上映され、日本映画プロフェッショナル大賞を受賞した。
「Vシネマには本当に助けられました。変わった役、とんでもない役……どんな役でもやりたいと欲が出てきた時で、悪役を、しかも主演でガッツリやらせてもらえた作品もあって、うれしかったですね。まだ素人に近いんで、なんとか爪痕を残したいと思って必死でやっていた。一作、一作、その役になって、とにかく一つ一つ続けていく。こんな役もやった、あんな役もやったと、役柄の経験を増やしたかった。役に対して欲張りなんです」

92歳の父を愛おしく感じる
以降、連続ドラマや映画への出演が加速していく。意外なことに阿部が映画で立て続けに主役を張るようになったのは、10年ほど前、45歳ごろからだ。その中の一つに、刑事・加賀恭一郎が事件の謎に迫っていく人気作品がある。テレビドラマ『新参者』シリーズから映画化された2作で、今年初めに公開された『祈りの幕が下りる時』は最終章となった。
「ドラマ『新参者』は8年続いて、この映画がシリーズの最後となりました。加賀は比較的動かない人物で、相手の芝居を自分の心に沈めていくというのか、静かな芝居をしていく。そろそろ刑事ものをしっかりやりたいと思っていた時に出合った役で、加賀を演じたことで僕自身にも得るものがたくさんありました。終えてみてこの8年間、加賀という男がどこかで僕を支えてくれていた、そんな気がしています」

刑事・加賀恭一郎を演じる阿部。左は共演の松嶋菜々子 (C)2018映画『祈りの幕が下りる時』製作委員会
今作では、それまで語られなかった加賀の身の上、在りし日の父母の姿も明かされる。阿部自身の父母について聞いてみた。
「母は17年前に他界したんですけど、父は今も92歳で元気です。70代でちょっと病気をして親父のほうが先に逝くんじゃないかと心配したんですが、おふくろが先に逝ってしまった。親父はおふくろを8年間看病して、入院してからもずっと見舞っていました。立派でしたね。よく父の背中とかいいますが、今になって親父の精神力の強さとか偉大さとか、いろいろなことが分かってきて、親父のことがなんだか非常に愛おしく思えます」
成功したという感覚はない

今、観客からも制作側からも、最も信頼される俳優の一人となった。年齢を重ねるごとに個性が際立ち、存在感はより濃くなっていくようだ。だが阿部は「(俳優として)成功したとか、特にそういう感覚はない」と言う。いつもただ一人の俳優として、闘志を秘めて現場に居る。
「監督や舞台の演出家は、やっぱり強烈な人のほうが僕には合っているみたいです。(良い作品をつくるために)たくさん難題を与えてほしいし、気持ちをどんどん追い込んでほしいんです」

エネルギーが飛び散るような現場が好きだと言った。
「挑戦しがいのある作品、例えば前作と全く違うとか、敢えて振り幅のある役を選んできましたが、そうした選択が今の僕を作ってくれたと思っています。僕はそのほうが結果がいいんです」
真剣なまなざしに、ひとすじ、俳優の道を歩いてきた人のひたむきさが感じられる。
役と実年齢のギャップを感じる時も

50代に入ったころ、初めて年齢というものを意識した。俳優としてのこれからの人生を思い、揺れ動いたことがあったそうだ。
「まだまだいろいろな役をやりたいという欲は、変わりなくあっても、役と年齢とのギャップが出てくることもあるわけで。オファーをもらえるのはありがたいのですが、もっと実年齢が若い役者のほうがきっといいだろうと思って、自分としては涙をのんで断らざるを得ないこともあったりする。そこはとても悔しい。40歳から50歳はおそらくそれほど変わらないだろうけど、これから先、60代にかけては、たぶんずいぶんと変わっていくはずだし」
それでも、と言葉をつなげる。
「『祈りの幕が下りる時』でもご一緒している山﨑努さんなど、80代で素晴らしい芝居をなさっている先輩たちの存在は、大きな励みになるし、活力を与えられています」

今、あらためて俳優という職業について、どう思うかを尋ねた。
「……そうですね、自分を役に投影しながら、いろいろな作品に出演し、違った役を演じることで、あ、自分はもしかしたらこういう人間ではないか、あるいはこういう面もあるのではないかとか、自分では認識していなかった僕という人間を確認できるようなところがありますね。その年齢、その時の自分と向き合う仕事というのかな」
そして、と深みのある言葉を残した。
「人を演じるということは、自分にそれだけのものが備わっているのかどうかを、問われているようにも思えます。普段からどう生きているのかと」

阿部 寛 (あべ・ひろし)
1964年、神奈川県生まれ。1987年、映画『はいからさんが通る』で俳優デビュー。代表作にドラマ『トリック』『結婚できない男』『下町ロケット』、映画『チーム・バチスタの栄光』『歩いても歩いても』『青い鳥』『柘榴坂の仇討』ほか。2013年、『テルマエ・ロマエ』で第36回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、第55回ブルーリボン賞主演男優賞受賞。『祈りの幕が下りる時』はBlu-ray&DVDが発売中。