1974年東京大学医学部卒業。1987年同大学医学部小児科講師。1989年焼津市立総合病院小児科科長。1995年こどもの城小児保健部長を経て、1999年緑園こどもクリニック(横浜市泉区)院長。1985年、プールの排水口に吸い込まれた中学2年生女児を看取ったことから事故予防に取り組み始めた。現在、NPO法人Safe Kids Japan理事長、こども家庭庁教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議委員、国民生活センター商品テスト分析・評価委員会委員、日本スポーツ振興センター学校災害防止調査研究委員会委員。
関連リンク(外部サイト)
記事一覧
1〜25件/136件(新着順)
 ミニトマトによる乳幼児の誤嚥を防ぐ〜食品メーカーのコマーシャル映像への取組み #こどもをまもる
ミニトマトによる乳幼児の誤嚥を防ぐ〜食品メーカーのコマーシャル映像への取組み #こどもをまもる 「みんなの毎日を安全に楽しく!」アイデアコンテスト(小学生対象)授賞式の開催 #こどもをまもる
「みんなの毎日を安全に楽しく!」アイデアコンテスト(小学生対象)授賞式の開催 #こどもをまもる 「サッカーゴール等固定チェックの日」を前に #こどもをまもる
「サッカーゴール等固定チェックの日」を前に #こどもをまもる こどもノーマークはNO! - 社会でこどもを守る #こどもをまもる
こどもノーマークはNO! - 社会でこどもを守る #こどもをまもる 乳幼児の転落を予防する - 補助錠の全戸配布ははたして有効か? #こどもをまもる
乳幼児の転落を予防する - 補助錠の全戸配布ははたして有効か? #こどもをまもる 埼玉県虐待禁止条例案について考える-Vol.2 アメリカの状況 #こどもをまもる
埼玉県虐待禁止条例案について考える-Vol.2 アメリカの状況 #こどもをまもる 埼玉県虐待禁止条例案について考える-社会でこどもを守るために #こどもをまもる
埼玉県虐待禁止条例案について考える-社会でこどもを守るために #こどもをまもる わが子がケガをした〜動画による発信の重要性と「市民科学」のすすめ #こどもをまもる
わが子がケガをした〜動画による発信の重要性と「市民科学」のすすめ #こどもをまもる 野球のバッティングケージによる傷害を考える #こどもをまもる
野球のバッティングケージによる傷害を考える #こどもをまもる ロープやひもによる窒息を予防するために #こどもをまもる
ロープやひもによる窒息を予防するために #こどもをまもる こどもの窒息を防ぐ 〜「聞かせてください」「みんなの声」への投稿から考える〜 #こどもをまもる
こどもの窒息を防ぐ 〜「聞かせてください」「みんなの声」への投稿から考える〜 #こどもをまもる こどもの溺れを予防するには 〜江戸川のケースについて考える〜 #こどもをまもる
こどもの溺れを予防するには 〜江戸川のケースについて考える〜 #こどもをまもる 日本でも「こどもは飛べない!」幼児の転落死をなくすには #こどもをまもる
日本でも「こどもは飛べない!」幼児の転落死をなくすには #こどもをまもる 「かかりつけエンジニア」始動!〜学校の施設・設備を見直してこども達のケガを減らす〜 #こどもをまもる
「かかりつけエンジニア」始動!〜学校の施設・設備を見直してこども達のケガを減らす〜 #こどもをまもる 新しい製品、新しいサービスと「こどものケガ」について考える〜ニューボーンフォト、肩車キャリアなど〜
新しい製品、新しいサービスと「こどものケガ」について考える〜ニューボーンフォト、肩車キャリアなど〜 コンセプト・ムービーができた 〜 Safe Kids Japanの活動指針
コンセプト・ムービーができた 〜 Safe Kids Japanの活動指針 「モグラたたき」と言われても〜楽しく安全な豆まきのために〜
「モグラたたき」と言われても〜楽しく安全な豆まきのために〜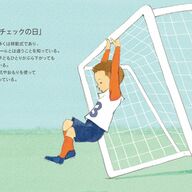 1月13日は「サッカーゴール等固定チェックの日」
1月13日は「サッカーゴール等固定チェックの日」 2023年 年頭所感 事故による子どもの傷害を減らす
2023年 年頭所感 事故による子どもの傷害を減らす また起きた!フォークリフトによる子どもの事故
また起きた!フォークリフトによる子どもの事故 ベランダなど高所からの幼児の転落を減らす〜再現実験が必要だ!
ベランダなど高所からの幼児の転落を減らす〜再現実験が必要だ! 11月に車内で子どもが熱中症になるか?〜岸和田の事故から考える〜
11月に車内で子どもが熱中症になるか?〜岸和田の事故から考える〜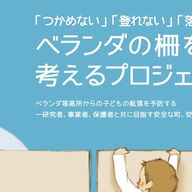 また起きた!「ベランダ等高所からの子どもの転落死」〜今後、どう取り組むべきか
また起きた!「ベランダ等高所からの子どもの転落死」〜今後、どう取り組むべきか 「園バス置き去り」を予防するために その5〜今回の対応の経緯を振り返る 今後に向けて〜
「園バス置き去り」を予防するために その5〜今回の対応の経緯を振り返る 今後に向けて〜 「園バス置き去り」を予防するために その4
「園バス置き去り」を予防するために その4





