老いるニッポンと模索する『紅白』──【2021年版】データで読み解く『紅白歌合戦』:3
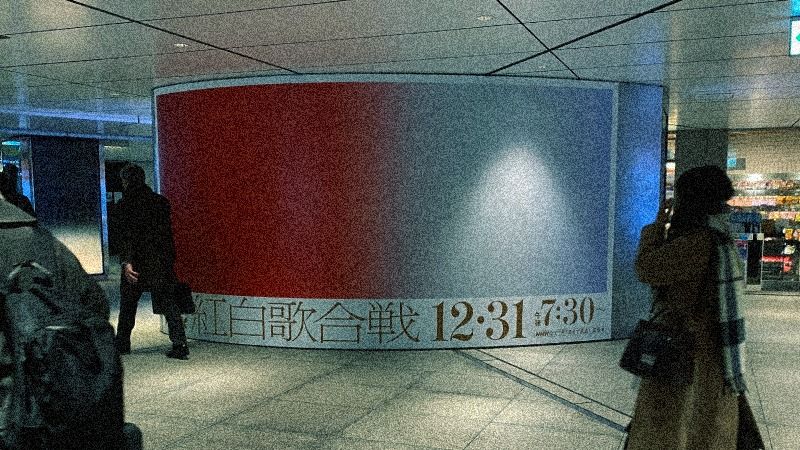
あさってに迫った『紅白歌合戦』。過去の連載2回では、出演回数と披露される曲のデータを確認してきた。そこでは常連勢が減り、メドレーが激減する現象が確認できた。
今回は、出演者の年齢を確認していこう。
高齢化率は過去最高を更新
昨年は65歳以上の高齢者の出演が12%と過去最高を記録した。それは常連が増えたことを意味しない。キャリアを重ねてはじめて『紅白』に出るアーティストもいるからだ。今年であればパラリンピックの開会式で注目された布袋寅泰が、59歳で初出演を果たす予定だ(2007年に石川さゆりのサポートギタリストとしての出演経験はある)。
今年は五木ひろしが今回は出演しないにもかかわらず、65歳以上の割合が過去最高を更新した(図1)。人数は昨年よりもひとり多い6人だ。むかしと異なるのは、こうした大御所に演歌勢が少ないことだ。細川たかしと天童よしみを除けば、ほかは郷ひろみやさだまさしなどアイドルやポップス、フォークの歌手たちである。
その一方で、34歳以下の若者の割合は史上2番目に低い40.4%にまで下がっている。2018年は若い出演者を増やす傾向が見て取れたが、そこからまた高齢化に進んでいる。

鈴木雅之は高齢者世代に
年齢別割合の推移をたどると、図2のようになる。1960年代に入るあたりから34歳以下の若者世代が増え、70年代前半にピークに達する。とくに1966~1967年は45歳以上の出演者はゼロ。最年長は当時43~44歳の三波春夫だった。高度経済成長の時代、『紅白』は若者たちの場だったのである。
東京オリンピックなどもあって著しい高度経済成長をした1960年代は、メディアの中心がラジオと映画からテレビに移っていった時代でもあった。それにともない多くの芸能プロダクションが誕生し、自社の所属タレントを送り出すようになる。1963年に生まれた芸能プロダクションの事業者団体が「日本音楽事業者協会」という名称なのも、この時代のポピュラー音楽の興隆の名残だ。
同時に、この頃は戦後すぐに生まれたベビーブーム世代(団塊の世代/1947-1951年生まれ)が成人を迎えたあたりでもある。たとえばこの世代に含まれる和田アキ子(1950年生まれ)やにしきのあきら(錦野旦/1948年生まれ)が初めて出演するのは、1970年のこと。戦後芸能界の興隆は、送り手も受け手も団塊の世代とともにあった。
だが、70年代中期を過ぎると若い世代の割合が減り、中高年層が徐々に増えていく。その傾向がより強まるのは90年代以降だ。なかでも1999年と2001年には、45歳以上の中高年世代が34歳以下の若者世代を上回る。
今年は、昨年と比較すると中高年層がやや増えた印象だ。これは鈴木雅之が65歳となって高齢者世代に含まれたり、ゆずの平均年齢が45歳の中年世代となったりしたためである。

出演者の平均年齢は41歳
出場者の新陳代謝は進んでいるものの、出演者の高齢化は近年ふたたび進行しつつある。平均年齢の過去最高は、2015年の41.3歳だが、その翌年からやや下がる傾向にあった。しかし昨年からまた年齢が上がる傾向を見せ、今年は40.8歳と史上2位タイの高さとなった。
日本社会が著しく高齢化しているので、公共放送の『紅白』もそれに準じているということかもしれない。今年も『紅白』から“卒業”していた細川たかしが、企画枠で復活したのもそうした需要に応えたものかもしれない。
日本の人口の平均年齢と『紅白』出演者の平均年齢をグラフにすると、以下のようになる(図3)。

戦後生まれのベビーブーム世代によって1960年までは『紅白』出演者の方が年齢が高かった。両者の平均が同じ29.3歳になるのは1961年のこと。それは、3年後の東京オリンピックに向けて高度経済成長を続け、テレビが急激に普及し、現在に続く芸能プロダクションの体制が構築された時期でもある(「パラダイムシフトに直面する芸能プロダクション」2020年8月27日)。
以降、視聴者と『紅白』出演者の年齢は2~4歳の間隔を保ちながら、ともに右肩上がりを続けていく。
しかし、それに変化が生じるのが00年代中期からだ。『紅白』が若返りを図るなどして出演者の平均年齢が40歳前後で推移するのに対し、日本の人口の平均年齢は右肩上がりを続ける(これは今後も当面続く)。
結果、その間隔が徐々に開いている。2018年には両者が9.1歳差、翌2019年には9.0歳の差が生じている。
一般的に、ポピュラー音楽をリードするのは若者と認識され、日本レコード協会の調査でもボリュームゾーンは高校生から20代との結果が出ている(「2020年度 音楽メディアユーザー実態調査」)。しかしこの若者世代は、40代後半から50代前半の第2次ベビーブーム世代の6割程度しかいない。もはや日本は若者が流行をリードする状況とは言えないのかもしれない。
若者が減り中高年層の厚みが増すなかで、『紅白』はそうした日本の状況にどう対応するか模索を続けているように見える。細川たかしの復活やMISIAの2年連続の大トリは、そうしたなかでのバランスなのだろう。
■関連記事
・紅白が「男女同数」を止めたら何が起きる? 民放特番の男女比に見る“衝撃の事実”《女性比率はMステ32%、FNS歌謡祭37%》──変わる紅白歌合戦 #2(2021年12月28日/『文春オンライン』)
・『紅白歌合戦』、ジャニーズ頼りからの脱却か?──SMAP・TOKIO・嵐がいない大みそか(2021年12月24日/『Yahoo!ニュース個人』)
・1980年代の『紅白歌合戦』になにがあったのか──メディアの変化、そして歌謡曲からJ-POPへ(2021年12月7日/『Yahoo!ニュース個人』)
・“しがらみ”から抜け出せない『紅白歌合戦』──中途半端に終わった2020年と今後のありかた(2021年1月2日/『Yahoo!ニュース個人』)
・なにをやっても文句を言われる『紅白歌合戦』──「国民的番組」としての期待と多様な日本社会とのギャップ(2017年12月31日/『Yahoo!ニュース個人』)










