博士(政策・メディア)。専門は社会学。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科助教(有期・研究奨励Ⅱ)、独立行政法人中小企業基盤整備機構経営支援情報センターリサーチャー、立命館大学大学院特別招聘准教授、東京工業大学准教授等を経て2024年日本大学に着任。『メディアと自民党』『情報武装する政治』『コロナ危機の社会学』『ネット選挙』『無業社会』(工藤啓氏と共著)など著書多数。省庁、地方自治体、業界団体等で広報関係の有識者会議等を構成。偽情報対策や放送政策も詳しい。10年以上各種コメンテーターを務める。
関連リンク(外部サイト)
記事一覧
1〜25件/120件(新着順)
 少年刑務所とはなにか
少年刑務所とはなにか ネット事業の必須業務化に向けた最新NHK改革と「スマホ受信料義務化」の誤解と懸念
ネット事業の必須業務化に向けた最新NHK改革と「スマホ受信料義務化」の誤解と懸念 自民党情報通信戦略調査会提言案とNHK文字ニュースの廃止、改悪に関する懸念
自民党情報通信戦略調査会提言案とNHK文字ニュースの廃止、改悪に関する懸念 官房長官会見における文科省による生成系AI活用検討に関する言及と教育に与える影響の「根本問題」
官房長官会見における文科省による生成系AI活用検討に関する言及と教育に与える影響の「根本問題」 放送事業者は総務省政治的公平に関する文書についてどのような認識を示したか?
放送事業者は総務省政治的公平に関する文書についてどのような認識を示したか? 総務省放送法に関する「政治的公平に関する文書」問題をどの視点で読むか――解釈変更と萎縮の有無を中心に
総務省放送法に関する「政治的公平に関する文書」問題をどの視点で読むか――解釈変更と萎縮の有無を中心に 「出生率が上がれば子ども予算倍増」木原官房副長官の発言が批判を浴びる背景
「出生率が上がれば子ども予算倍増」木原官房副長官の発言が批判を浴びる背景 二転三転する児童手当所得制限撤廃論、子育て支援と少子化対策を本気で検討する政党はどの党か?
二転三転する児童手当所得制限撤廃論、子育て支援と少子化対策を本気で検討する政党はどの党か?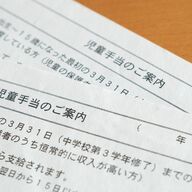 「異次元の少子化対策」と児童手当の所得制限撤廃をめぐる政治的構図
「異次元の少子化対策」と児童手当の所得制限撤廃をめぐる政治的構図 相次ぐ雇用調整助成金不正 2つの悪質さ
相次ぐ雇用調整助成金不正 2つの悪質さ 国葬儀の検証はなぜ非公開で行うのか?
国葬儀の検証はなぜ非公開で行うのか? 国葬儀に関する所感と評価、課題
国葬儀に関する所感と評価、課題 全国旅行支援は公正か?
全国旅行支援は公正か? 日本版偽情報対策と「ファクトチェック」ーーそもそもファクトチェック団体は何をしようとしているのか?
日本版偽情報対策と「ファクトチェック」ーーそもそもファクトチェック団体は何をしようとしているのか? 【追記】新型コロナウイルス感染症に伴う中小小規模事業者向け支援の対象にNPO法人等は該当するか?
【追記】新型コロナウイルス感染症に伴う中小小規模事業者向け支援の対象にNPO法人等は該当するか? 「土曜日、18時」の記者会見で総理が語ったこと
「土曜日、18時」の記者会見で総理が語ったこと 法務教官の専門性と重要性ーー認定NPO法人育て上げネット少年院スタディツアーに参加して
法務教官の専門性と重要性ーー認定NPO法人育て上げネット少年院スタディツアーに参加して 5000字で振り返る平成政治史: 令和で検討されるべき改革と諸課題
5000字で振り返る平成政治史: 令和で検討されるべき改革と諸課題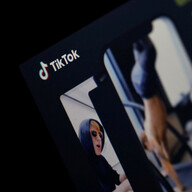 日本共産党の「TikTok」アカウント開設と脊髄反射的反応によるイメージ政治招来の懸念
日本共産党の「TikTok」アカウント開設と脊髄反射的反応によるイメージ政治招来の懸念 触法少年の社会復帰支援と「被害者軽視」 ーー新潟少年学院スタディツアーに参加して
触法少年の社会復帰支援と「被害者軽視」 ーー新潟少年学院スタディツアーに参加して 国立大学の授業料値上げを避けるために、安定的財源の拡充を。
国立大学の授業料値上げを避けるために、安定的財源の拡充を。 2019年版QSアジア大学ランキングが公開。日本の大学の地位をどう読むべきか。
2019年版QSアジア大学ランキングが公開。日本の大学の地位をどう読むべきか。 非テキスト系SNSが本格活用された初めての自民党総裁選と憲法改正国民投票運動
非テキスト系SNSが本格活用された初めての自民党総裁選と憲法改正国民投票運動 就活ルール廃止は、大学生と大学生活、就労環境にどのような影響を与えるか
就活ルール廃止は、大学生と大学生活、就労環境にどのような影響を与えるか 「石破ビジョン」は物足りない。
「石破ビジョン」は物足りない。





