店長がしゃべりすぎないのがバイト定着のコツ?〜ある居酒屋チェーンの挑戦〜

ここのところさまざまな業種で人手不足が問題になっており、中でも飲食店の状況は深刻です。
2019年4月の帝国データバンクの調査では、回答した飲食店のうち正社員については61.9%、非正社員については78.6%が「不足している」と答えています(「該当なし/無回答」を除く。出典:人手不足に対する企業の動向調査(2019年4月))。
そんな中、東京都内で20店以上の居酒屋を中心とした飲食店を経営する株式会社リロードエッジは、アルバイトの定着率向上を目的に「ミーティングの改善」に取り組みました。
アルバイトの定着とミーティングにどんな関係があるのか? 取り組みによってどんな変化が起きたのか? 同社を支援したコンサルタントの相崎哲史さん(株式会社MS&Consulting リレーション事業本部 部長)と、「博多満月 武蔵小杉店」の店長(当時)として相崎さんの指導を受けた丸野仁史さん(株式会社リロードエッジ ブロックマネージャー)にお話を伺いました。
■社員6人、アルバイト20人の居酒屋で週休2日を徹底
-- こちらのお店は何人くらいの方が、どのくらいのペースで働いているんですか?

丸野:社員が6人、アルバイトが20人くらいいます。社員は週5日勤務、アルバイトは週6日来てくれる子もいれば、週1〜2や月2回くらいの子もいます。
-- 丸野さんは、今はブロックマネージャーとしてこのお店ともう1店を見ているんですよね。店長は長くやっていたんですか?
丸野:いえ、この会社に入社したのが去年の4月で、同年の12月まで店長をやってました。
-- この会社の前は、何をされていたんですか?
丸野:赤坂の鉄板焼きの店で働いていました。
-- なぜ転職を?
丸野:学生時代から飲食の仕事をしたいと思っていて、一度は大手メーカーに就職したのですが、2年で辞めてそのお店に入りました。それから6年間いろいろ勉強させてもらい、仕事もとても楽しかったんですが、すごく拘束時間が長かったんですよね……。
だいたい昼の3時すぎから仕込みに入り、翌朝の5時の閉店後、締めの作業が終わる6時くらいまで働いて帰るというのを、月曜日から土曜日の毎日やっていました。僕は全く苦ではなく、楽しくやっていたんですが、結婚して子どもができても一緒に過ごす時間が全然ないわけです。家内から「もうちょっと条件がいいところがあるんじゃないの?」と言われまして、いろいろ探して巡り合ったのが、今のリロードエッジという会社です。
-- 拘束時間は減りましたか?
丸野:はい。週5日勤務で1日の拘束時間は9時間くらいです。僕も最初は、飲食店で週休2日なんてあるんだ! とビックリしたんですけど。
-- 同じ飲食店で、どうしてそんなに違うのでしょう?
丸野:会社の方針、ですかね……。そもそも給与形態が違うんです。以前は年俸制のような感じで、何日、何時間働くかはあまり問題になりませんでした。今の会社では、月給制で労働時間や勤務日数が決まっています。全店舗で週休2日にできているかは分かりませんが、僕はそういう条件で入ったので、自分の担当の店舗の社員には必ず週休2日とってもらっています。そのためにはシフト調整が必要なので、月2日くらいでも来てくれるアルバイトの存在は重要なんですよ。
-- ちゃんと休めることの重要性を実感していますか?
丸野:してますね。休まないと、いいアイデアも出てこないです。
■アルバイトを経営に巻き込むために注目したのが「店長のミーティングスキル」だった
-- では本題の「ミーティングの改善」について伺いたいのですが、これは去年の店長向け研修のテーマだったんですよね?どんな経緯で、相崎さんがこの研修をすることになったのですか?
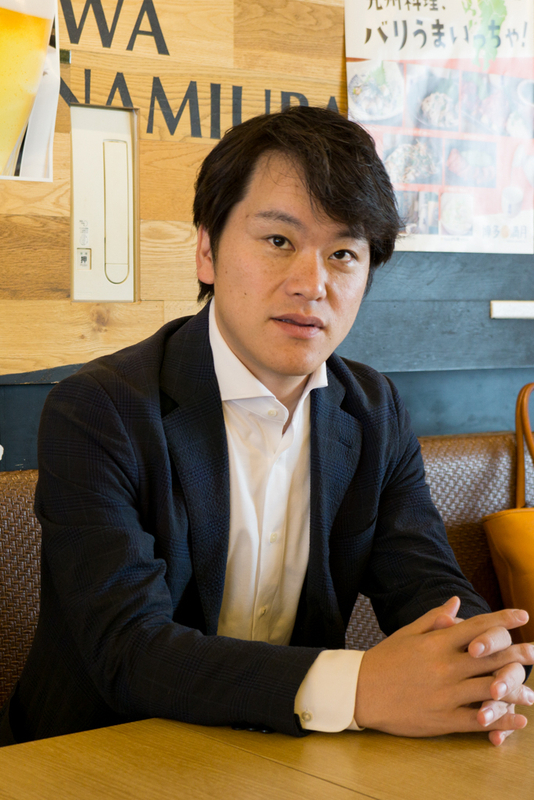
相崎:僕は全国のさまざまな飲食店や小売店の顧客満足と従業員満足を向上させるためのお手伝いをしていて、リロードエッジさんでの店長研修も4年ほど前から不定期にやらせていただいていたんです。その時々の状況に応じて内容を決めているのですが、今回はアルバイトの子たちをいかに店の経営に巻き込むか、ということが課題でした。
-- それは、やっぱり人手不足だからですか?
相崎:そうですね。いかに人を確保して定着させるかということを考えると、もちろんミーティングだけではダメなんですよ。まず、給料や勤務時間のような条件面での不満をなくさないと採用が難しいし、入っても辞めてしまいます。でも、不満を解消するだけでも足りないんですね。仕事の楽しさを感じてもらわないと、働き続けてもらうのは難しい。経営に巻き込むというのは、楽しく働いてもらうための方策です。
-- 経営に巻き込むために、「ミーティング」に注目したのはなぜですか?
相崎:ひとつには、店のメンバーを巻き込む方法として、リアルな対面の場で関係を作るのが手っ取り早いということがあります。その中で、1対1で仕事を教えたり面談をしたりということももちろん重要です。ただ、個別の指導よりもミーティングの方が、店長によるスキルの差が激しいんです。これまで効果的なミーティングの方法を教えられていない人がほとんどですから。
僕らの会社では「サービスチーム力診断」という従業員満足度調査を2万店やっているのですが、この調査の結果から、リロードエッジの全社共通の課題として「他社よりも店舗ミーティングが機能していない」ということがわかっていました。そこで、店舗ミーティングのレベルを上げることを目的に、月に1度、全部で6回の研修をやりました。
■ミーティングでの店長の役割は、話すよりも聴くこと
-- 研修を受ける前、アルバイトの定着率を高めるためにやっていたことはありますか?

丸野:楽しく仕事ができるかどうかが定着率の鍵になると思っているので、そのための工夫はしていました。
例えば、オープン直後の夕方はお客さんが少ないので、外に出て客引きに行くんです。それで連れてきたお客さんがどれだけお金を使ってくれたか、スタッフ別に集計して棒グラフにします。「今週は◯◯君が15万円。△△さんは8万円」みたいな感じでみんなが見られるようにすると、「あれ、ちょっと数字足りないんじゃないの」と気付いて「行ってきます」という子もいたり。ホールの担当だけじゃなく、キッチン担当でも「暇だから」と客引きに行く子がいるんですよ。
-- 仕事にゲーム感覚を取り入れているんですね。ミーティングに関しては、以前から実施されていたんですか?
丸野:社員だけのミーティングはやっていたんですけど、アルバイトも一緒に、というのはやっていませんでした。会社のルールとしてはやることになっていたんですけど……。
-- それは、丸野さんが必要性を感じていなかったから?
丸野:アルバイトを巻き込むミーティングって前の会社でもやったことなかったので、そもそも「集まるのかな?」という疑問もあったんですよね。このお店の前任者はそういうのがあまり好きじゃなかったみたいで、引き継ぎの時に「ミーティングをやってLINEで議事録を上げておくことになってるんだけど、それっぽい議事録を作っておけばいいから」という感じでしたし……(笑)。
-- ほかのお店はどうだったんでしょう?
丸野:うちと同じように、とりあえず議事録だけ提出して、できていないという店もあったと思いますよ。
相崎:やってはいるものの形骸化しているケースもありますね。例えば、毎月のお客様満足度調査の結果をみんなで確認して意見を出しあう会議をするものの、決定事項は「お客様へのあいさつを頑張ります」というフワッとした内容だったり……。
-- 逆に、ミーティングが機能している店に共通する特徴はあるのでしょうか?
相崎:僕らは、覆面調査員(ミステリーショッパー)による調査を年間に7万3,000店で実施していますが、優良な結果が出る店では、ミーティングにおけるリーダーの発言率が10%以内に抑えられているということが分かっているんです。
-- リーダーがあまり発言しない?
相崎:リーダーがしゃべりすぎず、メンバーに話をさせているんです。
丸野:研修でその話を聞いたんですけど、たぶん全店長が「勉強になった」と感じている部分だと思います。普通は90%くらい店長がしゃべってるんじゃないですかね。それが全く逆で10%くらいでよくて、あとは聴きだす方に集中すべきだと。
-- 目からウロコだったんですね。
丸野:はい。それを知るまでは、司会進行も自分でやりながら「次は何を話そうか」と考えているような感じでした。そうではなく、「次は何を聞いてあげようかな」という姿勢になって気が楽になりました。ほかの店長もミーティングがしやすくなったんじゃないかと思いますね。
■ミーティングを繰り返し、アルバイトも意見を聞かれることに慣れてきた
-- 研修では、ほかにどんなことをされたんですか? まずは、店長さんたちがミーティングの必要性を理解しなければ先に進みませんよね。

丸野:その通りです。
相崎:最初はみんな、「なんでここに呼ばれてるの?」という雰囲気でしたよね。自分ごととして捉えられるようになったのは、2度目の研修で各店の「サービスチーム力診断」の結果が返されてから、という人が多かったんじゃないかと思います。例えば「この店で働き続けたいですか?」という質問に対して2割くらいはネガティブな回答をしている人がいる、ということがわかるんですよ。
-- 丸野さんは、診断の結果を見てどう感じましたか。
丸野:「みんなこんなこと思ってるんだ……」と焦りましたね。僕がみんなに伝えたつもりでも、伝わっていないことがあるんだな、と。僕以外の店長も、「やばい、何とかしないと」と感じたと思いますよ。
-- なんとかするために、ミーティングのやり方を学ぼう、という気になったんですね。
丸野:そうですね。
相崎:診断結果を配って各店のレベルを客観的に振り返り、まずはミーティングのゴールを決めて事前準備をちゃんとしよう、というようなことから始めました。
研修後に実際に店でミーティングをやって次の研修でその結果を振り返る。それを繰り返して少しずつステップアップしていき、研修の後半では再度「サービスチーム力診断」をやって数値の変化を確認し、最終回で各店の取り組みの成果を発表しあいました。
-- 丸野さんも、研修が始まってすぐに店舗ミーティングを始めたんですか?
丸野:そうです。まずミーティングする日を決めるところから始めました。
-- シフト勤務のアルバイトでも、全員集まるんですか?
丸野:お客様満足度調査の結果が毎月20日頃に出るので、うちの店では20日以降の土曜日にミーティングをすると決めました。閉店後の12時半頃から朝2時くらいにかけてやるので、門限が厳しくて参加できない子もいます。そういうケースを除くと、その日にシフトに入っている子はだいたい参加してくれて、ミーティングだけ来る子も入れるとだいたい3分の1くらいは参加してますね。来られなかった場合でも、ミーティングで決まった方針や施策はひとりひとりに共有しているので、参加できるときに来てくれればいいと考えています。
-- 初めてやったときは、どうでしたか?
丸野:1回目は、とりあえずミーティングっぽいことをして終わった、という感じでした。2回目の研修で「サービスチーム力診断」の結果を見て「もっと巻き込まなきゃ」という意識になったのと、「話すより聴く」ということを教えられたのもそのときだったんですよ。そこで、2回目のミーティングからはバイトの子に意見を聞く、という形に変えました。
-- どういう風に聞いたんでしょう?
丸野:まずは会社のミッションや行動指針を説明して、「みんなこれを実現するために頑張るんだよ」という話をした後、売上を上げる具体策について意見を出してもらいました。
-- 意見を聞かれることに慣れていないバイトさんは、急に「考えて」と言われてもビックリしませんか?
丸野:最初は「えっ?」という感じがありましたね。「リキヤだったらどう思う?」「ミクはどうかな?」とか一人ひとりに聞くんですけど、僕も振り方が下手で、ぎこちない雰囲気でした(笑)。最近はみんなも慣れて、振られることがわかっているので、真剣に話を聞きながら自分の意見を考えてますよ。
店長研修もそういうやり方だったんです。相崎さんがずっと話をしているんじゃなくて、どんどん振られるから考えながら講義を聞かないといけない。そういうやり方に学びました。
■客数を増やすために”中ニ階”を作ろう!という意見が出てきて……
-- ミーティングをやるようになって、どんな変化がありましたか?
丸野:それまでは、社員が考えた施策をバイトに落とし込んで実行する、という考え方だったんですけど、バイトから意見を引き出して、その意見を反映させて売上を上げていく、という考え方にシフトしてきました。アルバイトの方も、みんなで売上を上げていこうという参加意識が高まってきたと思います。
-- どんな意見が出てきましたか?
丸野:具体的なアイデアが出てくるんですけど、すごい無理難題もあって……。
店の売上を上げるには、客数と客単価の2つを上げるしかないので、例えば「客数ってどうやったら増やせるか、どんなぶっ飛んだ意見でもいいから次のミーティングまでに考えてきてね」と宿題を出すんです。そうしたら、「”中二階”を作って座席そのものを増やせばいいんじゃないですか」みたいなことを言うんですよ。

相崎:それは無理難題だ(笑)。
丸野:ですよね(笑)。まずは「面白いね」と認めた上で「中二階って工事とか必要だから難しいかな〜。でも、座席を増やすっていうのはいいかもね」という感じで検討していきました。
実際、閉店する店舗からテーブルをもらってきて6席増やしたんですよ。ちょうど7〜8名の団体客が多かった時期だったので、もともと6人がけだったところにテーブルを追加して8名座れるようにしたりして。
-- 面白い! アイデアが活かされたんですね。
丸野:その後5ヶ月の客数をみると、前年同月比で3勝2敗というところです。全勝まで入っていないんですけど、「みんなの意見で店は変わっていくんだよ」ということを証明したかったんですよね。それで楽しみを感じてもらえばと。
■アルバイトの新鮮なアイデアは社員にとっても嬉しいもの
-- 今のエピソードはアルバイトの意見がうまく活かされた例ですが、経験豊富な社員が考えた方が早いし、的確だったりしませんか?
丸野:いや、同じ店で長く仕事をしていたら、新鮮なアイデアってなかなか出てこないんですよ。社員が最初から答えを持ってミーティングを始めることもありますけど、アルバイトがほかの角度から意見を出してくれることが多いです。
-- バイトさんに楽しいと思ってもらうためにポーズで意見を聞いているということではなく、店長や他の社員にとっても意味があるミーティングになっているわけですね。
丸野:そうです。
-- 「次のミーティングまでに考えてきてね」と宿題を出すのはすごくいいやり方ですよね。研修でそういう方法を習ったんですか?
丸野:いえ、飲食の経験が少ないアルバイトでもわかりやすくて楽しんでもらえるような投げかけの方法を考えたらこうなった、という感じです。今度のミーティングに向けては、「お客さんの5月病が吹き飛ぶようなぶっ飛んだ企画を考えてきてね」と言っています。(注:インタビューは4月に行いました)
-- 次はどんな宿題かな、と楽しみになりますね。この取り組みを始めて、アルバイトの定着率は向上しましたか?
丸野:辞める子はあまりいないです。僕が店長を引き継いだとき、1〜2人辞めました。長くやっていた店長が変わるとなると、何人か辞めるのは仕方ないと思うんです。ただ、それ以降は引っ越しだとかの理由以外で辞めたのは1人だけですね。それは僕だけの力ではなくて、他の社員の接し方なんかもあってのことですが。
相崎:リロードエッジ全体でみても、離職率は下がっています。それはミーティングの改善だけでなく、この何年かでいろいろな施策をしてきたことの積み上げによるものだと思います。
-- ミーティングをやるようになって、アルバイト同士の関係性には変化がありましたか?
丸野:ありますよ。僕がミーティングで議題にしていたのは売上を上げるということだったんですけど、このお店で一番長くバイトをしている子が「キッチンとホールの担当の間に壁がある」ということを課題に感じていて、その壁を取り払う施策を提案してくれました。それによって、ホールとキッチンが仲良くなったな、と感じます。
-- 店長が期待していた以上の課題解決が、アルバイト主導で進んだんですね。
スタッフの意見を引き出すことで参加意識や仕事の楽しさを感じてもらい、出てきたアイデアを業績の向上にも活かすーー。この取り組みは、飲食業に限らずさまざまな組織で参考にできると感じました。貴重なお話をありがとうございました。
(写真は全て筆者撮影)










