1977年、東京都生まれ。成城大学中退後、渡米。Bellevue Community Colleage卒業。「すべての若者が社会的所属を獲得し、働くと働き続けるを実現できる社会」を目指し、2004年NPO法人育て上げネット設立、現在に至る。内閣府、厚労省、文科省など委員歴任。著書に『NPOで働く』(東洋経済新報社)、『大卒だって無職になる』(エンターブレイン)、『若年無業者白書-その実態と社会経済構造分析』(バリューブックス)『無業社会-働くことができない若者たちの未来』(朝日新書)など。
関連リンク(外部サイト)
記事一覧
1〜25件/169件(新着順)
 夜の居場所を利用する若者たちの変化 392名への調査結果
夜の居場所を利用する若者たちの変化 392名への調査結果 4月1日から居場所を失ってしまう方へ
4月1日から居場所を失ってしまう方へ 生きることに迷った橋の上 男性が辿り着いた「とりあえず」
生きることに迷った橋の上 男性が辿り着いた「とりあえず」 高校中退者の4人に1人 別の高校への入学を希望
高校中退者の4人に1人 別の高校への入学を希望 ひきこもりの半数が女性、現場では
ひきこもりの半数が女性、現場では 4月1日から居場所を失ってしまう方へ
4月1日から居場所を失ってしまう方へ 変わり始めたKPI 就職一択支援からの脱却
変わり始めたKPI 就職一択支援からの脱却 家庭で否定されがちなゲーム 出会いのきっかけに
家庭で否定されがちなゲーム 出会いのきっかけに 夏休み明けの大学休学 「これからどうするの」の言葉を飲み込んだ母親
夏休み明けの大学休学 「これからどうするの」の言葉を飲み込んだ母親 若者たちは、今夜も帰らない
若者たちは、今夜も帰らない 働きづらい若者に「市民委員」という道を
働きづらい若者に「市民委員」という道を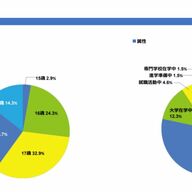 10代への現金給付 届け切るまで10回以上のコンタクトも
10代への現金給付 届け切るまで10回以上のコンタクトも 無業の若者 就活止まり、メンタル悪化
無業の若者 就活止まり、メンタル悪化 新しい夏休み 子どもには「さらっと、短く、何度でも」を大切に
新しい夏休み 子どもには「さらっと、短く、何度でも」を大切に キャッシュ・フォー・ワークの手法を活用して、就労支援を若者に
キャッシュ・フォー・ワークの手法を活用して、就労支援を若者に オンラインでの相談支援を阻む3つの不安
オンラインでの相談支援を阻む3つの不安 もうひとつの最前線 命を支えるNPOの葛藤
もうひとつの最前線 命を支えるNPOの葛藤 ひきこもり経験者に聞いた 自宅から出られない環境での生存戦略
ひきこもり経験者に聞いた 自宅から出られない環境での生存戦略 新型コロナウィルス ふたごを育てる292家庭の困りごと
新型コロナウィルス ふたごを育てる292家庭の困りごと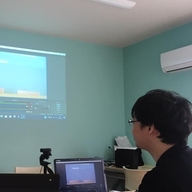 対人支援、迫られる支援モデルの変更 公設民営機関が考えなければいけないこと
対人支援、迫られる支援モデルの変更 公設民営機関が考えなければいけないこと 4月1日から社会的所属を失ってしまった方へ
4月1日から社会的所属を失ってしまった方へ 現役法務教官が口にした「少年院でこれほどコミュニケーションを重視した体育は見たことがない」の意味
現役法務教官が口にした「少年院でこれほどコミュニケーションを重視した体育は見たことがない」の意味 少年院経験者が語る 出院後の更生自立を阻むもの
少年院経験者が語る 出院後の更生自立を阻むもの 飲酒経験のある少年が9割以上、沖縄の少年院に学ぶ非行の現状
飲酒経験のある少年が9割以上、沖縄の少年院に学ぶ非行の現状 少年院に在院する少年たちに、投資家と起業家が語ったこと
少年院に在院する少年たちに、投資家と起業家が語ったこと





