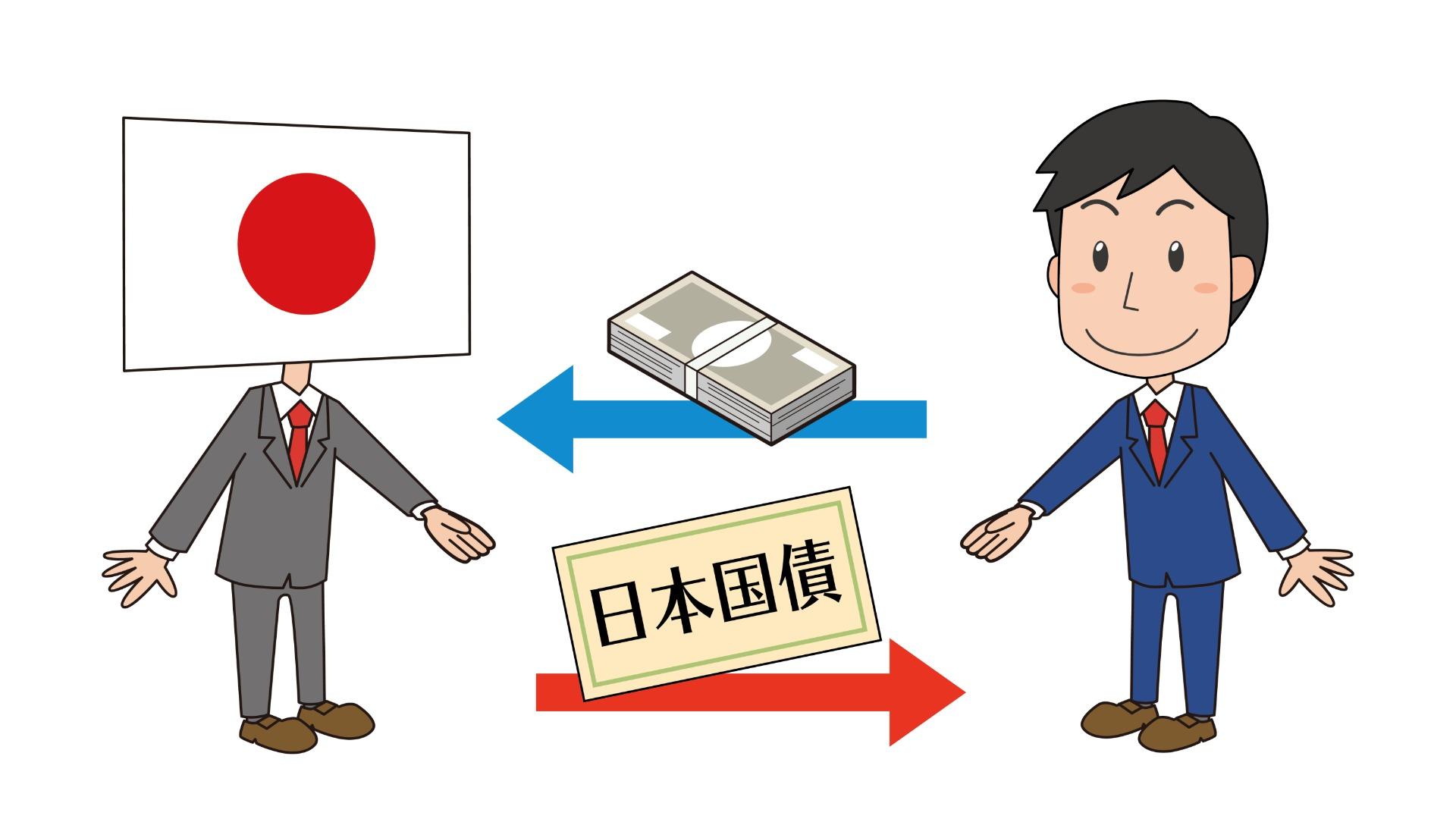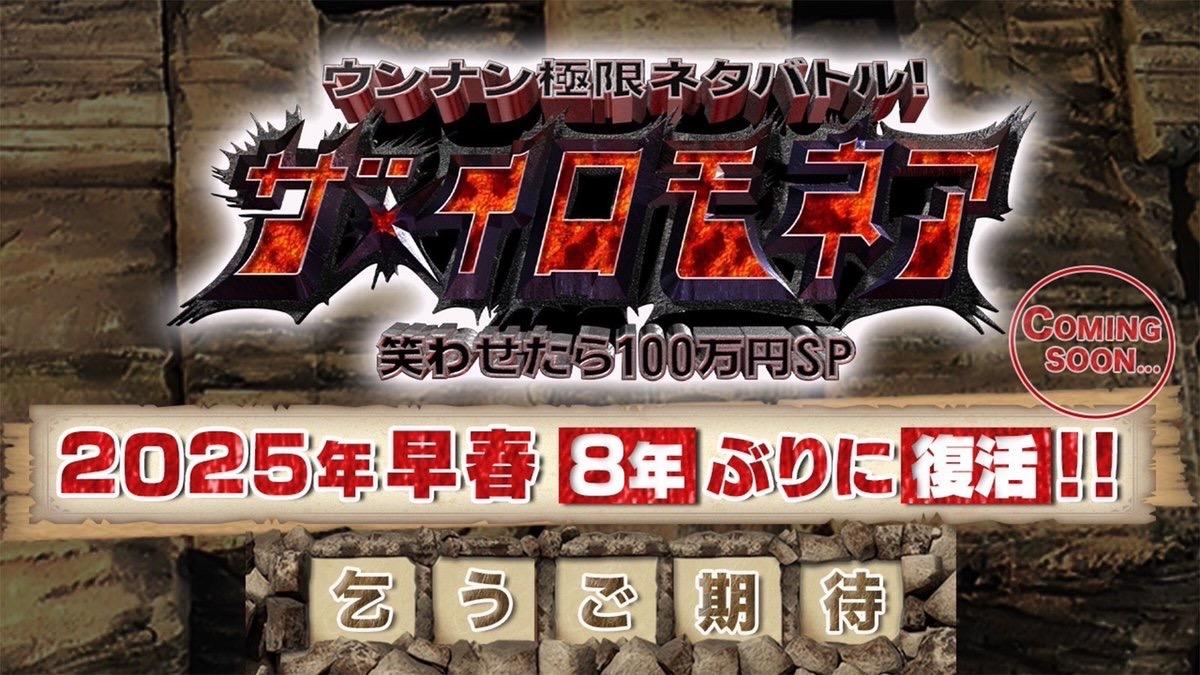ホテルは食品ロスを削減できるのか? 農林水産省との初めての意見交換会を通して得られた3つの気付き
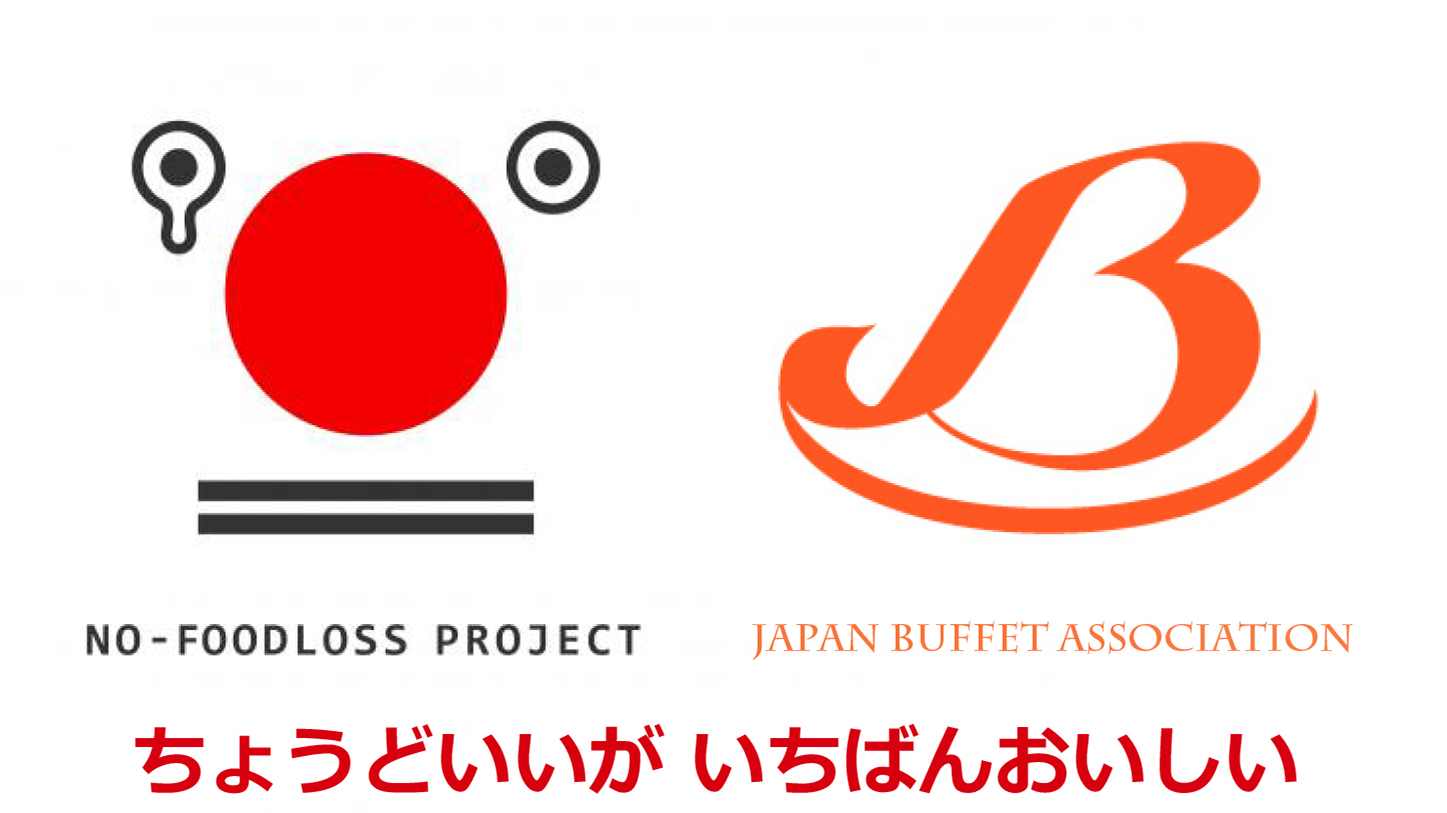
ホテルと農林水産省で意見交換会
プレスリリースでも配信されていますが、食品ロスの削減に向けて、大きな動きがありました。日本でほぼ初めて、ホテルと農林水産省が食品ロスに関する意見交換の場を持ったのです。
私が代表理事を務める一般社団法人 日本ブッフェ協会が主催して行われましたが、公共性がある取り組みなので紹介します。
背景

まず食品ロスに関して改めて説明しましょう。
まだ食べられるのに捨てられている食べ物は「食品ロス」と呼ばれており、日本では2014年度の食品廃棄物が621万トンにも上り、国民1人1日あたり約134グラムと、約お茶碗1杯分の食品ロスが発生しています。
この621万トンのうち家庭系食品廃棄物が282万トン、事業系食品廃棄物が339万トンになっています。事業系食品廃棄物では、42%を占める食品製造業の144万トンに続いて、35%を占める外食産業の120万トンが大きな比重を占めています。
日本ブッフェ協会は、外食産業が占める120万トンを少しでも削減できるように、ブッフェで提供されているものに対しては、ブッフェ本来の食べ方を周知することによって、食べ残しを減らしていきたいと考えています。
こういった流れの中で、日本ブッフェ協会に参加するホテルが農林水産省と話し合いの場を持つ機会がつくられました。
参加者

当日の参加者は以下の通り、14名が2時間もかけて率直な意見をぶつけ合いました。
農林水産省
- 河合亮子氏
農林水産省 食料産業局バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室 室長
- 鈴木健太氏
農林水産省 食料産業局バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室
- 松本健太氏
農林水産省 食料産業局バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室
日本ブッフェ協会
- 東龍
一般社団法人日本ブッフェ協会代表理事/グルメジャーナリスト
- 宮原謙一氏
一般社団法人日本ブッフェ協会理事/帝国ホテル東京/レストラン部次長
- 橋本良晶氏
一般社団法人日本ブッフェ協会監事/第一ホテル東京 副総支配人
- 内藤隆氏
一般社団法人日本ブッフェ協会理事/株式会社ESF 代表取締役社長
- 佃勇氏
一般社団法人日本ブッフェ協会 アドバイザリーボード/ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 副総料理長
- 秋浜鉄也氏
ザ・プリンスホテルさくらタワー東京・グランドプリンスホテル高輪・グランドプリンスホテル/料飲支配人
- 奥園恵美子氏
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ/支配人
- 窪田慎太郎氏
ハイアットリージェンシー東京/マーケティングコミュニケーションズマネージャー
- 清水敬氏
株式会社ニュー・オータニ/マネージメントサービス部
- 仁科勉氏
株式会社プリンスホテル/マーケティング部
- 後藤睦美氏
一般社団法人日本ブッフェ協会 事務局
意見交換内容

プレスリリースにはスペースの関係で「まとめ」しか掲載できませんでしたが、参加者それぞれの発言はこちらに掲載します。
食品ロス全般
まとめ
ホテルでは仕入れを効率化しているので、調理段階での食品ロスは少ない。ブッフェでも実演でサービスしているところは食品ロスを抑えられている。それぞれのホテルが食品ロス削減について考えているが、深刻な課題という捉え方ではない。
秋浜氏:廃棄は常にチェックしている。
仁科氏:CS(顧客満足度)を落とさないように、ポーションを調整するなり、ディスプレイを工夫するなりして、食品ロスの問題に取り組んでいる。
橋本氏:調理場での仕込み段階ではロスは少ない。宴会で多くの食品ロスが発生しており、1人が他の人の分も取ると全体的に食べ残し易くなる。大阪の系列ホテルでは、廃棄したものは肥料に再利用している。
窪田氏:シェフのおすすめを伝えたりしているが、食べ残しの問題はこれから取り組んでいくところ。
宮原氏:真空パックにして、小分けして使っているので、仕込み段階でロスは少ない。どれくらい食材が消費されるのか、ある程度は予測できている。ブッフェは自由度が高いので、メニューを組み易く、食品ロスにつながりにくい。バイキングコンシェルジュが案内して、おいしく食べられる工夫もしている。社内にグリーンチームがあり、食品リサイクル法に則ったエコサイクルを考えている。
佃氏:加工した適量の食材を仕入れており、実演でサービスして取り分けているので、食品ロスは少ない。ブッフェレストランの宴会プランでは、最初に盛り合わせを提供するようにしたら、食べ残しが減った。
奥園氏:農林水産省「ろすのん」と日本ブッフェ協会「ちょうどいいが いちばんおいしい」の製作物をテーブルに置いところ、よい活動だと好意的な反応をいただいている。仕切り皿も食べ残し削減に効果があった。
清水氏:ブッフェでは実演でサービスしているので、食品ロスが少ない。宴会でも調理スタッフとサービススタッフが相談しながら取り組んでいるので、食べ残しは多くない。
河合氏:ここに集まっている一流ホテルが発信していき、他のホテルに共有すれば、効果があるのではないか。
鈴木氏:日本語以外に、英語や中国語の製作物もあった方がよいのではないか。
ブッフェ台
まとめ
ブッフェ台に最後に残っているものは食品ロスとなってしまう。最後はブッフェ台にあまり残らないようにすることも可能だが、顧客満足度が低下する恐れが高いので難しい。客の意識も変えていく必要がある。
内藤氏:宴会の立食ブッフェでは食べ残しが多いのではないか。
奥園氏:食べる人と食べない人との差が激しいので、食べ残しは多くなってしまう。
河合氏:話に夢中になっていても、料理長からの説明があると再び食べることに集中できるのではないか。
仁科氏:幹事はブッフェ台が空になるのを好まないので、途中から前菜があった場所にデザートを置いたりして工夫している。
秋浜氏:ブッフェではコストが利益に関係するので、食品ロスを削減したいと考えている。しかし、宴会は売り切ってしまうので、食品ロスを削減しようという方向には、あまりならない。
宮原氏:宴会の食べ残しは、たくさん提供したいという日本人のおもてなしの心も影響しているのではないか。
橋本氏:中国でも同じ傾向が見られる。
窪田氏:ブッフェでは最後に料理がなくなっていると、口コミなどで料理がなかったと書かれてしまうのが悩ましい。時間が経過するにつれて、ブッフェ台の面積を小さくするなどアレンジしている。
仁科氏:終了時のブッフェ台は、開始時の3分の1程度の分量に調整している。売上に対して食品ロスは2%程度しかないので、ブッフェ台に残る分もランニングコストとして見込まれてしまっている側面がある。実演を行っていないと食品ロスはもっと多いのではないか。
橋本氏:ブッフェの規模によって、ブッフェ台での食品ロスの捉え方が違ってくる。
持ち帰り
まとめ
ホテルではリスクを考慮すると持ち帰りを承諾することは非常に難易度が高い。ただ、世の中の流れは変わってきており、持ち帰りたいという客の要望は高くなってきているので、何かしらの対応が求められてくるかも知れない。
秋浜氏:宴会やアラカルトで食べ残したものを持ち帰るのは、衛生ルールに則ると難しい。衛生面の管理は、昔よりもずっと厳しくなっている。ブッフェ台に一度提供したものは使い回すことはできない。一度提供してから2時間が経過したものも、衛生面を考えて廃棄している。
窪田氏:衛生面のレギュレーションでは、持ち帰りはできない。
奥園氏:持ち帰ると、全く管理できないので難しい。
河合氏:もしも持ち帰ったものを食べて問題が起きたとしても、しっかりと調査し、提供者に過失があった場合にのみ罰するようになっている。
宮原氏:食品ロスの目標値もだんだんと厳しくなっているので、何か手を打たなければならないと社内で議論している。
河合氏:事業系一般廃棄物を処理する値段は自治体によって異なる。値上げする傾向にあるので、一般廃棄物をできるだけ出さない方が、経営的にも好ましくなってくる。法律ではレストランで食べ残したものを持ち帰ることは禁止していない。特に宴会では、女性にデザートを持ち帰りたいという要望が多いので、何か対応できないか。
仁科氏:最近ではフランス料理店で最後の小菓子を袋に詰めて持ち帰らせてくれるところも増えている。ただ、持ち帰りを承諾するにしても、どこまでが持ち帰れるかという線引きは難しい。
意識
まとめ
食べ残し、食品ロスが課題であるという意識は高まってきている。ただ、経営的な観点からすると優先して取り組む問題とはなっていない。秋浜氏や鈴木氏が述べていたが、食品ロスの問題を、コスト削減やCS向上と絡めて考えていくと、ホテルでも取り組み易くなっていくと考えられる。
仁科氏:10年前であれば、ホテルは贅沢をする場所なので、食べ残して何が悪いのだという雰囲気もあったが、今は変わってきている。
秋浜氏:食品ロスの問題を解決することが重要であると認識してはいるが、残念ながら優先順位が高くなっているとは言えない。
清水氏:10年前にブッフェレストランをオープンする時から食品ロスの問題を考えていたので、バックスペースも整理した。
橋本氏:直営とフランチャイズとでは、取り組みや意識に少し温度差が感じられる。
奥園氏:ホテル館内全てのレストランでアンケートを取っているが、10月は3つのレストランで、食事の分量が多過ぎるという意見があった。今の時代はお客様も適量を望んでいるのではないか。
総論
私はブッフェ、および、ホテルレストランも専門にしていますが、改めて各ホテルが集まり、農林水産省と忌憚ない意見を交わしたことによって、いくつか大きな気付きがありました。
その中で重要となる3つのポイントについて言及します。
1つ目は、ホテルでは、コストや営業利益に直結するので、仕込みや調理の段階では食材をあまり無駄にしていないということです。ホテルには購買部があり、料飲部があり、調理部があることから、町場に比べればずっと組織化されています。流通から調理までしっかりと決められているホテルでは、食材が無駄になることがないように考えられています。
次に、ホテルで持ち帰りを承諾することは、私を含めた部外者が考えているよりも、はるかにハードルが高いということです。「それくらい持って帰ってよいのでは?」「何か起きても文句を言う客はいないよ」「持ち帰る人の自己責任だから」と思いがちですが、ホテルにはきっちりとしたレギュレーションが決められています。持ち帰った客が何かを訴えた場合、少しでも落ち度があれば極めて高い代償を払うことになりますし、例え全く落ち度がなかったとしても少なからぬ風評被害が発生します。経営的観点から述べるのであれば、そこまでのリスクを負ってまで、事業系一般廃棄物を削減する理由が見付かりません。
最後は、食品ロスの主因は食べ残しであるというです。そこには「お金を払ったのだから、食べ残してもいい」という客の理論武装、さらには、提供側の「足りないよりずっとよいのでは」という旧態依然とした考えがあります。
ブッフェに関して言及すれば、最初のセットアップ時の状態をクローズ時にまで維持しなければならないということが、食品ロスを生み出していることは確かでしょう。
日本人が本来備えていた素養

私はこれまで、食べ残しや食品ロスに関する記事を、以下のように書いてきました。
今回の意見交換会を通してでもそうですが、記事を書く度に、農林水産省が提唱する「食べものに、もったいないを、もういちど。」が訴える<食べ物に対する敬虔な気持ち>と、日本ブッフェ協会が考案したスローガン「ちょうどいいが いちばんおいしい」が揺り起こす<節度と謙虚さ>は共に、日本人に本来備わっていた素養ではなかったのかと考えさせられます。
しかし、ポジティブに鑑みれば、本来は日本人に備わっていたものであるのならば、これを取り戻しさえすれば、食品ロスの削減も進んでいくのではないか、それにはこのようにして発信していくことが重要であるのではないかと、私は思うのです。