【川上哲治と落合博満の超打撃論その4】「答えの出ないものを真剣に考え抜く醍醐味」
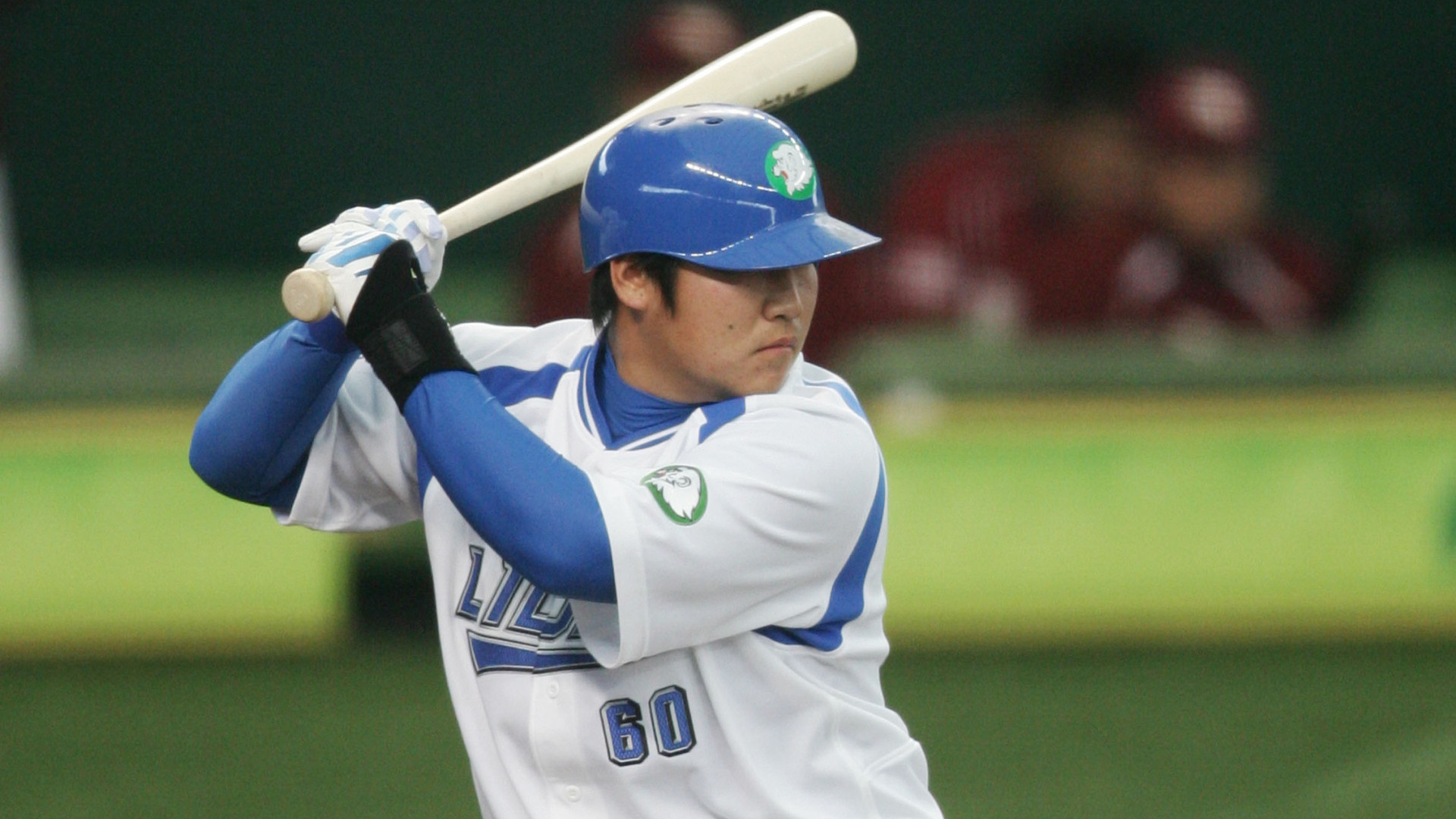
三冠王3度という栄光とともに“野球学者”に変身した落合博満は、対戦した投手の持ち球の特徴、捕手のリードの傾向などを一般的なセオリーの上に重ね合わせ、すべてのカウントにおける対処法を研究する。例えば、阪急のエース・山田久志に1ボール2ストライクと追い込まれたら、決め球のシンカーが外角をかすめるように曲がり落ちていく。それに対して上から潰すようにバットを出せば、打球は上がってアーチの軌道に乗る、といった具合だ。そして、ひたすらバットを振り込むというベーシックな技量を高めて実戦に臨む。
「基本的な球種、コースに対応できる技術が備われば、あとは最もボールに力があり、反対に打者にとっては最も対処し辛い内角高目のストレートへの対応を考えておけばいい」
この考え方に基づき、ネクスト・バッターズ・サークルから打席に向かう間にも自ら蓄えたデータに修正を加える。落合の分析は、投手がモーションを起こし、ボールがリリースされる瞬間まで続けられた。
「よく、決勝打を放った選手がお立ち台で『無心で打ちました』と言うでしょう。あれは本心なのかと、疑問に思った。私はバットを振る瞬間まで、色々なことを考えていた。いわゆる“欲の塊”だったから、決して無心になれたことはない。ただ、投手の指先からボールが離れてからの0コンマ何秒という時間では、長い間の鍛錬で培った反射的な身体の動きでボールを打ちにいっている。この間は頭で考えてはいないから、これを無心と呼ぶのなら私にも体験できたのかと思うけどね。
川上哲治さんの『ボールが止まって見えた』という言葉は有名だけど、あれは実際にあったことだと思う。私にとっては、どんなボールが来ても打てる、と言うよりは、自分の思い描いたようにボールが飛び込んで来るという状態が、年に何度かあった。苦手な投手との対戦で、普段は『ここへ投げ込まれたら苦しい』というようなボールでも、難なく弾き返せる。ヒッティング・ゾーンが広く、打ち損じが少ない。水道の蛇口から水を出して、細い口の瓶に入れようとすると、かなりの量の水が弾けてこぼれてしまうでしょう。あれが、打撃で言えば普通の状態。私の最高の状態は、瓶の口に広い漏斗をつけたようなもの。すべての水が、無駄なく確実に瓶に吸い込まれていく」
こうした状態も味方にして、落合は1985年に打率.367、52本塁打、146打点という圧倒的な成績で2度目の三冠王を手にすると、翌1986年も打率.360、50本塁打、116打点ですべて頂点に立つ。
見事に重なり合う川上と落合の歩んだ道
さて、ここまでの話を聞いて驚いたことがある。落合の歩んだ打撃王への道は、川上のそれに酷似しているのだ。天才だけで手にしてしまった初期のタイトル。その獲得後に、裏づけを求めて考え抜いた理想の打撃。そのプロセスでは、とにかくバットを振る、というシンプルな取り組みがベースになる。そして、超一流の領域へ――。
川上は、ボールが止まって見えるほど“無”になった状態、すなわちメンタルな部分から最高峰を征服した。一方の落合は、投げ込まれたボールをとらえるという動作を徹底的に解析し、それを自らの身体に染み込ませて実践する、すなわち理屈に基づいたフィジカルな面から同じ地点に立った。それでも落合が「極めていない」という心境は、川上の「極めてもその先がある。我々は打者の道の最後の関所、ここから先は超一流という道の通行手形を手にした」という言葉が代弁しているのではないだろうか。
落合は自らの野球人生を振り返り、また、これからの打撃人へのメッセージも込めて語る。
「私は、打撃フォームを少しずつ変化させながらやってきた。第三者の目ではわからなくても、技量や年齢が変わるに従って、それこそシーズン中でも形を変えた。それがよかったのか、それとも最初のフォームのまま通したほうがよかったのかはわからない。また、打撃というものは、もっとシンプルに考えられるのではないかと思う。プロ選手は、少年野球の指導ではいいスイングを簡単な言葉で教えられるのに、こと自分の打撃に関しては複雑に追求してしまう。だから打撃は難しいし、極めることなどないと感じている。ただ、答えの出ないものを真剣に考え抜く醍醐味はあるよね。それが私の仕事だったし、打撃技術のパズルで悩めば悩むほど、実は幸せなのかもしれない。
昔の選手は、“短くても太く”生きるのが美学だったと聞いた。私たちは、“太く、そして長く”生きたいと努力してきた。そして、昨今の選手たちは“長くするために細く”生きようとしているように感じられる。だから、簡単に休む選手が多くてひ弱な印象があるし、首脳陣のほうが選手に気を遣っているイメージもある。そんな状態では、これまでの偉大な先輩たちが打ち立ててきた記録を凌ぐことはおろか、近づくことさえ許されないでしょう。私は、誰が三冠王を獲るかという大きな希望を持って若い打者を見ていきたい。だからこそ、ひとりでも多くが“太く長く”を目指してプレーしてほしい」
野球について愛情をこめて饒舌に語る落合の眼差しは、投手に向かい合っていた時と同じ輝きを放っている。現役引退後も、左打者なら前田智徳、右打者では中村剛也の技術を高く評価し、最近でも山川穂高の打撃に注目している。現役を退いてどんなに時間が経っても、バットマンの道を歩み続けているようだ。
【川上哲治と落合博満の超打撃論その1】「ボールが止まって見えた」の真実










