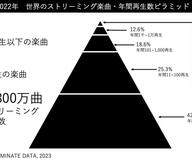宮崎駿が起こしたイノヴェーション 〜スティーブ・ジョブズの成長物語 ピクサー篇(9)

歴史は数々の天才たちの仕事が絡み合って出来上がっている。宮崎駿監督がアニメ産業に起こしたイノヴェーションは、ピクサーのラセター監督を目覚めさせ、巡り巡ってジョブズの復活、iPhoneの誕生、そして世界の音楽産業の再生にまで連なっていく───。
エンタメ産業そして人類の生活を変えたスティーブ・ジョブズの没後十周年を記念する集中連載、第十九弾。
■ジョン・ラセターと宮崎駿
二〇一四年、宮崎駿がアカデミー名誉賞を受賞した。日本人では黒澤明以来の快挙であり、アニメ監督としては史上初だった。この賞を得るともう他の賞は授与されなくなる、もしくは貰う意味がなくなるとすら言われている。映画界のノーベル賞といっていいかもしれない。
「アニメ史上、この芸術表現に誰よりも貢献した人物がふたりいます。ひとり目がウォルト・ディズニー。その次が宮崎駿さんです」
配給を担当したディズニー社を代表して、レッドカーペットの壇上に立ったジョン・ラセターCCO(チーフ・クリエイティヴ・オフィサー。当時)が献辞を並べるのを、宮崎駿は白い円卓で、こそばゆそうな笑顔をして聴いていた[1]。会場ではキャットムルも相棒のスピーチを聞いていた。ピクサーをジョブズと創業したキャットムルはディズニー・アニメーション・スタジオの社長となっていた。
ジョン・ラセターと宮崎駿。ふたりには言葉を超えた絆があった。
賞嫌いの宮崎がきらびやかなロサンゼルスの式場に出張ってきたのは、式中、喜びのあまりやたらとハグしてくるこの友人のためだった。若き日にディズニーをクビになったラセターは二〇〇六年、古巣のクリエイティヴの長に返り咲いていた。
ラセター監督は宮崎監督を「師匠」と呼び、宮崎はラセターを「恩人であり、無二の友人」と呼ぶ[1]。『千と千尋の神隠し』がディズニー配給となり、「世界の宮崎」が定着したのはラセターの尽力による。
授賞式のラセターは、世界が師匠を認めたのが嬉しくてしかたなかった。今ではすっかり恰幅のよくなったラセターだが、初めて会ったときはスリムだったと宮崎は笑う。宮崎も白髪ではなく、髭は剃っていた。
それは授賞式から三十三年をさかのぼった、一九八一年のことだった。
第二次ベビーブームも遠くなり、少子化に入った日本。まだ高齢化は始まっていなかったが、当時、音楽よりも低年齢層を相手にしていたアニメ業界は音楽業界に先駆けて、やがて来る国内市場の衰退に直面していた。
外需の開拓を余儀なくされたアニメ業界は本場アメリカへ挑戦に出ることになった。日米合作の大作アニメ『ニモ』(魚が主人公のあれではない)、その監督をまかされたのがまだ髪も黒く髭も剃っていた宮崎駿だった[2]。
彼らはアメリカ視察の一環でディズニー社にやってきた。そのときは若くて痩せていたラセターもまだディズニーをクビになってなかったのである。
幼少時、アメリカでも放映された手塚治虫の『鉄腕アトム』が大好きだったラセターは、日本から来たこのアニメ監督に興味津々だった。宮崎が挨拶代わりに置いていった『ルパン三世 カリオストロの城』のビデオテープを、彼はさっそく観たが冒頭から度肝を抜かれた。
うららかな緑の丘で、パンクしたフィアットを次元がジャッキアップしている。雲が影を落とし鳶が舞うなか、ルパンが「平和だねえ」と言いタバコを吹かす…。
このシーンは、ハリウッドではありえなかった。試写会で静かなシーンがあるとプロデューサーから「客がポップポーンを買いに行っちまうぞ!」と叱られる。それがラセターのいるアメリカの常識だったのだ。
だがこの静けさが、続くクラリス姫のカーチェイスを活かしている。のみならず静けさ自体が、何かを表しているような…。時を祝福しているような感覚にラセターは襲われたのだった[1]。
能を大成した世阿弥は「せぬ暇《ひま》がおもしろき」と言った。動きは種で、こころが花だと。動きのない間《ま》の余韻に、目に見えぬ何かが花開く。禅の「無」に通じる日本文化の基調だ。
禅や能を知らずとも、宮崎のテクニックを「間《ま》を置くというやつだ」とすぐ説明できるのは我々が日本人だからだろう。
衝撃は冒頭のみにとどまらなかった。『カリオストロ』を見終えた時、感動と悔しさが、ないまぜになって若きラセターを締めつけた。彼はディズニーのスタジオ中を走って、叫んでまわりたかった。
「な?な? 俺の言ったとおりだったろう? 大人だって楽しめるアニメは創れるんだ!」と[1]。
宮崎アニメは、ラセターの理想を先に実現していたのである。これこそディズニー社に勤めていた若き日々にみつけた、希望の方だった。
作家性。
大人をも魅せるには、めくるめくエンタメの隙間に見え隠れする作家性の深さがものをいう。深い作家性があれば、子供市場に閉じこもっていたアニメ産業は、大人をも相手にして一気に市場拡大できる。それこそ、停滞したアメリカのアニメ産業に必要なイノヴェーションだったのだ。
イノヴェーションの大家、経済学者シュンペーターの言うとおりだった。経済的動機ではない。宮崎のモノづくりの欲求が、世界に先駆けその革新を実現していた。
日本に行きたい。『カリオストロ』を観た若きラセターはそう思った。(続く)
■本稿は「音楽が未来を連れてくる」(DU BOOKS刊)の続編原稿をYahoo!ニュース 個人用に編集した記事となります。
関連記事:
失敗を繰り返した若き日のジョブズ ~スティーブ・ジョブズの成長物語~挫折篇(1)
iPhoneを予感していた29歳のジョブズ~iPhone誕生物語(1)
iPod誕生の裏側~スティーブ・ジョブズが世界の音楽産業にもたらしたもの(1)
[1] ジョン・ラセター、宮崎駿『ラセターさん、ありがとう』(2003) ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント
[2] 宮崎は後にこの映画の監督から降りた。