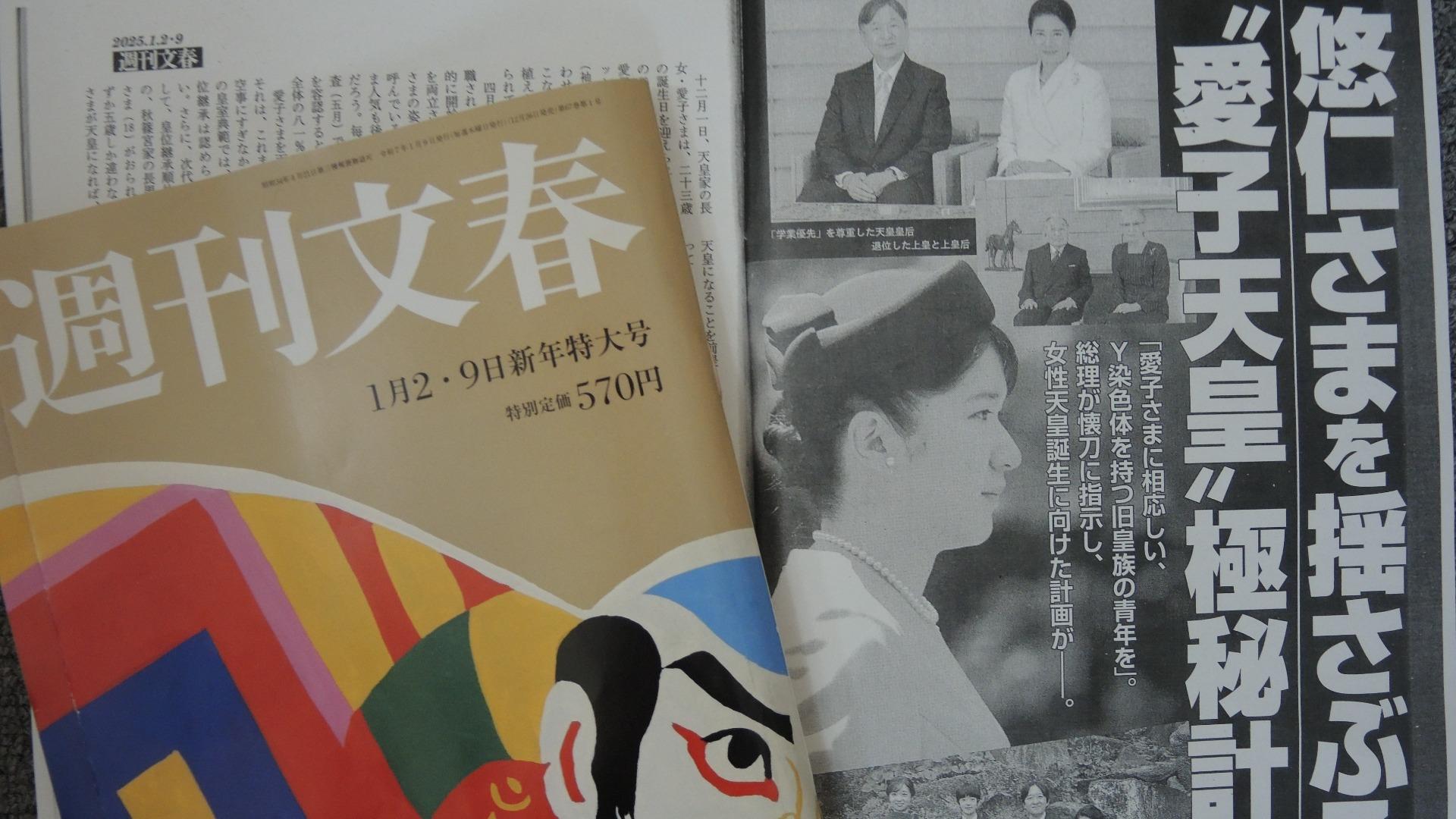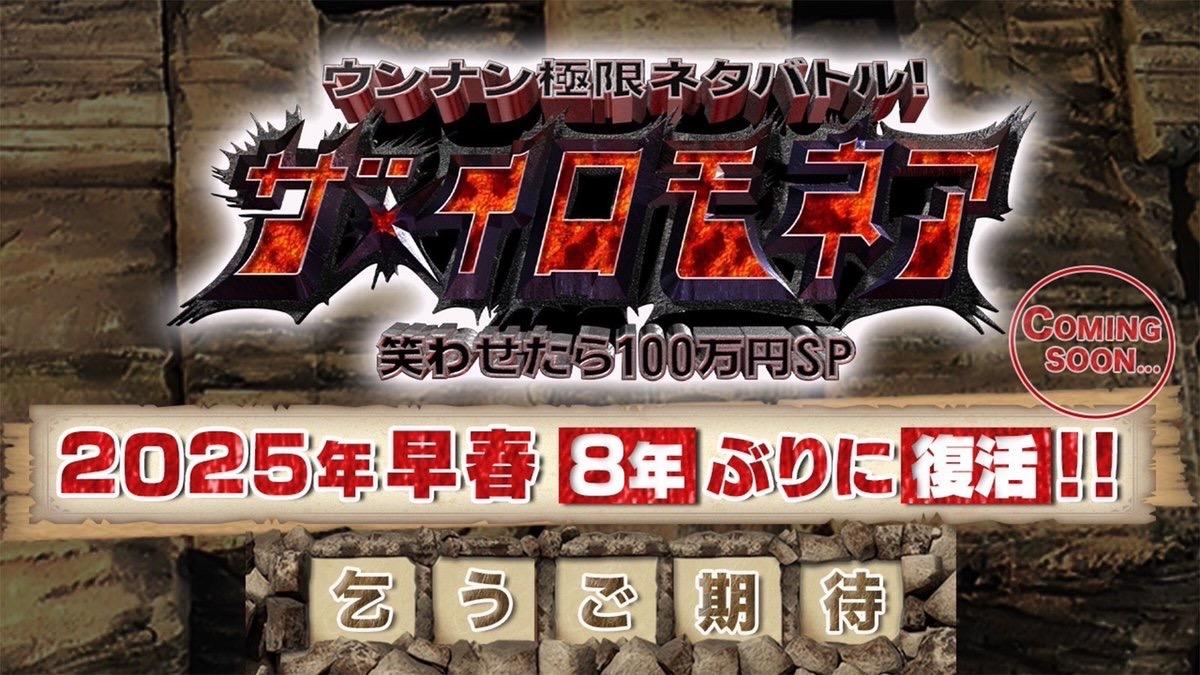岸田内閣不信任案否決の背後に見える自公連立再編を巡る岸田と麻生の戦い

フーテン老人世直し録(758)
水無月某日
東京都知事選挙の告示日、国会では立憲民主党が提出した岸田内閣不信任案に維新、国民民主党などが賛成し、自民党と公明党が反対して否決された。れいわ新選組は「野党第一党の戦っているふり、茶番には付き合えない」と声明を出して採決を棄権した。
れいわ新選組の指摘は全く正しい。この国会の最大テーマ「政治とカネ」について、立憲民主党をはじめとする野党は「戦うふり」を国民に見せるだけで本気で取り組まず、自民党が飲めない案を提出し数の力で押し切られることを望んでいた。
企業・団体献金や資金集めパーティの禁止を主張すれば、賛同しない自民党を「腐敗した政党」と批判することができる。しかしその主張が実現されることを野党も望んでいない。立憲民主党幹部が国会終了後にパーティ開催を予定していたことは、そうした事情を物語る。
野党が本気で岸田政権を退陣させる気なら、予算を成立させない戦いが必要だった。リクルート事件の直撃を受けた竹下総理は支持率が4%台になっても辞めなかった。野党は予算成立に抵抗して年度内成立を阻止したがそれでも辞めない。
しかし4月に入り、予算が執行されないため外務省が外国要人の来日を断り、「刑務所のメシが出なくなる」と言われた4月末、竹下総理は予算成立と引き換えに辞任を表明、6月初めに内閣総辞職した。権力を倒すにはそれだけの構えと力が必要である。
ところが立憲民主党の安住国対委員長は、政倫審で安倍派議員が弁明している最中に2月末の予算案衆院通過を黙認し、年度内成立を可能にした。それに野党は誰も異を唱えない。その時点でフーテンはこの国会が与野党なれ合いであることを確信した。
それからの野党は国民に向けたパフォーマンスの連続である。野党が企業・団体献金に反対するのは構わないが、しかし嘘を言うのだけはやめてもらいたい。国会で共産党の宮本徹議員は「先進国で企業・団体献金を禁止していないのは日本だけだ」と発言し、立憲民主党の長妻昭議員も「日本は規制が緩い国」と発言した。いずれも大嘘である。
以前ブログに書いたが孫斉庸立教大学准教授の研究によれば、OECD(経済開発機構)に加盟する先進38か国の中で、企業・団体献金を禁止している国は11か国、禁止していない国も同数の11か国ある。禁止しているのは韓国、フランス、米国などで、禁止していない国はスウェーデン、オーストラリア、ドイツなどである。
日本は企業・団体献金を政党には認めるが個人に認めていない。このように限定的な企業・団体献金を認める英国、イタリア、ニュージーランドなど12か国の中で日本は規制の厳しい方に分類されている。したがって世界の中で日本の政治資金規正法が緩いというのは間違いだ。
今回の安倍派の裏金問題は、政治資金規正法が緩いから起きたのではなく、それとは異なる背景があるようにフーテンには思えた。裏金を終わらせるには誰がいつから何の目的で裏金の仕組みを作ったのか、その解明から始めて裏金の深層に迫る必要がある。
ところが秋の総裁選をにらむ岸田総理は仕組みを作ったと思われる森元総理を守る姿勢に徹し、与党も野党も森氏の国会喚問に熱心にならない。そしてどうすれば政治資金の透明性を確保できるかを考えようともしなかった。
もっともらしい作り話も流布された。企業・団体献金を認めればそれによって癒着が起き政策がゆがめられるというのだ。例えば財界の献金によって法人税は軽減され、また原発をやめないのも献金があるからだという。
フーテンに言わせれば、法人税の軽減も原発維持も米国の要求である。米国に防衛を委ねている日本政府は従うしかない。問題にすべきは米国の要求を拒否できないこの国の従属体制だ。バブル経済に誘導されたのもデフレ経済に誘導されたのも米国の要求を拒否できないためだった。その従属体制を隠蔽するため献金の話に絡めた作り話が流布されるのである。
また企業・団体献金は利益誘導型政治を生むという批判もあった。米国政治を見てきたフーテンはその批判を不思議に思う。そもそも民主主義政治の基本は利益誘導である。国民は自分に利益を与えてくれる候補者に投票し国会に送り出す。選ばれた議員は選んでくれた有権者のために働く。
米国には企業や団体から依頼され法律を成立させるために政治家に働きかけるロビイストという職業がある。公に認められた職業で陰の仕事ではない。それを取り締まれば、利益誘導は非公然活動化し、国民から見えなくなる。
米国では献金を多く集める候補者こそ政治家にふさわしいと考えられている。だから候補者は献金額をすべて公表し裏金にしない。要するにこの問題は、制約を課さないで表に出させるか、制約を課して裏の世界に潜らせるかという問題だ。野党が主張する企業・団体献金やパーティを禁止しても別の仕組みが生まれ、裏金がなくなることはないとフーテンは考える。
官僚が権力を握り政治家を操る日本では、制約を課して政治家を抑える仕組みにすることが官僚にとっては都合が良い。だから政治資金の規制が強化され、その結果、資金が裏の世界に潜る。国会ではそれで良いのかという議論をして欲しかったが、国民が「政治とカネ」に目の色を変えるので誰もそれを言い出せない。そういう国会だったと思う。
ところで冒頭でれいわ新選組の声明を紹介したが、昨年の通常国会では同じことを維新の馬場代表が言って不信任案に反対した。国民民主党の玉木代表も不信任案に反対した。それが今年は維新も国民民主党も賛成に回った。
その背景を考えると、自民党の麻生副総裁と茂木幹事長が岸田総理と対立色を強めた事情が見えてくる。つまり自公連立の再編問題が「政治とカネ」を巡る国会審議の後ろで燃え上がっていたのである。
自民党と公明党の連立は1999年以来だから、民主党政権誕生で下野した3年余りを除き20年以上の実績がある。「福祉と平和の党」を標榜する公明党は政策的に自民党と水と油の関係だが、自民党のブレーキ役を果たす存在として影響力を保持してきた。
自民党にとって創価学会という全国組織をバックに持つ公明党との選挙協力は、政権を維持するために必要不可欠の仕組みである。それがなければあっという間に政権から転落する恐れがある。しかし協力関係も20年を超えると軋みが生じてくる。
次の衆議院選挙から適用される10増10減の選挙区割りを巡り、去年5月に公明党幹事長が「東京における自公の信頼関係は地に落ちた」と発言するなど、一時は選挙協力を解消するところまで関係は悪化した。8月に岸田総理が山口代表と会談して協力関係をようやく修復する一幕があった。
しかしその後も麻生副総裁が、一昨年の「敵基地攻撃能力」の保有を含む安保3文書の与党協議で公明党が慎重姿勢を示したことを批判し、公明党を「がん」と酷評した。麻生氏には憲法改正や武器輸出を実現するため公明党を連立から外したい思惑がある。
この記事は有料です。
「田中良紹のフーテン老人世直し録」のバックナンバーをお申し込みください。
「田中良紹のフーテン老人世直し録」のバックナンバー 2024年6月
税込550円(記事5本)
2024年6月号の有料記事一覧
※すでに購入済みの方はログインしてください。