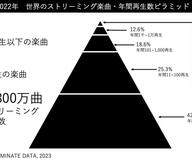ディズニーも苦しんだイノヴェーションのジレンマ 〜スティーブ・ジョブズの成長物語 ピクサー篇(7)

イノヴェーションのジレンマは近年、日本の家電産業、世界の音楽産業も苦しんだ致死率の高い難病だ。Appleもそれで倒産しそうになった。そしてジョブズはこのジレンマを何度も乗り越えてみせたゆえに史上最強の経営者と呼ばれるようになった。
が、彼が初めてそれを成し遂げることになったのはコンピュータ産業においてではなく、その鍵をもたらしたのはアニメおたく上がりのアーティスト、ラセター監督だった───。
音楽産業、エンタメ産業のみならず人類の生活を変えたスティーブ・ジョブズ没後十周年を記念した集中連載、第十七弾。
■天才創業者の死後。イノヴェーションのジレンマ
ハリウッドの丘の麓。
椰子の並木道、屋敷、世界の六大映画スタジオが、カリフォルニアの陽を浴びて佇んでいる。音楽産業が売上を十倍しても届かぬ、映画産業の本拠地だ。
なかでも元祖「アニメの聖地」、ディズニー・アニメーション・スタジオは人気スポットだ。入場門から見えるスタジオはミッキーマウスの青いとんがり帽子をかぶり、魔法をかけたように観客を集めている。
今ではディズニー社はたった一社で、世界の音楽産業の全売上を軽く超える。
だが、ラセターの働いていた一九八〇年前後は、売上低迷でスタジオに重い空気が淀んでいた。ウォルト・ディズニーが没して十五余年。天才創業者を失ったディズニー社は売上のみならず株価も凋落した。何かを変えなければいけなかった。だが、創業者が偉大なあまり、過去の成功モデルにしがみついていた。
天才の死後、会社は彼の残してくれた大切なファン層を、なんとしても守らなくてはいけなかった。「ウォルトによれば…」が上層部の口癖になっていた[1]。「ウォルトならどんな作品を創っただろう?」
それがマンネリを招き、ルーカスやスピルバーグ等々、勢いのある新人監督に次々と客を奪われていった。しかしディズニー色を離れたら、既存のファン層も失ってしまう…。クリステンセン教授の言う、典型的なイノヴェーションのジレンマに嵌っていたのである。
選択と集中だ、という人間もいた。赤字部門に転落したアニメ・スタジオを閉鎖し、ディズニーランドだけで稼げばいい、と。が、それは「アルバムを作っても儲からないならライヴだけやればいい」とミュージシャンに説教するような愚見だった。
ウォルトはディズニーランドを「永遠に未完の作品」と呼んでいた。新作アニメがなく「完成」してしまった先には、ディズニーランドは没落が待っているだけだったのだ。
管理職に臆病が蔓延していた。何も新しいことができない。ディズニーに憧れて入社した若手は押しつぶされそうになっていた。「心が引き裂かれそうだった」とラセターは振り返る。「あれは、僕が思い描いていたディズニーじゃなかった」[2]
そんな停滞の最中にあって、ディズニー社がCG映画『トロン』を手掛けたのは、大きな賭けだったのだろう。
主人公がコンピュータ・ゲームのなかに閉じ込められ、脱出を図る。CGを駆使した映像と大人向けのストーリーは、既存のディズニー作品とかけ離れていた。
『トロン』の監督はそのストーリーを、伝説のアーケードゲームPong《ポング》で遊んでいるときに得たという。大学を中退したジョブズはこのゲームに惚れ込んで、アタリ社に入社。「盛りだくさんよりもシンプルが受ける」という、後のAppleに通じる哲学をこのゲームから学んだという。
『トロン』のCGシーンは、当時の技術的限界でたった十五分に限られていた。が、パイロット版の映像を観たラセターは身震いが止まらなかった。
「ウォルトが待っていたのはこれだぜ」
彼は振り返って同僚に言ったという[3]。まるで亡きディズニーが後ろにいるかのように。
■テクノロジーと超一流アーティストの関係

中世の西洋画をいま見ると子供が描いたように見える。顔が平坦で、背景も乏しく、感情表現も貧しい。ルネサンスの絵画はこの点、技術的に進化した。
ダヴィンチの絵は、光と影を巧みに使うことで人物像は奥行きを持ち、こころの深淵までも表現した。彼は持ち前の科学的センスをアートに導入した。遠近法と陰影法を集大成したダヴィンチは、美に新たな時代をもたらすことになった。
アナログのセル画からデジタルのCGへの進化はルネサンス時代、絵画の世界に起きた2Dから3Dへの転換に似ている。
「テクノロジーはアートを刺激し、アートはテクノロジーを挑発するんだ」
のちに成功したラセターは口癖のようにそう言うようになったが、初めてCGに触れた彼の驚きは、世の新しもの好きが新技術に驚くのとは質が異なっていた。ルネッサンス級のなにかを彼の精神は直覚したのだろう。彼はむしろ技術の方に刺激を与えるほどのアーティストへと成長していくことになる。
映画産業は音楽産業と同じ父を持つ。ふたりとも科学者エジソンの子供といえる。この頃、音楽産業でもアナログからデジタルへの転換が起きようとしていた。
一九八〇年代初頭、音楽産業はディズニーと同じく、売上が三分の二となる深刻な不景気に喘いでいた。そんな中、音楽アーティスト出身のある日本人企業家が世界の音楽産業を変えた。
Sonyミュージックの創業者にして、後にSony本社の社長ともなる大賀典雄のことである。彼の導いたCD革命は、世界の音楽産業に空前の黄金時代をもたらした。
大賀のCD革命は当初、レコードにこだわる世界中のメジャーレーベルから猛反対を受けたと書いたが、ソニー社内でも反対が無かったわけでもない。というよりSony創業者、井深大その人が反デジタルの筆頭だった。だが井深は、大賀たちが情熱を燃やす姿を見るうち、いつしか「がんばれ、競争相手のフィリップスに負けるな」と応援するように変わっていったという。
もしアナログ世代のウォルト・ディズニーが生きていたら、彼もはじめCGに反対したかもしれない。が、ラセターらの情熱を見るうちに応援する側に回ったのではないか。井深とディズニーからは同じ匂いがする。
ウォルト・ディズニーもまた、最先端の技術を貪欲なまでに取り入れたアーティストだった。
映画と音楽の融合をもたらしたトーキー。ゼログラフィー、クロマキー、マルチプレーンカメラ等々。最新技術でこの芸術形式の表現を広げ、アニメ産業の礎をこの星に築き上げた。
執筆中の現在も、VRの普及などで映像技術に革新が進みつつあり、ディズニーやラセターのように、VRを大衆芸術の域に導ける映像アーティストが待望される。
かつて音楽ビデオの誕生が新たな映像の才を発掘し、それがデジタル化とともにやってきた音楽の黄金時代を助けることになった。
映画産業に訪れたデジタル化の話に戻ろう。映画『トロン』の発表と前後して、ディズニー社はジョージ・ルーカスのスタジオへ視察団を手向けた。その一団には、アロハシャツのジョン・ラセターが交じりこんでいたのだった。
彼は興味津々だった。なにせ『スターウォーズ』の続編、エピソードⅤはそこかしこにCGが取り入れられていた。できることなら、ルーカスフィルムのCG集団と一緒に仕事をしてみたかった。
後にピクサーの創業者となる物静かな男、キャットムルがスタジオで待っていた。(続く)
■本稿は「音楽が未来を連れてくる」(DU BOOKS刊)の続編原稿をYahoo!ニュース 個人用に編集した記事となります。
関連記事:
失敗を繰り返した若き日のジョブズ ~スティーブ・ジョブズの成長物語~挫折篇(1)
iPhoneを予感していた29歳のジョブズ~iPhone誕生物語(1)
iPod誕生の裏側~スティーブ・ジョブズが世界の音楽産業にもたらしたもの(1)
[1] ディヴィッド・A・プライス著 櫻井祐子訳『メイキング・オブ・ピクサー』(2011)早川書房 第3章 p.80
[2] 同上 第3章 p.81
[3] 同上 第3章 p.83