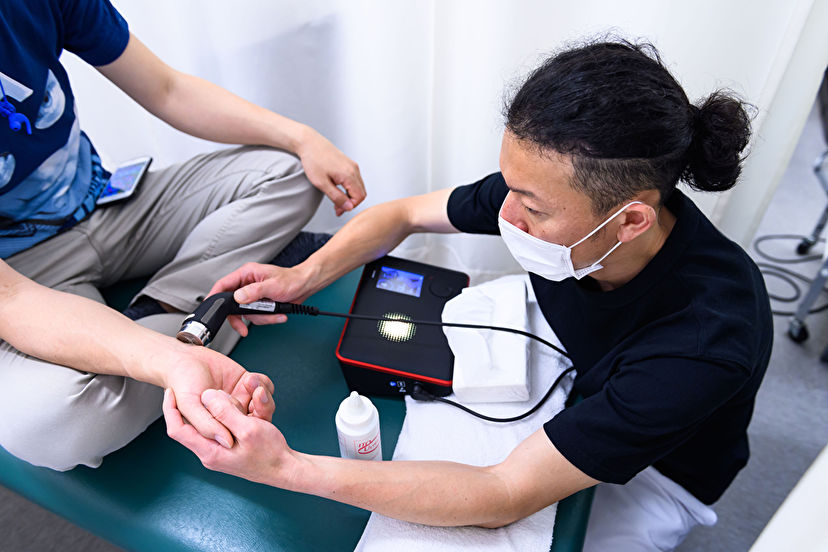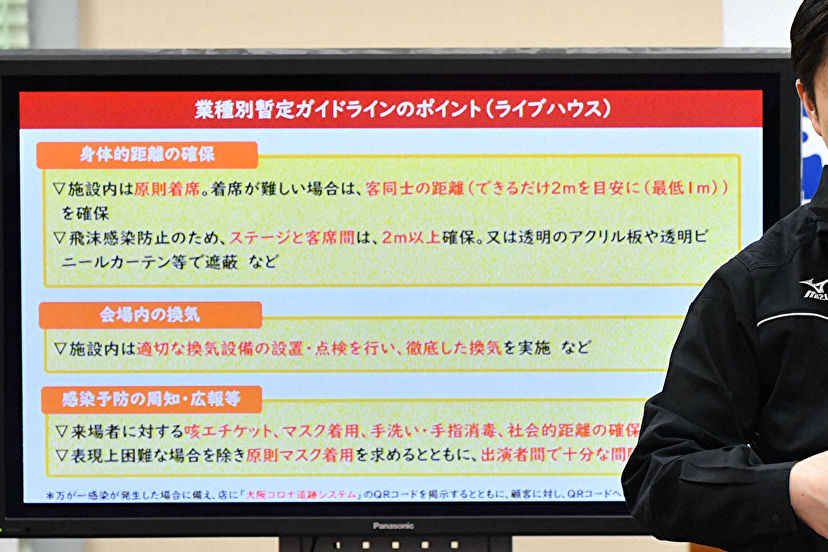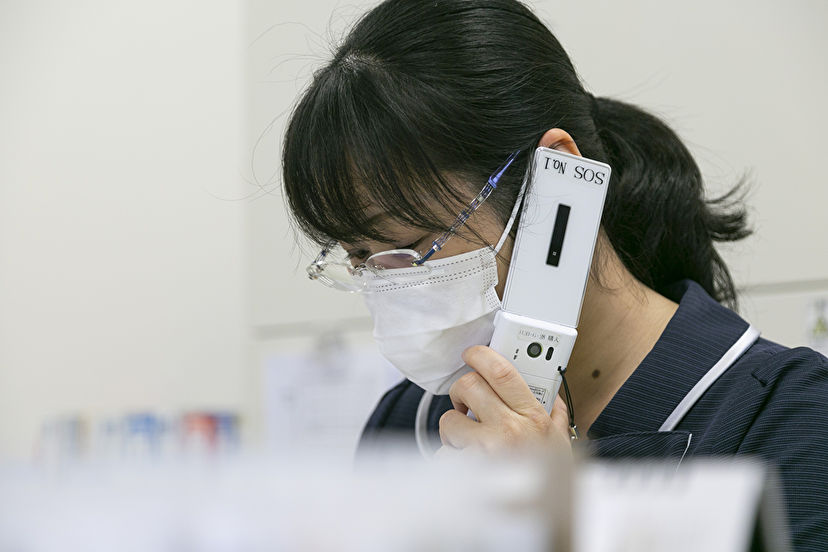初めての一人旅は高校1年生の春休み、国鉄の切符を手に周遊した東北地方だったという作家・沢木耕太郎。それから半世紀以上、さまざまな国々を旅して回ってきた彼は、新型コロナウイルスで世界への門扉が閉ざされる今、何を思うのか。沢木が語る「コロナ禍」「東京五輪2020」、そして「旅と人生」。(取材・文:山野井春絵/撮影:殿村誠士/Yahoo!ニュース 特集編集部)
(文中敬称略、本記事の取材は今年6月に実施)
想像し得ないことが起こるのは当たり前
80年代・90年代のバックパッカーブームを後押しし、日本中の若者を旅へと駆り立てた沢木耕太郎の『深夜特急』(新潮文庫・全6巻)。主人公「私」の一人語りで綴られる、アジア、中東、ヨーロッパの旅は、いつ読み返しても新鮮なときめきを与えてくれる。
沢木は現在72歳。一貫してメディア出演を控えているというが、すらりとした体躯に背筋の姿勢の伸びた姿勢、精悍なまなざしは、旅に生きる作家のイメージそのまま。はじめに、この春のステイホーム期間はどのように過ごしていたのか尋ねた。
「とても規則正しい生活ですよ。朝は6時に起床したら、顔を洗って、白湯を一杯飲みながら原稿を書き始め、9時に朝食。そこから10時に仕事場へ行き、14時くらいには自分でクッキングをして昼食をとる。食べながら欧米のニュースダイジェストを見て、15時から18時までまた仕事。帰宅したら、19時に夕食。21時くらいから音楽を聴いたりしながら、少し調べものなんかをする。この3月以前から、ずっと同じ作業を繰り返していました。そこに、『旅』がなかったというだけ。日常は、何も変わらなかったですね」

変わらない日常を過ごしながら、世界中に広がるコロナ禍のニュースを眺めていたという沢木。20代の頃から世界を股にかけたハードな旅を経験してきた彼に、新型コロナウイルスはどう映ったのだろうか。
「語弊があるかもしれませんが、ごくごくシンプルに、大したことではないんじゃないかなと思う。僕たちのように高齢だったり、もともとハンディを抱えている人が肺炎になったら重症化するのは、実は当たり前のことですよね。仮に僕が、この新型ウイルスにかかってしまい、重症化して死ぬことがあったとしても、それは病気に『縁』があっただけだと思うわけです。もちろん、罹患を避ける努力や、人に何か迷惑をかけないように心がけるのは大切なことだと思うけれども、生活のすべてを変えようという気には全然ならない。それでも、もしかかってしまったとしたら、ちょっと予定よりは早いかもしれないけど、70代までは生きることができたし、人生を十分楽しませてもらったんだから、何の文句もありません。だから、何か世界はすべて変わって生き方を変えなければ、というような話になると……そういう人がいたって構わないけど……、僕はタイプが違う、それだけのことかなと思います」
熱心な『深夜特急』ファンなら、お気づきだろう。この流行り病についての考え方は、すでに『深夜特急』で表明されている。当時、天然痘が流行していたインドから、パキスタン国境の街へとバスで移動するシーン。
** インドを歩いているうちに、ある種の諦観のようなものができていた。たとえば、その天然痘にしたところで、いくらインド全土で何十万、何百万の人が罹っているといっても、残りの五億人は罹っていないのだ。そうであるなら、インドをただ歩いているにすぎない私が感染したとすれば、それはその病気によほど「縁」があったと思うより仕方がない。ブッダガヤで何日か過ごすうちに、私はそんなふうに考えるようになった。
(略)
そのうちに、私にも単なる諦めとは違う妙な度胸がついてきた。天然痘ばかりでなく、コレラやペストといった流行り病がいくら猖獗(しょうけつ)を窮め、たとえ何十万人が死んだとしても、それ以上の数の人間が生まれてくる。そうやって、何千年もの間インドの人々は暮らしてきたのだ。この土地に足を踏み入れた以上、私にしたところで、その何十万人のうちのひとりにならないとも限らない。だがしかし、その時はその病気に「縁」があったと思うべきなのだ。(『深夜特急4 シルクロード』より)**

ニューノーマル。新しい生活様式。ポストコロナ社会。もはや世界は、これまで通りではない。……毎日そんな論調が世に溢れるが、沢木には少しのブレもない。
「若いうちにやっておいたほうがいいことに、『旅』と『スポーツ』があると思っています。それはどちらも、『思いがけないことが起きる』から。例えばサッカーならば、90分間の中で、瞬間瞬間にどう対応するかということを常に問われるわけです。そうすると、それに対応する能力が身についてくる。旅もそう。思いがけないようなことが起こるんだけど、『思いがけないことが起きる』ことを予想することは可能なわけです。大事なことは、それにどう対応するか、ですよね」
人生もまた、思いがけないことが起きるもの。今回のコロナ禍も、同じことだと沢木は言う。
「こういう想像し得ないことが起こるのは当たり前で、自分がそこにどう対応するかを決めていくだけだと思う。世界や人生が変わっちゃうとか、それほど大騒ぎするほどのことなのかな? 僕の場合は、高齢というリスク要因を抱えていることになるし、場合によっては死ぬこともあるだろうけど、その時はその時。『それで何か問題がありますか?』と自分に問えば、何もないと答えるだけです」
今回の東京五輪には「大義」が見えなかった
アトランタ五輪を題材にした著作『冠』でも知られ、数多くのスポーツ取材を重ねてきた沢木。「東京2020五輪」については、どう見ているのだろうか。「昨年末の段階では、取材もしない、原稿も書かないことに決めていた」が、この春になって、思いが変化してきたという。
「もともと東京オリンピックを取材して書いてほしいという依頼をいくつか受けていました。でも考えた揚げ句、昨年末にすべて断った。この東京オリンピックには大義がないと感じたからです。そもそも東京で開催する意味があるのかどうか……。オリンピックというものは、自国で開催したいという国民の強い欲求とともに、他国の人たちもその国での開催に納得し、喜んでくれることが必要条件だろうと思います。1964年の東京オリンピックは、戦後の再建のお披露目のようなものを、世界の多くの人たちが割と温かい目で見てくれていたと思います。しかし、2020年の東京オリンピックは……積極的に肯定する人たちは少ないんじゃないでしょうか」
「復興五輪」というまやかし。コンパクトでエコロジカルにといいながら、総額3兆円とも言われる費用がはじき出された東京五輪は、まったく無意味だ、と沢木。
「たった一つ意味らしきものがあったとすれば、1964年を知らない若い人たちが、オリンピックを自国開催するという経験、それだけでしょうね。今度のオリンピックについて祝福するという気持ちを持てない僕が、参加する必要はないんじゃないかと思った。だから断ったんです。ところが、だよ」

コロナ禍の影響で、東京五輪は1年延期となった。このニュースが、沢木の意識を変える。
「コロナとの戦いに終わりはないのかもしれませんが、中休みというか、いったん緩やかな休戦か終戦があるとして、そうした中でのオリンピックというのは、世界の人たちにとって、意義のあるものになり得るんじゃないか、と思ったんです。古代ギリシャのオリンピックというのはそういうものでした。それはどの国でやってもいい。もちろん日本で開催したって構わないわけで、コロナとの戦いに疲れた世界の人々の束の間の休息、あるいは『祝祭』を、みんなで味わおうというオリンピックが開催されるならば、僕も参加したい。そう思うようになりました」
しかし現実的には、来年の開催も難しいだろう、と沢木は冷静だ。
「コロナウイルスのローテーションは、まだまだわからない。来年になれば大丈夫と楽観視することはできませんよね。だからせめて、2年後がいいと思いました。オリンピックには初期の頃、『中間年大会』というものが存在していました。第1回の開催国であるギリシャが、毎回アテネでやりたいというので、一度だけ、本大会と本大会の間に、アテネで『中間年大会』というものが開催されています。ギリシャの経済状態が悪くなって、2回目以降は開催されませんでしたが……。そういう歴史的な前例もあるわけだから、2年延期論ならば賛成だった」
人生の未来予想図は、今も昔もない
「僕は『こうなりたい』というような思いを持たないタイプの人間です。今、目の前にある仕事をやってきただけで、自分の生き方、方向性なんて考えたこともなかったし、今もないです。ライフワークとして書きたいというものもない。これは面白そうだからやってみようかなっていうことは常にあるけれども、ごくごく近い距離のことしか考えずに生きてきたような気がします。だから、さっきの話に戻ると、例えば明日、新型コロナウイルスに感染して重症化して、1週間後に死んでしまっても、1年先にやりたいということもないから、構わないわけ、全然。自分の好きなことだけをやってきたので、『ここで終わり』って言われても、神さまに不平は言わないっていうことなんです」

こんな書き手になりたい、こういう仕事がしたいと思うことは、なかった。
「やりたいことだけをやってきたらこうなったっていう、それだけの話だから。だけれども、それを貫くためには、リスクがある。ちょっと偉そうなことを言うようだけど、力が必要だと思う。やりたいことだけをやって生きるには、やっぱりこちらの力量が必要だし、場合によっては、相手を納得させる話術だったり、政治力も必要になる。僕は、基本的には、ほとんどの仕事の依頼を断ってきました。でも、どんな内容なのかは確認するようにはしていました。まれに、何千個に一つくらい、自分にとって『おっ』と思うことが起きるからです。そういう偶然に対しては、なるべく柔軟でいたい。自分のやりたいことを通す頑なさと、その柔らかさを併せ持って、僕である、という感じがします」
遠い先の目標を持たず、目の前だけを見ながら生きてきたという沢木が、人生の中で魅せられたのが、長距離の移動を伴う「旅」だった。作家として、一人の人間として、沢木耕太郎にとって、旅とは何か。
「ちょっとかっこよく言えば『途上にあること』、要するにプロセスですよね。行く先のどこか、何かが目的なのではなくて、どこかに行くまでが『旅』。だと思う。僕にとっての旅は、やっぱりプロセスを楽しむものなんだよね。結果的にたどり着けなかったとしても、問題ないんです。行かれなかったっということがあっても、下世話な言い方をすると、『それは面白いじゃないか、ネタになるじゃん』と(笑)」
「たとえばケープタウンに行ってみたいということは、一瞬で決められることでしょう。そこまで行くのに3年かかろうが、目標を決めること自体には1秒かからない。そこへ行くこと、やりたいと思う仕事に何年もかかってしまうようなことは、もちろんあり得ます。僕は5年ほど続けている作業があるんだけど、それはやりたいことが5年経っても終わらないというだけの話です。それが少しずつ積み重なって、今ここに僕がいる、ということかもしれない」

一方で、若い人に対して、「旅をすべきだ」という物言いはしたくない。沢木は著書で何度もそう書いてきた。国内旅エッセーをまとめた近著『旅のつばくろ』(新潮社)にもこうある。
日本の若者たちが外国旅行をしなくなったと言われて久しい。
それもあって、私のような者にまで、もっと外国を旅せよという「檄」を飛ばしてもらえないかといった依頼が届くようになった。
だが、申し訳ないけれどと、そうした依頼はすべて断ることにしている。
ひとつには、私も若いとき、年長者の偉そうな「叱咤」や「激励」が鬱陶しいものと思えていた。だから、自分が齢を取っても、絶対に若者たちに対するメッセージなどを発しないようにしようと心に決めたということがある。(『旅のつばくろ』より)
「若い人がどうとかっていう物言いはしないようにしてきましたし、それはこれからも変わりません。ただ、すごく気になっているのは、みんながこの状況を過度に恐れすぎていること。周囲の目もあるだろうし、罹患に対する恐れもあるのかもしれないけど」
沢木は『深夜特急』の後書きで、これから旅をしようと思う若者への餞(はなむけ)として「恐れずに、しかし気をつけて」というメッセージを記している。まずは恐れることなく旅に出ればいい、ただし注意は怠るな、と。
「今、僕が感じているのは逆です。注意深くある必要はあっても、そんなに恐れる必要はないんじゃないかな。今ならこう書きますね、『気をつけて、しかし恐れずに』」
沢木耕太郎(さわき・こうたろう)
1947年東京都生まれ。横浜国立大学経済学部卒業後、ほどなくルポライターとして出発し、鮮烈な感性と斬新な文体で注目を集める。1979年『テロルの決算』で大宅壮一ノンフィクション賞、1982年に『一瞬の夏』で新田次郎文学賞を受賞。その後も『深夜特急』や『檀』などを次々に発表し、2006年『凍』で講談社ノンフィクション賞、2014年に『キャパの十字架』で司馬遼太郎賞を受賞。近年は長編小説『波の音が消えるまで』『春に散る』を刊行。今年4月、緊急事態宣言下の発売となった国内旅エッセー『旅のつばくろ』(新潮社)が話題に。