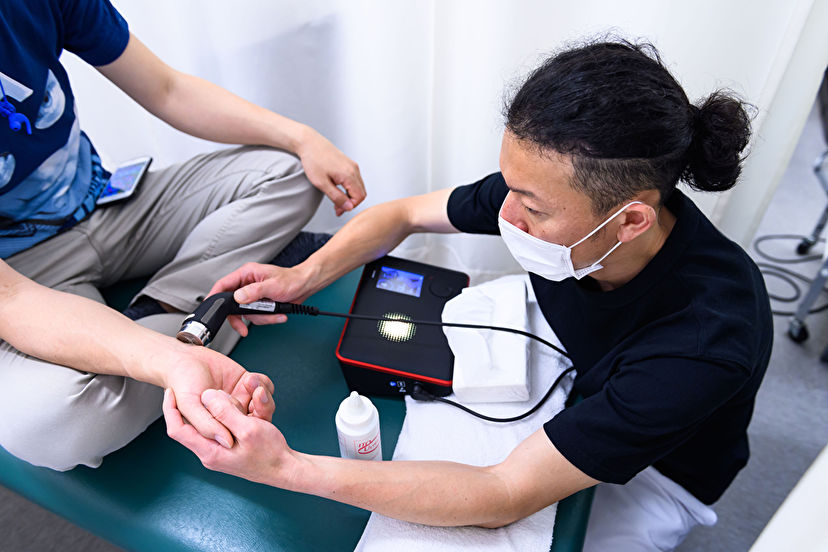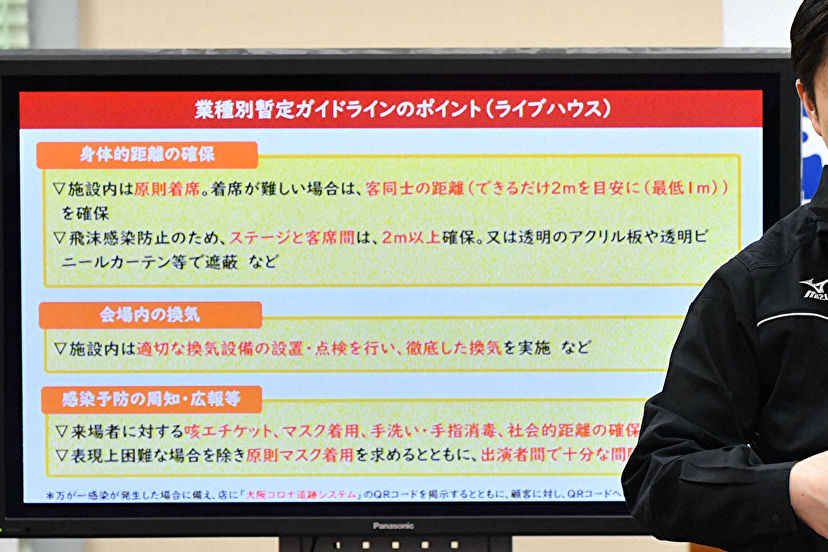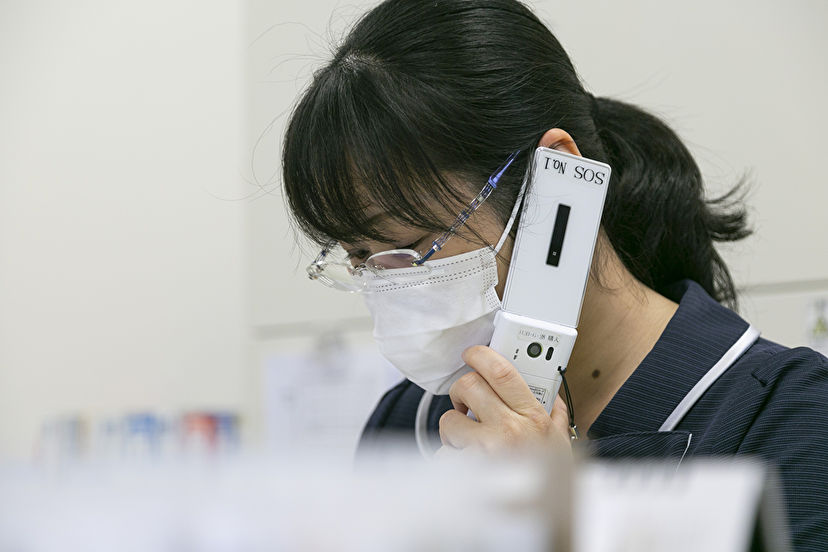「格差社会や自己責任論ではいよいよ立ち行かない」。新型コロナウイルスの感染拡大が、社会の仕組みや制度、習慣に世界的規模で影響を及ぼしている。コロナ禍のいまをどう生き抜くか、これからの社会をどう生きるか。社会のあり方や人々のコミュニケーションについて多くの作品を書いてきた作家の平野啓一郎さんに聞いた。(取材・文:内田正樹/Yahoo!ニュース 特集編集部)
平野啓一郎(ひらの・けいいちろう) 1975年、愛知県生まれ。京都大学法学部卒業。1999年、『日蝕』で芥川賞を受賞。小説『決壊』『ドーン』『かたちだけの愛』『空白を満たしなさい』『マチネの終わりに』『ある男』、エッセー『私とは何か 「個人」から「分人」へ』『「カッコいい」とは何か』など、著書多数(撮影:編集部)
解消されない不安とどう向き合うか
――新型コロナウイルスの影響が長引いています。いま置かれている状況をどう捉えていますか。
東日本大震災のときと似ていますが、心情的な違いとしては国内外に「逃げ場がない」ということでしょうか。束の間でも、苦労を忘れさせてくれる別の場所や支援体勢に入れる地域があるだけでかなり違うと思います。今回は移動が制限されていて、誰かの手助けをしたくても、ボランティアにも行けない。
僕は普段からあまり落ち込まないほうですが、新型コロナにかかった方々の体験記を立て続けに読んでいたら具合が悪くなってきて、しばらく読むのをやめました。そのとき、音楽鑑賞や読書がずいぶんと心の安定につながりました。体調を見ながら、そうした時間も設けたほうがいい。
――音楽や演劇など、芸術・文化への深刻な影響も懸念されています。
「芸術とは何のためにあるのか?」「大して役に立たない」と言う人もいますが、いまほど、多くの人々が熱烈に「コンサートに行きたい」と言っている瞬間もないでしょう。芸術・文化が社会に不可欠だと骨身に染みている。守らなければいけないし、そのための補償を、政府は責任を持ってするべきです。
僕は、コロナ明けに行く生のコンサートは、どんな音楽でも泣く自信があります。1曲目から最後まで泣き続けているかもしれない。演奏家も泣いていると思う。いま想像しただけで涙ぐんでしまう。

東京・銀座。人も車も少ない(撮影:中野敬久)
――平野さんは「分人」という視点から数々の著作を書かれています。「分人」とは、「人には、対人関係の数だけ、そこに合わせた自分の個性が存在する」という概念ですが、コロナ禍が対人関係に及ぼす影響についてはどうお考えですか?
僕は人間が自由に生きるバランスにおいて、分人の構成と比率のコントロールが重要だと考えています。好きな分人を生きる時間が相対的に長く、不愉快な分人を生きる時間が短くて済むという構成が理想的な状態です。でも、自宅待機で分人を限定されてしまうとストレスが増えていく。
仕事相手といるときの自分。友達と接する自分。いろいろな自分を同時に生きているからこそ、家族との自分が楽しい。他の分人を生きられないことで満たされない欲求や欲望の全てを家族に満たしてもらおうとすると、相手にとって興味のない話に付き合わせてしまうとか、つい無理な要求をして、互いに強くストレスを抱えてしまう恐れがあります。
いまは大人から子どもまでストレスを抱えています。幸い、ネットが蟄居生活の中にも脱出口を作ってくれていますから、Zoomなどでのやりとりで、物理的には対面できなくなった人との分人を上手く維持する必要があると思います。案外、住まいは遠くても好きな人との関係が近くなる時期かもしれません。
口論になったときや意見が合わないときは、無理に言葉で修復しようとしても悪化してしまう可能性がある。少し距離を置いて、互いにクールダウンしてもいいのでは? いらいらしたまま話し続けても事態は悪いほうにしか進まない。不安というものは、いくら気休めを言われたところで根源から解消されないかぎりはなくならない。政府の対応や会見にしても、「お気持ち」なんか話されたって仕方がない。

東京・渋谷(撮影:中野敬久)
窮状は言葉でちゃんと伝えるべき
――有事における内閣のリーダーシップも問われています。
誰がどういう責任で対策や指示を担っているのか、指揮系統が見えてこない。中長期的な展望を提示することもなく、直近の2週間ぐらいのことばかりを語っている。もっと具体的なシナリオを話してくれたらまだ納得もできるのですが、「国民を信頼している」とか「みんなで頑張って」と言うのは、結局、「全て自力で何とかしろ」と言っているようなもの。そういう意味で、安倍首相のメッセージの発し方は非常に悪い。自分の発する言葉がどういう効果を生むのか、もっと考えるべきでしょう。
現状をどこまでも正確に伝えて、いくつかのシミュレーションを立てて、何をどれだけ成功させれば、どれほどの経済的なダメージで抑えられるのかなど、きちんとリスクの段階を可視化して、国民に要請を伝えなければ。官邸の意向やさじ加減一つみたいな状況は極めて不安だし、権力の乱用も危惧されます。国民は声を上げるべきで、その効果も出ていますが、支持率対策で政策が動揺するという懸念もあります。

休業中の百貨店(撮影:中野敬久)
――給付金の支給や全世帯への布マスク配布など、政策に対する疑問や批判、要望も多々上がっています。
政府に対して、感情的に怒ることも必要だと思います。「生きるか死ぬか」という窮状が政府に伝わらないときは、強い言葉で訴えるしかない。当然でしょう。権力者に対して「批判をするな」というのは、民主主義国家として間違っていると思います。おかしな政策を批判するのも国民の当然の権利です。代案も必要です。自分たちの国なんですから。政府を批判する人を無責任と言う人もいるけれど、ただ見ていることのどこが責任ある態度なんですか。
――自分の訴えを言葉で強く伝えるためには、どうすればよいのでしょうか?
短い言葉よりも、ある程度まとまった長さの文章で訴えるほうが効果的だと思います。Twitterの140文字で伝えられる思いは限られるし、その中で強い気持ちを表そうとすると、どうしても「バカ」とか「ふざけるな」といった短い常套句になりがちです。それも数が集まれば力になるのかもしれませんが、本当に人の心を動かすのは、十分に検討された、まとまった長さの文章だと思います。
政治家への直接的な訴えもあるでしょうし、マスメディアへの寄稿があり、SNSやブログがある。2016年の「保育園落ちた日本死ね!!!」というブログのように、シェアされていくなかで有意義な影響力を持つケースもあります。

来訪者の減った夜の街(撮影:中野敬久)
コロナが収束したら終わりじゃない
――コロナ後の社会をどう生きればいいのでしょうか?
かなり長期にわたってトラウマを引きずるはずです。傷を癒やすためには、2020年代が丸々費やされるかもしれない。今後そうしたテーマの文学や芸術もさらに増えるでしょう。「生活が変わる」という事実を受け入れて、いかに生きていくか。そのための具体的な解決策のヒントを手に入れるためにも、本や芸術、文化は必要不可欠です。
――新潮社によると、1947年にフランスの作家アルベール・カミュが発表した小説「ペスト」の文庫版は2月以降に15万4000部増刷され、累計発行部数が100万部を超えました(2020年4月現在)。
最近あらためて読んだのは鴨長明の『方丈記』です。火事・竜巻・飢饉・地震という不幸のオンパレードで人が死に続け、結局は「社会の安定を目指さない」という、近年提唱されてきた「持続可能な社会」とは正反対の認識に達している。その結論に全て同意というわけではなく、隠遁でよいのか、ということも含めて、災害が頻発する時代の日本で生きることを考えるうえで、興味深い一冊だと思います。

(撮影:中野敬久)
――私たちが過去の経験から学べることとは?
1990年代以降、世界は10年ぐらいの単位で激変を迎えてきた。まず80年代末から90年代初頭にかけては東西冷戦の終結と、日本でもバブル景気の崩壊があった。ゼロ年代は9・11とともに始まって、インターネットが広く浸透していった。2008年のリーマン・ショック後、10年代は3・11が起こって、その後遺症がやっぱり10年近く続いた。いま、ここで地震とか、何かもう一つ来られると本当に困るけれど、この先の10年間は、もう「新型コロナの時代」なんだと腹をくくるしかない。
国連の安全保障理事会では世界の紛争の停戦も議論されています。第1次世界大戦の終結もスペイン風邪の影響が大きかった。人間同士が戦争や紛争で殺し合う余裕さえなくなってきたし、「自分さえよければ」という生き方では、最終的には社会が壊れてしまう。もう格差社会や自己責任論ではいよいよ立ち行かないと思う。世界がいい方向に進むようなビジョンを一人ひとりが持つべきです。ディストピアが来るか、「悲惨だったけど少しはよくなったこともある」となるか、いまはその瀬戸際ではないでしょうか。

(撮影:中野敬久)
――いまを生き抜くために、どんな心構えを持つべきでしょうか?
これはコロナが収束したら終わりという話じゃない。地球温暖化の問題もあるし、日本だって夏は猛暑で秋は大きな台風も来る。もしかすると今後の「日常」とは、非常事態と非常事態の間で、ちょっと息継ぎするぐらいの時間となるのかもしれません。非常時には非常時なりの生活が持続できるよう準備しておかないと、ウイルスのたびにこんな大打撃を受けていたら、ちょっと持たない。
かつて戦争を体験した世代のかたは「生きていくために必死で何でもやった」と話されていましたが、ここから1、2年は本当に腹をくくって、焼け野原に立つような気持ちで「生き残ってやる」という意志を強く持つことも大事だと思います。やらない理由、できない理由を山ほど持ち出して、意欲的な取り組みを潰すのは、もう止めるべきです。
あくまで政府には補償を求めますが、その前提で、例えば自分の能力を何でも収入源にするような“才能のメルカリ化”だとか、VR(仮想現実)のようなテクノロジーやクリエイティブなアイデアを駆使する試みを決して馬鹿にせず、少しでも楽しみながら取り組むべきだと思います。いつか、「もう、コロナのときは何でもやってどうにか食いつないだね」と語り合うためにも。
内田正樹(うちだ・まさき)
1971年生まれ。東京都出身。編集者、ライター。雑誌『SWITCH』編集長を経て、2011年からフリーランス。国内外のアーティストへのインタビューや、ファッションページのディレクション、コラム執筆などに携わる。