常識への挑戦が真の価値を生む W+K Tokyoジョン・ロウ氏/埼玉大学准教授 宇田川元一氏の対話

米オレゴン州ポートランドで創業し、現在は世界8ヶ所に展開するグローバルなクリエイティブ・エージェンシー(広告の企画・制作を生業とする会社)であるWieden+Kennedy (以下W+K)。前回は、広告会社としては珍しいゆとりのある働き方や、その背景にある同社のモットーなどを紹介した。
今回は、W+K Tokyoのマネージング・ディレクター ジョン・ロウ氏へのインタビューをお届けする。聞き手は宇田川元一氏(埼玉大学大学院 人文社会科学研究科 准教授)。イノベーションを生み出す新しい組織像を研究する、今注目の経営学者だ。
目先の利益ではなく、永続的な価値を作り出すことにベストをつくす
宇田川:今の広告業界はどんな問題を抱えていると思いますか? それに対してW+Kではどんなアプローチをとっているのでしょうか?
ロウ:この業界の最大の問題は、コモディティ化だと思います。特に日本の企業は、ブランドの構築に関してあまり意識を払わず、とにかく低コストでたくさんの広告を出すことに注力しているという傾向があります。差別化を図らないクリエイティブ・エージェンシーは淘汰されてしまうでしょう。W+Kとしては、クリエイティブのクオリティによって差別化をしています。私たちも、サービスの幅をもう少し拡げることを考えないわけではありませんが、クライアントのブランドを構築し、永続的な価値を出していくことを大切にしたいので、それを犠牲にしてまで利益を追うことは考えていません。
宇田川:ブランドを構築し、永続的な価値を出していくというのは、具体的にはどういうことでしょう。
ロウ:私が初めて担当したクライアントは、米テキサス州の10億ドル規模のカーディラーチェーンの会社でした。その社長に教わったのは、1台の車を売ろうとするんじゃない、顧客の生涯に渡る車のビジネスをするんだ、ということです。目の前の1台を売ることに注力しすぎると、全体像が見えなくなってしまうのです。現在の広告業界では、今の売上を最大化しよう、この商品が売れればいい、という傾向があります。でも我々としては、もっと長い意味でのビジネスに貢献したいと考えているのです。
多くの会社が短期的な目標や収益ばかりにとらわれている状況を、アムステルダムのオフィスにいる私の同僚は「麻薬中毒のようなものだ」と言っています。短期的には快楽が得られるけれど、長期的には非常に有害なものだということです。長生きするため、長期的な価値を得るためには、中毒から抜け出さなければいけません。
宇田川:すごく共感します。色々なところである種の依存症というものが起きていますよね。
ロウ:存症症になってしまうのは、短期的な利益を示すたくさんのデータがあまりにも簡単に手に入るからですね。データを集めて、それに意味付けをし、報告するというやり方が日常化されていて、経営層もそういったデータの裏付けがありさえすれば安心するという図式ができています。「以前にこういうやり方でこういう成功を収めました」というデータさえあれば、みんな納得する。だからどんどん中毒になってしまうのです。
宇田川:依存症は孤独から生じる、とよく言われます。例えば、家庭内で孤独を感じていて、その辛さを解決するためにお酒を飲んでしまうとか。同じようなことが、今の日本のビジネスの世界でも起きているのでしょう。W+Kはそれをどうやって避けているのでしょう。クライアントの孤独に寄り添うようなアプローチが取られているのではないかと思うのですが?
ロウ:我々が大事にしているのは、クライアントのボイス(Voice:内なる声、思い)を明確にすることです。この考え方が生まれたのは、W+Kの最初のクライアントであるナイキとの仕事を通じてです。ナイキも最初はまだ始まったばかりの会社でしたから、我々は一緒にブランドのボイスを考えてきました。コカ・コーラや資生堂のように、すでに深い歴史のある会社と仕事をする場合は、歴史を遡り、自分たちをどう表現してきたのか、変わらないもの、変わってしまったものは何か……、といったことを明らかにしていき、そのブランドのボイスを明確にしていくのです。


全く新しいものを作り出すため、失敗を恐れない環境を作る
宇田川:クライアントに提供しているものと会社のカルチャーとのつながりについてお聞きしたいと思います。通常、広告というのはモノを売るためのものと考えられていますが、W+Kではそうではないんですね。「良い企業とその顧客との間に“強く刺激的な関係(Strong Provocative Relationships)”をつくる」という経営理念を掲げていらっしゃいます。このことと、皆さんのモットーである”Fail Harder”というのは強く結びついているのでは? つまり、当たり前であることに対して”Provocative(挑戦的・刺激的)”であれ、ということですよね。
ロウ:まず、”Fail Harder”という言葉が生まれた経緯をお話しましょう。これは1980年代なかばに創業者のダン・ワイデンが言い出したことです。若いコピーライターが、入社して3ヶ月くらい経っても何も書いてくれなかったので、ダンが「どうしたんだ?」と聞いたそうです。すると彼女は、周囲の期待をプレッシャーに感じ、みんなを失望させたり失敗するのを怖がっていました。ダンは、「ここに来たすべての人達が、人生の中でベストな仕事をできる環境を作りたい」という理想を持っていました。だから若いクリエイターが失敗を恐れて力を発揮できない状況を危惧し、「心配しないで。3回くらい失敗して見せるまでは、僕を満足させられると思うなよ」と言って励ましたと伝えられています。
私たちが恐れなければいけないのは、失敗することよりもインパクトのないものを出してしまうことです。そのため、これまでの成功体験にとらわれず、今まであったものよりも更に良いものを作ろう、という高い目標を掲げています。失敗への恐れがあると、過去に見たことがあるもの、馴染みのあるものに流れてしまいがちなので、そうならないためにも、ハードルを高く上げた上で、失敗しても大丈夫、という環境を作ることが大事なのです。
宇田川:なるほど。
ロウ:次に“Provocative”に関してですが、印象的なものを作るには、深いレベルでの人間的な理解や繋がりが重要です。“Provocative”と言っても単にショッキングで派手な広告を作ろうということではなく、見る人にインパクトがあって心に残る関係性を結ぼうということです。涙を流したり、笑ったり、共感したり……、エモーショナルなレベルで結びついた記憶はなくならないものですから。クライアントに対しても儀礼的で表面的なビジネスしかしていなければ忘れられやすい。だからクライアントとも、“Provocative”な関係性を持つことが重要です。
宇田川:お話を伺っていて、既存の常識に挑戦していくこと、つまり“「失敗すること」に失敗しない“のが大切なのではないかと感じました。
ロウ:ビジネスの外の世界では、失敗から学ぶのが普通ですよね。アスリートの世界でも、科学の世界でも、失敗は成功の元だと言われています。ですが、ビジネスにおいては失敗が許されにくい。だから似たようなものが量産されるのだと思います。特に日本のマーケティングにおいては、みんなが拠り所にする確固たる常識があるんです。例えばシューズを売るときにはこういうやり方、ビールを売る時はこう、コスメならこう――、今までそれで成功したからそれでいきましょう、というわけです。ですが、そのやり方は他のブランドもやっているわけで、今までのやり方を踏襲しても、消費者はどちらを選べばよいかわかりませんよね。差別化のためには、全く新しいやり方が必要なのです。
宇田川:上司の評価を気にするあまり失敗を恐れてしまうということもあると思いますが、評価の制度で何か工夫しているところはありますか?
ロウ:評価シートに”Fail Harder”という項目はありませんが、例えばその人のアイデアが1年に1度も採用されなかったとしても、いつも斬新なアイデアを出していることを高く評価する、ということはありえます。

突然のオフィス閉鎖「カオス・デイ」を試みた理由
宇田川:この東京オフィスでは、「カオス・デイ」という取り組みをされたそうですね。
ロウ:あれは面白かったですね! 確か金曜日だったと思うのですが、朝みんながオフィスにやってきたら、鍵が閉まっていて入れない、という状況にしたんです(笑)。
これは、元々はダン・ワイデンにインスパイアされたものです。彼はいつも、「カオスの中でこそ、意味のある仕事ができる、真に生きたものができる」と言っています。整然とした規律が必要な人もいると思いますが、ダンは、アイデアも人もぶつかりあって、混沌とした中で新しいものが生まれると考えていて、そのカオスな状況を意図的にも作っていこうとしていました。日本では特に、上の人のアイデアに下の人が従うということが多いですね。アイデアがどこからでも出るようになるためにも、カオスは必要だと思います。
「カオス・デイ」によって、みんなにはダンの考え方を伝えると同時に、仕事は会社以外のスペースでもできるものという意識を持ってほしかったのです。社員の中には「今日は仕事しなくていいってこと?」と言う者もいましたが、そうではなくて、仕事はきちんとしてくださいと伝えました。その1週間くらい前から、SlackとかGoogle の色々なツールとか、共同作業に使えるツールを紹介していたのですが、その日の16時から重要なプレゼンを控えていたチームなんかはパニックになっていましたね。でも、ひとりのクリエイターの自宅に集まって、一生懸命準備していました。そういう危機的状況を一緒に乗り越えて、チームの結束は高まったと思います。常に少し予想外の事が起きるような状態をキープすることで、みんなよく考えるようになりますし、ダンが理想としている生きたアイデアが生まれる組織になるのだと思います。
宇田川:その話を聞いて思い出したのが、社会学の「エスノメソドロジー」という研究領域の話です。エスノメソドロジーは、我々の常識を暴き出すために、あえて、一度常識を疑ってみることを重視するんです。例えば「おはよう」と言われた時、普通は「おはようって、何時から何時までのことを指すんですか?」なんてことは聞きませんよね。そんなこと言わずに「おはよう」と返すのが常識とされている。でも、ある人にとって常識的に正しいことの背後には、語られていないこと、無視されていることがあるわけです。それは同じ常識を持たない人に対する差別にもつながります。だから、いかに語られない部分を掘り起こしていくのかということを大事にしているのが、エスノメソドロジーのひとつの議論なんです。
ロウ:今の世の中で当たり前とされている現状を疑うというのは、物事に柔軟性を持たせるために重要ですね。それは今の政治の状況にも通じる話で、大統領選でドナルド・トランプが当選したのは、これまでの常識が古く固いものになってしまったことに対する反動だったのだと思います。もう、政治家ではない人を選ぼうという意思が働いたのでしょう。それに対してクリントンは非常に政治家的な人だったので、負けてしまった。強い反動が起きるのは、元の世界があまりにも固定化してしまっていたからだと思うので、そういう意味でも、会社であれ何であれソフトな状態を保っていくことが大事だと考えています。
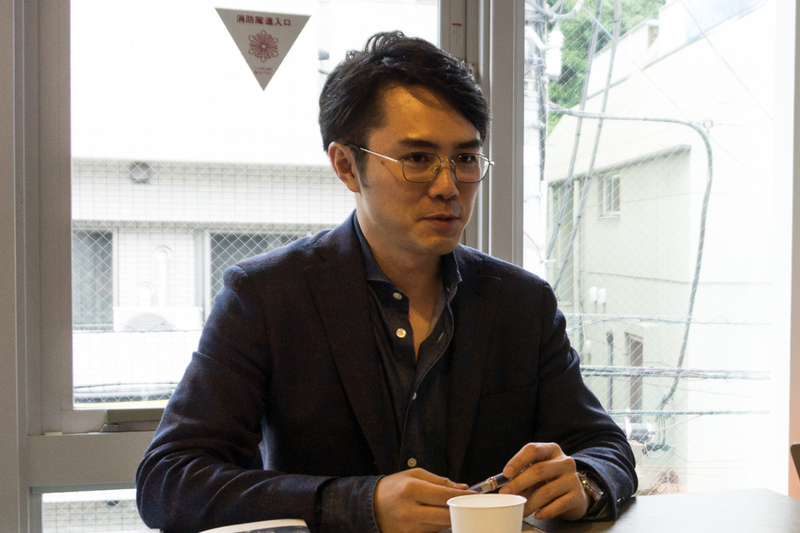
3分の1の文化でハイブリッドな組織を作る
宇田川:W+Kのスピリットを伝えていくのに、東京と(W+K本社がある)ポートランドとで違うところは沢山ありますよね。だとすると、必ずしもポートランドと全く同じやり方を踏襲することが最適なわけではないと思います。その点については、どう考えていますか?
ロウ:まずW+Kの世界8つのどこのオフィスでも、トップマネジメントは、エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター2人、マネージング・ディレクター1人の3人体制です。東京の場合、ひとりはアムステルダムのW+Kから来たイギリス人のマイク・ファー、もうひとりの長谷川踏太はもともとW+Kではなかった日本人、私はポートランドのW+Kから来ています。3人がそれぞれの異なる背景を持っているのです。
そして、組織のカルチャーは3分の1文化というものがあって、私たちマネジメントチームによるものが3分の1、次の3分の1は W+Kのスピリット、残りの3分の1はローカルカルチャーで作られると考えています。だから、なるべく日本の若いスタッフを採用するようにしていて、今は75%が日本人のスタッフです。そうすることで、その地域に合ったコミュニケーションでクリエイティブワークを生むことができる環境になっていると思います。
宇田川:なるほど、よくわかりました。今日はありがとうございました。
後日、宇田川氏より対談を振り返っての考察をいただいた。
W+Kのユニークな広告は、ユニークなマネジメント・スタイルとワーク・スタイルに支えられている。そして、それは、アメリカの中で最もリベラルな文化を持つと言われるポートランドの文化が色濃く反映されたものでもある。
リベラリズムとは、私たちが知らず知らずに疎外していた他者の痛みに共感し、その痛みと連帯をしようとする思想である。W+Kはグローバル・ビジネスの文脈にこのリベラリズムの思想を実践する企業なのではないだろうか。
我々が当たり前だと思っている思考は、決して世界の全てではない。W+Kの凄みは、その当たり前の外側にある別な在り方を発掘していくことにある。Fail Harderを目指すこと、Provocativeであることを重視すること、そして、具体的な働き方の施策は、そのための思考装置なのだ。カオス・デイの実践は、その典型的なもので、我々が当たり前だと思っているものに対する挑戦だ。W+Kは、クライアントにも、消費者にも、そしてメンバーに対してもその姿勢を崩さない。そして、それはW+Kの理想とする社会の在り方なのであろう。
常々、こうした先進的と呼ばれる企業を見ていて感じることは、そこに未達の理想があることだ。現状を良しとせずに、それを変えていこうとしているのである。
我々は、その理想と、現状の世の中への違和感を大切にする姿勢とに、深いレベルで共感を覚える。もちろん、ビジネスとして成功することは非常に重要なことであるが、同時に、成功することは何の理想を目的とするのかを見据えていなければ、その成功は単に利益の奴隷に過ぎなくなるからだ。
そんな青臭い理想なんて、ビジネスには何のリアリティもないと言う人も多いだろう。だが、青臭い理想のないビジネスには、我々の痛み、人生へのリアリティがない。W+Kが世界最大の独立系エイジェンシーとして活躍していることが示すことは、我々の人生へのリアリティを探求しているからこそのことだろう。
ジョンさんがインタビュー中で語ったように、組織に柔軟性をもたせ、クリエイティビティを発揮するためにも、青臭い理想を具現化するために根気よく考え、実践し続けることが不可欠だ。それがW+Kを独自のものにしてきたし、それが今では欠かせない彼らの強みになっているのである。結果的には差別化された戦略を実践していることになっているが、決して差別化戦略を無理やり考えた結果ではない。彼らが現状を当たり前としなかったこと、見えていない現実を探り続けたこと、そして、それを具体的なビジネスの中に実現してきたこと、そのことが彼らをユニークにしてきたのである。現実の中に理想を実践することを諦めないこと。そのことが、私たちを世の中に唯一無二な存在にさせる。独自のビジネスを作り上げ、価値を創造することに近道はない。だが、そのための扉は、私達が目を向けていない方向に常に開かれているのである。










