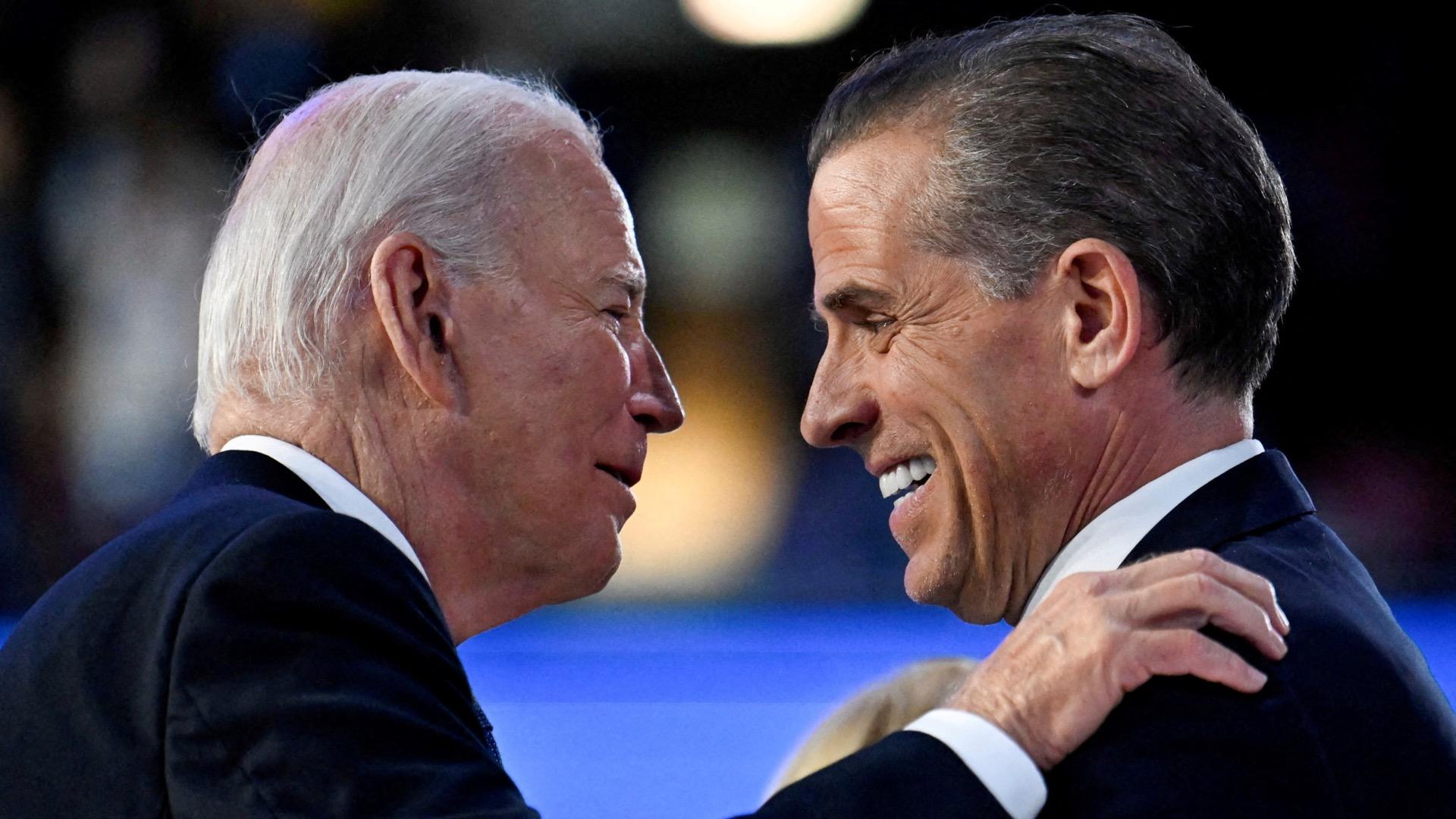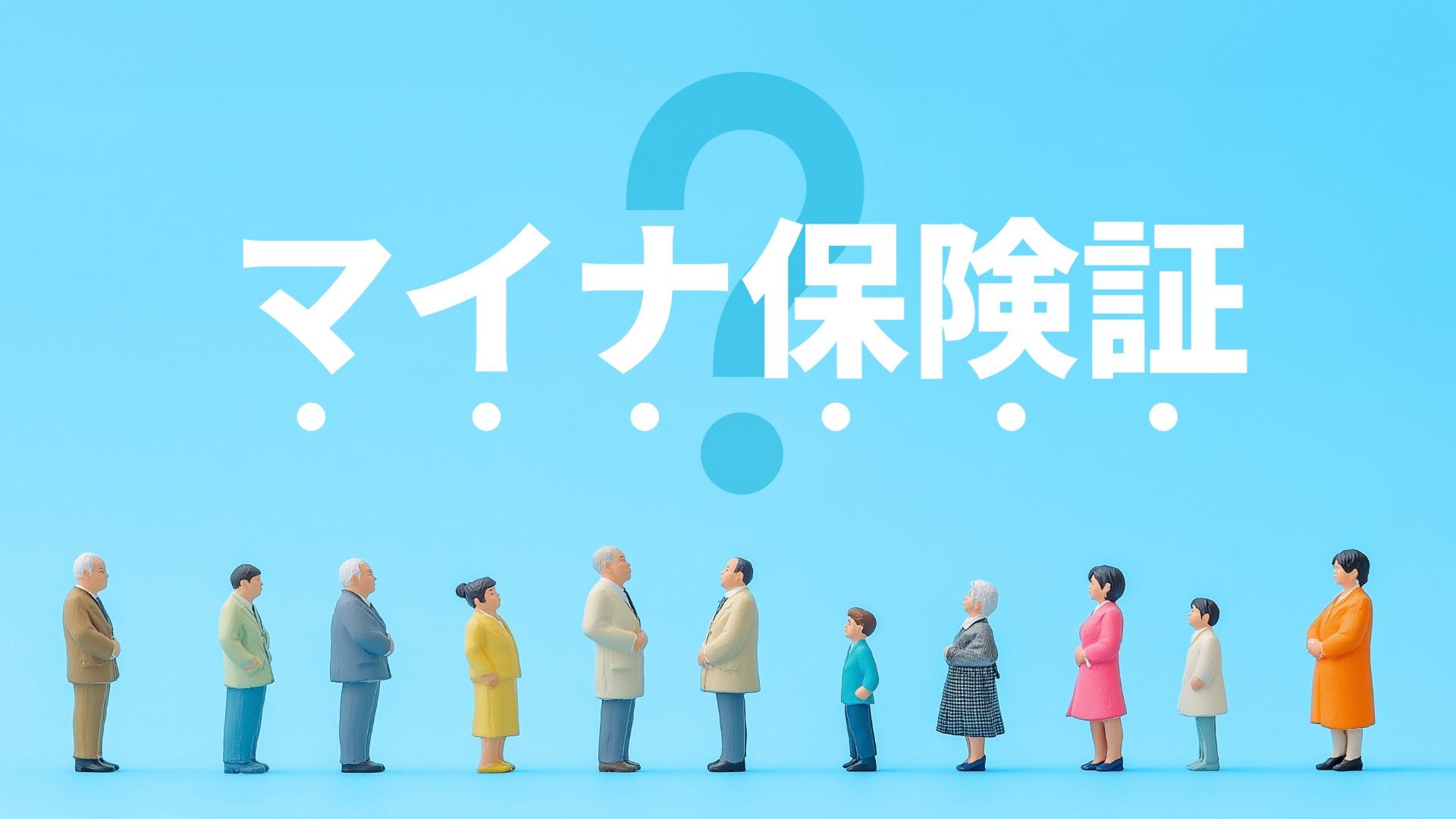上層寒気と下層暖気の温度差が大きいと大気不安定 下層が極端に温まると上層のちょっとした寒気でも不安定

「ライデン」で雷を観測
大気が不安定となると積乱雲が発達し、雷が発生します。
この時に強い光(電光)と大きな音(雷鳴)とともに、電磁波を発します。
この電磁波は、雲と雲の間の放電(雲間放電)と雲と地上の間の放電(落雷)では、電磁波の特徴が異なっています。
気象庁では、全国30ヵ所の空港に検知局を設置し、ライデン(LIDEN:LIghtning DEtection Network system)と呼ぶ雷監視システムで、東京都清瀬市にある中央処理局において電磁波の分析を行い、雷に関する情報を作成しています(図1)。

「ライデン」は、システムの英語表記の頭文字ですが、「電光と雷鳴」を意味する言葉である「雷電」をかけています。
「ライデン」の情報は、空港における地上作業の安全確保や航空機の安全運航のために航空会社などに直ちに提供するほか、雷活動度(4:激しい雷、3:やや激しい雷、2:雷あり、1:雷の可能性あり)の分布図とともに気象庁ホームページで公開しています。
関東南部の5月8日(水)の雷雨
令和6年(2024年)5月8日は、上層に寒気が南下したことに加え、西から東日本の太平洋側では、晴れ間が広がり、日射によって地表付近が温まって上下の気温差が大きくなりました。
このため、大気が非常に不安定となって積乱雲が発達し、雷が発生したのですが、上層に南下した寒気は強いものではなかったために、発雷は局地的でした(図2)。

全国で最高気温が25度以上の夏日を観測した地点数は、ゴールンウィークが始まった頃の4月28日には521地点(気温を観測している全国914地点の約57パーセント)、終わる頃の5月5日は524地点(約57パーセント)だったのですが、これに比べれば、5月8日48地点(約5パーセント)、9日19地点(約2パーセント)と激減しています(図3)。

ただ、ゴールデンウィーク中の気温が記録的に高かっただけで、今の気温は季節的に特に寒いというものではありません。
そして、週末にかけては、再び気温が高くなる見込みです。
週末にかけての気温
週末にかけて、日本付近を大きな高気圧が通過する見込みです(図4)。

このため、西日本~東日本、東北南部では晴れとなり、東北北部から北海道および南西諸島は概ね晴れる見込みです。
気温は全国的に高くなり、夏日を観測する地点数は、5月10日は西日本を中心に214地点(約23パーセント)、11日は関東から東北・北陸を中心に441地点(約48パーセント)となるでしょう(図5)。

下層の気温は上がりますが、上層に寒気が入っていないために上層と下層の温度差は大きくはなく、大気が不安定になって発雷するということはなさそうです。
東京の最高気温と最低気温の推移をみると、5月9日は最高気温が18.9度、最低気温が10.2度と平年を下回りましたが、平年を下回った日より、平年を上回った日の方が多くなっています。
それも、2月20日の23.7度、3月31日の28.1度など、平年を大きく上回る季節外れの暖かさの日が少なくありません(図6)。

1ヶ月前の寒い気温が出現するより、1ヶ月後の暖かい気温が出現するほうが多く、時折2ヶ月後の暑い気温が出現するイメージです。
この傾向は、東京だけでなく、全国的な傾向です。
しかも、気象庁が5月9日に発表した一か月予報では、日本中が気温が高くなる確率70パーセント以上という、前代未聞の予報となっています(図7)。

今年、令和6年(2024年)は、記録的な暑さとなった昨年並み、あるいは、昨年以上の暑い年になりそうです。
早め、早めの熱中症対策が必要な時代になっています。
そして、下層がこれだけ暑くなると、上層にちょっとした寒気が流入しただけで、上下の温度差が大きくなって積乱雲が発達します。
常に、局地的な豪雨、落雷、突風に注意が必要な時代にもなっています。
図1、図4の出典:気象庁ホームページ。
図2、図5、図7の出典:ウェザーマップ提供。
図3、図6の出典:ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成。