DX銘柄2022のグランプリは中外製薬と日本瓦斯 2020年から銘柄を比較する
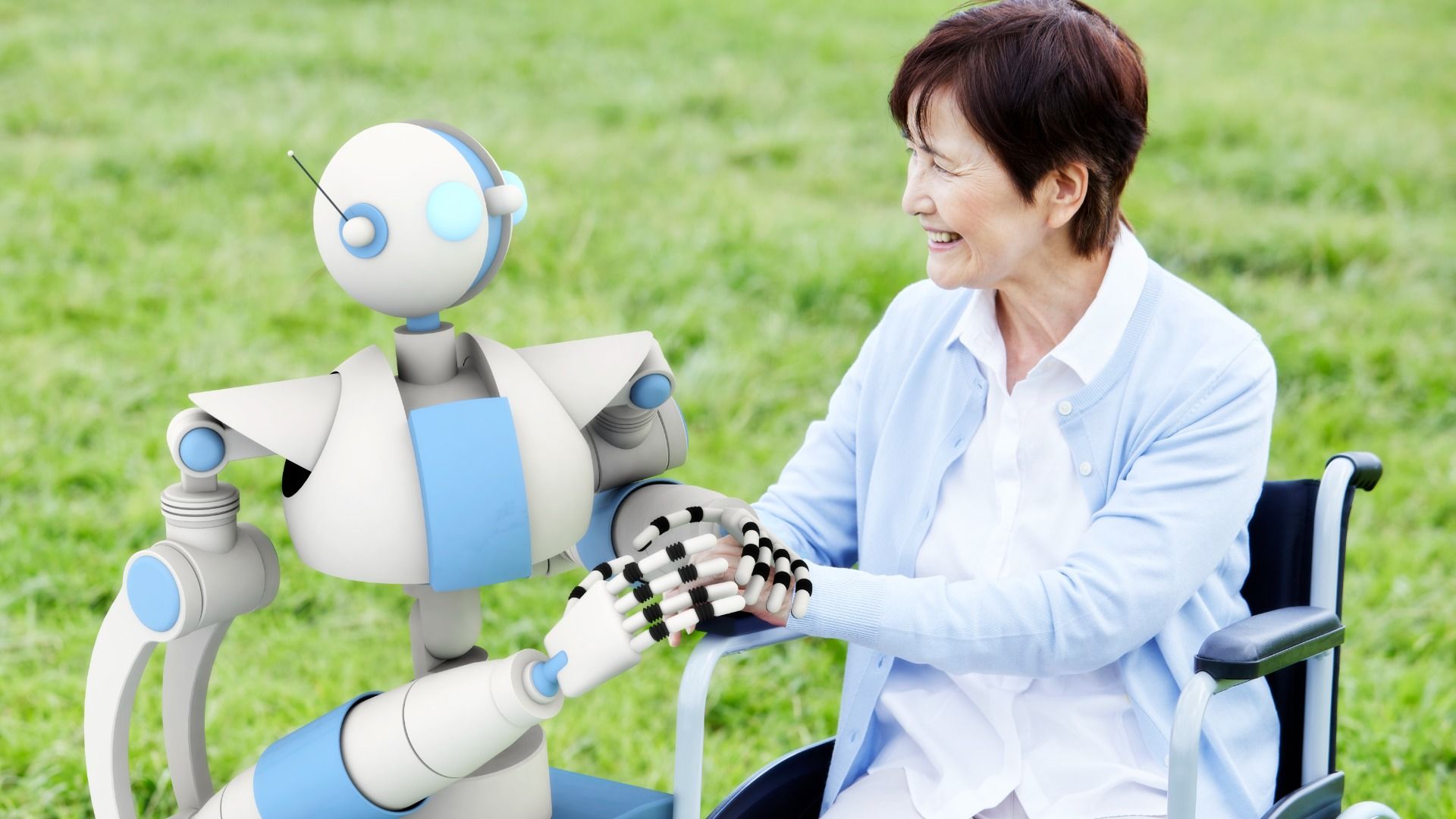
6月9日、経済産業省は「DX銘柄2022」選定企業33社を発表した。
DX銘柄は、優れた情報システムの導入やデータの利活用にとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのものの変革および経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業として選定される。つまり、単なる作業ツールや業務のデジタル化を推進する企業ではなく、ビジネスの変革に向けてデジタルを活用している企業を、DX銘柄として選定しているのである。
2015年より経産省は、経営革新や収益水準、生産性の向上に向けて積極的にITを利活用している企業を「攻めのIT経営銘柄」として選定してきたが、2020年からはこれを発展させて「DX銘柄(デジタルトランスフォーメーション銘柄)」とした。今回の選定企業は、以下の通りである。
清水建設、サントリー食品インターナショナル、味の素、旭化成、富士フイルムホールディングス、中外製薬、ENEOSホールディングス、ブリヂストン、AGC、LIXIL、小松製作所、IHI、日立製作所、リコー、トプコン、凸版印刷、アシックス、日立物流、SGホールディングス、商船三井、ANAホールディングス、ソフトバンク、KDDI、トラスコ中山、日本瓦斯、ふくおかフィナンシャルグループ、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、SBIインシュアランスグループ、東京海上ホールディングス、東京センチュリー、GA technologies、三井不動産、応用地質
※うち中外製薬と日本瓦斯はグランプリ企業
ところでこの銘柄、前に選定されたからといって、今回も選定されるのではないのが特徴である。業種ごとに2020年から今年までの選定企業を整理してみると、次のようになる(筆者が作成)。かなり流動的だが、その中でも継続して選ばれている企業は見事である。

選定の方法
DX銘柄2022は、どのように選ばれたのか。「DX銘柄2022」選定企業レポートの中には、選定のプロセスが書かれている。
まず、東京証券取引所の上場企業約3,800社に「デジタルトランスフォーメーション調査2022」を実施する。調査に回答した企業401社のうち「DX認定」を取得している企業を銘柄への応募とみなして、選定の対象としている。
次に一次評価として、ビジョン・ビジネスモデル、戦略、成果と重要な成果指標の共有、ガバナンスの4つの観点から「選択式回答」によるアンケート調査を行う。これと過去3年平均のROEに基づいてスコアリングを実施し、一定基準以上の企業を銘柄の候補企業として選定する。
二次評価として、一次評価の候補企業によるアンケートの「記述式回答」について、DX銘柄評価委員が評価を実施する。それをもとに最終選考として、DX銘柄評価委員会による最終審査を実施し、業種ごとに優れた企業を「DX銘柄2022」として選定するのである。このように、アンケートへの回答が主となり、それを有識者である評価委員が判定するのである。アンケートは「企業」に対して行われ、一般の従業員に対してではない。
「企業」とはいっても、回答者は一人ないし少数の人間である。多くの場合、それはDXを推進する担当部署の者であろう。だとすれば、DX銘柄への選定は、有識者らの観点を理解している者が社内に存在するかどうかが鍵となる。そうであれば、ビジョンやビジネスモデルが、来たるデジタルの展望や将来像と乖離している場合には、高い評価を得るのは難しいと考えたほうがよさそうである。
変革は「化」から生じない
よいビジョンやビジネスモデルが生じないのは、DXに限らず大抵の場合、物事の本質を理解していないからである。
例えば、ある会社のホームページにはDX化という用語が書かれているが、そもそもXはトランスフォーメーションを意味するのであるから、DX化では「デジタル変革」化となり、言葉として成り立たない。揚げ足をとっているわけではなく、DXとは何であるかということに真正面から向き合わないから、このような間違った言葉を使ってしまうのである。
まず変革とは「化」の発想で生まれるのではない。よって、ある会社のように競合との差別「化」のためにデジタルを利活用しようというのでは、変革は生じないのである。変革は、描く未来やあるべき姿を展望することから始まる。改善の連続ではなく、人びとにとっての新たな価値の想起から、変革は生じるのである。
ドラッカーに倣っていえば、その展望は「すでに起きた変化や起こりつつある変化」を捉えることから生まれる。変化の根拠は何か。その先に何が生じるのか。そうであれば、いかなるビジネスが人びとに求められるのか。脳内で妄想するばかりでなく、多様な知見に触れることで、明確なイメージがわいてくる。
展望やイメージは、現在のビジネスの仕方では実現できない。よって、どうすれば実現できるのか、新しい価値が届けられるのかを、いちからモデルとして考案するのが適当である。このとき、あまり自社のリソースの有無について考えないほうがよい。それに引きずられ、再び「化」の発想に戻ってしまうことが多い。
モデルが検討されたとき、ようやくリソースについて考えることができる。社外のパートナーや内部人材、それから、デジタルな手段である。ようするに、ビジネスモデルに必要とされるパーツをかき集めて、全体像を組み上げていくのである。暫定でもよいから、ひとまず最後までやり切っておくことをお勧めする。
最後に、新たなビジネスモデルと現在のビジネスモデルとを比較して、そのギャップを把握する。あるべき姿と現状との差に存在するのが問題であるが、その問題を解決するための手段を講じるのが、ここで行うことである。解決策をプロセス化して、いつまでに行えば新たなビジネスモデルが実現されるのかを明確にする。かくして、変革に向けた活動が明確になる。全体として一貫した戦略が練り上げられるのである。
描いたビジネスモデルには、たえず疑問を投げかけておくとよい。なぜなら新たなプレイヤーも、より可能性を秘めたテクノロジーも、次々と生まれてくるからである。よって変革を実現するには、知識を得つづけなければならない。継続的な学習を取り入れ、「わかっている人」を育成することが、変革へのプロセスである。










