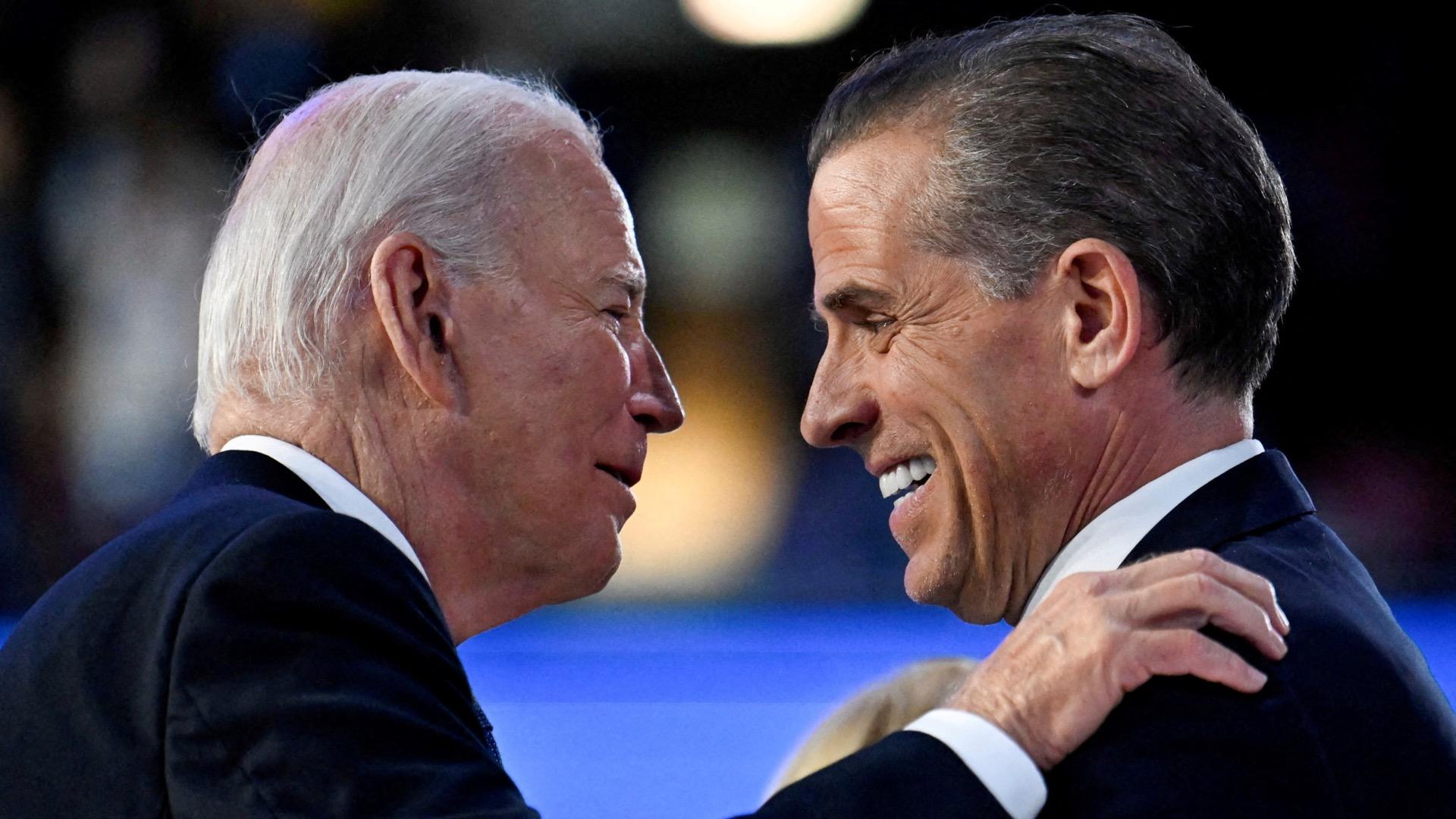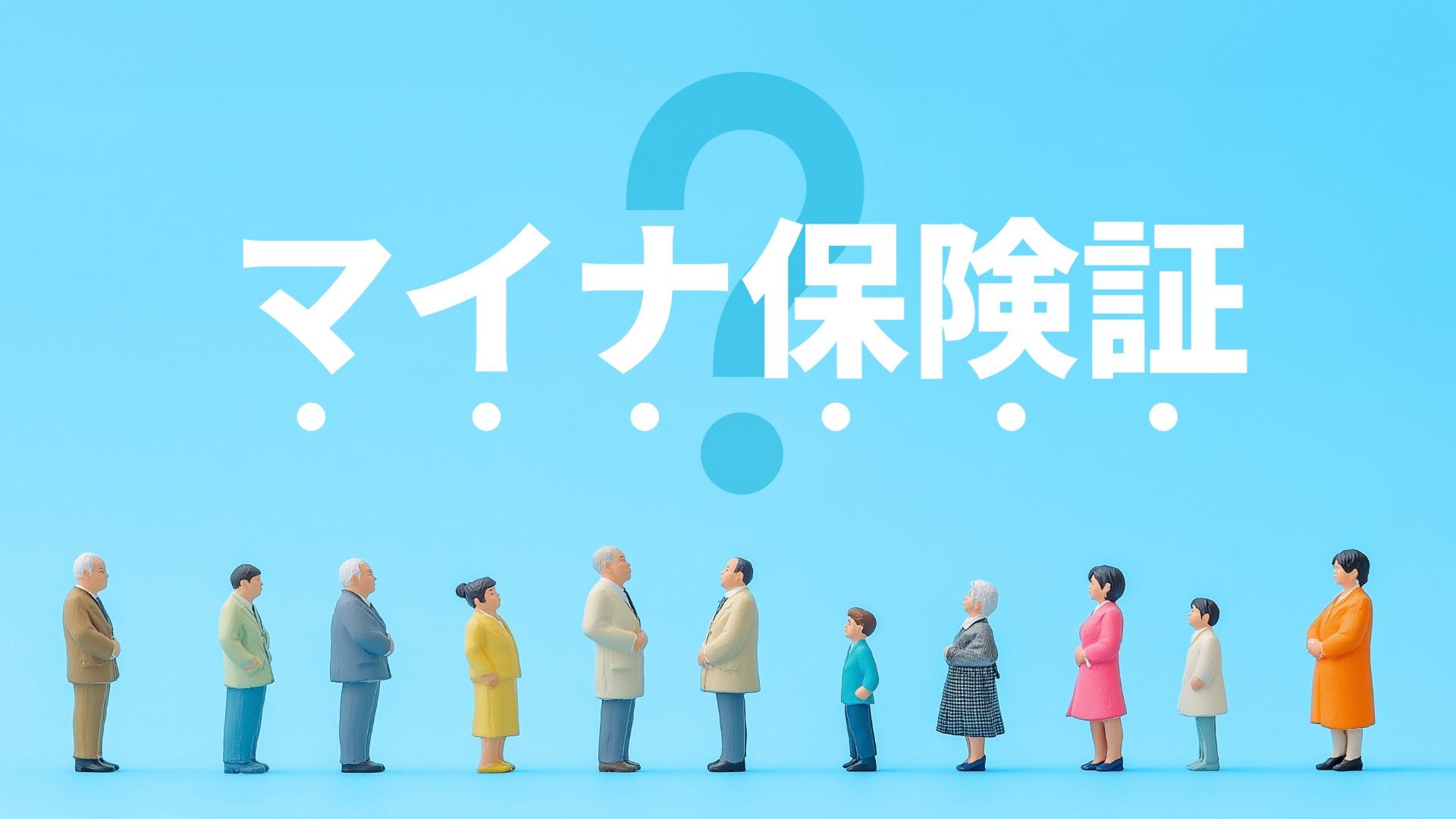「桜田門外の変」が起きたのは、上巳の節供(ひな祭り)の大雪の日

上巳の節供
季節の変わり目にあたって祝いを行う節日(せつにち)に供御(くご)を奉ることを節供(せっく)といいます。
節句と書くことが多いのですが、この節供は5つあります。
1月7日の人日(じんじつ)、3月3日の上巳(じょうみ)、5月5日の端午(たんご)、7月7日の七夕(たなばた)、9月9日の重陽(ちょうよう)の5つです。
ということは、昔の人は、季節を春夏秋冬の四季ではなく、これに梅雨を加えた五季を意識していたことになります。
3月3日の上巳の節供は、桃の花が咲く頃であることから「桃の節供(節句)」と呼ばれています。
3月3日に桃の花というと、早いと感じると思いますが、日付は旧暦です。年によって大きな差がありますが、今の暦でいうと、約1ヶ月後ですので、まさに桃の季節です。
雪が降るということは、めったにありませんが、年によっては、季節外れの雪ということがあり、過去には「雪の上巳の節供」で大事件が起きています。
降雪中に起きた三大事件として、多くの場合、
・「赤穂浪士討ち入り」(元禄15年12月14日、1703年1月30日)、
・「桜田門外の変」(安政7年3月3日、1860年3月24日)、
・「二・二六事件」(昭和11年2月26日、1936年2月26日)があげられます。
昭和11年(1936年)については、大手町に中央気象台(現在の気象庁)があり、詳しい雪の観測が残されていますが、気象観測が行われていない元禄15年と安政7年については、日記等から推測するしかありません。
桜田門外の変
江戸時代、江戸在府の諸大名は、節供の日に江戸城に登城して祝を述べていましたので、登城する大名行列を一目見ようと江戸町民が集まってきました。
このため、諸大名にとって節供の日は見せ場でしたし、人が集まってきても不審には思いませんでした。
安政7年(1860年)の上巳の節供の日は、前夜から続く大雪でした。
この日、登城途中であった大老の井伊直弼(46歳)は、桜田門外で日米条約に反対する水戸・薩摩藩士17名によって暗殺されるという「桜田門外の変」が起きています。
桃の節句の賀詞言上のため、必ず登城するという日を狙った犯行でした。
大老警護の彦根藩士たちは、大雪のため、柄袋で刀を覆っており、このため抜刀が遅れたことが暗殺を許した原因と言われています(図1)。

このときの大雪は、南岸を通る低気圧によるものと考えられています。
江戸城で桃の節供が行われたといっても太陰暦の3月3日です。太陽暦に直したら3月24日と3月下旬になります。
南岸低気圧が通過するとしても雪にはなりにくく、例年なら桜が咲く季節です。
大老が白昼暗殺されたことで、幕府の衰退が公然となり、倒幕への動きが急になったこの事件ですが、多くの年のように大雪が降っていなかったら、日本の運命は変わっていたかもしれません。
なお、警視庁の隠語が「桜田門」というのは、警視庁が「桜田門外の変」が起こった皇居の桜田門の近くにあるからです。
東京の終雪
「なごり雪」には、「春に入ってから降る雪」と、「春になっても消え残っている雪」の2つの意味があります。
昭和49年(1974年)に伊勢正三が作詞・作曲し、後にイルカがカバーしてヒットした昭和の名曲「なごり雪」は、「春に入ってから降る雪」を歌っています。
東京の駅を舞台とし、少女から女へと脱皮する少女との淡い別れの歌ですが、伊勢正三によれば、モチーフとしたのは出身地である大分県津久見市の津久見駅とのことです。
気象用語に「なごり雪」という言葉はありませんが、対応する言葉というと、前者の「春に入ってから降る雪」に対応する「終雪(冬のシーズンで最後に降る雪)」になります。
東京の終雪を、記録が残っている明治10年(1877年)から令和5年(2023年)までの147年間で調べると、3月下旬が一番多く、最も早い終雪は、昭和48年(1973年)の1月15日です(図2)。

全期間の平均が3月16日となりますが、これは、近年の暖かくなって終雪が早まっている期間が含まれています(図3)。

明治34年(1901年)から大正14年(1925年)までの平均は3月26日と今より遅く、「桜田門外の変」があった江戸末期が、明治末期から大正時代の気候に似ていれば、3月24日に大雪になるかどうかは別として、雪が降っても不思議はなかったと思われます。
ただ、終雪は今冬が終わってからでないと確定しません。
今冬の東京は、2月23日8時50分から10時50分までみぞれが降り、そのあと雪(みぞれを含む)が降っていません。
このまま雪が降らないとなれば、2月23日が終雪となり、かなり早い終雪ということになります。
ただ、今週半ばの3月5日は、本州南岸を低気圧が通過する見込みで、関東北部の山地で雪となる見込みです(図4)。

今のところ、東京都多摩地方は雪またはみぞれ、東京都心は雨の見込みですが、少し寒気が強まって東京都心でもみぞれや雪になれは、終雪の日が3月5日以降ということになります。
図1の出典:饒村曜(平成11年(1999年))、イラストでわかる天気のしくみ、新星出版社。
図2、図3の出典:気象庁ホームページをもとに著者作成。
図4の出典:ウェザーマップ提供。