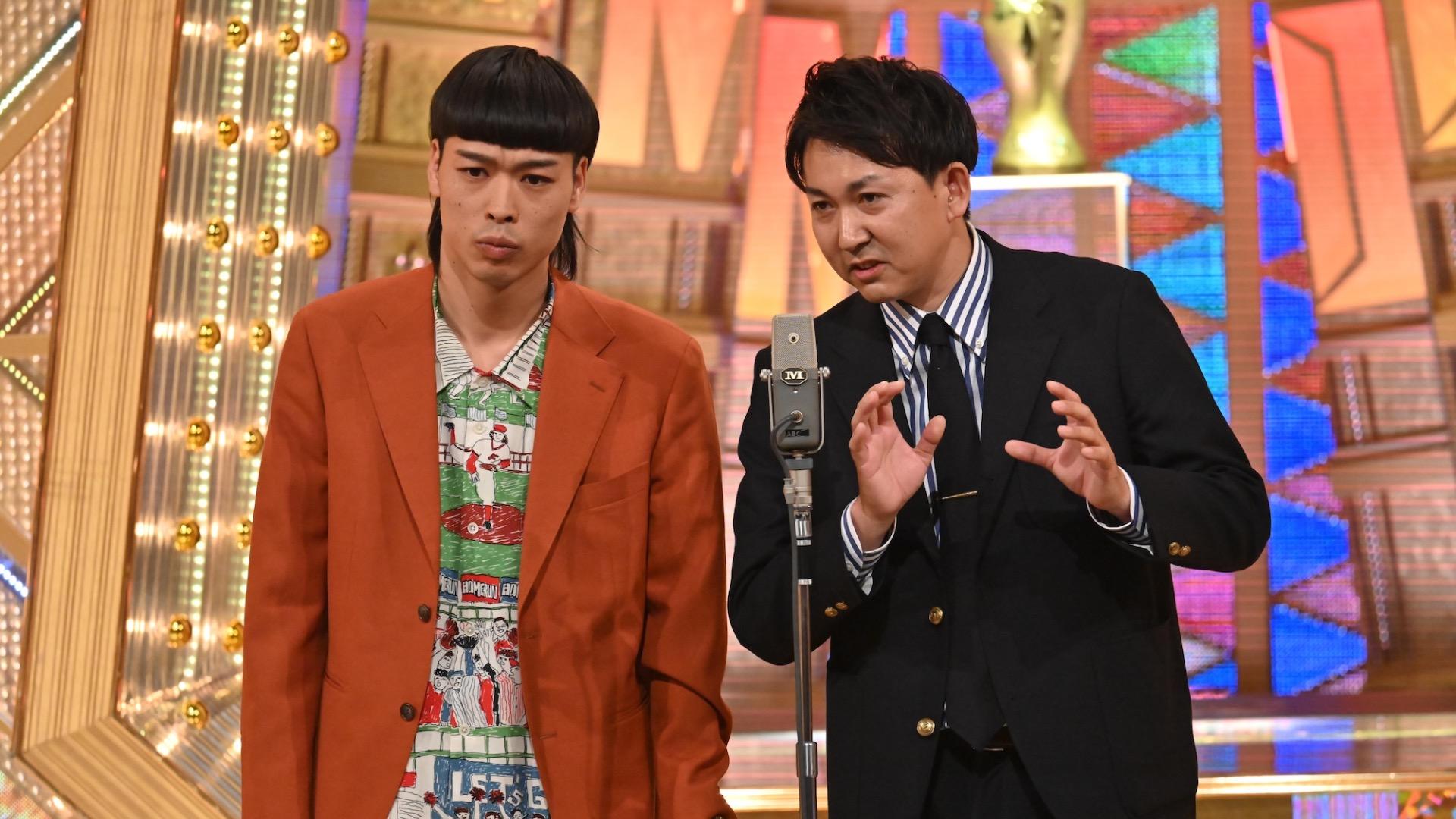【洪水の中、隣人を救助すべきか?】「高齢女性を救助後、流された夫」記事ヤフコメまとめ解析

大雨で高齢女性を救助後、目の前で流された夫…和歌山・紀の川の妻「答えが出ない1年」
和歌山県内で初めて線状降水帯の発生が発表され、死者2人、行方不明者1人を出した昨年6月の大雨から、2日で1年になる。紀の川市の酒井寿夫さん(当時72歳)は近所の高齢女性を救助後、犠牲になった。夫が流されるところに居合わせた妻の清子さん(70)は「思った以上に水かさが一気に増えた。誰も責められませんし、答えが出ない1年でした」。複雑な思いを語った。(後略)読売新聞 6/2(日) 9:13配信
大雨の降りやすいシーズンに入りました。上述の記事に記載の通り、6月に入れば人の命を奪うような水災害が発生するものです。河川の流域では洪水によって道路が川のようになって濁流が流れくだり、水に囲まれれば家屋から脱出するのが困難になります。そういった危険の中、困っている隣人を救助すべきか、この記事には300件以上のコメントが寄せられました。寄せられたコメントをまとめて、文意の特徴で分類して解析してみました。図1をご覧ください。

コメントを大きく分けると、この災害のニュースに限ってコメントを書いている例はむしろ少なくて、水難事故をもっと広くとらえて、そういった中で自分は水難で困っている人を助けに向かうのかどうなのかという考えを書いている例が多かったようです。この記事に先立って富山県で発生した水難事故で、男性が川に飛び込んで子どもを助けようとした記事が掲載されていて、その内容に引っ張られた感じのコメントが多数ありました。
300件以上のコメントのうち、(必ずしも災害における隣人救助にこだわらず)水に飛び込んで救助することに否定的なコメントが半数を大きく超えました。否定も肯定もあるような両論併記のような中立的なコメントは全体の1/8程度で、肯定的なコメントは数%見られました。その他は、飛び込むことの是非に言及することを避け、自分の体験などの知識をユーザーと共有しようとしているコメントからなっていました。
◆否定的なコメント
この現場では水量が多くて「水は胸の付近まで到達し、流れは速くなった(記事より)」状況で、これでは洪水で人がどうしても流されてしまいます。そういった中で隣人を助けに向かった人の頼りはロープ1本。次の例は、装備の観点でこの救助は困難だったと感じているようです。
とてもかわいそうなお話です。時を戻す事はできませんが、救助用のロープは手だけでは水流の圧力に耐えて手繰り寄せる事は若い人でも困難です。体に巻いて縛ってから手繰り寄せるべきでした。奥さんの側はロープをどこかに結びつけてあったと思います。数メートル先の夫(ほとんど目の前)に、水嵩が増すから急いで戻ってきてねと、叫んでいたのかもしれません。救助した女性をその家の高い方に移動させて、その女性が助かったのであれば、 無理に水嵩の増した道を戻らない選択は出来なかったのか悔やまれます。なにせ、咄嗟の判断が求められる時は、5秒間でも10秒間でも冷静に状況を把握しないといけないという貴重な教訓を教えて頂きました。ご冥福をお祈りいたします。
否定的なコメントを寄せた方に比較的共通するワードがありました。それは「自分を抑える。」
河川や海岸や火事場それと駅ホームの落下などなど救助したくなる場面があると思いますが、自分を抑える強い心とその場にいた周りの人々が止める強力な補助が必要です。犠牲者をこれ以上増してはいけません。
家族の側からみて、「身内は自分を抑えられない性格」だと気が付いている方がいて、客観的にみたら「災害現場で何をするかわからない」とたいへん心配のようです。
私の夫も正義感が強く溺れてる人がいたら助けてしまうタイプなので、あなたはもう普段運動もしてないから無理、若い体力のある人に任せるしかないの。と言ってます。助けに行く人は素晴らしいですが充分に気をつけていただきたいです。
「家族には救助に向かってほしくない」というコメントが比較的多く見受けられました。それは連れ合い、子ども含めて自分の家族すべてに対してそのように願っているように見受けられます。
冷たいかもしれないけど、家族には「たとえ見知らぬ誰かが流されていても助けに行かないように」と言っています。川は本当に怖いです。助けられる体力やスキルなどがあればいいかも知れませんが、どちらも兼ね備えていない家族にはくれぐれもそう言っています。素晴らしい行為だとは思いますが、素晴らしいと言うと助けに行かない事が悪のように捉えられてしまうので、とても難しいですね。
否定的なコメントを一貫して眺めてみると、「抑えられずに飛び込む自分」がいて、それに対して「自制してほしい」と思う家族の姿があるように感じます。
◆中立的なコメント
災害の場面ごとに条件が異なるとして、否定的なのか肯定的なのか、自分では決めかねるような場合に中立的なコメントになる傾向があります。
今日のニュースで、「子供が流され、橋にいた人は見てるだけ、自分が飛び込んだ」と、救助に成功した若者がインタビューに答えていた。見てただけの人を責められない。飛び込んだ人もそれはそれで尊い行為。個人的には、助ける側のスキルだ体力だとか、どっちがいいとかでなく、それをする本人が、納得いく方をするしかないのではないかと思っている。
ここで「今日のニュース」とは、富山県で発生した水難事故で、男性が川に飛び込んで子どもを助けようとしたニュースのことを指します。「本人が納得いく方をする」という文面から感じられるように、自分や家族ではない見ず知らずの人に向けた言葉かと考えられます。このコメントに対してつけられた「共感した」4691クリック数(6月7日13時)は、他のコメントを圧倒している点で注目されるコメントです。
◆肯定的なコメント
前述した中立的なコメント例は、ニュース公開以来ほぼコメントの上位に掲載されていました。その分「共感した」方が一定数おられて数を集めていたので、もしかしたらそういった意見に対して、次のようなコメントが寄せられたのかもしれません。
ここは難しい判断。助けるのも正解。助けないのも正解。だけど人間は心を持った生き物。助けるのが正解のような気がする。自分も同じ気持ちだから。
洪水時に逃げ遅れた家族や隣人を助けられるのか?
氾濫流か浸水かで、水の中にいる人を助けられるかどうかが大きく変わります。氾濫流とは、堤防が壊れ河川外に水が流れ出ることで勢いのある流れを指します。一般的な2階建ての木造住宅が倒壊・滑動・転倒するほどです。浸水とは、流れはほぼないのですが、洪水の水がたまった状態です。その水深は時に5 mを超えることすらあります。
両方とも洪水の時には道路が冠水している可能性が極めて高く、救助隊を呼んでもすぐには来てくれません。道中で救助車両が水没してしまうため、車両移動以外の手段を使わざるを得ず、いつ到着するのか皆目見当がつきません。それまでの間、だからこそ、家族や隣人を自分たちの手で助けなければならないという発想に至ります。
氾濫流にさらされている家屋やその周辺にいる人を救助する術はほぼない状態です。激しい流れの中で人間はどうやっても思うように活動できないからです。例えば「大雨で洪水時、徒歩避難は安全か危険か 歩くなら深さの限界はどこか? #災害に備える」では、膝上高さを超える水深では足元がすくわれて簡単に人が流される様子がよくわかります。
一方、浸水している1階にいる家族を2階に移動させるために助けることは可能でしょうか。それは、助けに行く人が救命胴衣を着装するなど浮力をきちんと確保していれば不可能ではありません。ただ、そのような体験を一回でもしない限り、本番で実行することはなかなか難しいので、「温水プールを利用した家屋内1階浸水想定セットの紹介」にあるように、専門的なインストラクターによって解説がなされる体験会に参加するのもいいかと思います。