断水の長期化は「市長と知事の不仲」のせい? そもそも緊急時の給水や復旧はどのように行われるのか?
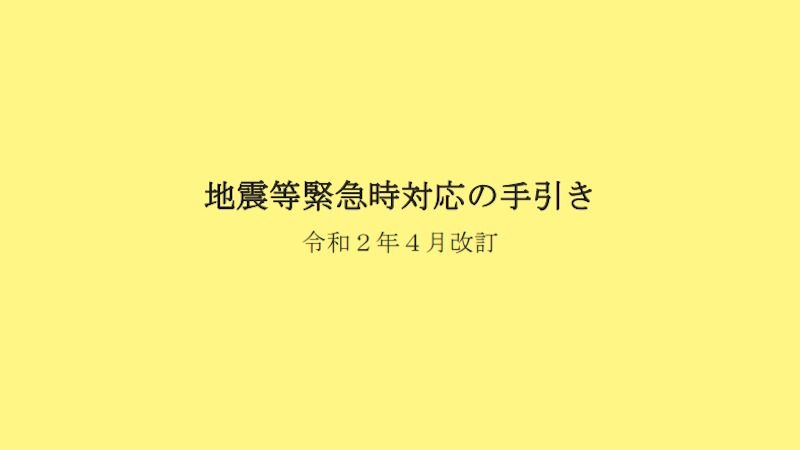
緊急時には指揮命令系統の確立と共有が大切
静岡市清水区の断水被害への対応を巡り、行政の対応の検証を求める声があがっている。静岡新聞によると「区内には『川勝平太知事と田辺信宏市長の不仲が、ちぐはぐな対応を招いたのでは』と指摘する声もある」という。(「清水区断水 行政対応遅れ、検証求める声 「知事と市長不仲が招いた」指摘も 台風15号支援」静岡新聞 2022.9.29)
緊急時には指揮系統の確立と共有が大切だ。政治家がリーダーシップを発揮することは大事だが、政治的背景やパフォーマンスで指揮系統を阻害するようなことはあってはならない。
では、そもそも緊急時の給水や復旧はどのように行われるのだろうか。
水道事業は主に各自治体が行っているが、被災した場合、単独では対応できないケースも多い。
そこで全国の水道事業者が加盟している日本水道協会は、「地震等緊急時対応の手引き」をまとめている。もともとは阪神・淡路大震災における応援活動の教訓を活かす目的で作成され、新潟県中越地震、東日本大震災などの経験を経て、ブラッシュアップされてきた。

手引きを策定するだけではなく、訓練も行われている。2018年11月には今回の被災地である静岡市で「全国地震等緊急時訓練」が行われた。(日本水道協会 全国地震等緊急時訓練 平成30年度応援訓練の実施状況について)
静岡市水道局が状況を把握し、日本水道協会に応援を要請
手引きや訓練があったにもかかわらず、なぜ断水が長期化したのか。
これについて状況把握、給水活動、復旧活動、情報発信などに分けて、今後検証していく必要があるだろう。
現時点でも、給水活動と復旧活動の進捗状況を切り分けて発信すれば、これほどまでに市民の不満は高まらなかったのではないか。
前述の手引きには「災害発生時には住民等に不安やあせり及び混乱等が生じないよう、水道施設の被害状況、復旧見通し等、住民が必要とする情報を適時適切に提供し、住民生活への影響を最小限に抑える」との記述がある。
今回の場合、静岡市水道局が状況を把握し、日本水道協会に応援を要請し、地域のリーダーである名古屋市上下水道局が応援に入っている。24日には災害対策本部ができたが、最初の給水車配置場所は9ヶ所だった。さらにここには断水の原因についての記述がない。

このことから断水の原因を、どの程度把握していたのかを検証する必要がある。
災害時の断水は水道施設の破損、風倒木による停電などが多いが、今回の場合は、清水区の9割の水を確保する承元寺取水口が倒木や土砂で埋まり、水が得られなくなった。
未明の事故で、かつ現場は増水していたので近づいて目視できなかったと考えられるが、いつの時点で、どのように状況を把握し、どのように対策を打ったか。その後、どのように状況変化を把握し、どのような対策に切り替えたかを公表し、点検していくべきだろう。
事態の重さから、復旧に時間がかかりそうだと判断したなら、その旨を市民に伝え、給水車の数、給水拠点の数を増やすこともできただろう。
また、時間の経過とともに応援の給水車が増えたが、それをどこに配置するかという給水拠点のつくり方に問題はなかったのだろうか。その点でのリーダーシップの取り方も検証する必要がある。
取水口の復旧作業の難しさ
復旧作業は難しいものだったと考えられる。
水源の興津川から谷津浄水場に水を送る取水口に流木や土砂などがたまり、取水施設を覆うように大量の流木などが散乱していた。
当初は重機を入れる予定だったが、現場が狭く、道路が冠水している場所もあり、人海戦術に切り替えた。手作業で流木を除去したのちも、取水口内部に土砂が詰まっていたので、それを取り除く必要もあった。
そもそも日本水道協会の手引きは「地震等緊急時」とされているように、主に地震の経験に基づいて策定されている。地震の場合、水道施設の破損、水道管の破損への対応がメインとなり、手引きにもその方法が手厚い。
今後は水害にともなう事故に関する知見も蓄積していく必要がある(西日本豪雨などの経験は一部記載されている)。たとえば、今回のような取水口の復旧に限っては、早めに自衛隊に応援を要請するなど、役割分担を検討する必要もあるだろう。
今回のような断水は今後も発生する
この10年間を振り返ると豪雨が原因の断水が増えている。

さらに厚生労働省が、2018年に、全国の上水道事業及び水道用水供給事業(1355 事業)を対象に、重要度の高い水道施設(取・導水施設、浄水場、配水場)の災害対応状況について緊急点検を行った。(「水道における緊急点検の結果等について(情報提供)」)
その結果、土砂災害警戒区域に位置していた施設は2745か所(全体の14%)あり、そのうち2577か所(全体の13%)は特段の対策が行われていなかった。
また、浸水想定区域内に位置する施設は3152か所(全体の16%)あり、そのうちの2552か所(全体の13%)は特段の対策が行われていなかった。
こうした施設は水害時に機能しなくなる可能性があり、事前の備えが必要だ。
そもそも取水口がなぜ埋まったのかを流域(山に降った雨が川になって集まり海まで注ぐ区域)という視点で考える必要がある。
重ねるハザードマップで調べると、今回被災した承元寺取水口付近、さらには興津川の上流部にも土砂災害の発生しやすい場所が広がっている。上流からの流木や土砂が今回の事故の原因である。

気象庁は、気候変動にともない短時間に激しい雨の降る日が増加すると予測しており、今回のような断水は今後も起こり得る。
断水の長期化は「市長と知事の不仲」のせいなどと矮小化すべきではなく、水道事業者は、土砂災害や浸水災害も考慮に入れ、総合的な対策を立案する必要がある。










