【その後の鎌倉殿の13人】北条泰時が災害直後の御所修築にすぐにゴーサインを出さなかった訳
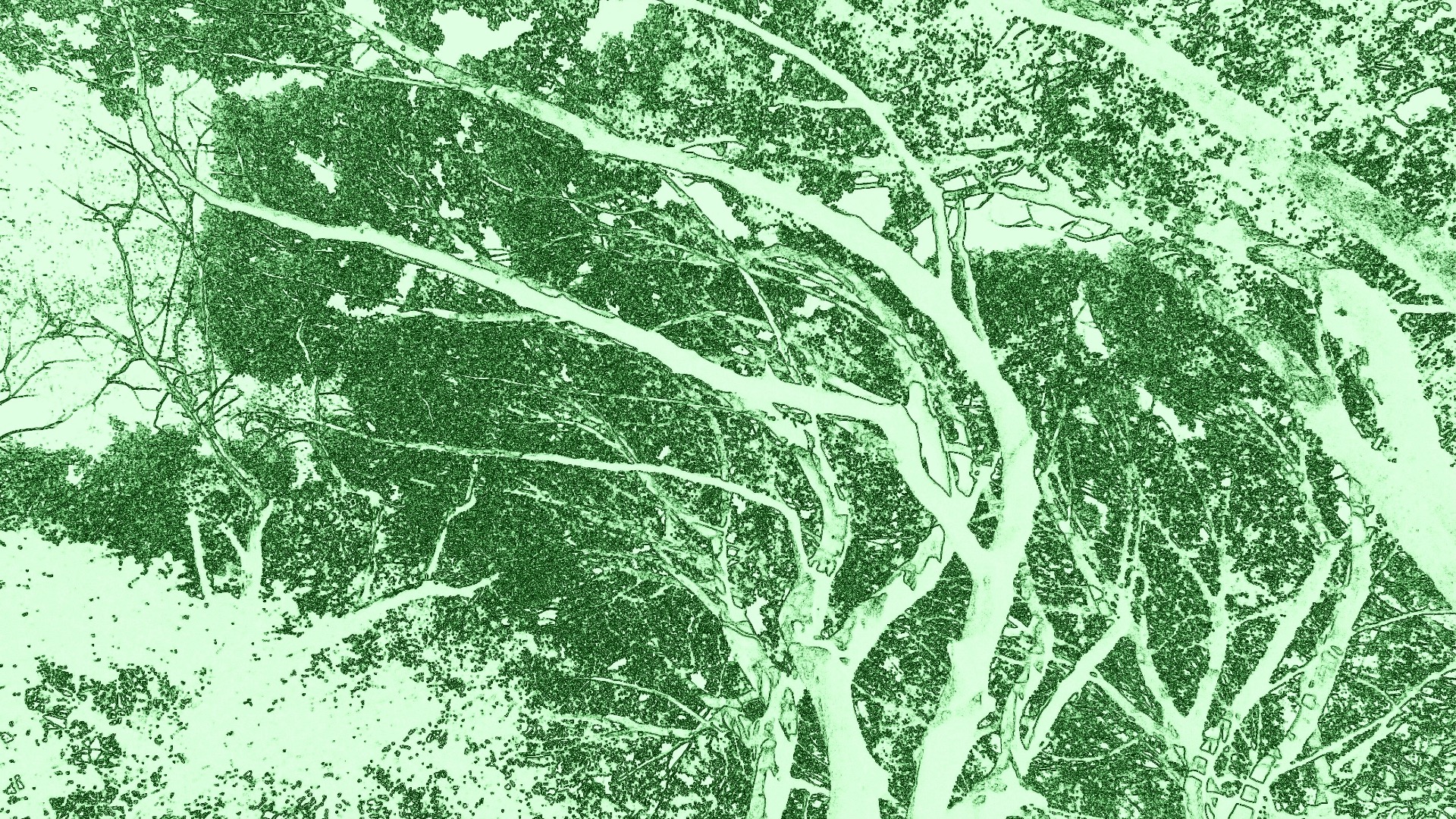
安貞2年(1228)10月7日。雨降る中、この日の晩に「大風」が発生しました。大風により、鎌倉幕府の侍所、中門の廊下、竹御所(2代将軍・源頼家の娘)の侍所などが皆、転倒してしまいます。その他の邸も多くが破損してしまいました。梁(建物の建設時に使用する構造材)は、大風により、路地に吹き飛ばされ、往来の人々を襲います。それにより、多くの人が亡くなったようです。翌日には、雨は止み、晴れとなりました。幕府としては、大風で破壊された幕府御所の修理等を行わなければなりません。その奉行には、後藤基綱(基清の子。父・基清は承久の乱においては官軍に加勢。基綱は幕府方)が任命されます。どのように修理を行うかについて、執権・北条泰時の邸で会議がありました。ある人が会議で言います。「大風や洪水の時に、転倒した屋舎の修築は、日和の選定などしないで、建立するのが、普通である」と。しかし、泰時はその見解を不審に思い、陰陽師・安倍晴賢を呼び寄せます。晴賢は「昔、朝廷の木工寮の建物が風で転倒しました。最近では、鳥羽殿が洪水にて破損しました。どちらも修理の儀式に従って建てました。そういうことで、倒れた建物は、やはり、吉日に建てるのがよろしいかと思います」と主張したのでした。泰時としては(我が意を得たり)という思いだったでしょう。現代においては、災害時には日和の選定などしないで、すぐさま修築するとの見解が妥当でしょう。泰時の見解の方が因習に捉われているように思ってしまいます。










