日本にも「近隣トラブル解決センター」が必要です! 悲惨な事件や無駄な訴訟をなくすために
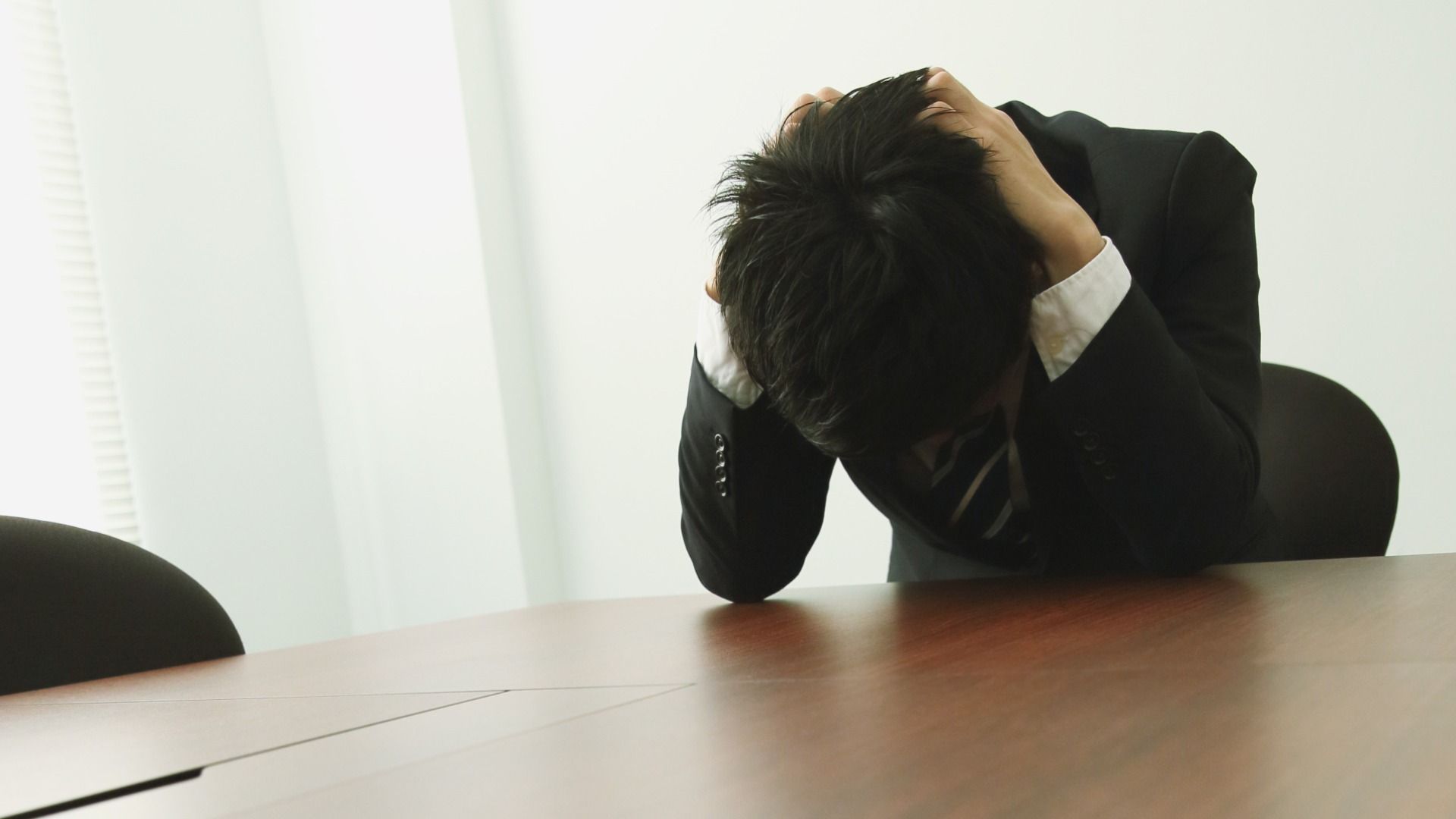
米国では、近隣トラブルのような小規模紛争の解決を目的とした組織(NJC:前記事で紹介)が存在し、それが有効に機能しています。しかし、我が国にはこのような社会システムが存在せず、そのため、小さなトラブルがエスカレートして大きな悲劇に繋がるケースが多く発生しているのです。その典型的な事例も既に紹介しました。
我が国にも様々な紛争解決のための制度がありますが、既に点検したように何れも近隣トラブルの解決には不十分です。近隣トラブルにはNJCのような解決システムが有効であり、我が国にも同様の組織が必要な時代になっています。ここでは、日本版の近隣トラブル解決センターを提案し、その内容について説明します。自治体関係者の方々には是非目を通して頂きたいと思います。
近隣トラブル解決センターの位置づけ
想定する近隣トラブル解決センターの紛争解決制度の中の位置づけについて説明します。下図は、既往記事(韓国でのマンション騒音殺人事件は典型的なケース、他国の話とスルーできない訳)で一度説明した紛争心理段階AHAに関して、それに対応した解決法を示したものです。

まず、トラブルの極めて初期の段階で、まだ相手に対して怒りや敵意の感情が湧いていない時には、当事者同士で話し合いを行うことが可能です。比較的冷静に話し合いが行われ、問題が拗れることなく、双方にとって納得の出来る解決策を自ら見つけ出すことができるからです。なぜなら、何を欲しているかは当事者自身が一番良く知っているからです。
しかし、当事者の間に相手に対する怒りや敵意が発生してしまった段階での、当事者同士だけでの話し合いは極めて危険です。この段階では、話し合いの中に相手に対する非難や攻撃の要素が必ず含まれてくるため、何の手立てもなくそのまま話し合いを行えば、必ず話し合いは決裂して口論に発展し、反って相手に対する憎しみが増大し、状況が更に悪化するだけに終わります。状況の悪化だけで済めばよいのですが、時には口論がエスカレートして突発的な殺傷事件などに繋がることもあり、現実に発生している騒音事件の多くがこのパターンです。
このような状況の話し合いには、両者の感情をうまくコントロールして冷静に話し合いを進める仲介者の存在が不可欠です。仲介者は公平中立であり、かつ非難や攻撃合戦に流れがちな話し合いを円滑に進めるだけの調停の技法を持ち合わせていることが要求されます。これらの詳細な調停の技術や進め方については、前記事の「米国式現代調停の技法」として、簡単な例を挙げて説明しました。この段階の解決の目標は、仲介者による調停によって当事者間の険悪な関係を改善することであり、それが実現すれば自ずと解決策が見つかってくることになります。すなわち、話し合いによって関係修復の余地が残されている状況がこの心理段階です。
トラブル心理の第2段階である敵意を感じる状態になると関係修復型の解決は極めて困難になります。敵意にステップアップする要因は、図にあるように相手の悪意を感じることであり、こうなると解決を求める気持ちより相手を許せない気持ちの方が強くなり、相手に何らかの報復を与えないと気が済まない状態となります。このような状況では、訴訟などの報復型の解決法で対応するより仕方なくなる。何らかの決着をつけなければトラブルは終了しないため、これもやむを得ない方法といえます。
トラブルの心理段階が更に進み、相手に攻撃性のパーソナリティ特性を感じるようであるなら、これは警察による対応を依頼する必要があります。とはいえ、実際に事件が起きるまでは警察の対応は鈍く、それが結局事件に繋がるという過去の事例も多いため、自分自身で最大限の防御的対処を行うことが肝要となります。
以上のように、トラブルに対する対応は、当事者の心理段階に応じてなされるべきものであり、トラブルの前段階、怒りの段階、敵意の段階、攻撃性の現れてきた段階によって各々対処が異なることを十分に認識しておかないと、解決はおろか、不慮の事件に巻き込まれる危険性もあるのです。
この心理段階の中で、我が国の紛争解決の社会システムとして不足しているのが、「怒り」の段階での関係修復型の解決システムです。この解決システムがないと、発生したトラブルは一気に敵意や攻撃性の段階に進んでいってしまい、解決は困難になります。この不備を補うためのシステムが、提案している近隣トラブル解決センターなのです。では、具体的にどのような組織なのかを以下に説明します。まず、近隣トラブル解決のための日本型の分担スキームについて説明し、その後、近隣トラブル解決センターの内容について説明します。
苦情、トラブルの分類による分担スキーム
近隣とのトラブルが発生して被害感を持った場合には、通常、役所や警察、あるいは保健所、時には学校といった公的な機関へ苦情を訴えるのが通常です。苦情を受けた自治体の職員たちは、事情の聴取や状況の確認を行ったのち、必要であれば相手方に注意や指導を行うというのが一般的な対応ですが、苦情の内容は様々であり、その内容に応じた適切な対処というものがあるはずです。この分類を図に示しました。

まず、典型7公害に分類される公害苦情や廃棄物などの苦情に関しては、公害等の発生者に対する行政的な指導や改善命令、改善勧告といった対応が有効な対処となります。法的にも、各種の公害関係の規制法や環境条例等に違反することが考えられ、直接的な被害者を生み出す可能性もあるので、強制的な手法も含めて速やかに解決を図らなければなりません。したがって、これらの苦情処理には自治体が当たることが望ましいといえます。
また、苦情により指摘される内容が極めて悪質な場合や暴力的な要素を持つ場合には、行政より警察による対処、すなわち警告や場合によっては検挙という処置を行うことも前提として、警察によるトラブル処理を行った方がよい場合があります。刑事事案に関する様々な情報や特殊な経験が必要とされることも多いため、所轄の警察の対応が望ましいといえます。
これらに属さない様々な苦情やトラブルが存在しますが、地方自治体等へのヒアリングによれば、その殆どは近隣関係によるものです。また、この件数が現在では最も多いということです。このような近隣関係のトラブルを、ここで提案する近隣トラブル解決センターで解決しようというものです。生活関連のトラブルや人間関係、ペットの苦情、コミュニティに関わる問題や、近隣が対象となる一部の騒音、悪臭などの苦情・トラブルなど、地域住民や勤労者、学生を対象としたトラブルの処理です。これらのトラブルは、基本的に当事者の話し合いで解決されるのが望ましいものであり、自治体の職員や警察が安易に介入すると、逆に状況が拗れて悪化する可能性があります。自治体や警察では十分に対応ができない近隣トラブルを、話し合いで解決するためのシステムが必要なのです。
日本版「近隣トラブル解決センター」の要点をまとめて以下に示しました。主なところは米国NJCと同様のシステムとなっています。
1) 公的紛争解決機関
近隣トラブル解決センターは、地域の自治体が設置し運営する。人口100万人程度に1カ所を想定し、各都道府県および政令指定都市に設置する。簡易裁判所の一部門として、民事調停の前段階の解決システムとして位置づけることも可能。
2)近隣トラブル等を処理対象
解決センターは、公害苦情以外の近隣トラブルや人間関係に関わるトラブル全般の解決を担う。
3)米国式現代調停による解決
解決手段は、ウインウインの解決を目指す米国式現代調停による。当事者同士が同席で話し合い、調停者の仲介により当事者同士の関係修復に基づく解決を目指す。調停者による調停案の提示はなく、当事者同士が解決案を話し合う。
4)ボランティア調停員の活用
調停は市民ボランティアが担当し、所定の調停技法に関するトレーニングを受けてこれにあたる。
5)無料の住民サービス
解決のための調停プロセスは、地域住民に無料で提供される。トラブルの早期ピックアップによる早期解決をめざし、解決センター職員は積極的にトラブルに係わる。
米国型の紛争解決システムを日本に導入してうまくゆくのかとの懸念は杞憂と考えます。訴訟数や弁護士数などの違いはありますが、基本的に米国と我が国での状況に大きな違いはないため、十分に成立すると考えられます。日本人には、アメリカ人のように面と向かって議論するような土壌がないため、調停が有効に機能するか疑問であるとの意見もありますが、これはあくまで調停員のスキルの問題であり、十分にトレーニングを受けた有能な調停員が事にあたれば問題はないといえます。
また、このような近隣トラブルの無料の解決センターなどができると、苦情を誘引して、逆に苦情件数が増えるのではないかという指摘もあるかと思いますが、近隣トラブル解決センターの認知度が高まれば、上記のような面も現れてくる可能性は十分に考えられます。しかし、近隣トラブルでは、初期の段階の対応が特に重要であることを考えれば、トラブルがエスカレートする前の些細な段階で話が持ち込まれることは、解決も容易になり、むしろ好ましいことであるといえます。したがって、苦情を誘引するということではなく、今まで埋もれていた苦情を処理できるということであり、決してマイナスの効果ではありません。
近隣トラブル解決センターで事案を受け入れ、解決プロセスに乗せるためには、自治体の担当部署や警察、あるいは保健所などとの連携が不可欠であり、これがないと解決センターは十分に機能しません。また、公的機関であり、自治体や警察との連携が成立しているということが、トラブル当事者にセンターでの解決の期待を持たせることにもなり、トラブル処理の入り口での対応として大変重要です。自治体の担当部署や警察などとの連携を確保しつつ、トラブル苦情の内容に応じた対処の住み分けにより、トラブル事案を有効に解決に結びつけることが可能となり、最終的には地域住民の安心安全に関する満足度が向上することに繋がります。
最後に、我が国の現在のトラブル処理体制というものを図化すると下図の通りとなります。前記事で示したNJCのシステム図と較べると、これは解決システムや処理体制と呼べるものではないことは明白であり、現状の体制の不十分さが認識できるでしょう。トラブルに巻き込まれた時、相談できる場所があることだけでもトラブルの心理負担は軽減します。今はそれもありません。悲惨な事件や無駄な訴訟をなくすために、日本にも「近隣トラブル解決センター」が必要です。











