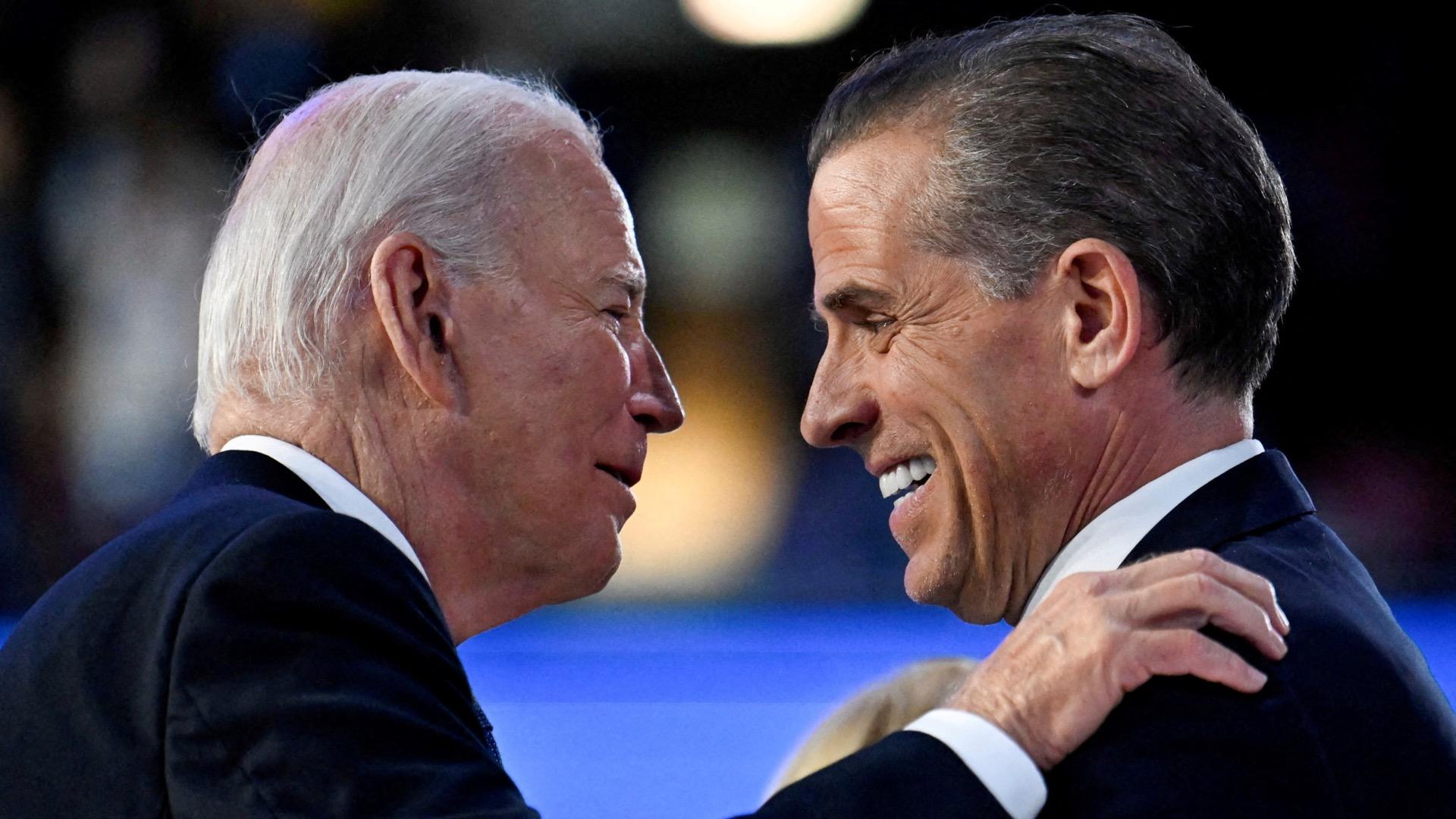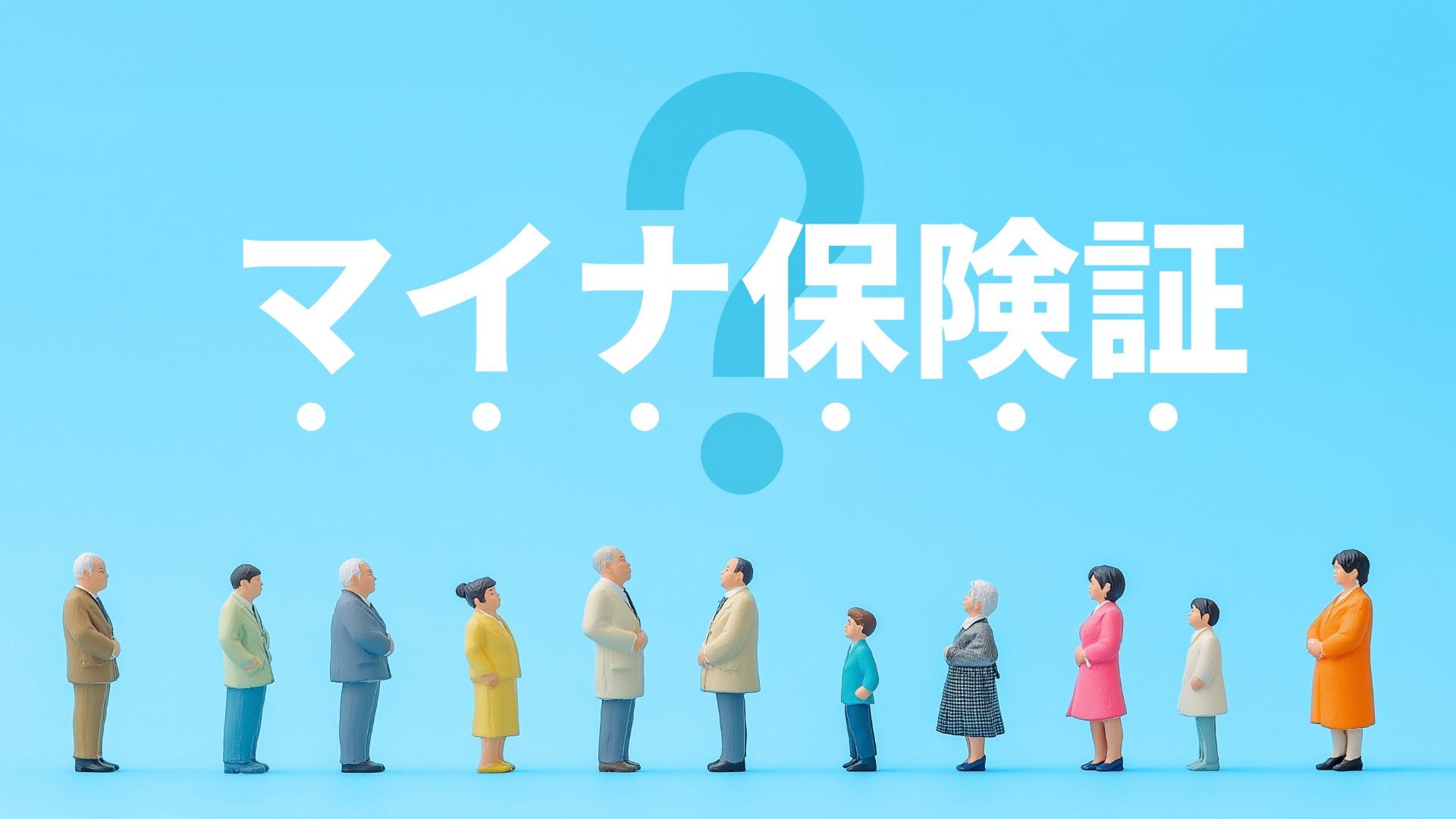今週末にかけて大きな移動性高気圧による晴天と気温上昇 日本は春と夏の二季に

大きな移動性高気圧
令和6年(2024年)5月2日は、本州南岸の前線上を低気圧が通過したあと、大陸から大きな高気圧が移動してきました(タイトル画像)。
このため、南西諸島を除いて、晴天域が広がってきましたが、寒気が残っているため最高気温が25度以上の夏日を観測したのは17地点(気温を観測している全国914地点の約2パーセント)にとどまり、最低気温が0度未満の冬日は80地点(約9パーセント)もありました。
ゴールデンウィークが始まった頃の4月28日(日)には、夏日が521地点(約57パーセント)もあるなど、記録的な暑さとなった時に比べれば、寒く感じられますが、これで、ほぼ平年並みです(図1)。

移動性高気圧がかなり大きいため、5月3日は西日本~北日本の広い範囲で晴れる見込みです。
ただ、南西諸島では雲が多く、所により雨で雷を伴うでしょう。梅雨入りの平年は沖縄で10日、奄美で12日ですので、沖縄・奄美地方ではそろそろ梅雨入りの気配です。
今週末にかけて低気圧が接近する北海道と前線に近い沖縄で雲が多い他は、大きな移動性高気圧に覆われるため、晴れて気温が上昇し、5月4日のみどりの日は、4月28日には及ばないものの、全国の約45パーセントで最高気温が25度以上の夏日となると予想されています。
紫外線も強くなっていますので、屋外で行動するときは、暑さと紫外線に注意してください。
今年の気温の変化傾向
今年の東京の最高気温と最低気温の変化傾向を見たのが、図2です。

最高気温は、1月は平年より高い日が多く、下がってほぼ平年並みでした。2月は、20日に23.7度という記録的な暖かさとなったあと、23日には4.0度まで一気に寒くなるなど、寒暖差が大きくなっています。
寒暖差が大きい傾向は3月も続き、3月31日には最高気温が28.1度と、あとわずかで最高気温が30度以上の真夏日となるところでした。
最低気温も、最高気温と同様に、平年より高い日が多く、下がってほぼ平年並みとなっています。
最高気温・最低気温ともに、5月1日から2日は平年並みでしたが、3日以降は平年より高くなる見込みです。
天気は、ゴールデンウィーク後半は晴れの日が続き、ゴールデンウィーク明けの7日から9日は、低気圧が本州付近を通過するため雨の予報ですが、気温は平年より高く推移しそうです(図3)。

来週や再来週の予報をみると、これまでに比べ、傘マーク(雨)や黒雲マーク(雨の可能性がある曇り)が増えてきました。
降水の有無の信頼度が5段階で1番低いEが多い予報ですが、梅雨の気配がそろそろしそうです。
気温が平年より高い日が多い傾向は、東京だけでなく全国的です。
年平均気温偏差は年によって増減がありますが、長期変化をみると、どんどん気温が上昇していることを示しています。
また、気温偏差が一番大きかったのは、去年、令和5年(2023年)の1.29度とずば抜けて高い値となっています。
また、2位が令和2年(2020年)の0.65度、3位が令和元年(2019年)の0.62度、4位が令和3年(2021年)の0.61度、5位は令和4年(2022年)の0.60度と、年平均気温偏差の高い年の上位5位まで令和が独占しています。
つまり、令和という年は、これまですべてでランクインです。
令和5年(2023年)は、1月こそ-0.03度と僅かにマイナスでしたが、その他の月はプラスで、特に3月と9月は大きなプラスでした(図4)。

今年、令和6年(2024年)も、4月まで各月で平年を上回っています。つまり、15か月連続で平年を上回っています。
そして、1月から4月までを比べると、令和6年(2024年)は、記録的な暑さの昨年、令和5年(2023年)を上回っています。
つまり、令和の6年間で、年平均気温偏差の高い年の上位6位までを独占する可能性があります。
近年は、昔の夏期間の始まりの気温は、気温上昇によって1ヶ月ほど早い時期になり、昔の夏期間の終わりの気温も、気温上昇によって半月から1ヶ月遅くなっています。その結果、夏期間は昔に比べてかなり長くなっています。
また、夏が早く始まりますが、春に気温上昇量が一番大きいことから、春の終わりの時期が早まりより、春の始まりの時期が大きく早まることで、春期間も長くなっています。
これに対し、厳しい残暑によって秋が始まる時期が大きく遅くなるわりには、秋が終わって冬になる時期が遅くならないため、秋期間は短くなります。
そして、冬期間は始まりが遅く、終わりは早いということで、寒い時期は昔に比べてかなり短くなり、寒くなっても一時的ということになります。
令和は記録的な暑さの時代で、これまでの「春夏秋冬の四季」というイメージとは違い、「春と夏の二季」というイメージになりそうです。
タイトル画像、図3の出典:ウェザーマップ提供。
図1,図2の出典:ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成。
図4の出典:気象庁ホームページをもとに筆者作成。