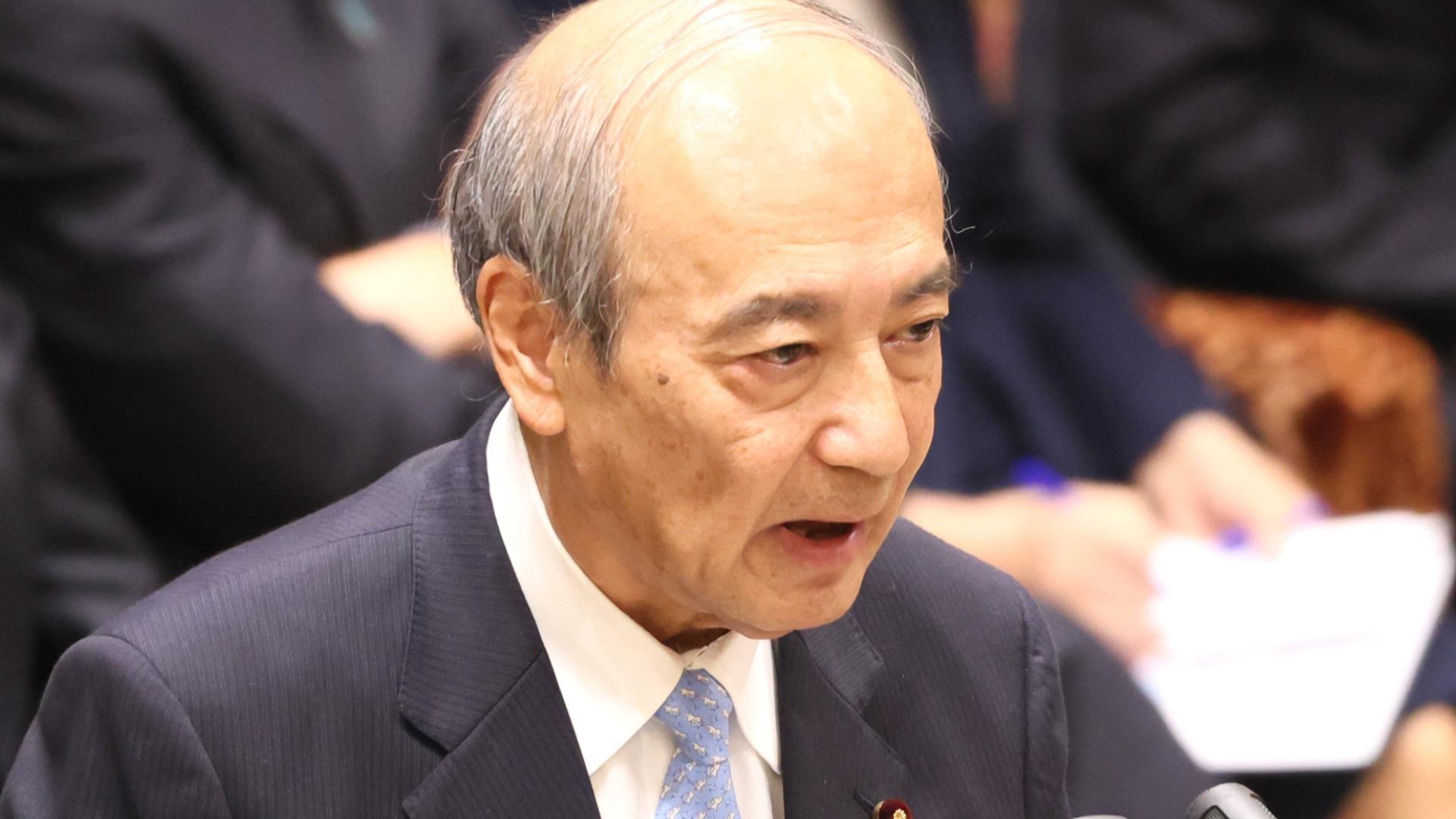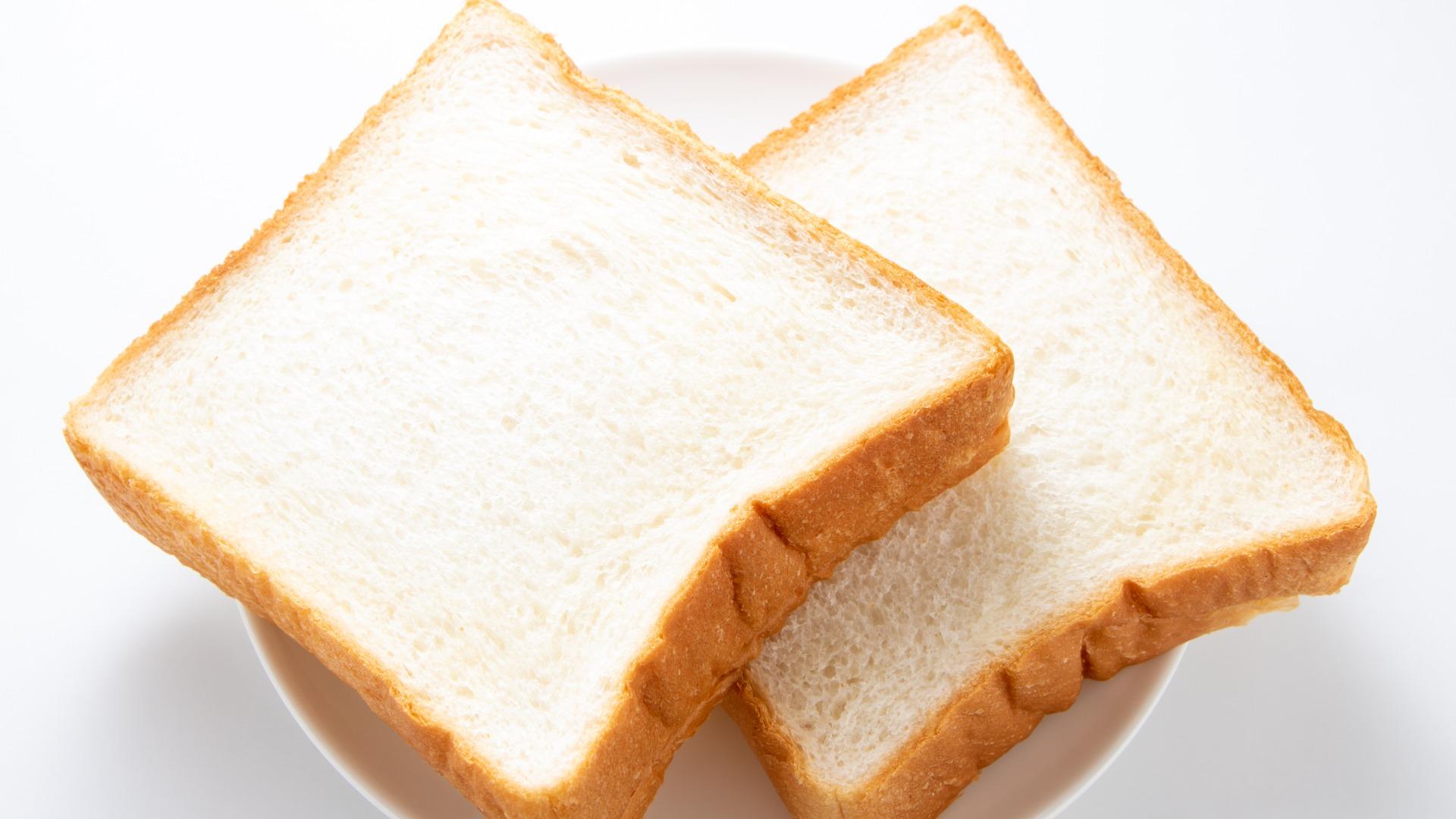松平家康の大ピンチ!三河一向一揆が勃発した原因について、有力な2つの説を比較する

大河ドラマ「どうする家康」では、三河一向一揆が勃発した。今回は、三河一向一揆が勃発した原因について、深掘りすることにしよう。
永禄6年(1563)の秋、三河一向一揆が勃発した。『松平記』などは、永禄5年(1562)に三河一向一揆が勃発したとするが、現在では誤りであると否定されている。なお、三河一向一揆の顛末については、こちらを参照ください。
肝心なことであるが、三河一向一揆に関する一次史料は皆無に等しいため、先述した『松平記』のほか、『三河物語』などの二次史料に拠らなくてはならない。そうした事情が研究を難しいものにしている。
三河一向一揆が勃発した理由については、主に2つの理由が指摘されている。1つは「不入特権侵害説」、もう1つは「流通市場介入説」である。以下、その2つの説を簡単に紹介しておこう。
①不入特権侵害説
松平家康は三河支配を展開するなかで、一向宗寺院が保持していた不入の特権を侵害した。不入とは、権力者の使者が年貢の徴収のため、田畠などに入ることを拒否する権利である。家康は、その特権を侵害したというのである。
②流通市場介入説
こちらも家康が三河支配を展開するなかで、一向宗寺院が保持していた水運、商業などの特権を掌中に収めようとした。それゆえ、一向宗は猛反発し、三河一向一揆が勃発したというのである。
この2つの説が有力視されているが、決定的な裏付け史料がないので、決め手に欠けるというのが現状である。ここで重要なのは、当時の家康が今川氏と交戦状態にあったことである。
戦争には兵糧米が必要なのだから、一向宗寺院からも徴収する必要があった。一説によると、家康は兵糧米の徴収をめぐって一向宗寺院とトラブルになったので、一向宗は反松平勢力と結託し、一揆を催したという。
当時の状況を考えると、もっとも穏当な説ではないだろうか。
〔主要参考文献〕
新行紀一『一向一揆の基礎構造』(吉川弘文館、1975年)
煎本増夫『幕藩体制成立史の研究』(雄山閣出版、1979年)
中野和之「戦国期三河本願寺門徒団における『一向一揆』」(『仏教史研究』19・20号、1984年)
本多隆成『定本 徳川家康』(吉川弘文館、2010年)