1964年生まれ。上智大院修了。テレビ朝日で「ニュースステーション」ディレクターなどを務める。2002〜3年フルブライト・ジャーナリストプログラムでジョンズホプキンス大研究員としてイラク戦争報道等を研究。05年より立命館大へ。08年ジョージワシントン大研究員、オバマ大統領を生んだ選挙報道取材。13年より現職。2019〜20年にフルブライトでジョージワシントン大研究員。専門はジャーナリズム。ゼミではビデオジャーナリズムを指導し「ニュースの卵」 newstamago.comも運営。民放連研究員、ファクトチェック・イニシアチブ(FIJ)理事としてデジタル映像表現やニュースの信頼向上に取り組んでいる。
関連リンク(外部サイト)
記事一覧
1〜25件/48件(新着順)
 ジャーナリズムとは何かを再考する(4の後編) 大学生でもできる「普遍化」の考え方とは
ジャーナリズムとは何かを再考する(4の後編) 大学生でもできる「普遍化」の考え方とは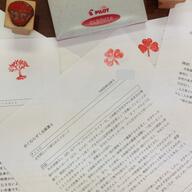 ジャーナリズムとは何かを再考する(4の前編) 「『エモい』だけの記事」の原因とは?
ジャーナリズムとは何かを再考する(4の前編) 「『エモい』だけの記事」の原因とは?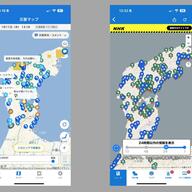 発生から10日:能登半島地震報道を振り返りメディアの課題を考える(後編:デジタルで「寄り添う」とは)
発生から10日:能登半島地震報道を振り返りメディアの課題を考える(後編:デジタルで「寄り添う」とは) 発生から10日:能登半島地震報道を振り返りメディアの課題を考える(前編:テレビの速報を検証する)
発生から10日:能登半島地震報道を振り返りメディアの課題を考える(前編:テレビの速報を検証する)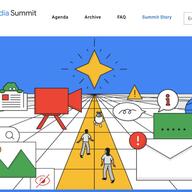 生成AIの脅威にファクトチェッカーはコラボで対抗する:「信頼されるメディアサミット」報告(その1)
生成AIの脅威にファクトチェッカーはコラボで対抗する:「信頼されるメディアサミット」報告(その1)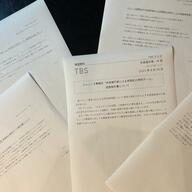 ジャニーズ問題の収束にテレビや業界に覚悟はあるか?ー「納得できる解決への道筋」を考える
ジャニーズ問題の収束にテレビや業界に覚悟はあるか?ー「納得できる解決への道筋」を考える ポリティファクトに政治ファクトチェックの意味を聞く 〜Global Fact10報告(その5)
ポリティファクトに政治ファクトチェックの意味を聞く 〜Global Fact10報告(その5)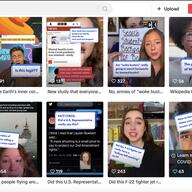 Z世代はティックトックでファクトチェックを伝える 〜Global Fact10報告(その4)
Z世代はティックトックでファクトチェックを伝える 〜Global Fact10報告(その4) ファクトチェッカーが「コミュニティノート」に慎重な理由 〜Global Fact10報告(その3)
ファクトチェッカーが「コミュニティノート」に慎重な理由 〜Global Fact10報告(その3)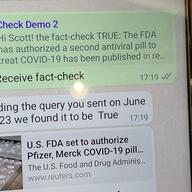 エンジニアが取り持つ「予防的ファクトチェック」〜Global Fact10 報告(その2)
エンジニアが取り持つ「予防的ファクトチェック」〜Global Fact10 報告(その2) 「コンテンツ・モデレーション」という難問 〜Global Fact10報告(その1-後編)
「コンテンツ・モデレーション」という難問 〜Global Fact10報告(その1-後編) あの時ツイッターで何が起きていたのか 〜Global Fact10報告(その1-前編)
あの時ツイッターで何が起きていたのか 〜Global Fact10報告(その1-前編) ジャーナリズムとは何かを再考する(3)「オフレコ破り」の背景と「その先」の議論をしよう
ジャーナリズムとは何かを再考する(3)「オフレコ破り」の背景と「その先」の議論をしよう 「鳥は本物じゃない」運動で見えた「陰謀論」の生態系:Global Fact 9 報告(その2)
「鳥は本物じゃない」運動で見えた「陰謀論」の生態系:Global Fact 9 報告(その2) 誤情報の背景にあるストーリー全体をファクトチェック: Global Fact 9 報告(その1)
誤情報の背景にあるストーリー全体をファクトチェック: Global Fact 9 報告(その1) 「ジャーナリズム」とは何かを再考する(2)面白くてためになるニュースのために必要なこと
「ジャーナリズム」とは何かを再考する(2)面白くてためになるニュースのために必要なこと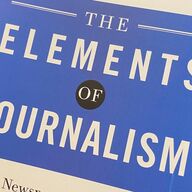 「ジャーナリズム」とは何かを再考する(1)『ジャーナリズム10の原則』をかみしめる
「ジャーナリズム」とは何かを再考する(1)『ジャーナリズム10の原則』をかみしめる メディアの「独立」と「信頼」を、Choose Life Project、読売新聞と大阪府から考える
メディアの「独立」と「信頼」を、Choose Life Project、読売新聞と大阪府から考える ワクチンの議論で見えた「限界と課題」 コロナで変わるファクトチェック:ふたつの国際会議から(下)
ワクチンの議論で見えた「限界と課題」 コロナで変わるファクトチェック:ふたつの国際会議から(下) 日本で拡がらない理由を再考する コロナで変わるファクトチェック:ふたつの国際会議から(中)
日本で拡がらない理由を再考する コロナで変わるファクトチェック:ふたつの国際会議から(中)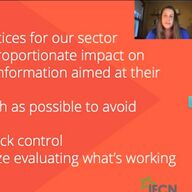 ファクトチェッカーのメンタルが危ない コロナで変わるファクトチェック:ふたつの国際会議から(上)
ファクトチェッカーのメンタルが危ない コロナで変わるファクトチェック:ふたつの国際会議から(上)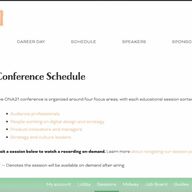 障がい者、マイノリティもアクセスできるジャーナリズムという考え方 〜ONA21での議論から
障がい者、マイノリティもアクセスできるジャーナリズムという考え方 〜ONA21での議論から 五輪報道で何に注目するか 〜異常事態で問われるジャーナリズム
五輪報道で何に注目するか 〜異常事態で問われるジャーナリズム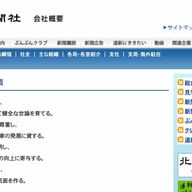 北海道新聞が読者の信頼のために踏むべき手順とは 〜旭川医大の事件から、全メディアに考えてほしいこと
北海道新聞が読者の信頼のために踏むべき手順とは 〜旭川医大の事件から、全メディアに考えてほしいこと 東日本大震災から10年:報道各社のインタビューを見直し、考えた
東日本大震災から10年:報道各社のインタビューを見直し、考えた





