【戦国時代】敵将へ嫁ぐことになった美しき姫君たち!過酷な運命にも自らを貫いて生きた女性・3選
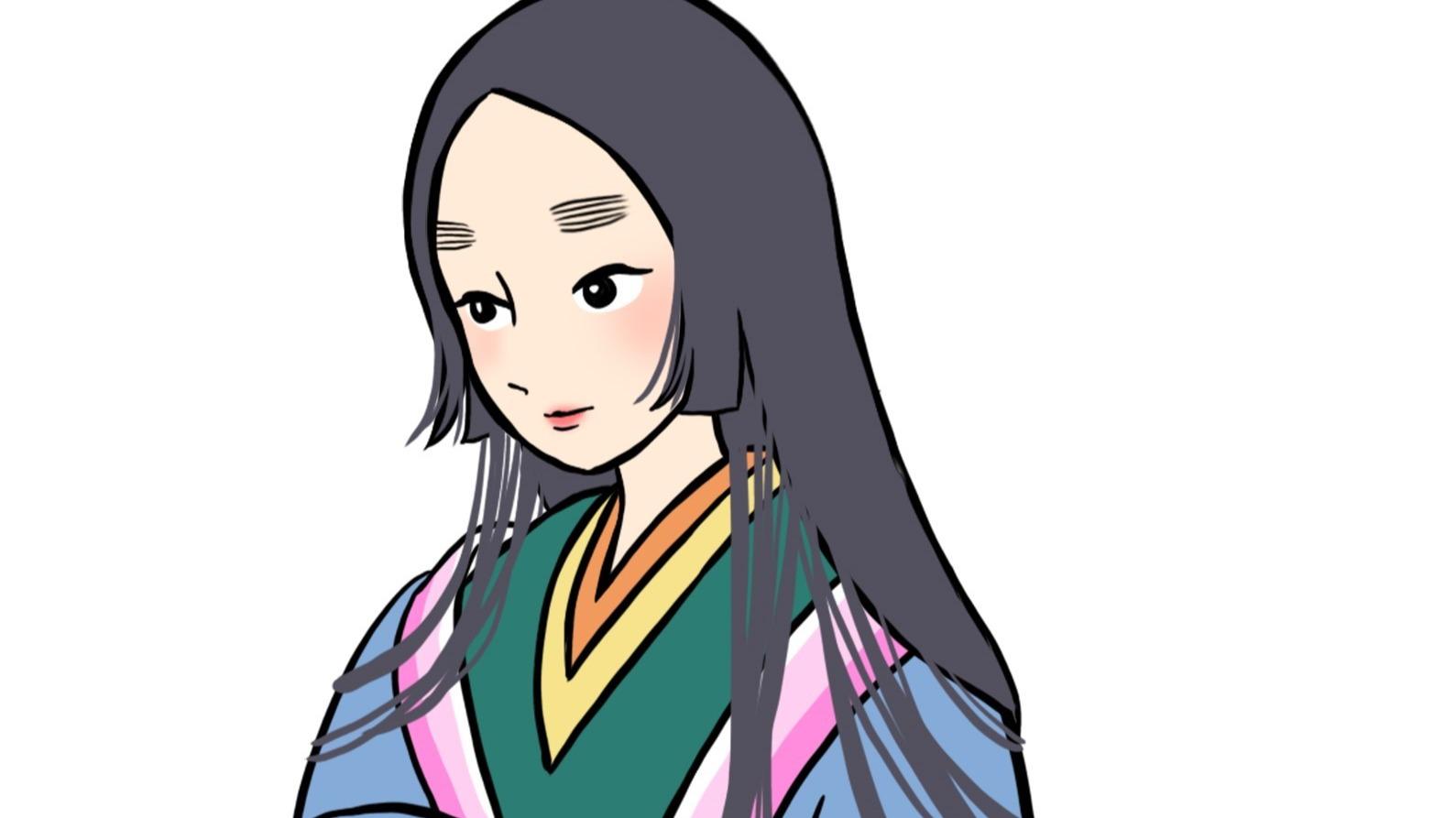
昔の名家・・とりわけ乱世の時代にあっては、自分達の一族が生き残りを図るため、政略結婚は当たり前に行われていました。
しかし敵・味方の陣営がめまぐるしく変化する戦国時代にあっては、嫁ぎ先が出身勢力の敵となってしまったり、敗北して敵陣営に生き方を決められてしまう例もありました。
そうした激動の運命に放り込まれた姫君は、どのように当時を生き抜いて行ったのでしょうか。この記事では、そうした中でもとくに際立つ、3人の女性をピックアップして、ご紹介したいと思います。
①諏訪姫(すわひめ)~亡国から天下人の母を目指す~

彼女は武田信玄の側室にして勝頼の母という重要人物ですが、その足跡は不明な点も多い、たいへんミステリアスなお姫様です。
後の記録では“かくれなき美人”とも評されていますが、もともとは信玄と敵対した諏訪氏の娘でした。しかし父が戦いに敗れ、諏訪家が武田家に乗っ取られる形になると、信玄に嫁がされる運命となったのです。
かつて大河ドラマ“風林火山”では「そのような辱めなど受けぬ!」とばかり自害しようとしますが、主人公の山本勘助に「私があなたのお子を、武田家の跡取りにしまする!」と、説得されるシーンが描かれました。

「お館様はいずれ天下をお取りになるお方。さすれば、あなたのお子が天下を治めることになりまする」と、一時の恥を捨てて壮大な夢を目指すように言い、作中で勘助はことあるごとに諏訪姫を支えていました。
実際に勝頼は武田家の最大版図を築いたと言われ、一時は信長や家康の勢力を、押していた時期もあります。結果的には届かなかったとはいえ、天下取りレースの有力候補だったとも言うことができ、あながち絵空事ばかりではなかったかも知れません。
しかし、もともと信玄には正室やその息子も存在した上、武田家の家臣たちにとってみれば、諏訪姫は敵対して戦った一族の出身です。とうぜん全員からは良く思われず、そうしたなか子の勝頼を後継ぎにまで育て上げた精神力と手腕は、並大抵ではありません。
運命に翻弄されながらも未来への展望をあきらめず、自らの意志を貫いた姫君と言うことができるでしょう。

なお余談ですが、現代では長野県諏訪市の公式キャラクター“諏訪姫”として、萌え要素を取り入れた、可愛らしいビジュアルでも描かれています。

日本を代表する祭りのひとつ、御柱祭でも有名な諏訪市ですが、訪れた際にはぜひ諏訪姫の足跡にも思いを馳せると、より味わい深いかも知れません。
②お市の方~子孫に天下の行く末を託して~
戦国の覇者となった織田信長の妹にして、記録では“日本一の美貌”とも評されている、お市の方。
それだけ耳にすると、何とも羨ましい身の上に思えてしまいますが、彼女もまた乱世の荒波に翻弄される運命を辿りました。

当初、信長がともに天下統一を目指した大名、浅井家に嫁いで2男3女を授かったと言われ、そこまでは幸せな人生と言えたかもしれませんが、夫の浅井長政が織田家と敵対関係に。
夫と主家の板挟みとなってしまいますが、浅井家が滅ぼされた際は両軍の計らいで、命を助けられます。その後は織田家の有力武将、柴田勝家と再婚するも、今度は彼が秀吉と敵対関係に。
またも嫁ぎ先が滅ぼされ、3人の娘は城から脱出させるも、自らは夫とともに自刃して運命をともにしました。

ちなみに2023年の大河ドラマ“どうする家康”の脚本では、非常にプライドの高い人物として表現され、戦時中は甲冑姿で現れたり、秀吉に「気安く触るでない」とビンタするシーンも、印象的でした。
彼女を演じた北川景子さんは、お市の方はどのような相手でも物怖じせず、もし男に生まれていたならば、自ら出陣したいと考えるような人物像を意識したとコメントしています。
一方で感情のみならず、女性の身では武将たちの様な権力は振るえず、秀吉に娘たちを連れて行かれるときも、抗うことは出来ないと現実を直視。
そうした過酷な現実にあっても世を嘆かず、強く生き抜いた人物像には、演技を通じて勇気をもらったと語っていました。

お市の方も、その足跡だけを辿ると悲劇にも見えますが、人生の幸不幸は他人からは簡単に推し量れない部分もあります。
3女の「お江の方」は徳川幕府2代将軍・秀忠の妻となり、2人の間に生まれた子は3代将軍の家光となりました。
また末娘はやがて天皇に嫁いで皇后となるなど、お市の方から連なる血統は、日本の歴史の中核とも言える部分を担っています。
その強くうつくしい生き様は、子孫へと受け継がれており、そのとき蒔かれた種は後の世に花開いたと、そのように解釈することも出来るのではないでしょうか。
③甲斐姫(かいひめ)~最強の敵勢にも屈しない姫武将~

ときは戦国時代の後半、甲斐姫は関東の小勢力、成田家という大名の長女でしたが、彼女もまた“東国無双の美人”と評される記録が残されています。
しかも、ひとたび合戦となれば自ら鎧をまとって出陣、勇ましく最前線で戦ったという、昨今のアニメや小説の創作も顔負けなエピソードで、伝説となっているお姫さまです。
主家の力が強大であれば、主君の一族を「前線に出させるなんて、とんでもない」と止められたかも知れませんが、小勢力で余裕がない状況であれば「全員が何でもやらなければ」という風潮にもなりやすかったでしょう。もしかすると甲斐姫が戦場に立った背景にも、そうした経緯があったのかも知れません。

ちなみに敵勢は、成田家とは比較にならない豊臣家の大軍であり、しかも率いるのは名立たる名将ぞろいでした。
通常であれば即刻、降伏しても当然な戦況にあっても屈せず、甲斐姫は「ひるむな!」と叫びつつ、自らナギナタで敵兵をなぎ倒し、成田兵を鼓舞したと伝わります。
そのうえ戦国武将の中でも頂点レベルの軍才をほこる、真田幸村の軍が攻め寄せたときも、一歩もひるまず城を守り切ったという言い伝えもあり、そんなエピソードには思わず胸が熱くなってしまいます。

このように、もともと甲斐姫の一族は豊臣家と敵対しましたが、秀吉が天下を統一すると甲斐姫の存在に興味を持ち、みずからの側室に指名。
日本全国を掌握した秀吉が、一度は逆らった勢力の人物を名指ししたのですから、いかに甲斐姫が類まれな女性だったか、うかがい知れます。
いちやく天下人の妻となれることは嬉しかったのか、それとも仕方ないと従ったのかは、彼女自身にしか分かりません。しかし、ただでさえ女性の思い通りにならない乱世を、縦横無尽に生き抜いた生涯は、歴史上でもひときわ異彩を放っています。
彼女の活躍については、後世に様々な尾ひれがついた可能性もありますが、そうした点を差し引いても、天下に名をはせた“姫武将”として、思わずロマンを感じずにはいられない女性です。
敵将へ嫁ぐことになった戦国の姫君たち

このように、戦国時代には容赦なく迫りくる過酷な運命を、ときに強く、ときに巧みに立ち回った姫君が存在していました。
最近は様々な歴史作品で、こうした女性の生き様がクローズアップされる機会も増えましたが、天下統一を目指して武将たちが激しく戦う裏側で、懸命に生き抜いた女性たちの姿があったことも、歴史のたいへん興味深い一面です。










