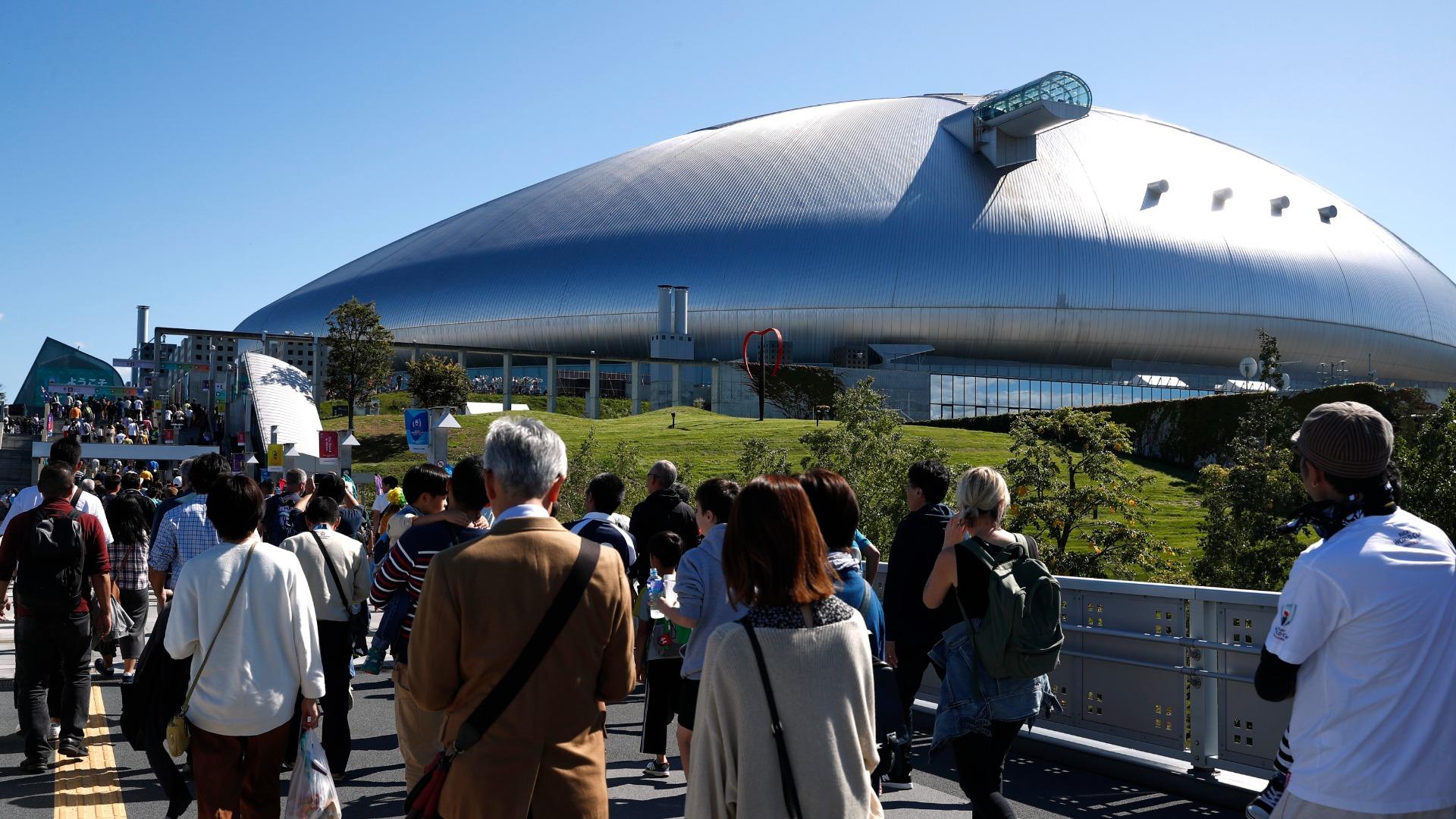【深読み「鎌倉殿の13人」】源頼朝が弟の義経を上洛させた、その深い意味を考える

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」第15回では、源義経が兄・頼朝の命により上洛した。その深い意味を掘り下げてみよう。
■源頼朝、弟に出陣を命ず
寿永2年(1183)7月、木曽義仲は平家の軍勢を蹴散らして、晴れて入京を果たした。しかし、義仲配下の将兵が飢饉のため、食糧を強奪するなどしたので、早々に朝廷以下、京都市中の人々から敬遠された。
寿永2年(1183)10月、源頼朝は後白河法皇から「寿永2年の宣旨」を獲得し、東国支配の根拠を得た(「寿永2年の宣旨」の詳細はこちら)。これだけでなく、宣旨には大きな効果があった。
早速、頼朝は後白河から「寿永2年の宣旨」を獲得したことを宣伝し、とりわけ「東海、東山、北陸の3道の荘園を元に復すること」を重要視した。
当時、北陸道に基盤を置いていたのは、木曽義仲だった。頼朝は北陸道を含めた東国の年貢を後白河に運上することを名目とし、上洛しようとしたのだ。ただ、この段階では、義仲討伐を目的にしていたのか不明である。
とはいいながらも、同年閏10月には、頼朝配下の武将が奥州の藤原秀衡のもとに馳せ参じたという噂が流れていた(『玉葉』)。秀衡はこの情報を義仲に流し、東西から頼朝を攻めようとしたという。むろん、この作戦は実行に移されなかった。
そもそも頼朝は自らが出陣して、上洛するつもりだった。しかし、天候不順による飢饉により、京都が深刻な食糧不足に陥っていることなどを知り断念した。あるいは、秀衡の鎌倉襲撃を恐れた可能性もあろう。
■源義経の出陣
そこで、頼朝は弟の源義経と配下の中原親能に出陣を命じた。義経に出陣を命じたのは、頼朝の名代としての地位だったのは明白だろう。ほかの有力な御家人ではなく、義経でなくてはならなかった。しかし、義経の知名度は低く、『玉葉』には仮名の「九郎」としか書かれていない。
大河ドラマの義経ほど酷くないにしても、まだ世間知らずだったのは疑いない。そこで、重要な役割を演じたのが、かつて下級貴族として活躍した親能である。義経が軍事的な面を任されたのに対し、親能は来るべき朝廷との交渉に当たる役割を期待されていた。
この頃になると、親能のほか、三善康信、大江広元ら京都の下級貴族の出身者は、頼朝のブレーンとして活躍していた。武官と文官の期待される役割は、明確だったようだ。
■京都に迫る軍勢
義経が率いる軍勢は、やがて伊勢に入り、着々と京都を目指した。この情報は義仲の耳にも入り、その動きを牽制するのに十分だったといえよう。その後、義仲は京都市中でさまざまな対応に追われていた。
『玉葉』によると、当初、義経の軍勢は数万と言われていたが、実際はわずか500~600にすぎなかった。やがて後白河が幽閉されるなどしたので、義経は速やかな入京を促された。
しかし、義経にはその判断ができず、ただちに鎌倉に飛脚を送り、頼朝の指示を仰ごうとした。つまり、義経は軍勢を率いて上洛したものの、何ら権限がなかったのである。
翌年の寿永3年(1184)1月、頼朝は義仲と戦うことを決意し、義経をその先陣に命じた。そして、弟の範頼に数万の軍勢を授け、義経の援軍に向かわせたのである。
■むすび
大河ドラマを見る限り、義経は義仲討伐にやる気満々だったが、実際はそうでもなかった。そもそもは威嚇、牽制が目的だったが、後白河の危急により、義仲討伐に舵を切ったのが真相だろう。両者の戦いについては、後日改めて詳しく検討することにしよう。