最初に予報円で予報が発表されたのは昭和57年6月の台風5号・三陸沖での大きな予報誤差で大問題に
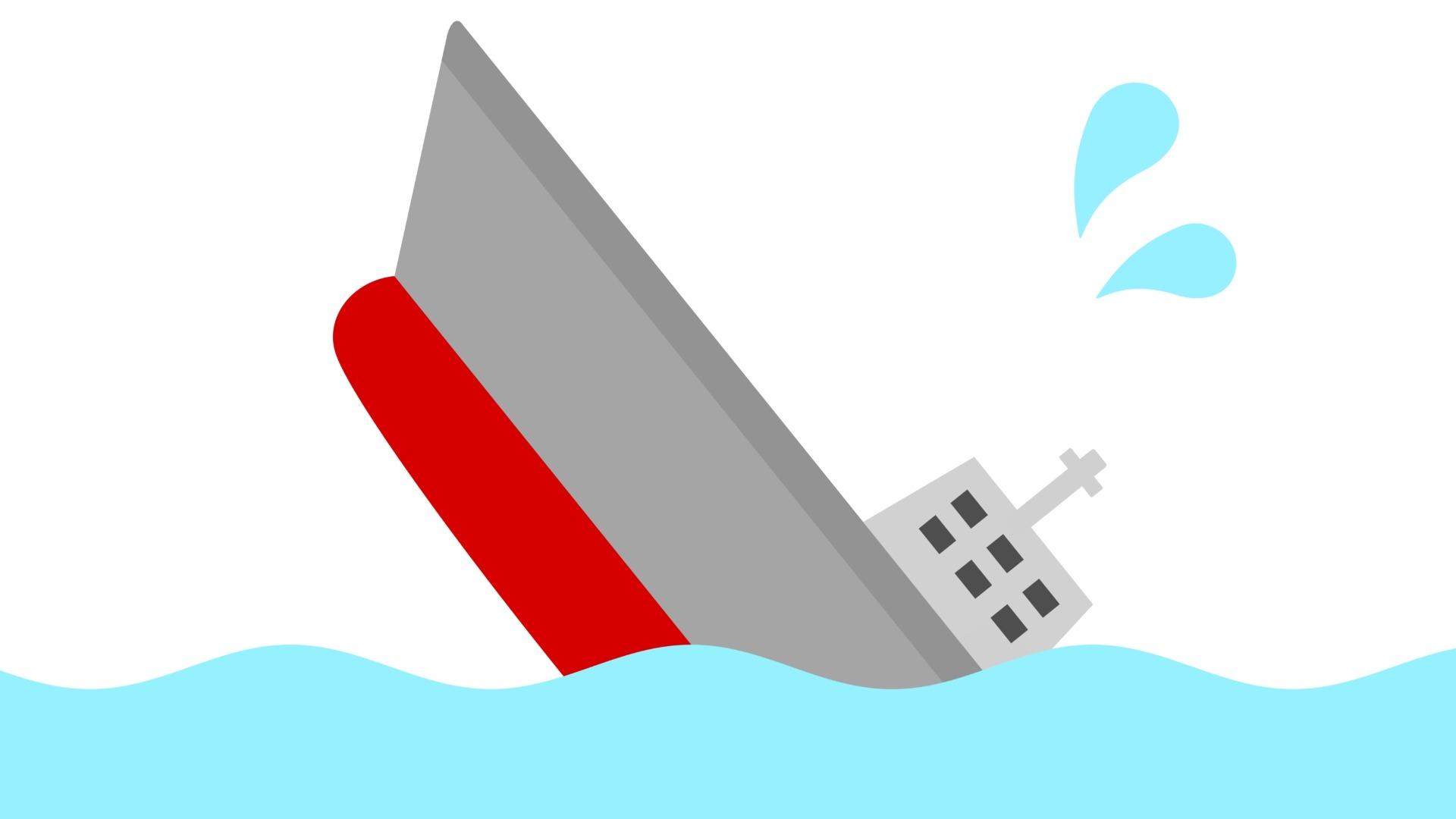
台風の予報円表示
いまでは予報円が当たり前のように使われていますが、台風予報円が最初に使われたのは今から42年前の昭和57年(1982年)6月の台風5号からです。
戦後の日本は、大きな台風災害が相次ぎ、死者が4桁(1,000名以上)の大惨事となるのが珍しくありませんでした。それを何とか減らせないかと予測の上でも様々な努力がなされてきました。
たとえば台風予報の扇形表示もその1つです。
台風の24時間先予報において、気象庁では、台風の進行方向だけでも予報しようと、昭和57年(1982年)5月までの約30年間、誤差幅をつけた「扇形表示(進行速度は難しいので一本の線上に表示)」を使っていました。
第二次大戦後の相次ぐ台風災害の中で、予報精度が非常に悪くても、何とか進行方向だけでも正しい予報を出して防災に役立てようとする当時の予報官達の苦労の結晶が「扇形表示」です(図1)。

しかし、最初から大きな欠点を持っていました。それは、予報誤差には、進行方向と進行速度の2種類があるのですが、扇形表示ではその形から、進行速度の誤差が全くないかのような印象を与え、「台風はまだ来ないだろう」と人々に誤った判断をさせてしまったことです。
そこで考えられたのが、「予報円」を用いた表示方法です。台風の予報誤差には、進行方向と進行速度の2種類がありますが、多くの例で調査すると、両方の誤差がはぼ等しく、予報位置を中心とした分布となっています。
精度の良い予報になればなるほど予報位置の周りに集中した分布となり、精度の悪い予報ほど周辺部にも広がっている分布となります。
気象庁の発表する予報円表示の予報円は、表示の簡明さ、情報伝達のわかりやすさ等を考え合わせ、円の中に70%の予報が入るということで半径を決めた予報円を採用しています。
このため、予報円の半径は、ほぼ台風の進路予報誤差の平均に対応しています。
昭和57年(1982年)の台風5号
最初に予報円表示をした台風は、今からちょうど42年前、昭和57年(1982年)6月下旬の台風5号です。
6月21日15時にフィリピンの東で発生した台風5号は、発達しながら小笠原近海を北上し、日本の南から小笠原諸島近海に進んでいます。
このときの台風進路予報は、概ね正確で、予報円の中に入っている予報でした(図2)。

しかし、関東の南東海上を進む6月26日15時頃からは、予報が大きく外れています。
気象庁は、台風5号は加速しながら北東進するという予報を続けていましたが、実際は三陸沖をほぼ等速度で北上し、6月27日15時には温帯低気圧に変わっています(図3)。

6月27日3時に発表した24時間先の予報は、実際の台風の位置との誤差が1070キロもあるなど、台風5号が小笠原諸島から三陸沖を北上しているときの進路予報誤差は、のきなみ大きなものでした。
このため、三陸沖では、台風が東海上にそれると思っていた漁船群が台風5号に巻き込まれています。
増澤譲太郎気象庁長官は、立平良三予報課長も同席した6月30日の気象庁記者クラブでの会見で、次のように述べ、記者からの質問に答えています(当時、筆者は気象庁予報課で台風予報等の業務に従事)。
(気象庁長官の話の要旨)
三陸沖一帯が暴風域に入ることは予報されており、海上に対する警報も発表されていた。遭難原因はこれから詳しく調べられるであろうが、その一つとして進路予報が正確でなかったことは報道されたとおりだと思う。これが唯一の遭難原因だと判断するのはわれわれの立場ではないが、結果的に進路予報がはずれたことを申し訳なく思う。
進路予報は、すべてを総合的に判断した結果であり、発表の段階では、その判断が最も正しいものであった、と考えている。だが実際は台風はそれとちがう動きをしたことについて、庁内に台風予報検討委員会を設けて検討することとした。
(主な質問と答え)
Q 昨年までの扇形方式の方が判りやすいのでないか。予報円は、この範囲からはずれることはない、という印象を与えてしまう恐れがある。
A 慣れて頂ければ、今度の予報円方式の方が使いやすいことが理解されると思う。PRにつとめたい。昨年までの扇形方式は、進行速度について誤解を生む恐れが大きい。それに比べれば予報円は、理解されれば使いやすいはずである。
Q 予報円方式の見直しを検討委員会で行うのか。
A 今回の予報誤差は、予報円方式という表示の方法に原因があったのではなく、予報そのものがまずかったのである。予報円方式に大きな欠陥があるとは考えていない。後戻りはしない。
台風予報検討委員会
昭和57年(1982年)台風5号のあと気象庁内に設けられた台風予報検討委員会は、同年10月12日に結論を気象庁記者クラブにおいて報告しています。
(検討委員会結論の一部)
1 台風5号についての作業は、台風予報作業指針などにもとづいて行われており、指向流、統計予報、数値予報等、十分に考慮がはらわれていた。
2 台風5号は、従来用いてきた技術にもとづく予報結果と異なる振舞いをしており、それが大きな誤差を生じた要因であり、進路予報の技術を見直す必要がある。統計予測資料、数値予報資料に当面いそいで可能な限りの改良や補正法を開発するとともに、気象衛星資料を含め、諸資料の総合的利用技術の再編成に努める。
3 時間のかかる課題として、個々の予報技術の総合判断が必要となるが、現段階では原理的原則的な理解にとどまっている。総合判断技術を定量化し、多数例について検証してゆくが、委員会はこれを継続することとし、部分的にでも確立されたものが出来次第、遂次台風予報作業に導入してゆく。並行して、予報部と気象研究所との連携を一層強めて、台風に関する基礎的研究の推進とその成果の台風予報作業への導入について、恒常的努力を続ける。
予報円表示が始まった最初の台風である台風5号によって、様々な課題が浮き彫りとなっていますが、それらを克服することで、台風進路予報の精度が徐々に良くなっています。
24時間予報の年平均誤差は、予報円表示が始まった昭和57年(1982年)は210キロの誤差でした。翌年も、その翌年も、しばらくは予報誤差の年平均が200キロを超えていました。
しかし、昨年、令和5年(2023年)の年平均誤差は61キロと、予報円表示が始まった頃に比べ、7割も減っています(図4)。

そして、予報精度が向上したことをうけ、48時間先、72時間先と予報時間が延長され、平成21年(2009年)からは、96時間先(4日先)、120時間先(5日先)まで予報されるようになっています。
これらの延長した予報も精度が徐々に良くなっており、予報円表示が始まった頃の24時間予報の誤差は、現在の4日先の予報の誤差と同程度となっています。
最初に予報円が使われた台風5号の大きな予報誤差が信じられないほど、現在の台風進路予報の技術は進歩しています。
図1の出典:饒村曜(平成5年(1993年))、続・台風物語、日本気象協会。
図2の出典:饒村曜(昭和57年(1982年))、台風進路予報表示方法の変遷について、測候時報、気象庁。
図3の出典:気象庁資料をもとに筆者作成。
図4の出典:気象庁ホームページ。










