進路指導担当者が知ると得する話・1~朝日新聞「明日へのLesson・クエスチョン」が優れている理由
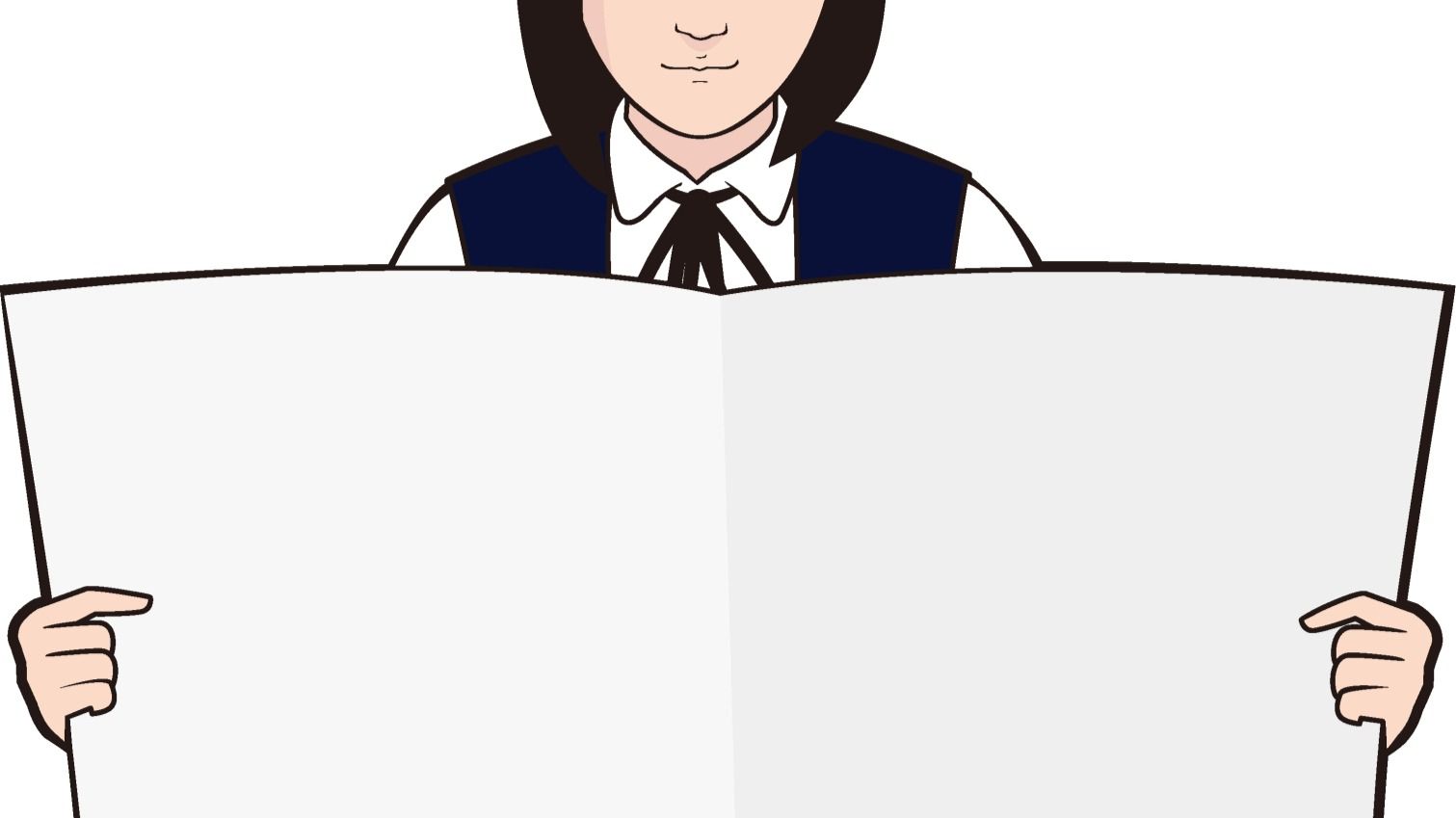
◆読解力重視と言うけれど
共通テストは明らかに読解力重視に変わった。この傾向は一般入試でも、総合型選抜・学校推薦型選抜でも、中堅以上の大学であれば、変わるところがない。
で、この対策として、よく出るのが「新聞を読もう」である。
ところが、高校・進路指導担当教員であればご存じの通り、それでうまく行くケースは多くない。
この理由は、別の回で出すが、根本的に新聞の読み方を高校生が誤解していること、その誤解を高校教員や新聞社なども解こうとしていない点にある。
私が高校の進路講演などでよく話すのが、「全部読むのではなく、面をチェックせよ」である。
◆全国紙で唯一の入試解説コラム
今回、ご紹介するのは朝日新聞「明日へのLesson・クエスチョン」である。
「明日へのLesson」は朝日新聞の毎週木曜に掲載されている教育面だ。週替わりで内容が代わり、第三木曜は「クエスチョン」、すなわち、入試問題の解説コラムとなっている。
全国紙・地方紙とも、大半が教育面を設けており、入試時期になると、共通テストなどの解説記事を掲載する新聞も全国紙を中心に多い。
が、大学入試問題を題材に解説するコラム(かつ、定期掲載)は、この「明日へのLesson・クエスチョン」が唯一の存在だ。
あえて言えば、日本経済新聞の毎週火曜掲載「受験考」くらいか。ただ、こちらは約800字、かつ、題材は中学受験から大学受験までバラバラ。塾講師の独白という形を取っている。
「明日へのLesson・クエスチョン」は毎回2500字相当、題材は国立大や難関私立大、共通テストの問題である。解説するのは、その問題の科目に関連する予備校講師や専門家で、毎回、変わる。
掲載は2019年4月10日から。2回目の2019年5月29日掲載分は「著者が解く」シリーズとして、村上陽一郎に九州大で出題された問題を解説させた。
この「著者が解く」シリーズは2020年から、「特別編・著者が解く」シリーズに改編され、掲載時期も第三週ではなく、不定期掲載となった。2020年の1回目は山極寿一・前京都大総長、その後も内田樹(哲学者)、小川洋子(作家)など、錚々たるメンバーを出している。
◆なぜ出題するのか、その意図も解説
このコラムが単に入試問題を解説しているだけなら、予備校サイトの入試解説欄などと変わるところがない。
このコラムの秀逸な点は、なぜその問題を出題するのか、背景はどうなっているのか、などを分かりやすく丁寧に解説している点だ。
たとえば、2022年11月17日掲載の青山学院大学経済学部の数学問題については、数学講師の大澤裕一が解説。
医学部などで出題される難問を批判しつつ、この青山学院大学経済学部の問題をこう評価する。
※以下、有料版読者にのみ公開
項目は
◆なぜ出題するのか、その意図も解説(続き)
◆2019年・バックナンバー
◆2020年のバックナンバー
◆2021年のバックナンバー
◆2022年のバックナンバー
◆科目は罠、関連分野・学部からの検討を
合計約3300字
以下は有料版購読の読者にのみの公開となります。
この記事は有料です。
教育・人事関係者が知っておきたい関連記事スクラップ帳のバックナンバーをお申し込みください。
教育・人事関係者が知っておきたい関連記事スクラップ帳のバックナンバー 2022年12月
税込550円(記事1本)
2022年12月号の有料記事一覧
※すでに購入済みの方はログインしてください。










