日本学術会議がトランスジェンダーに焦点をあてた提言を発表「特例法を廃止し、性別記載変更法の制定を」
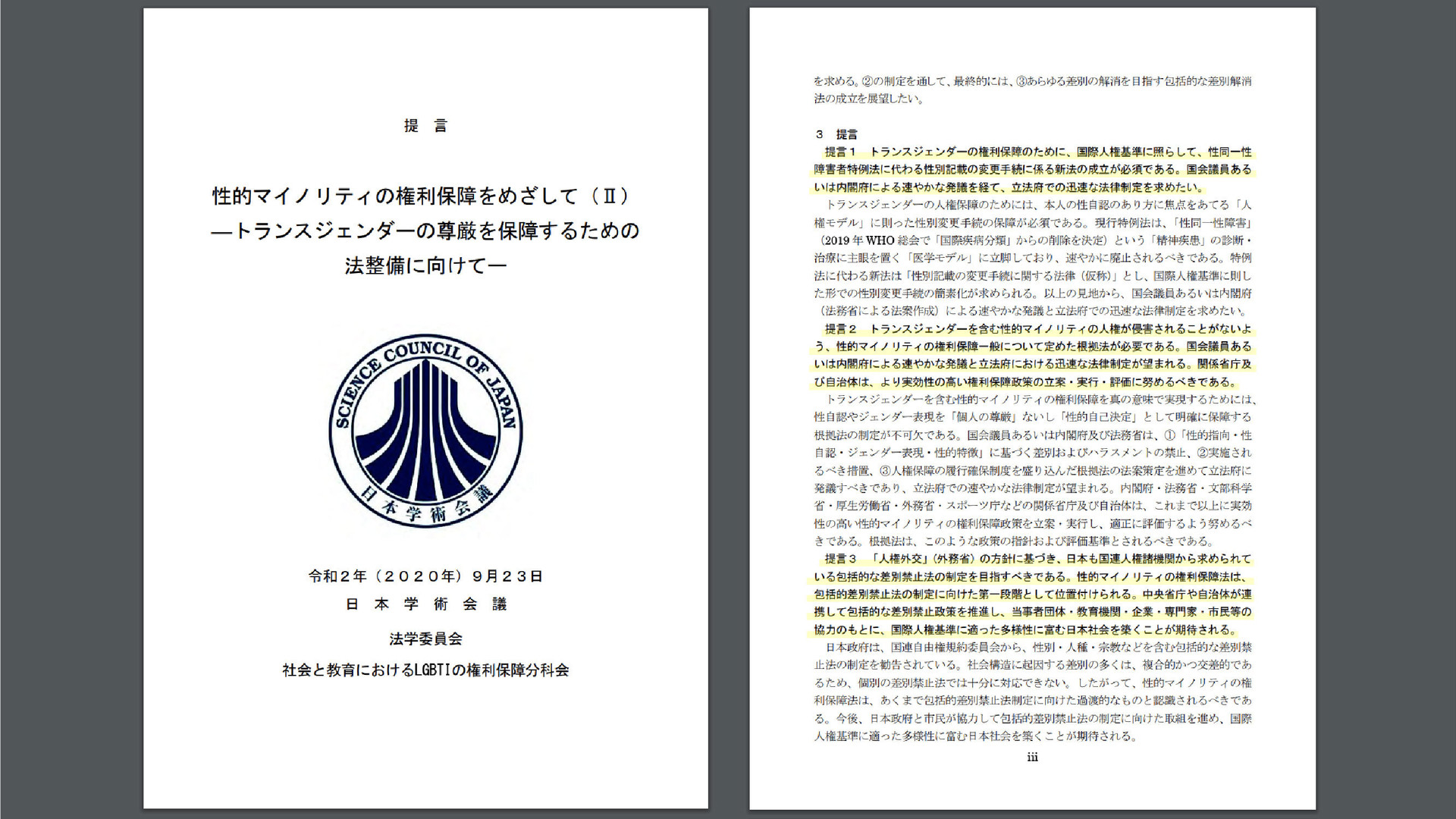
内閣府の特別機関「日本学術会議」が24日、トランスジェンダーに焦点を当てた提言を発表した。
3つの提言の主な内容
- 性同一性障害特例法の廃止と性別記載変更法の制定
- SOGIESCに基づく差別禁止法の制定
- 性的マイノリティだけでなく包括的差別禁止法の制定
日本では「性同一性障害特例法」により、トランスジェンダーは法律上の性別を変更することができるが、その要件のハードルが高い。
提言では「性同一性障害特例法を廃止」し、「性別記載の変更手続に係る新法」を制定すべきだと述べられた。
また、そもそもトランスジェンダーを含む性的マイノリティの人権を保障するために、SOGIESC(性的指向や性自認、ジェンダー表現、性的特徴)を理由とする差別を禁止する法律の制定も必要だとした。
さらに、日本は国連から性別・人種・宗教などを含む「包括的な差別禁止法」の制定を勧告されている。提言では、性的マイノリティに関する差別禁止法はあくまで一つのステップであり、包括的な差別禁止法が必要性だと述べられた。
法律上の性別変更「高すぎるハードル」
提言書によると、国内で性別適合手術が解禁されたのは1998年の埼玉医科大学での手術だという。しかし、法律上の性別を変更することはできなかった。
2003年に成立した性同一性障害特例法は「日本で唯一の”LGBT法”」であり「特例法は自らの性自認に基づいて法的性別を変更することを可能にした待望の法律であった」と述べられた。
特例法は、法律上の性別を変更するために、2人以上の医師による「性同一性障害」の診断と5つの要件にあてはまることを求めている。
5つの要件
- 年齢要件:20歳以上であること(成年年齢の引き下げに伴い、2022年4月1日から18歳以上に)
- 非婚要件:現に婚姻をしていないこと
- 子なし要件:現に未成年の子がいないこと
- 手術要件(生殖不能要件):生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
- 外観要件:その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
特例法の成立時点では、こうした要件は諸外国とさほど変わらなかったが、2006年に「国連人権理事会」が創設され、性的マイノリティに関する差別解消の動きも活発化。「EU諸国を中心に急速に法的性別変更の要件緩和が進んでいった」という。
特例法は国際人権基準から取り残された状態の法律となっている。
提言書によると、トランスジェンダーとして把握されている人は、全国で4万6千人と推定されており、2004年の特例法施行から2018年12月31日までに、性別取扱いの変更審判を受けた人は8,676名だという。
「トランスジェンダー推定数の2割弱にとどまるにもかかわらず、手続の利用者が少ない」のは、特例法の5つの要件が「高すぎるハードル」だからと指摘された。
医学モデルから人権モデルへ
これまでは、国際的にも「性同一性障害」という精神疾患の診断や治療をベースとして「医学モデル」の法律が整備されてきた。
しかし、近年は2013年にアメリカ精神医学会の診断マニュアル「DSM-5」で「性同一性障害」は「性別違和(Gender Dysphoria)」に名称を変更。2019年には、WHOの国際疾病分類「ICD-11」で「性同一性障害」を削除。「性の健康に関する状態」という章に「性別不合(Gender Incongruence)」が新設され”脱病理化”へと進んでいった。
こうした流れについて、提言では「身体の治療に主眼をおく『医学モデル』から、本人の性自認のあり方に焦点をあてた『人権モデル』への移行を意味する」と述べられた。
5つの要件を検証
提言書では、性同一性障害特例法の設ける5つの要件について検証し、特例法の廃止と、新法の制定について提言がなされている。
【1】年齢要件
特例法は「20歳以上」でなければ法律上の性別を変更できないとしている。(成年年齢の引き下げに伴い、2022年4月1日から18歳以上に)
この年齢要件については、ノルウェーで2016年より医療機関の診察やホルモン療法、不妊手術を経ずに当事者の申請だけで、法律上の性別の変更が可能であることを紹介。「未成年である16歳から本人の意思に基づき、6歳から16歳未満までは、親の同意を得て申請することができる」という。
日本でも養子縁組年齢や遺言年齢の規定に合わせて、15歳に引き下げることができると説明。また、「もし生殖不能等の手術を要件から削除すれば、医療同意年齢を考慮する必要性がなくなり、年齢要件を課す必要すらなくなる」と述べられた。
【2】非婚要件
法律上“男女”として結婚をしているトランスジェンダーのカップルの場合、一方が性別を変更すると「同性婚状態」になってしまうため、結婚をしている場合は性別を変更できない。
これについて提言書では、ヨーロッパや中央アジアの34ヵ国で非婚要件がなくなっている点に触れ「今日では同性婚を認める国が増え、非婚要件はなくなる傾向にある」と説明。
さらに、ドイツでは2017年に同性婚が認められる前から、ドイツ連邦憲法裁判所が性別の変更は「人格権」が優先されるとして非婚要件の撤廃を求め、数ヶ月後に法改正が実現したという。
「その結果、同性婚が容認される前に10 年間にわたり、ドイツには事実上、同性婚が存在することになったが、その数はきわめて少なく、ドイツの婚姻秩序に混乱が生じることはなかった」
【3】子なし要件
特例法では、未成年の子がいる場合は性別を変更できないとしている。これは「父=男」「母=女」という家族のあり方の図式が崩れ、子に心理的な混乱などをもたらす可能性があるからというのが理由とされている。
しかし提言では、ひとり親や同性パートナーのもと育つ子が増えているなど、すでに「家族は多様化」している点に触れ、「『女である父』『男である母』は子の心理的混乱をもたらすという理由付けには根強い『無意識の偏見』」があると指摘された。
さらに、そもそも子が向き合うのは親の法律上の性別ではなく、服装や言動など、親の見た目の性別であり、見た目の変化にはすでに直面している子どもにとって「戸籍の性別記載の変更によって影響を受けることはない」とした。
【4】手術要件(生殖不能要件)
特例法は、法律上の性別を変更する場合に生殖器を除去する、いわゆる「性別適合手術」を要件として設けている。しかし、トランスジェンダーの中には手術を望む人もいれば、望まない人もいるのが実態だ。生殖機能を強制的に剥奪することは人権侵害であると国際的にも批判されている。
この要件は、例えばトランスジェンダー男性が子どもを出産した場合「母となる男性」となるなど、「さまざまな混乱や問題が生じる可能性」があることから設けられたという。
しかし提言では「21世紀に制定・改正されたヨーロッパ・中央アジア54ヶ国の法的性別変更法のうち、41ヶ国の法が生殖不能要件をもたない」ことに触れ、想定される「混乱」というのは、親子関係を規定する別の法律によって回避できるものであると言及。「トランスジェンダーの生殖機能を剥奪することによって解決すべき問題ではない」とした。
【5】外観要件(外性器近似要件)
最後の「外観要件」は、性別適合手術によって生殖器を除去するだけでなく、変更する性別の性器に似た外観を備えることを求めている。
これは、公衆浴場などで「社会的混乱」が生じる可能性があることを考慮して設けられたものだという。
これについても提言では、「トイレ、更衣室、公衆浴場などの施設については、メーカーや施設責任者の協力を得て設備や環境の改善が可能であり、個室トイレの開発など実際に改善が進められている」ことや、「トランスジェンダーを装う『なりすまし』は犯罪行為であり、刑事法で対応すべき」という点を言及。
「身体への侵襲を受けない権利」は、憲法13条によって保障されており、費用負担や身体的な理由、医療事故リスクなど手術を受けられない人もいることから、合理的とは言えないと述べられた。
特例法を廃止し「性別記載変更法」の制定を
提言では、性同一性障害特例法を廃止し、「法的性別変更の手続を定める『性別記載変更法(仮称)』」を制定すべきだと述べられている。
なぜ性同一性障害特例法の要件の改正ではないのか。
これについては、もはや国際的な医療水準において使用されていない「性同一性障害」という概念を用いるべきではないという点や、特例法の根幹をなす5つの要件を削除することは、改正の範囲を超えているという点から、新法を制定すべきだとした。
また、ドイツでは3年以上性自認に合わせて生活したいと望んでいるとい要件であることや、フランスでは裁判所の決定により、法的性別を変更できること。アルゼンチンでも、医師の診断書を必要とせず、本人の自己申告によって性別の変更を登録できることから、「自己申告」によって性別を変更できることが求められるとした。
さらに、性別の再変更は少なからず存在するため、性別の再変更を認めるドイツにならって「性別記載変更法」でも認めるべきとした。
その際「(性別の再変更は)きわめて例外的であり、自己申告制を採用すると法律上の性別を頻繁に変えるという事態は生じない」と述べられた。
トランスジェンダーの権利保障のための政策の推進
仮に「性別記載変更法」が制定されても、これはあくまでも性別変更について規定するものであり、トランスジェンダーの権利を保障する法律ではない。
提言では、学校や職場など、あらゆる場所でトランスジェンダーを含む性的マイノリティが直面する困難に対して権利保障法や政策が急がれると指摘。
中には、医療従事者に対する性の多様性に関する教育や、スポーツにおける性的指向や性自認(SOGI)に関する差別禁止。政治・メディアにおける差別的表現について「ヘイトスピーチ」の規制対象にSOGIを追加すべきだとした。
また、刑事収容施設における処遇について「性自認やジェンダー表現を含む人権の尊重は被収容者においても十分に確保されなければならない」とし、入国管理センターの運用がSOGI差別を含め、そもそも人権の視点が欠如している点について言及、「現状の変革は急務」とした。
SOGIESCによる差別禁止をステップに「包括的差別禁止法」を
そもそも日本の法制度は、性的マイノリティを直接的に規定する文言が不在であり、かつ、何が差別にあたるのかという定義も不在、そして人権保障のための独立した国際人権機関が不在という「三つの不在」について言及した。
「差別」の定義がないことで、例えば「嫌悪する自由」や「差別はなく区別」だと差別の正当化が行われることもある。世界120ヵ国以上で国内人権機関が設置されているにもかかわらず、日本にはこうした人権機関が存在しないことの問題点が指摘された。
そして、提言ではトランスジェンダーを含む性的マイノリティの権利保障を真の意味で実現するためには「性自認やジェンダー表現を『個人の尊厳』ないし『性的自己決定』として明確に保障する必要」があると述べられ、「SOGIESC(性的指向・性自認・ジェンダー表現・性的特徴)にもとづく差別やハラスメントの禁止」が必要だとした。
さらに、国や地方公共団体による基本計画の策定は不可欠であり、「性的マイノリティ等の多様な性のあり方に関する意識啓発や理解増進の取組も必ず含まなければならない」と述べた。
一方で「人権保障は第一義的に公権力に課せられた義務」であり「意識啓発や理解増進は人権保障の実現のために必要な土壌ではあるものの、これを人権施策の前提条件と位置づけるのは本末転倒である」と言及。
また、提言では、日本が国連人権諸機関から「包括的な差別禁止法の制定」を求められていることから、性的マイノリティに関する権利保障法はあくまでも第一段階であるとして、性別・人種・宗教など包括的な差別禁止政策の推進が求められた。










