樋口尚文の千夜千本 第138夜「カミング・ホーム・アゲイン」(ウェイン・ワン監督)
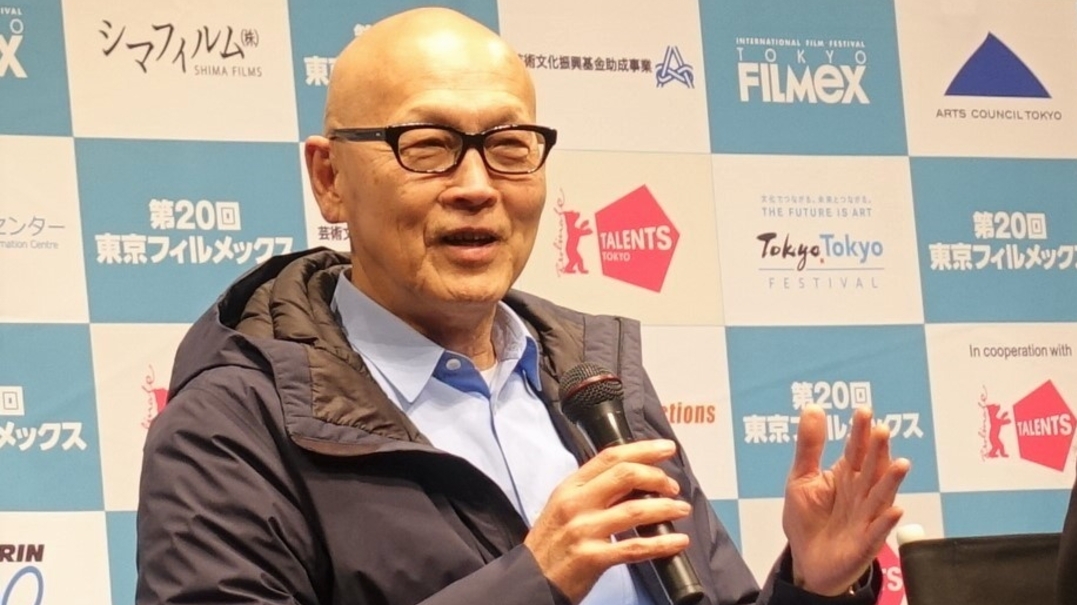
名匠のふしぎなパルスと変容のゆくえ
いくぶんやんちゃだった『スラムダンス』の後、代表作『ジョイ・ラック・クラブ』『スモーク』にさしかかった頃のウェイン・ワンの節度と均衡を近作に求めると、かなり面喰らうかもしれない。実際、ゼロ年代に入っての『赤い部屋の恋人』あたりからはウェイン・ワンがどこに向かっているのか途方に暮れる観客が増えていったことだろう。
そういう意味では、新作『カミング・ホーム・アゲイン』も多くの観客に肯定的に受け止められたとは到底思えない。私も期待とともに目を凝らして、ちょっと呆気にとられる感じではあったが、しかしかなり興味深い作品には違いなかった。そもそも香港に生まれ、カリフォルニア大学で学び、香港のテレビ局に就職するも違和感を覚えてサンフランシスコに移り住んだウェイン・ワンは、国を超えた越境者の祖国なるものとの齟齬や不安定な感覚をモチーフにしてきた。
その典型例である2007年の『千年の祈り』は、アメリカに移り住んで結婚生活が揺らいでいる娘を案じて中国の老父が渡米する物語だったが、そのロケット工学者を自称する気のいい老人は、公園で知り合ったペルシャ語の夫人とは言葉を超えて親しくなれたのに、同じ言語を話す娘からは忌み嫌われてコミュニケーションを遮断される。父は中華鍋を仕入れて頑張って料理をつくり、娘とふれあおうとするも、彼女は箸をつけたかどうかぐらいで父との会話を拒む。父にはだめな親だったという自覚も、逆にわかってほしい事情もあって、いわばこれは贖罪と和解のための訪問であり、料理であった。
このたびの『カミング・ホーム・アゲイン』の原作・脚本を手がけたチャンネ・リーは、韓国生まれの米国作家で、出身はソウルだが幼少時に医師の父の都合で渡米し、以後はアメリカで大学を卒業し、ウォールストリートでアナリストをやった後に作家となった。そのアナリストの横顔は本作でも反映されていて、かなり自伝的な作品と言えるのだろう。移民としてアメリカに渡った母、まさにチャンネ・リーの小説の出世作の題名であるネイティブ・スピーカーとしてアメリカで育った息子の間には、じわじわと溝が深まる(息子をエリートとして育てるために寄宿学校に送り出したこともかえってそれに拍車をかける)。
それで息子はウォール街で働くエグゼクティブとして母とは疎遠になっていたが、母が末期がんと知ってサンフランシスコに舞い戻る。息子は、余命いくばくもない母への贖罪と和解を期して、大晦日に母に習った韓国料理をせっせと作り、食べさせようとするが‥‥。そんな物語である『カミング・ホーム・アゲイン』は、みごとに『千年の祈り』の逆バージョンであるわけだが、あの中国系の父娘の物語に比べると、このたびの韓国系の母子の物語は凄まじくハードボイルドで、時としてヒステリックでもある。
その容赦ない、やや露悪的なくらいの描写に、心穏やかな着地点を期待した観客たちは神経を逆なでされたかもしれない。だが、『千年の祈り』から十数年を経て老いの季節に入ったウェイン・ワンにとっては、人と人との関係に可能なものと不可能なものとの隔たりはより尖鋭に見えてきたのかもしれない。これを雑な終わり方とする感想もあったが、それにしてははるかに自覚的に物語を放り出す感覚があって、これもまたウェイン・ワン流の「もののあわれ」ではなかろうかと思った。
日本で撮った異色作『女が眠る時』の物語の処理についても同じものを感じたが、最近のウェイン・ワンの撮影方法やカットの選択などを見ていると、弛緩ぎみかと思えば性急であったりひじょうに独特なパルスがあって、行儀のいい『スモーク』の時分とは別人のようである。この作家のふしぎな変容をもっと追いかけてみたいと思う。










