これからの飲食店はデジタルアドレスを持たないと生き残れない
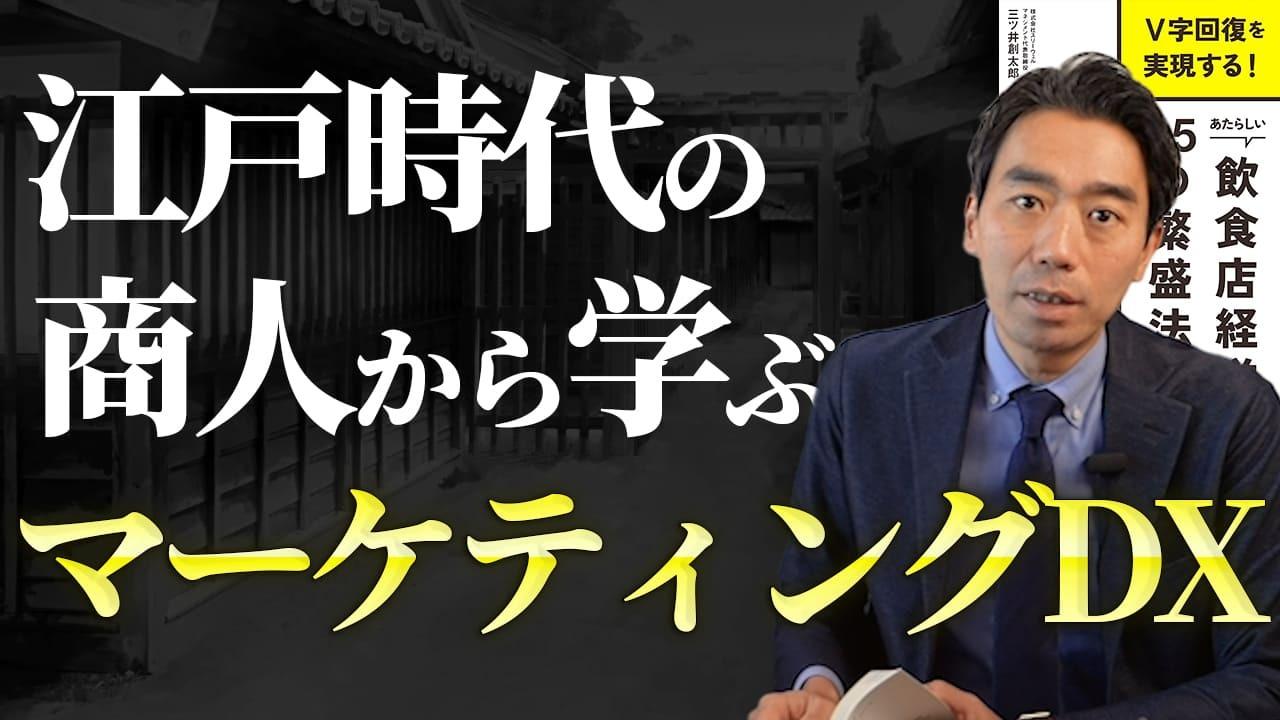
飲食店コンサルティング会社スリーウェルマネジメント代表コンサルタントの三ツ井創太郎です。
前回のコラムでは、理論原価分析で原価を下げる手順についてお話をさせて頂きました。
今回のコラムでは、飲食店経営において、これからの時代を生き残るのために必須となるマーケティングDXについてお話をさせて頂きます。
なお、今回の内容はYouTubeチャンネルでも解説していますので、よろしければ下記よりご覧ください。
(筆者作成)
江戸時代の商人から学ぶ!不景気時代を乗り越えるマーケティング戦略
最近よく聞くようになった「DX」という言葉。DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、一言で表すと「デジタル技術導入によるビジネスの変革」です。
マーケティングDXとは、デジタルマーケティングを行う社内組織体制の構築や、デジタルマーケティングで得たデータなどを活用したビジネスモデルの変革を意味します。

はじめにお伝えしたいのは、「江戸時代の商人」についてです。「マーケティングDXの話なのに、江戸時代の商人?」と不思議に思った方も多いかもしれませんが、江戸時代の商人には、これからの時代を生き抜く集客戦略の大きなヒントがあります。
皆さんは「江戸の大火」という話を聞いた事がありますか?江戸時代は火事が非常に多く、2~3年に一度、大火事に見舞われる地域もありました。
商人達は、火事が起きると高額な商品よりも「顧客台帳」を優先して持って逃げたそうです。そして、火事が納まった後、顧客台帳を見ながら「馴染み客」の自宅を訪ね、自身の無事と営業再開の挨拶をしていきました。こうした挨拶の中で、馴染みのお客様が来店や購買をして下さり、少しずつ商売を復興させていったそうです。
顧客台帳がたくさんある店舗では、顧客台帳を持って逃げるのが大変なため、水に濡れても字が消えないよう顧客台帳をこんにゃくノリ等で加工し、火事が発生した際には、お店の前の井戸に顧客台帳を投げ入れてから逃げたそうです。
さらに注目するべき点は、「江戸時代には2~3年毎に大火を繰り返していた地域もあった」ということです。こうした地域ではせっかく火事から復興しても、また2年後にお店が全焼するといったことも珍しくありませんでした。繰り返す“経営危機”において、「顧客台帳」を持っていない店舗は次々と廃業に追い込まれていったのです。

これからの時代の顧客台帳=デジタルアドレス
私はこれからの時代の飲食店経営においても「江戸の大火」の教訓は大いに役に立つと思っています。商売において最も重要なのは「馴染みのお客様」です。そして、「馴染みのお客様」に「自店のコンテンツ=価値情報」を「迅速」かつ「ダイレクト」に届けるためには、「顧客台帳」が必須となります。
これからの時代の「顧客台帳」とは、当然ながら江戸時代のような紙の台帳ではなく、デジタルであることが特徴です。私はこれを「デジタルアドレス」と呼んでいます。
中小企業でも有効活用ができるデジタルアドレスの例としては、①LINE公式アカウント(旧LINE@)②メールアドレス③SNS(Instagram、X、Facebookなど)④お客様の携帯電話番号などが挙げられます。
個人情報保護法等にはもちろん留意した上で、これからはデジタルアドレスをフル活用したマーケティングに力を入れていくことが重要です。こうした戦略は、何も大手企業だけの戦略ではありません。実際に支援先の飲食店でも、デジタルマーケティングを活用したことで、コロナ禍でも前年売上を超えているお店がありました。
繰り返し起こる大火事という経営危機の中で、顧客台帳を持っていないお店が次々と廃業をしていったように、これからの時代はお客様のデジタルアドレスを保有していない飲食店はかなり集客に苦戦することになるでしょう。

「うちのお店には、デジタルを活用した集客は必要ない!」
中には、このように考えている飲食店経営者の方もいらっしゃいますが、大切なのは「お客様はどうやってお店を探すのか」というお客様視点で考える事です。
現在、お客様は、グルメサイトやSNS、Googleビジネスプロフィールなど様々なデジタル情報を活用して、最新の店舗情報を検索するようになりました。このような中で、お店からの情報発信がデジタル化できているお店は、より多くの情報を、より多くのお客様に伝えることができます。
さらに、お客様のデジタルアドレスを獲得できているお店は、グルメサイトなどに費用を払うことなく、いつでも直接、お客様に店舗の最新情報を届けることが可能になります。こうしたコスト面においても、デジタルマーケティングは有利なのです。
次回のコラムでは、具体的なデジタルマーケティングの手法に関してお話をさせて頂きます。
最後までお読み頂きありがとうございました。
(筆者作成)
<筆者プロフィール>
飲食店コンサルティング会社スリーウェルマネジメント
代表取締役 三ツ井創太郎
https://www.threewell.co/business










