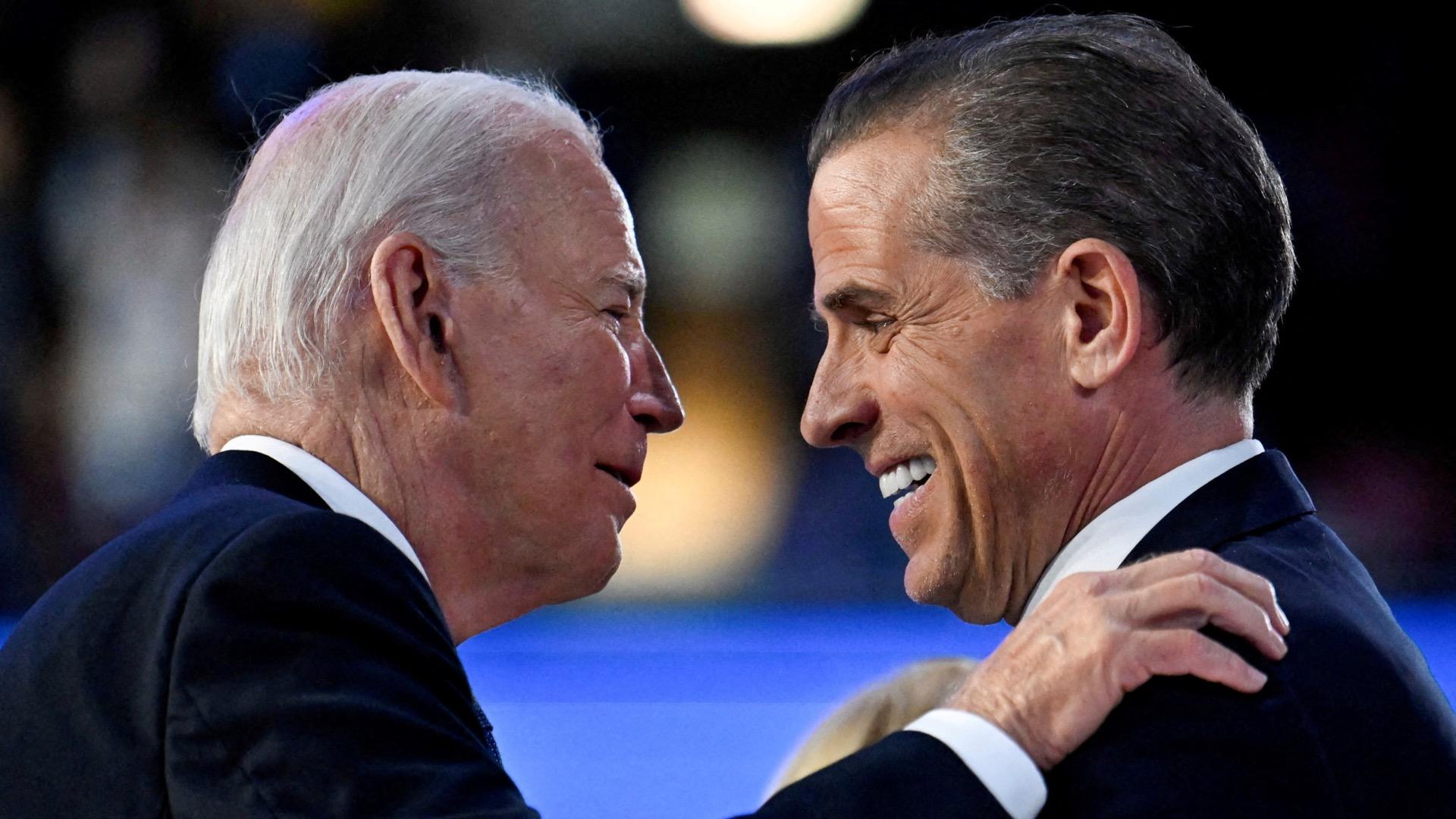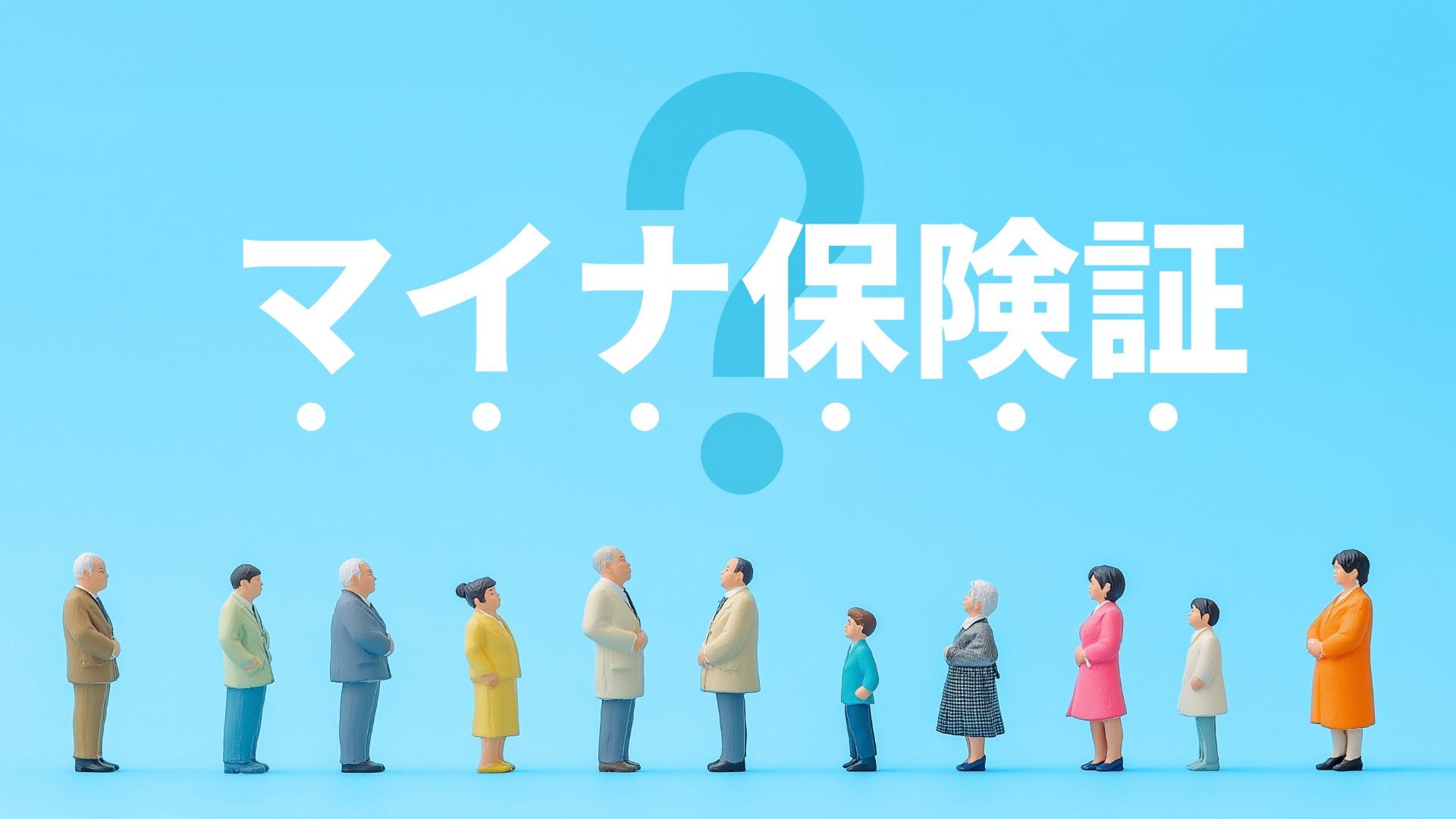コカ・コーラが八王子で森林や湿地を整備する深い理由

社員が里山環境や生物多様性の重要性を理解するねらい
6月21日、コカ・コーラ「森に学ぼう」プロジェクト in 東京はちおうじ(主催:日本コカ・コーラ、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社)が、東京都八王子市の上川の里特別緑地保全地区(以下、上川の里)で行われた。
社員が里山環境や生物多様性の重要性を理解するのがねらい。NPO法人森のライフスタイル研究所の協力のもと、参加した社員60人が「上川の里」で間伐、地ごしらえ、枝打ちなどの森林整備を体験する計画が立てられた。
間伐……森林内の木を切り倒して木と木の間隔を空け、林内に日照を入れる
地ごしらえ……伐採後に取り残された木の根や枝などを整理する
枝打ち……ある高さまでの枝を、付け根付近から除去する
ところが、当日はあいにくの大雨。社員は上川の里を視察したのち、木工製作やネイチャープログラムを体験した。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の金澤めぐみさんは(コミュニケーション戦略統括部統括部長)は、「環境教育プログラム『森に学ぼうプロジェクト』は、水資源保全活動の一環として自然の大切さ、環境保護の意義などを理解するのが目的。体験できなかったのは残念だが、現場に来たことで日常業務では感じられない新たな視点がもてたと思う」と語った。
なぜ飲料水メーカーの社員が森林整備をするのか
森林にはさまざまな機能があるが、その一つが水をたくわえ、きれいにすること。落ち葉や枝などを目に見えないサイズの生物が細かく分解し、それらが長い時間をかけて少しずつ積もっていく。それが森の土なのだ。だからふかふかのスポンジのよう。この土が降った雨をたくわえ、地下にしみこませる。また、雨が土と土のあいだを通るとき、水はきれいになる。
日本コカ・コーラ株式会社副社長の田中美代子さん(広報・パブリックアフェアーズ&サスティナビリティー推進本部)は、「コカ・コーラのビジネスは水の恩恵を受けている。水保全は重要なミッション」と語った。
世界的に水資源の不足が懸念されるなか、2021年、米国のザ コカ・コーラ カンパニーは「責任ある水の利活用と水資源保全のためのグローバルフレームワーク」を策定し、「OUR OPERATIONS(工場の運営)」「OUR WATERSHEDS(流域)」、「OUR COMMUNITIES(地域社会)」の3点を大切にする。
「工場の運営」、「地域社会」は聞いたことのあるワードだが、いったい「流域」とは何だろうか。
水平ではない土地に雨が落ちたとき、水は傾斜にそって低いほうへ流れていく。流れは集まってやがて川となり、大きな川に合流し、最終的には海に注いでいる。
流域とは、降った雨が地表や地中を流れ、やがて一筋の川として集まり海へ出ていくまとまった単位のこと。
同じ流域に暮らす生き物は、流域の水を分配しながら生きている。だからこそコカ・コーラは、責任ある水の利活用と水資源保全を「流域」で行うと宣言しているわけだ。

水資源保全の方法の1つが、地表面から地下に水を浸透させる「水源かんよう」。森林や湿地を保全することで、地表面を早く流れていったり蒸発したりする水を、地中にしみこませることができ、地下水を増やすことができる。
日本国内でコカ・コーラを製造する21工場周辺の19流域において、2024年末までに、水源かんよう率100%以上をめざす。これは生産のために汲み上げた以上の水量を地下に浸透させることを意味する。
ただし、多摩工場(東京都東久留米市)では、現在のところ水源かんよう率100%を達成できていない。そこで昨年6月、工場の取水ポイントの上流部にある八王子市と協定を締結し、森林や湿地の保全活動を行い、水資源の保全を図っている。
自治体と企業が連携して里山を復元する
この活動は八王子市にとってもメリットがある。上川の里は、かつては豊かな田園地帯だったが、25年ほど前から荒れてしまい、産業廃棄物の処分場の建設計画が持ち上がったこともあった。
その後、市民が手入れをしているものの、労力は不足している。
管理不足から、木々の枝が重なり合って林内に降る雨はわずか。日が当たらないので下草が生えず土壌を保つ機能が低下し、隣接する湿地に土砂が流れだしていた。
昨年の協定締結後、コカ・コーラはNPO法人 森のライフスタイル研究所と連携し、間伐や植林などの森林整備を行ったり、休耕田などの湿地から土砂や倒木を取り出し、生き物に配慮した水辺を整備している。

八王子市の初宿和夫市長は、「企業と連携しながら里山を復元できる。環境を大切にする企業のお手伝いができるのはありがたいこと」と語った。
水資源の保全だけでなく、ネイチャーポジティブ経営の重要性がますます高まるなか、こうした自治体と企業の連携は増えていくだろう。