なぜ、今、ジョニー・デップで『MINAMATAーミナマター』なのか。

「アーティストの責任の一つには、人の助けになるということがあると信じています」(アンドリュー・レヴィタス)
なぜ、今、ドキュメンタリーではなく、ジョニー・デップ主演のドラマとして水俣を描くのか。
報道写真家W.ユージン・スミスが1971年からの3年間、水俣に暮らし、当時の妻アイリーン・美緒子・スミスとともに1975年に発表した写真集『MINAMATA』。アンドリュー・レヴィタス監督作『MINAMATA−ミナマタ−』は、世界に水俣病の存在を知らしめたその写真集を原案にしているが、正直、観る前にはこの疑問を抱いていた。
しかし、作品を観れば明らかになるその答えは、公開に先駆けてジョニーととともにオンライン記者会見に参加したアンドリュー・レヴィタスの冒頭の言葉からもうかがえるとおり。
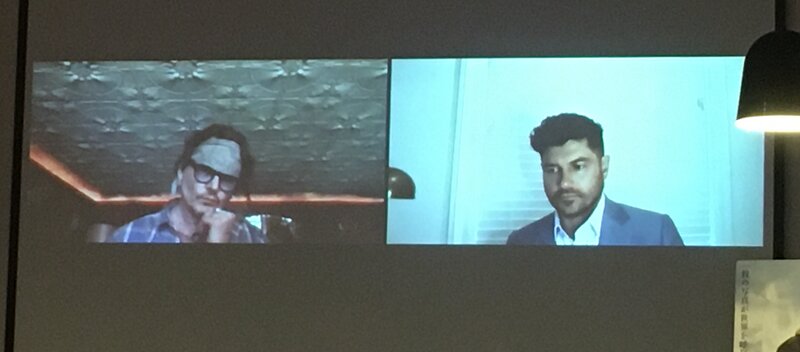
ジョニーがプロデューサーも務める本作が描くのは、報道写真家として輝かしい実績を残しながらも心に深い痛みを抱いていたユージンの再生のドラマでもある。事実と時系列が異なる部分はあるが、疑問に思った箇所が実際はどうだったのか調べてみるきっかけになるのも、実話が題材の映画の魅力の一つ。
「ユージン・スミスというアーティストの目線を借りて描くことによって、クリエイティブで詩的な方法で真実を伝え、水俣の皆さんの今も続く闘いを知ってもらうことができる。こうした工業汚染がいかに世界で多くの人を苦しめているかを広い視野で見ると同時に、水俣の勇敢な人たちが、皆さん自身や身近な人々を投影できる人たちに見えてくるのではないでしょうか」(レヴィタス)

ユージンを演じるジョニー・デップが、評判以上に素晴らしい。酒浸りになっていたユージンが水俣の現実を知り、再び報道写真家として立ち上がる姿を、まさに、そこにただ存在するといった感じの自然さで演じている。
「ユージン・スミスは、戦争体験でかなり心身に、特に心に傷を負っていました。自己破壊的な要素があり、自分の作り出す芸術にも納得がいっていなかった。過剰に繊細な人でもありましたし、いわゆる“いい人”の印象を与える人ではありませんでした。彼には、かつて私が演じた『ラスベガスをやっつけろ』の原作者ハンター・S・トンプソンと通じる部分があると思います。彼らは痛みを抱えている。それは繊細さゆえに生じる痛みです」(ジョニー)
ある意味、ハマり役ということだ。
時代は、テレビの登場で報道写真誌が衰退しつつある1970年代前半。そんな苦境のなか、ユージンを支える『LIFE』誌の編集長ロバート・“ボブ”・ヘイズ(ビル・ナイ)の報道写真への誇りと心意気にも胸が熱くなる。

だが、この作品は水俣の問題を提示するだけで終わらない。エンドロールでは福島第一原発事故を含む世界各地の環境汚染が映し出される。水俣と同じように、今もまだ世界のあちこちで問題が生まれ、続いているという事実にも改めて気づかせてくれるのだ。
「こうした環境汚染の問題は、汚染されていない健康な暮らしを営むという私たちの基本的な権利を奪っています。水俣でのこと、福島でのこと、そして石油の流出による海洋汚染。それぞれ別個のことのように見えますが、実は根っこは全部同じ。そもそも人間の暮らしを良くするために開発されたテクノロジーが、皆のためにではなく、少数の富める者のさらなる利益のために利用されてしまう。(こうした問題を)映画という形で提供することは、日本の皆さんにも、“あなたの声は届くんだ。立ち上がって行動するべきだ”と伝え、企業が“常に社会に責任を持って行動すべきだ”という意識を持つことに繋がると思っています」
「世界中で起きている問題の解決は、実は自分たちの中にあるんですよね。ですから、今現在よりもより良い生活、より良い明日を手にするために、何が人々の利益になるのかを考えて行動していきましょう」(レヴィタス)

時間が経ったからといって、問題は自然と解決されるわけではない。
「なぜ、今?」という疑問を抱いたのは、水俣病について何も知らないも同然なのに、わかっているようなつもりでいたから。
『MINAMATA−ミナマタ−』は、自分が何も知らないということを教えてくれた。そして、より良い未来のために一人一人がどうあるべきかを考えさせてくれる。
「カラヴァッジオの眼を持つ」とジョニーが讃える撮影監督ブノワ・ドゥロームによる美しい映像や、坂本龍一の音楽とともに紡がれる物語は、あなた自身と世界を見つめ直させてもくれるはずだ。
(c)2020 MINAMATA FILM, LLC
『MINAMATA−ミナマタ−』
TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開中










