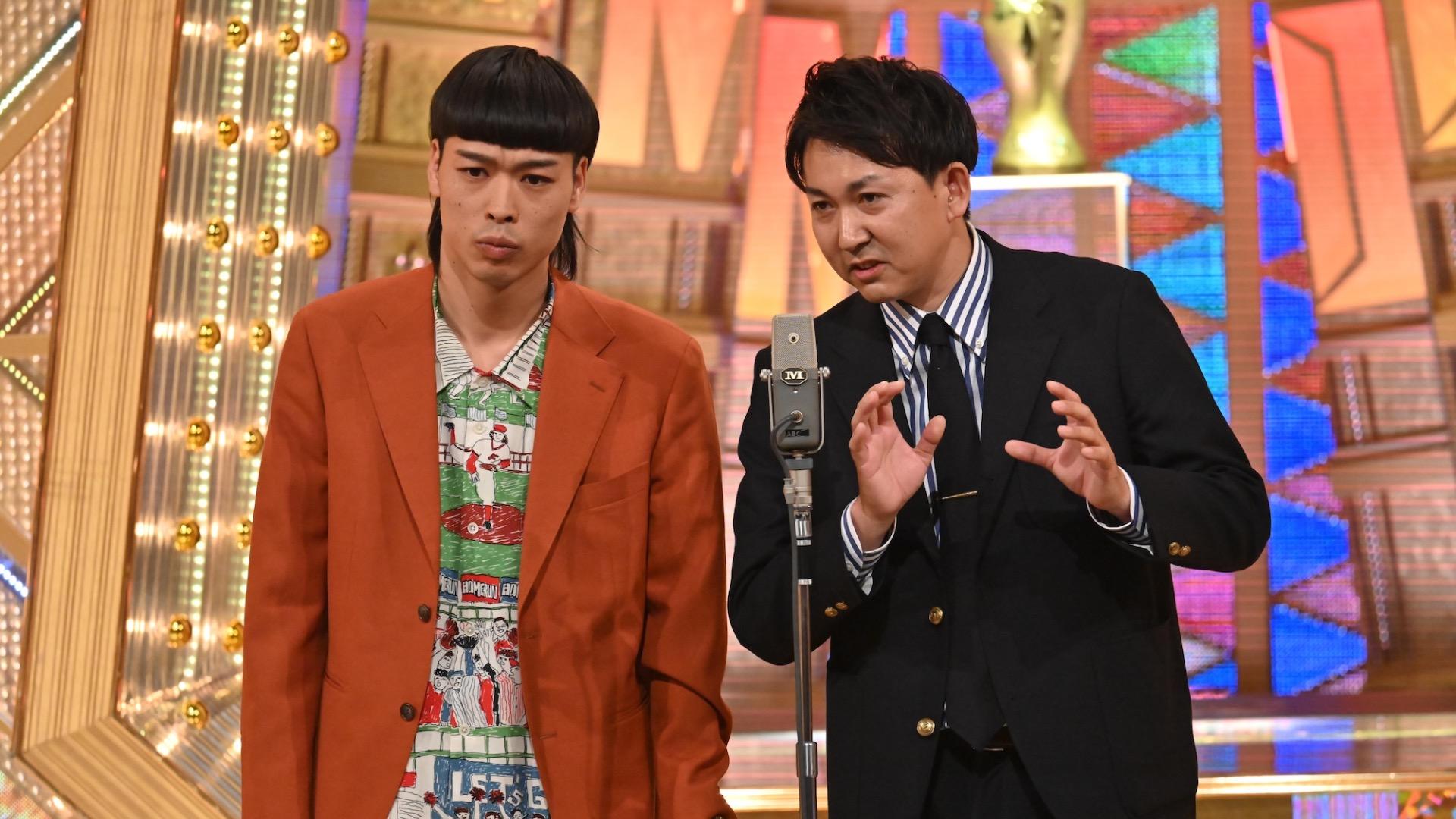政府が検討している「少子化対策「支援金」」で負担軽減される低所得者2600万人とは誰か?

報道によれば、政府は「少子化対策の財源に充てるため、社会保険料に上乗せして徴収する「支援金」制度に関し、低所得者の負担軽減措置を設ける方針を固めた」とのことです。
少子化「支援金」徴収、負担軽減 低所得者2600万人、政府検討(共同通信社 2023年11月19日)
負担軽減の対象となるのは、「自営業者や無職の人、75歳以上の後期高齢者らのうち約2600万人」となるようです(上記報道)。
報道からは低所得者の定義が不明ですので、詳細は分かりませんが、例えば、厚生労働省「国民生活基礎調査(令和4年)」で、低所得者を年間所得200万円未満としてみると、全世帯の19.7%、約5世帯に1世帯が相当し、この数値を日本の総人口1.25億人に機械的に掛け算すると、2450万人弱となり、2600万人にはピタリ一致はなりませんが、まぁまぁ近い数字が得られていると言えるのではないでしょうか?
そこで、世帯主×所得階層別のデータ(厚生労働省「国民生活基礎調査(令和4年)」2.所得票第26表「世帯数,世帯主の年齢(10歳階級)・所得金額階級別」)で、年間所得200万円未満層の年齢別の分布を見ると、下記のグラフのようになります。

各所得階層とも、65歳以上の高齢者の占める割合が高く、特に50万円から200万円未満では7割を超えています。
その結果、本記事で仮に低所得層と定義した年間所得200万円未満の所得階層に占める65歳以上の高齢者の割合は71.8%と、低所得層といっても4世帯のうち3世帯弱が高齢者となります。
つまり、こども家庭庁は、異次元の少子化対策の財源は、公的医療保険に上乗せすることで、現役世代だけでなく高齢者まで幅広く対象とするなどと言っていますが、実際には主に現役世代から徴収されることになる訳です。
そもそも、異次元の少子化対策の出生増効果が定量的に全く示されないまま、予算規模と財源だけ早々に決まっていくこと、そしてさしたる議論もないままに社会保険料の流用が当然視されていることには、大きな違和感しか筆者は感じません。
さらに、現役世代の社会保険料負担が重すぎて、結婚や出産、子育ての余裕が奪われているという少子化問題の本丸を放置したまま、なぜ敢えて、現役世代から取って現役世代に配る少子化対策を実施しようとするのか、下図のような社会保障給付の世代別歪みを正そうとしないのか、政府の問題意識と解決策に疑問が尽きません。

結局、高齢者の票を気にするあまり、全世代で少子化の財源を負担するという当初の目的を忘れ、住民税非課税世帯という名目で高齢世帯への給付金バラマキを正当化したのと同じ手口を踏襲しているのだと言えるでしょう。