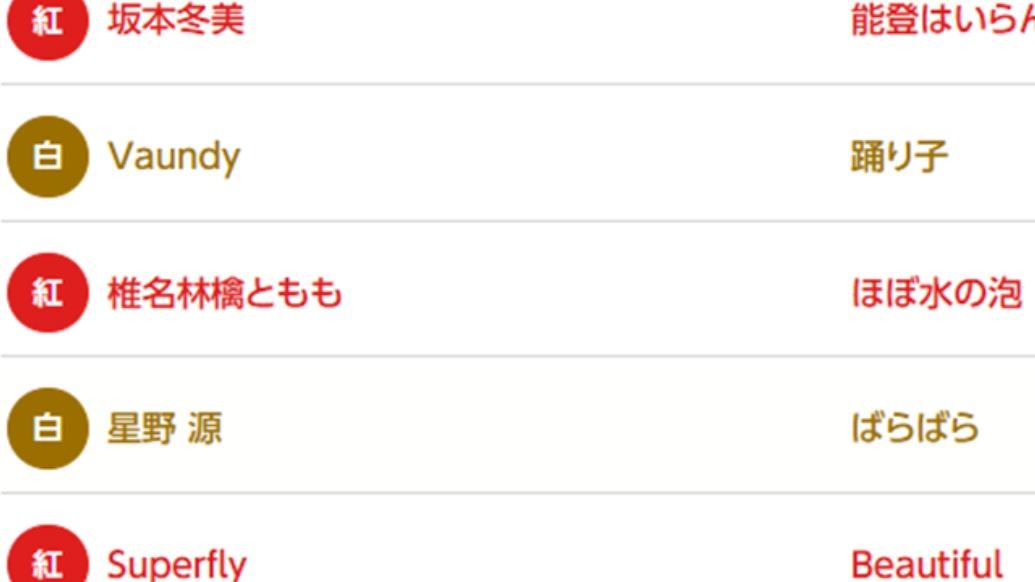ネコの「可愛さ」はずるい。駆除される動物について考える

小笠原諸島で絶滅危惧種などの鳥を襲うノネコ(野生ネコ)を捕獲した話を読んだ。(「小笠原が救った鳥」有川美紀子著)
生息数が約40羽まで激減した小笠原諸島の固有種であるアカガシラカラスバトを守るために、この鳥を獲物としていたノネコの捕獲事業を紹介している。その数は800匹近くまでになったようだが、おかげでアカガシラカラスバトも数百羽単位まで増えた……。
なかなか感動的な話なのだが、気になったのは、捕獲したネコは全部東京都の獣医師会に送って里親を探しているという点である。なぜ駆除ではなくこの方式をとったのか、なぜ可能だったのか、と考え込んでしまった。
現在、日本国中で獣害が問題になっている。シカ、イノシシはもちろんサルやクマまで、今や日本列島は人間社会に害をもたらす野生動物だらけだ。その中で目立たないが深刻な被害をもたらすのがノネコである。
ノネコは100%捨てられた(逃げ出した)飼い猫および、そこから繁殖した子孫である。街中で人間とそれなりに関わって生きるノラネコとは別扱いする。彼らが餌とするのもほぼ野生動物となるが、その中には希少種も多く、沖縄ではヤンバルクイナ、奄美ではアマミノクロウサギといった絶滅危惧種を襲っている。鳥獣のほかにも昆虫や両生類なども対象だ。ノネコが増えすぎると、地域の生態系を壊しかねないのである。
またネコは基本的に日本にはいなかった動物だから、外来種である。(現在ペットになっているネコの大半は欧米から持ち込まれた品種。)
ネコ害が深刻なところでは捕獲・駆除の対象となる。その点は、ほかの獣害をもたらす野生動物と一緒だ。たとえばシカは、農林業被害だけでなく天然林の植生を破壊しがちで、そのため鳥類の一部が生息しなくなった事態も報告されている。
だから駆除が求められているのだが、ノネコを対象とした駆除を実施しようとすると、常に「動物愛護団体」からの猛烈な抗議と反対運動が起きる。そのため駆除が進まない。ノネコが殺している鳥獣には向けられない同情がネコには集まる。だからこそ小笠原諸島のように幸運な例も生まれたのだろう。
だがシカやイノシシなどは、銃でしとめる場合はもちろん罠にかかった個体も最終的には全部殺す(一部に他地域への放獣方式などもある)。むしろ課題は、駆除個体を焼却や埋設処分するのではなく、肉や毛皮を利用できないか、という点に向いている。
だが、ネコでそんな議論は起きないだろう。一昔前ならネコの皮を三味線に使ったというが……。小笠原諸島の事業でも、最初は殺処分を考えたらしいが、東京都の獣医師会側からの提案を受けて、全部引き取ってもらうことになったそうである。
しかし、それは捕獲事情の負担を増やすことになった。ノネコのかかった箱罠ごと運び下ろさないといけないうえに、船に乗せるまでの飼育も必要となる。効率やコストを考えると、大変な手間のかかることをしたわけだ。それでも実行したのは、やはりネコを殺したくないという思いからだろう。
ただ殺処分を行うことになったら、捕獲事業参加者には辛い作業が必要となり、モチベーションが落ちて(島民の支援や理解も望めなくなり)事業を遂行できなくなっていたかもしれない。その意味では、捕獲者の精神的な負担を減らすことと、世間の事業への理解を得る点で大きく貢献したのかもしれない。
そこで思うのだ。なぜネコは特別扱いなのか。シカやイノシシなどは問答無用で殺されているのに。
考えて行き着くのが、「ネコは可愛いから」という一点になる。可愛い、しかも人になつく。飼い方次第で身近なペットになるから、殺せないわけである。実際、小笠原諸島のノネコも、完全に野生下で生息していたはずなのに、捕獲後の訓練で人になつくようになったそうである。
しかし……ちょっと「ずるい」と思う(笑)。シカだって可愛いのに。現に、奈良のシカは天然記念物であり、奈良公園を訪れる観光客のアイドルだ。
実際、奈良のシカが増えすぎたから頭数制限を……と県が施策を打ち出したら、全国から抗議が殺到したという。なかには「私の住むところではシカを殺しているが、奈良では殺すな」という意見もあったそうだ。
ところで野生動物を飼育し家畜にするには、いくつかの条件がある。
まず、人に役立つこと。肉や乳、毛皮、角の提供のほか、人の仕事の手伝い(狩猟や牧畜、門番など)もある。ネコも、本来は人の貯蔵した食糧を荒らすネズミなどを獲ることを求められたはずだ。
また基本的に飼いやすく餌などの調達も楽であること。ウマはおとなしいから家畜になったが、シマウマは気性が荒くて人の思うように動かすのは難しい。タケしか食べないパンダやユーカリだけのコアラ、アリだけのアリクイなども飼育は難儀だ。
繁殖させやすいというのも条件だろう。飼育するかぎりは増やすことが必要だからだ。常に野生から捕獲するのは効率が悪すぎる。
そんな条件を満たした家畜が、ウシ、ウマ、ブタ、ヤギ、ヒツジ……そしてイヌとネコなどではないか。
そのなかでイヌとネコなどは、人の琴線に触れる仕種をする。とくにネコはツンデレで心を揺さぶる。ずるい。この「可愛い」という感覚、曲者である。これが家畜に留まらせず、愛玩動物化した原動力となったのだから。
現在、日本では年間4万5000万頭以上のネコが殺処分されているそうである。これは飼いネコ、ノラネコが対象。ノネコは入っていないだろう。それに対して殺処分をゼロにしようという運動も起きて、涙ぐましい努力もされている。捕獲したネコを全部救っている小笠原のケースは特殊と言ってもよい。
だが、シカやイノシシはどちらも年間60万頭前後駆除されている。それでも獣害は減らず、駆除数を2倍にする目標が掲げられるほどだ。しかし、シカやイノシシの里親を探そうという声はついぞ聞かない。物理的にも無理だろうが。
シカも可愛いのだけど。イノシシはちょっと怖いが、よく見ると可愛いところもある、と思う。ウサギといい勝負。しかし、ネコには負けるか。。。
この「可愛い」は、冷静な理屈を飛び越えた行動を取らせる。人の心に与える影響としては、喜怒哀楽以上に最強なのかもしれない。
おりしも今年は動物愛護法の5年に1度の改正の年。今回は若齢イヌ・ネコの売買規制や、飼育環境の適正化義務が焦点のよう。一部では産業動物(家畜や実験動物など)の扱いも盛り込もうとされているが、ほとんどの目はイヌとネコにしか向いていないだろう。
しかし動物と向き合う際は、「可愛さ」抜きに冷静な目を持ってほしい。獣害駆除、あるいは食肉にするため殺す際でも、アニマルウェルフェア(動物福祉)の心がけは忘れないでいるべきだろう。