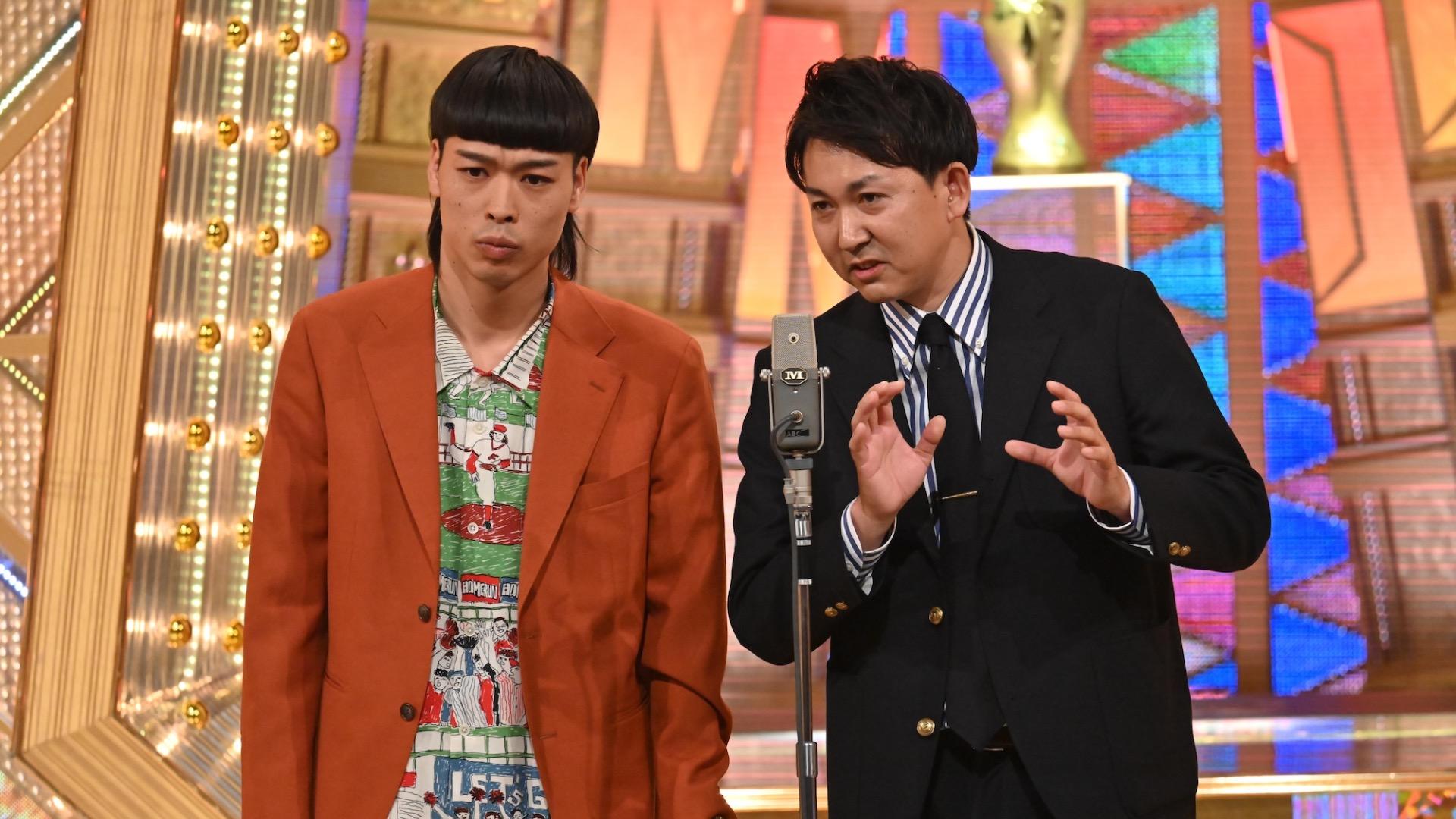【挑戦する私学】いかにして「生きる力」を育むか?(東京女子学園編)

今、私学を中心に「探究」の波が訪れている。新学習指導要領では予測不可能な時代を「生きる力」の育成に焦点が当てられ、そのために「主体的・対話的で深い学び」が提唱されている。探究型という学びのカタチは「主体性」が必須条件であり、従来型の学習とはコンセプトも実践方法も異なるため、多くの現場では混乱が続いており、私のもとにも多くの相談が寄せられている。このシリーズでは、男子校・女子校・共学校それぞれの探究実践事例を取り上げて、考えてみたい。
学校がチャレンジすることの意義
コロナ禍で顕著だった傾向の一つに、チャレンジする学校への生徒保護者の信頼が挙げられる。昨年の臨時休校要請下では、リスクを取ってオンライン化やハイブリッド化を目指して試行錯誤した学校と、リスクを取らず様子見状態で出遅れた学校とに二極化した。当然のことながら、人材も機材もノウハウも不足する中でのチャレンジになったため、特に授業のクオリティー的に成功とはいえない学校も多かった。
しかし、学校や教師が「予測不可能」な状況に適応すべく奮闘する姿自体に感謝し刺激を受けたという生徒・保護者の声を少なからず耳にした。一方で、様子見校の生徒からは「うちの学校は何もしてくれなかった」「宿題が出されただけでやる気にならなかった」という声が聞かれた。これは、リスクを取らなかったこと自体がリスクになったといえる。
本質的な探究導入を実現する設計

今回取材させて頂いた東京女子学園は、その名の通り女子校である。三田駅近くの好立地にあり、現在新校舎を建築中である。女子校は全体的に伝統的で保守的な校風を持つ学校が多く、探究などの新しい学びへの取り組みに積極的な学校が多いとは言えない。女子校に進学させたいという保護者が保守的な傾向があることも原因の一つだろう。そんななかで、限られた時間をマネージして、従来型の学習に本質的な探究学習を導入することは、それ自体がチャレンジだといえる。
学校教育における探究のハードルには大きく3つある。1つ目はカリキュラム、2つ目は評価、そして3つ目は多人数制である。そもそも探究は誰かに言われて、決められた時間内で、みんなと同じことをする活動ではない。真逆である。探究の教材を作っている企業も散見するが、基本的に授業時間内で収まるようにという方針で作られ、評価もしやすく設計されている。それでは従来型の授業と構造的に変わらない。
東京女子学園は、これらの三つをクリアーすべくかなり大胆な授業設計を実現している。まず、単位がないゼミ形式ということが挙げられる。「探究ゼミ」を担当する教師は、本当に自由にやりたいことを設定し、年度の初めに生徒たちにプレゼンする。生徒たちは、全部で15のゼミの中から自由に選択することができるため、対象学年が設定されていなければ、中1から高2まで5学年が共に活動し学ぶことになる。教師に主体性や探究心がなければ、主体性や探究心を身につける授業などできない。無論チャレンジ精神も同様だろう。
もちろん、すべての授業が理想通りうまく行っているわけではない。問題は山積している。すべての教師が探究マインドを持ち、探究的に生きているわけではない。しかし、それはどんな学校現場でも同じである。生徒の笑顔と成長が認められる成功事例があり、それを生徒が主体的に選択できる環境にあることが重要だ。
特筆すべきは、その柔軟性だ。生徒がやりたいと言ったことを、実現するために即調整する。カリキュラムに支配されるのではなく、教師が自分の世界観で作っている授業だからこそ、それが可能なのだろう。
事例1 『新校舎建設に参加しよう!』

このゼミは、新校舎建設現場の工事の音が気になっていたところ、むしろもっと近くで体感できないかと着想したという。どうせ工事しているのだから、それを学びに活用しようというアイデアだ。女子高生ならずとも、工事現場に立ち入る経験はなかなかできない。
ゼミを担当する棚橋毅教諭は、熊谷組に直談判し、探究への協力を取り付けた。事前のカリキュラムは一部しか設定せず、活動を進めていく内に自然に湧き上がった興味関心をシェアしていくという方針ではじまった。それを受けて熊谷組が工程に学びの機会をアレンジしていく。その結果、実際にコンクリートを流し込んだり、クレーンに乗ったりという経験の中で、あらゆる教科を越境した学びが実現している。私が取材に訪れた当日は、生徒から出された熊谷組の女子社員と女子会をするというアイデアが実現し、私を含め男性教師陣も蚊帳の外でプロジェクトが進行していた。そのような運営を含め本質的な探究の時間が育まれていた。
事例2 『教材屋さんにもの申す』

このゼミは、老舗出版社である明治図書出版が制作中の教材に対して意見をすることでよりよいものにすることを目的として活動をしている。担当の唐澤博教諭は、「自分たちの学びが、大人のリードでいいのかって思いませんか?」とメッセージで呼びかけた。
「もともと強制されて勉強することが嫌いだったからこのゼミを選びました」という未来創造コースの高2生徒は、「自分が渡されたときに、やってみても良いかなと思う」教材にするために、「ガンガン言いますね。文字が読みにくいとか」。実際に、デジタル教材のバグを発見して貢献したこともあるという。「出版社の方が本気なので、毎週ほんとうに楽しみですね。私にとっては、このゼミが一番だったと思っています」と目を輝かせていた。
事例3 『東京女子体操第2を作る』

30年以上の歴史がある「東京女子体操」が映像化されていないことに目をつけた担当の近藤桃代教諭は、未来へこの伝統を伝えるため、まずちゃんと身体の動きが分かるような映像作品を作るゼミを考えたという。
その際、1年間では時間が余るので、今の生徒が同じ曲で「第2」の振り付けを考えたらどうなるだろう、と思いついたという。第2の振り付けテーマは「やせること」。しっかりと自分たちの実益も考えた「自分ごと」の探究になっている。取材当日は、生徒からの提案で急遽、K-POPをつないだ音源でダンスをすることでインスピレーションを共有していた。「第2が完成したら、第3ですね。次は「部分やせ」がテーマかな」と、生徒と一緒に楽しんでいる姿が印象的だった。
探究する姿勢と実践
学校組織が大改革することは難しい。しかし、少しずつアップデートしていくことはできる。繰り返すが、すべてがうまく行っている学校はないと断言できる。パンフレットやホームページからはその実情はうかがい知れないし、当然偏差値から分かるものでもない。特に私の専門分野の一つである「探究」においては、まだまだ本質的な実践が出来ているといえる学校は少ない。
まずは、相性の良さそうな「実践」が選択できる学校を知ることが、進学先を決める上で鍵になる。過渡期である今は、成功事例だけでなく「挑戦」に注目したい。挑戦すること自体が、探究に他ならないからである。もちろん、挑戦すれば良いというものでもない。学校組織は大前提としてサスティナブルである必要がある。つづけられる改革をしなければ信頼は得られない。学校においても経営陣と現場の感覚のズレを散見する。改革を進める学校には、なによりも生徒と現場の教員を大事にすることを切に願う。引き続き、挑戦する私学の実践を教育実践者の視点で取材し、伝えていきたい。