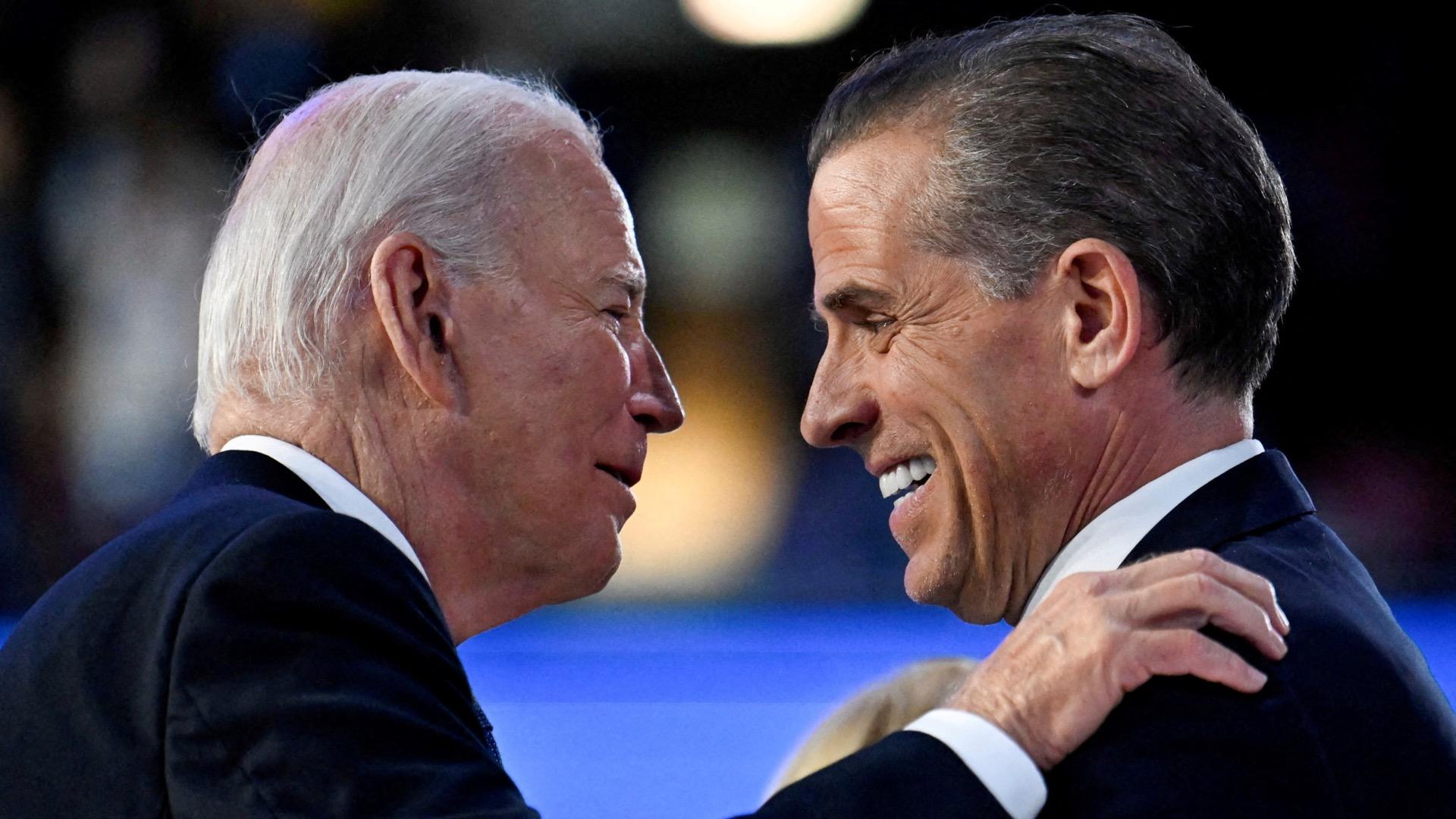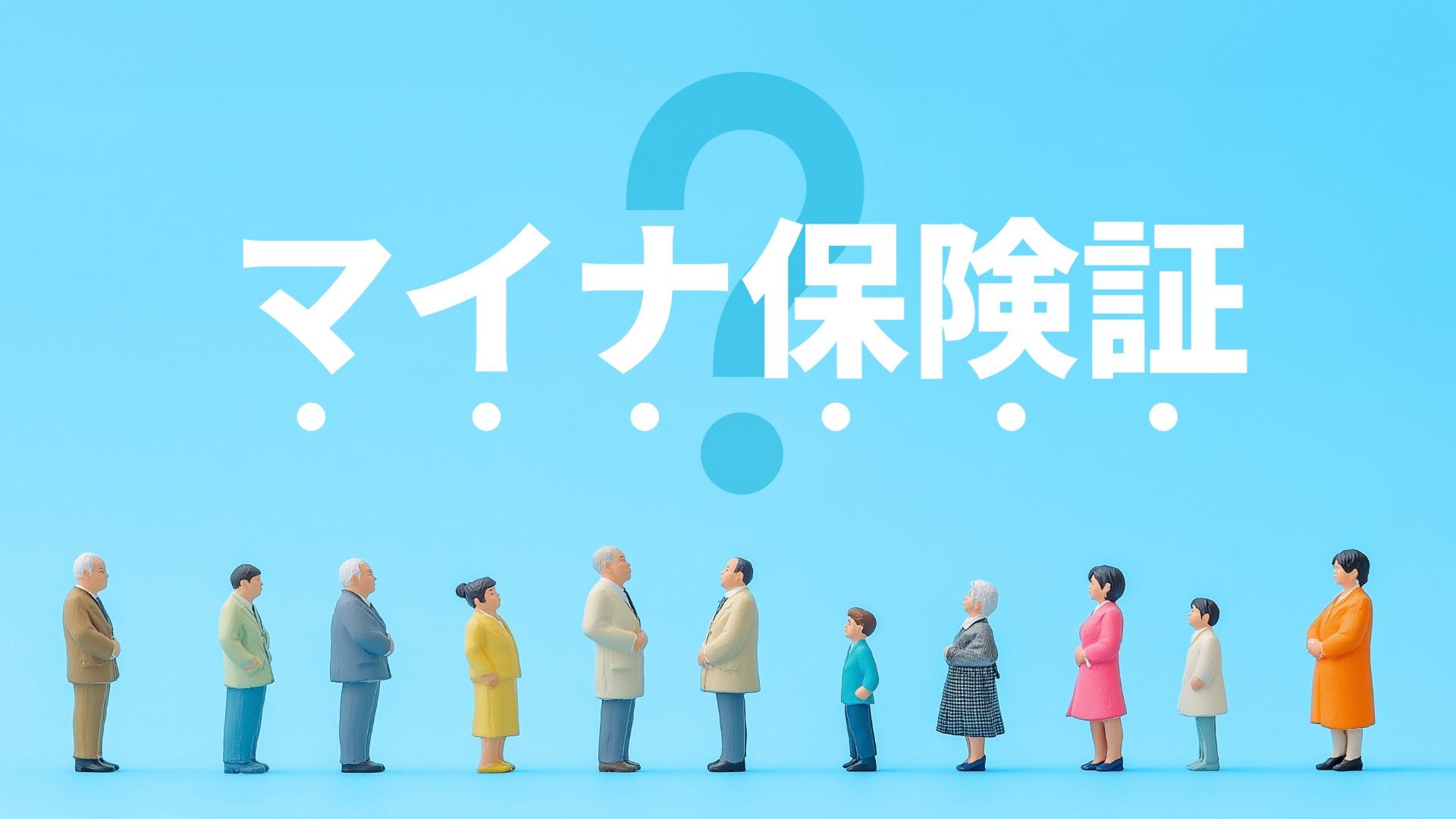子どもが叩いてくる!物を投げる!困った行動の5つの原因と対処法を幼児教育講師が徹底解説!【後編】

幼児教育講師のTERUです。
日々の子育て本当にお疲れ様です!
今日は前回に引き続き『気に入らないと物を投げる!落とす!人を叩く!』というテーマについてお話しします。
前回の記事がまだの方はぜひ併せてご覧ください。
【4.敏感期の反復行動やブーム】
『敏感期』とはモンテッソーリ教育でいわれる言葉で、子どもが成長の過程で様々な行為や動作を繰り返し、その動きを習得したり自分の知的好奇心を満たしていく時期のことをいいます。
お子さんが低年齢、0歳〜5歳くらいに多いのですが、悪意があってその行為をしているのではなく「これをしたらどうなるんだろう?」という好奇心から物を投げてしまったり、物を投げた時の音やその動作が面白くて、何回も繰り返してしまう時期であるということですね。
特に3歳くらいまではその傾向が強く、さらにそこから上の年齢でも大人の声かけや反応から子どものブームになって物を投げたりする行動を繰り返してしまうということもあります。
例えば、子どもがボールを投げたときにパパが「おー!すごい!上手ー!!」と大げさに何度も褒めたことがきっかけで、そこから何かと投げたがるブームが始まったという子もいます。
投げるのが好きになのは良いことでもあるのですが、そういった行動でお困りのときは次の方法を試してみてほしいなと思います。
1)危なくないもので好きなだけやらせる

このような時期におもちゃを何度も落としたり投げたりするのは、先ほどの通りその動作から何かを習得しようとしていたり、どうなるんだろう?という好奇心からくるものだったりします。
それをしつこく止めてしまうと、子どもの好奇心はいつまで経っても満たされません。
ですので、もしその物が「まぁ投げてもいいか」と思うものであれば一旦そのまま自由にやらせてあげる。
そしてそれが投げると危ないものであれば、他に投げて良いものを渡してあげて、投げたり落としたりする行為を満足するまでさせてあげることで、いつしか他のことに興味が向いてやらなくなっていくかもしれません。
投げる代替品としては
- ベビー用ボール
- ふわふわボール
- 新聞紙ボール
などで夢中になってくれれば理想ですが、落ちるときの音などを楽しんでいることが多いので、その場合はちょっと試行錯誤が必要かもしれませんね。
2)家の中の危ないものをガードする
自由に物を投げさせてあげるという選択をした場合、ここに投げられると困るというものはなるべくガードしておくのが得策です。
- 床にジョイントマットなどを敷いて床が傷つかないようにする
- ガラス飛散防止シートで窓などが割れないようにする
少し手間ですがやっておくことで最悪の事態は避けられますよね。
3)投げてはいけないものは目につかないところに
満足いくまで投げさせるという方法をとっても、全然ブームが去らないということも普通にあります。
そうなると、言葉で伝えて理解をしてくれる年齢になるまでは、投げて困るものや危ないものは見えないところや手に取れないところに保管するという根本対策が必要かもしれません。
なるべく自由にやらせてあげたいとはいえ、本当に投げては困るものはたくさんありますからね。
4)食事を投げるなら少ない盛り付け&切り上げ!

“お子さんが食事を投げて遊んでしまう”というお悩みも多いですよね。
これも一時的なしょうがないことで、満足したらやめるようになっていきます。
ですが、食事を粗末にさせたくないと思われる方も多いと思いますから、そんなときの対策としては
・一度に盛りつけすぎないようにする
・食事に飽きてきたら切り上げる
というのが良いかと思います。
盛り付けの量が少なければ投げる張り合いがないですし、やはり飽きてきたら遊びたくなってしまうものです。
全部食べることにこだわりすぎてダラダラと1時間近く食事の時間といったような状態が常態化しているのであれば、切り上げることが助けになるかもしれません。
5)親の顔を叩くなら『悲しい表情』などしかないかも・・・
これはかなり多くご相談をいただきます。そして正直対策がかなり難しい。
これもある意味でのブームのようなものなのですが、親の反応が楽しくて顔を叩いてしまっているということが多いです。
なので、まずはなるべく反応をしない。
とはいえ、力が強くなってくると痛いし反応しないなんて無理!という状態であれば、親が悲しいという表情を見せたり、泣き真似をしてみたり、根気強く説明したりしながら、伝えていくしかないのかなと思います。
【5.そもそも投げてはいけないことや扱い方を理解していない】

ここまで色んな原因に対する対策をお伝えさせていただきましたが、ここで皆さんと考えたいのは「それ本当にちゃんと教えたかな?理解しているかな?」ということです。
例えば、子どもが車のおもちゃを頻繁に投げるとします。
そして親の様子を伺っているなと感じたので“反応をしない”という方法を取ったけれど一向に変わる様子がない。
その場合、もしかしたら原因は『ちゃんと教えていないから』かもしれません。
お子さんが低年齢であれば、実は良い使い方を理解していないことは多いです。
なので、できる対応として
1)正しい使い方の見本をもう一度見せてみる
今の車のおもちゃのケースでいえば「こうやって遊ぶんだよ!」と床を滑らせる見本を見せてあげたりすると意外にそれを真似してちゃんと遊ぶようになることもあります。
他にも、そっと渡す見本を見せる。優しく片付ける見本を見せる。といった感じでもう一度良い見本を見せてあげましょう。
そんなこと理解してるはず!と思っても実は伝わっていないことも多いので、一度試してみてくださいね。
2)感情に訴えかけるように伝える
子どもは理論より感情に訴えかけて伝える方が響くことがあります。
・おもちゃを落としたりするなら「おもちゃがかわいそう。痛そう。」
・ママを叩くのであれば「ママ叩かれて痛い。悲しい。」
などと言いながら本当に悲しそうな顔をして感情が動くアプローチをすると、子どもの理解を促進することもあります。
3)〇〇するとどうなる?と聞いてみる
会話ができる年齢であれば
・「物を投げるとどうなるかな?」
・「人を叩くって良いこと?良くないこと?」
などを聞いてみるのもありだと思います。
返ってきた答えで子どもの理解の段階が確認できますね。
他にも
・「他の子に当たったらどうなる?」→ケガをする
・「このおもちゃを床に投げたらどうなる?」→壊れて遊べなくなるかも
・「窓に当たったらどうなる?」→窓が割れてしまうかも
などと、質問をしながらお子さん主導で一緒に考えていけると良いですね。
【これらの選択肢をどう選んでいくか?】
ということで、今回過去一と言って良いくらい対応の選択肢を多くご紹介しましたので、ちょっと混乱した!という方もいらっしゃるかもしれませんね。
これらを一度に全部やるなんて無理ですから、この選択肢の中からご家庭に合いそうなものを少しずつ試してみてほしいのですが、そのときに大切なのが、まずは『観察』から始めるということです。
何の観察かというと「どんなときに物を投げるのか?叩くのか?」という観察です。
その観察で傾向として、
- 親がこんなことをしたときにその行動をする
- 子どもがこんな状態のときにその行動をする
などといったことが見えてくれば、選択肢が選びやすくなります。
【どんな対応にも共通する最重要ポイント】

最後に、今回の子どもが叩く!物を投げる!行為への対応においての最重要ポイントをお伝えして終わろうと思います。
1.どの対応も即効性の効果を求めず時間をかけてゆっくりと変わっていくことをイメージする
これらの対応はすぐに効果が出るものばかりではありません。
むしろ多くの対応は時間をかけて徐々に効果が見えてきます。
焦らず関わっていきましょうね!
2.ガミガミ怒って躾けるという方法だけは良くない方向へ行く確率が高い
どの対応も時間をかけてゆっくり変わっていくとはいえ、唯一『ガミガミ怒って躾ける』という方法だけは良くない方向へ行く確率が高いと僕の感覚では感じています。
“対応の成果が出るのは時間がかかる”ということだけ頭の片隅に残って、ガミガミ叱る方法もいつか成果が出る!と継続する結果になっては良くないと思ったので念の為お伝えさせていただきます。
3.まずは否定せずに気持ちに共感をしてあげる対応をベースに
子どもが叩く!物を投げる!ということの根底には「わかってほしい!」という気持ちが隠れていることも多いです。
どんな対応の選択肢を取ったとしても
・「○○がしたかったのね」
・「○○がいやだったのね」
という気持ちへの共感は意識的に伝えていくことをおすすめします。
そういった共感の言葉が、そのときの子どもの心を落ち着かせ少しでも冷静に自分の行動を抑制していくパワーになりますからね。
いかがでしたでしょうか?
かなりボリュームのなる内容になってしまいましたが、少しでもお役に立てる部分があれば嬉しいです
皆さんの子育てを応援しています!
オススメの関連記事はこちら
動画でより深く学びたい方はこちら