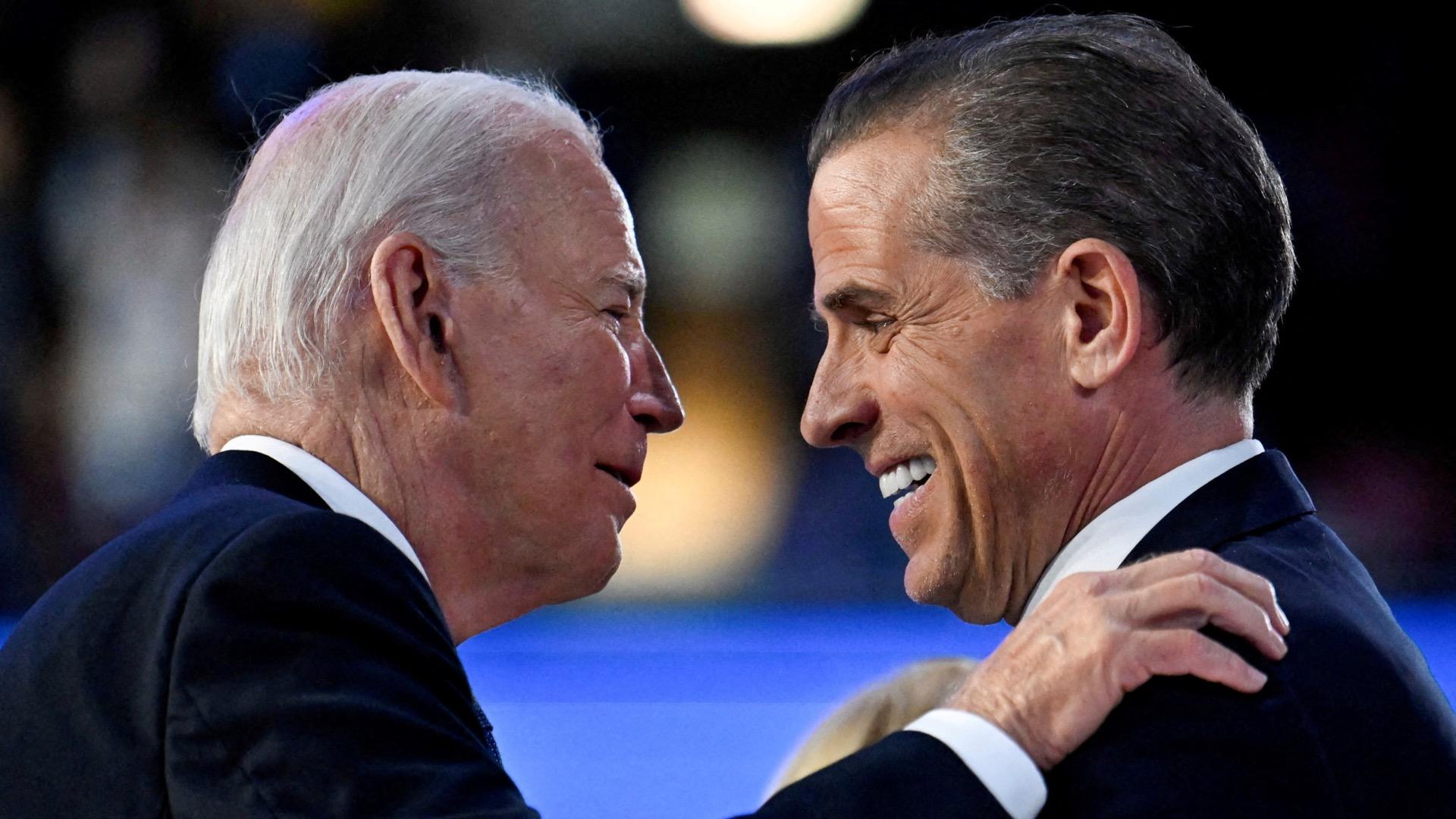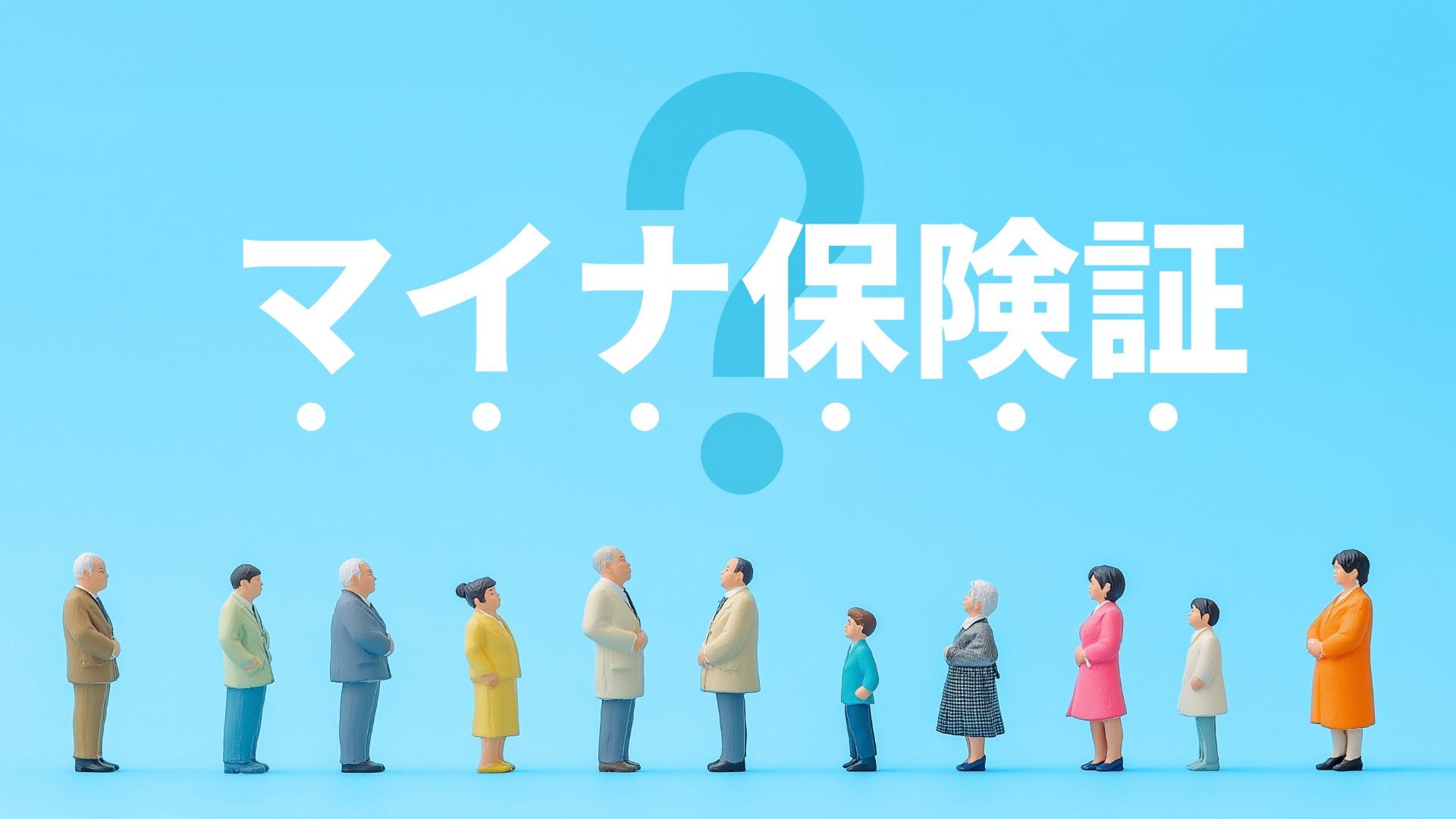「子どもが叩いてくる!物を投げる!」困った行動の5つの原因と対処法を幼児教育講師が徹底解説!【前編】

幼児教育講師のTERUです。
日々の子育て本当にお疲れ様です!
今日は『子どもが気に入らないと物を投げる!落とす!人を叩く!』というテーマでお話しします。
【主な5つの心理】
まずこの「物を投げたり叩いたりする」という行為の子どもの心理にはどんなものが考えられるでしょうか?
私は大きく分けると5つ考えられると思っています。
- 注意を引きたい
- その行為で何かが上手くいくと学習している
- 気持ちを表現する方法がそれしかない
- 敏感期の反復行動やブーム
- そもそも投げてはいけないことや扱い方を理解していない
この5つです。
実際は、この5つの要素が複雑に絡み合って、その行動をしているということがほとんどですから「これが原因!」と決めつけずに「こんな可能性があるのか」くらいに捉えてみてくださいね。
では、それぞれ詳しく解説していきます。
【1.注意を引きたい】

子どもが物を投げたり、人や何かを叩いたりするのは、注意を引きたいからかもしれません。
もしそうであれば子どもにとって『長く注意を引けたら成功!』になります。
そして、それを学習して、
- 寂しい
- かまってほしい
- 相手にしてほしい
といったときに同じ行動をするようになっていくわけです。
そんなときに私たちが取れる選択肢は全部で5つあります。
1)反応しない
お子さんが物を投げたり叩いたりしたときに、実験的に反応しないでみるとその行為で注意が引けないことがわかり、その行動をしなくなるかもしれません。
2)低いトーンで対応
こういったとき、どうしても大人も大きな声で「やめて!」とか「ダメ!」などと言ってしまいがちですが、それが子どもにとっては「面白い!」とか「注目されている!嬉しい!」という学習になっている可能性もあります。
あえて淡々と低いトーンで対応すると思った通りの反応が来なくて、その行動へのこだわりが少なくなるかもしれません。
3) 短く注意してパッと終わる!
もしお子さんに対して注意をするのであれば、ダラダラ長く注意するのではなく、短くビシッと注意するというのも大切です。
4)良い行動ができたときにちゃんと伝えていく
ここまでの3つはお子さんが良くない行動をしたときの対策でしたが、忘れないでおきたいのが『子どもが良い行動をしたときにどのような声かけをしていくか』です。
子ども目線に立てば、良くない行動のときは注意されて良い行動の時には何も言ってもらえないのでは良い行動をしようと思いませんよね。
今まで投げていたものを優しく渡すことができたり、大切に使う様子が見られたら
・「優しく渡してくれてありがとう!」
・「大切に使えてるね!」
・「大切にしてもらえてきっとおもちゃも嬉しいね!」
お母さんを叩くことが癖だった子が優しくお母さんの頭を撫でてくれたら
・「ありがとう!優しく触ってくれてお母さん嬉しい!」
などと伝えてあげましょう。
このように良い行動のときにちゃんと伝えてあげることで、少しずつ良い行動で親が自分に注目してくれることがわかり悪い行動が減っていったりします。
5)一緒に楽しむ時間を増やしてあげて注意を引く必要のない環境を作る
絵本の読み聞かせや、一緒に遊ぶ時間、話を聞いてあげる時間を少しずつ増やしてあげることで、子どもは自然と日々の中で親が自分に注意を向けてくれているんだという安心感を得ることができます。
それによって、あえて良くない行動で注意を引く必要がなくなり、投げる!叩く!という行動が減っていくかもしれませんね。
即効性があるものではありませんが、今回の問題だけではなく色んな良くない行動へのアプローチの土台でもあります。
【2.その行為で何かが上手くいくと学習している】

もし子どもが怒りながら物を投げたり、わがままを言いながら叩いたりした後、その状況を回避するために大人が『子どもの望む行動』をしてあげていることが常態化しているとしたら、その行為で何かが上手くいくと学習しているかもしれません。
例えば、お菓子を買ってもらえないときに親を叩いて、困った親がお菓子を買ってあげたとします。
周りの目などもありどうしようもないと感じるお気持ちもよく分かるのですが、子どもの思考回路を考えると、
『怒ってママを叩けば買ってもらえる』
と思ってしまっている可能性はありますよね。
それが常態化していると、何か思い通りにならないことがあると叩いたり、物を投げたりして自分にとって都合の良い状況に持っていこうとするわけです。
なので『子どもが怒ったときに子どもの思い通りになる対応をしすぎていないか?』をチェックしてみて、もし心当たりがあれば、まずは落ち着くまで抱きしめてあげるなどといったスキンシップや安心できる行為に変えていけると良いですね。
【3.気持ちを表現する方法がそれしかない】

子どもは言葉で表現するより手足で表現することの方が最初は得意なので、何か嫌なことがあったり上手くいかないことがあると手で人を叩いたり物を投げたりして表現してしまいがちです。
ただ、ここで間違えてはいけないのが『気持ちを表現することは間違いではない』ということです。
嫌なことを嫌と伝えることは大事ですし、上手くいかないことを悔しい!と伝えることも大事なことです。
その手法が間違っているだけですね。
もしそのように「気持ちを表現する方法がそれしかないのでは?」と感じる場合は、次の3つの対応の選択肢が考えられます。
1)他の表現方法を教えてあげる
お子さんがお母さんをすぐに叩くのであれば
・「何かを伝えたかったらママの肩をトントンってできる?」
と伝えて一緒にトントンする練習をしてみる。
会話でコミュニケーションが取れる年齢であれば
・「悲しい気持ちになったら『悲しかった!』って教えてくれると嬉しいな」
・「『今怒ってるよ!』って教えてくれる?」
と伝えてみる。
このように、叩く・投げるのではなくこういうやり方で教えてね!と日々伝えていってあげることで、少しずつ子どもの取れる選択肢が広がっていくかもしれませんね。
2)「何が嫌だった?」と聞いてから一緒に次の対応の選択肢を考える
お友達との関わりで自分のテリトリーを侵されたことで叩いたり、物を投げてしまったりしてしまうことも多いですよね。
そんなときは、もちろんですがまずはパパママがお友達と相手の親御さんに謝り、その後2人の空間で「何が嫌だった?」と聞いてみてください。
そして「おもちゃを取られて嫌だった」とお子さんが言ったのであれば、
・「そっか。それが嫌だったんだね。気持ちはとてもわかるけど、叩くのは良くないね。じゃあ次は『順番に使おう』と言ってみるのはどう?」
といった感じで提案してみたり、一緒に考えられる年齢であれば「次はどうしたら良いかな?」と聞いてみても良いですね。
子どもが何を思ってその行動をしたのか?を聞き、そして嫌だった気持ちは認める。
そこから他の選択肢を考えていくことで、お子さんも受け入れやすく、他の表現方法を増やしていく助けにもなります。
3)「〇〇ならいいよ!」と代替案を渡す
お子さんがおもちゃを投げてしまうといったとき。
投げないように他の選択肢へ導くのも良いですが、投げても良いような物を渡して
・「このおもちゃは投げると壊れてしまうから投げてはいけないよ。でもこのボールは投げていいよ!どうぞ!」
と伝えてあげると効果が出る場合があります。
ただただ行動を禁止されるのは子どもにとって受け入れづらいですが、禁止と一緒に許可をされると比較的ですが受け入れやすかったりします。
いかがでしたでしょうか?
次回は後編をお届けしますので楽しみにお待ちください。
皆さんの子育てを応援しています!
オススメの関連記事はこちら
動画でより深く学びたい方はこちら