自治体初? 東京・杉並区が選挙の「投票マッチング」を導入
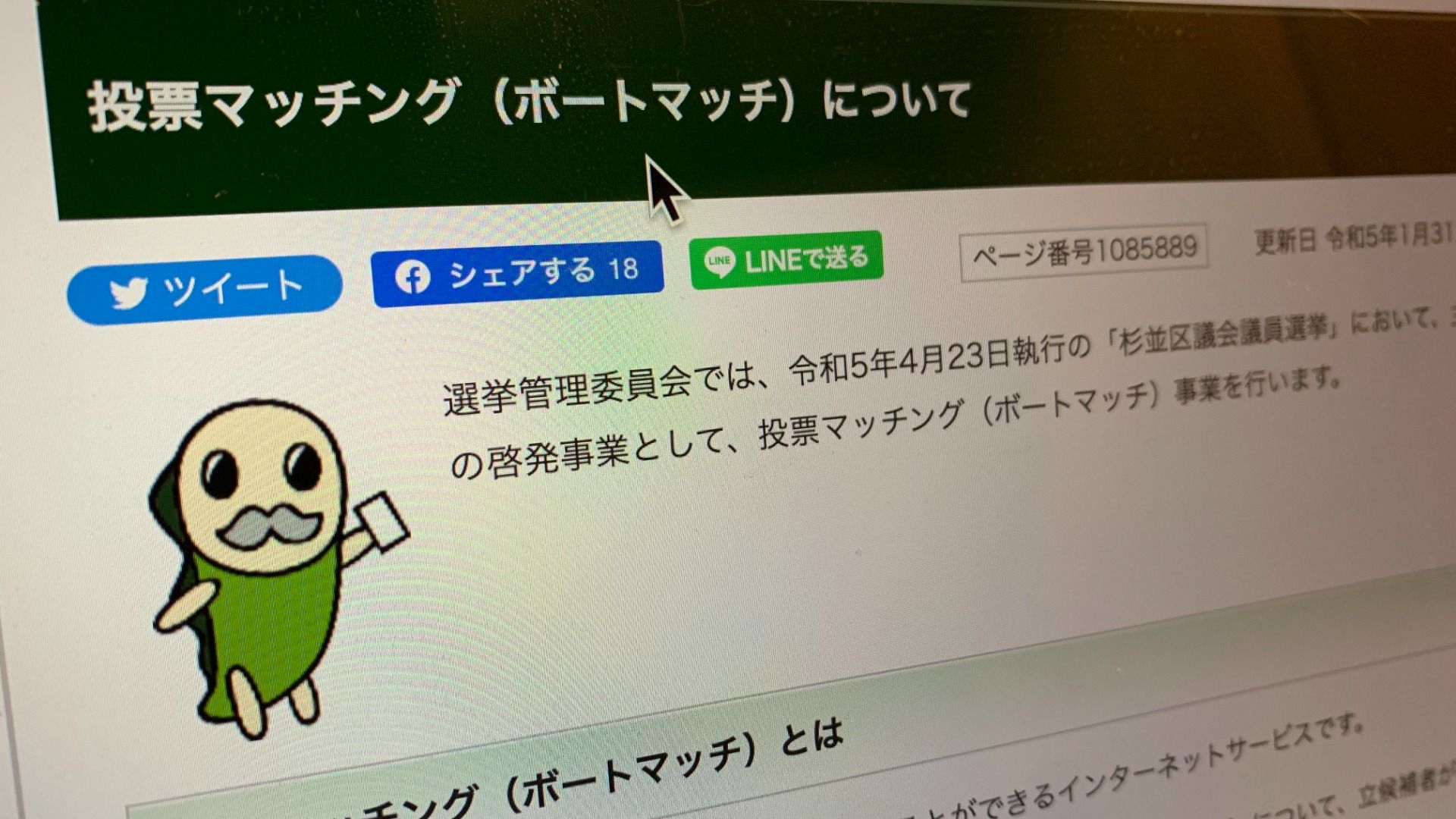
東京都杉並区の選挙管理委員会は今年4月の杉並区議会議員選挙で、有権者が自分の考えに近い候補者を知ることができる「投票マッチング(ボートマッチ)」のサービスを導入する。目的は投票率の向上にあるが、自治体主体では初の試みとみられる。
投票マッチングはインターネットを活用した新しい情報サービスで、20年ほど前から新聞社などのメディアが主に実施してきた。地方自治体の選管が主体となるのは異例だ。専門家は「自治体では初めてだろう」と指摘。杉並区選管も「調べた範囲では自治体の先行例はなかった」とする。
同選管は、選挙情報サイト「選挙ドットコム」にシステムの構築と運営を委託して、投票マッチングを提供する。利用者は選挙期間中にパソコンやスマートフォンからサービスにアクセスし、区政に関する20個の設問に回答することで、自分と一致率が高い候補者を知ることができる。
杉並区の岸本聡子区長は1月31日の記者会見で、投票マッチングについて問われ、「公正中立の立場で取り組みを進め、少しでも選挙が区民に身近なものになるように、その成果に期待しています」とコメントした。

「20代の投票率の低下をなんとかしたい」
自治体として異例の投票マッチングの導入に踏み切ったのは、投票率の向上のためだ。「一番の理由は、20代の投票率の低下をなんとかしたいということ」と、杉並区選管の江川雅志事務局長は語る。
杉並区の人口は約57万人。有権者数はその9割ほどだが、区議選の投票率は2015年が40.1%、19年が39.5%と低迷している。特に20代の投票率が低く、19年は20.4%しかなかった。
「若者たちになぜ投票に行かないのかと聞くと、『どんな人が出ているのか分からない』『顔と名前は分かっても、どういう主張なのか分からない』という声が多い。そうであれば、投票マッチングによって、それぞれの候補者がどういう主張を持っていて、自分の主張とどれだけ近いのか分かる、というのが大事ではないかと考えたんですね」(江川事務局長)
杉並区議選は定数48。大都市圏の選挙ということもあり、候補者の数は毎回70人近くになる。有権者はその中から1人を選ばなければならないが、選挙ポスターで初めて見る顔も多いのが現実だ。そんな状況の中、投票マッチングで選挙に関心を持ってもらい、投票の参考にしてもらおうという狙いだ。
他のネットサービスと同じようにスマホから簡単にアクセスできて、いわばゲーム感覚で利用できる。紙の選挙公報を読むよりも、若者には親しみやすい方法といえそうだ。
「昨年6月の区長選の前から、投票率を上げるために、インターネットを活用して何か仕掛けができないかと議論してきました。目標は、投票率を5ポイント上げることです」
江川事務局長はそう意気込む。

ポスター掲示板の「QRコード」で周知をはかる
今回の投票マッチングでは、区政に関する20個の質問が用意される予定だ。決めるのは、公募で選ばれた「投票率アップ企画委員会」の12人の委員たち。15問は杉並区の実行計画についての質問で、残りの5問はそれ以外から設定する。
区議選の候補者たちはそれぞれの質問に対して「賛成」「やや賛成」「中立」「やや反対」「反対」という5つの選択肢から回答を選ぶ。さらに、なぜそう答えたのか、理由を200字以内で記入できるようにする。
「質問の多くは、区議会で承認された実行計画に関するものなので、公平性が担保できます。また、利用者に質問を読んでもらうことで、区の政策はこうなっていたのかと知ってもらう機会にもなります」(江川事務局長)
これまでも国政選挙や知事選では、新聞社などのメディアが投票マッチング(ボートマッチ)のサービスを提供してきた。しかし、区議選や市町村議選といったレベルの地方選挙で、投票マッチングが実施されるのは異例のことだ。
もう一つ、従来の投票マッチングと違う点がある。選管が主体である点を生かして、投票マッチングサイトのURL(アドレス)の「QRコード」が、区内に500カ所以上ある選挙ポスターの掲示板に表示される予定なのだ。
選挙の投票前にポスター掲示板を見る有権者は多い。その際にQRコードを通じて、投票マッチングのサイトへアクセスし、投票の参考にすることができる。これは、新聞社などの民間企業では実現できなかった周知方法だ。
「ポスター掲示場のQRコードが一番効果があるのではないかと思っています。なかには、投票マッチングの結果をSNSに投稿する人もいるでしょう。それで情報が拡散して、さらに利用が促されるのを期待しています」(江川事務局長)

新制度への「区議の反応」は賛否さまざま
選挙への関心を高め、投票率を向上させるために導入が決まった杉並区選管の投票マッチング。だが、誰もが歓迎しているわけではない。特にマッチングの対象になる区議たちの反応はさまざまだ。
「投票マッチングの設問を作るときに、行政の恣意的な視点が入る可能性がある。いくら公正中立に運用すると言ったところで、その担保をどう取るのか。100%白だと言えない状況で選挙に突っ込むのはおかしい」
そう批判するのは、自民党の渡辺友貴(わたなべ・ともき)区議だ。さらに、質問への回答が選択式であることも問題だと指摘する。
「政策には、単純にイエスかノーで答えられない問題もあるのに、5択で答えろというのは雑だと思います。民間ならまだしも、行政が主導して実施するのは間違いでしょう」
一方、無所属の堀部康(ほりべ・やすし)区議は「投票率の低下は長年の課題だった。杉並区のような究極の大選挙区では、これぐらいのことをやらないと投票率を上げられないだろう」と、投票マッチングを肯定的に評価している。
堀部区議も「もしかしたら自分にとって不利な質問が設定されるのではないかという不安はあります」と明かす。しかし「投票率を上げるためには、まずやってみることが大事」と指摘する。
「むしろ心配なのは、批判されるのを恐れるあまり、投票マッチングの内容がつまらないものになってしまうことです。初めての試みなのでいろいろ難しい面はあるでしょうが、こういう取り組みがうまく根付けばいいなと思います」

「とても難しい取り組みであるのは間違いない」
杉並区選管の取り組みの意義と課題について、選挙の情報サービスに詳しい選挙ドットコム顧問の高橋茂さんに尋ねた。
高橋さんは「おそらく自治体初。それくらい画期的な試みです」としながら、投票マッチングのメリットについて次のように説明する。
「投票先を決めるのが困難な場合に、質問に答えていくだけで自分の考えにマッチする候補を示してくれるので、投票に対するハードルが下がり、投票率が上がることが期待されます」
その一方で、「質問しだいでは特定候補へのマッチングが集中する懸念がある。そのため、質問の作り方が非常に難しい」と指摘する。
また、候補者がマッチングを意識して本来の主張と異なる回答をした場合、「それをチェックする仕組みがなければ、実際の政策と整合性がない回答をもとにマッチングがされてしまう恐れもある」という。
「マッチングの結果をどのように判断して投票行動に反映させたら良いのかという指針も含めて、とても難しい試みであることは間違いありません。まずは実施することが大事ですが、その結果がどうなったのかという分析は、他の自治体も大いに注目するはずです」










