樋口尚文の千夜千本 第34夜 ドラマ「64」(大森寿美男 脚本)
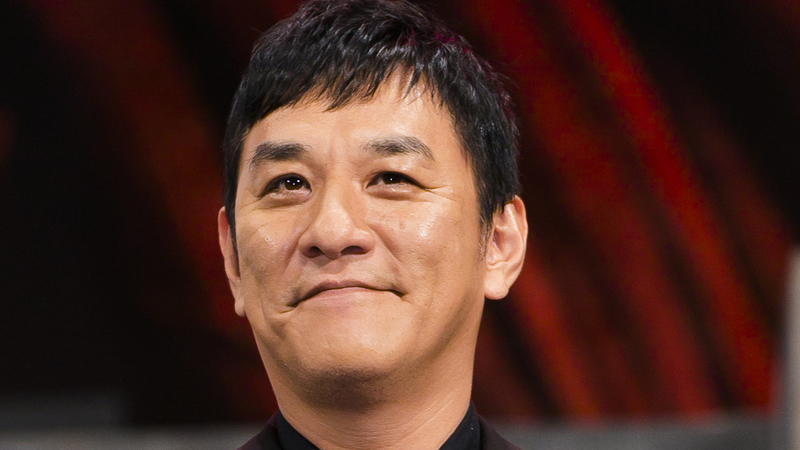
雪崩のごときサスペンスに呑まれる知的活劇
本レビューのトップページの口上に”映画からテレビドラマを横断する”とうたっているのに、これまでテレビドラマを俎上に載せたことがなかった。筆者は映画中心の評者だが、キネマ旬報に20年近くテレビ時評を連載していたぐらいだから(20年間、かたぎの仕事もしながら映画だけでなく毎クールのドラマをすべてチェックし続けるというのは、もはや千日回峰行じみた苦行で)ドラマへの思いもそんじょそこらの「放送評論家」氏より強烈にたぎっているつもりなのだ。にもかかわらずドラマをとりあげなかったのは決してかきたてられるドラマがなかったからではなくて、単に筆者が無精であるがゆえのこと(投稿の気まぐれで間歇的な頻度がそれを物語る)なのだが、今回はそんなふうに自分を甘やかしてはおられぬ傑作にめぐりあったので、おずおずと筆を執っている。
それは、NHK土曜ドラマ枠の『64』で、横山秀夫原作の警察小説を大森寿美男が脚本化、井上剛が演出を手がけた。この原作者=脚本家=演出家のコンビといえば、ドラマ好きならすぐピンと来るであろうが、2005年のNHK土曜ドラマの傑作『クライマーズ・ハイ』のスタッフである。となると期待はいや増すばかりであったが、もう初回の出だしからしてその期待に十二分に応える野心作で、まだ放映たけなわだが次の回が待ち遠しくてならない。
地方都市のD警察の広報官の三上(ピエール瀧)は急な警察庁長官の視察の仕切りを命じられて気が重い日々だが、そこにたった1週間しかなかった昭和64年に勃発した少女誘拐殺人事件、通称ロクヨンの記憶が亡霊のように蘇る。長官による慰問を遺族(段田安則)に頑なに固辞され、不審に思った三上はこの遺族や当時この事件に関わった同僚の刑事(柴田恭平)たちをたずね歩く。その行動を監視する警務部の調査官(吉田栄作)の影もちらほらするなか、三上はずっと隠匿されてきた内幕を知って動揺するのだが、それから刑事部長(中原丈雄)の謎の命令や鍵を握る元同僚刑事(萩原聖人)の失踪など変事が相次ぐなか、ロクヨンをそのまま再現する誘拐事件が発生する・・・。
『クライマーズ・ハイ』も新聞社における経営陣と現場の対立、現場内のセクショナリズム、社外から会社への圧力など、さまざまな組織の壁が招く摩擦軋轢に個人がどう対峙してゆくかということが主題になっていたが、『64』も警察組織における似た構造のドラマであり、前作を実に臨場感ある緊迫感をもって描いたこの気鋭のスタッフが、今回もピエール瀧の広報官の視線で得体の知れない組織内のうごめきをダイナミックに描き出している。このドラマが何より素晴らしいのは、敵が見えないこと、そもそも真実の敵を誰と措定すべきか判然としないこと、そこにこそサスペンスの核があるという確信のもとに、回を追えども追えども視聴者を宙吊りにしながら謎が増殖し続ける、という点である。もうとうに佳境を過ぎているのに、ピエール瀧のもやもやとした表情は定番となり、謎がまた謎を呼び、われわれの緊張感はほどかれることがない。
こうしてわれわれを甘やかさずサスペンドし続ける大森脚本と井上演出ゆえに、本作は文字通り高級なサスペンスとなっている。途中、開示される謎の秘密のひとつは、それが重大事を引き起こした原因とされアンタッチャブルなものとなっているが、しかし案外とこれはずっこけた些細な話であった。しかしそこがまた典型的で、暴かれた秘密はそんなものだが、それがたまさか重大事を招いたがために、どんどん秘密をめぐる嘘や壁は増殖してゆくのであり、ドラマとしてはまさに秘密の謎解きや帳尻合わせなどよりも、その謎のはびこる過程そのものがサスペンスの最も大事なところである。謎はサスペンスがどきどきと息づくさまそのものであり、謎解きはサスペンスの死である。
映画では一連の樋口真嗣監督作品や白石和彌監督『凶悪』などを筆頭とする性格俳優的な起用で評価を集めているピエール瀧の主役起用が話題となったが、この脚本と演出が全話をかけてサスペンスの塊のような作品を目指している意図に照らせば、ピエール瀧の一貫して苦虫を噛み潰したような、そのまま表情を停止させてしまったような面立ちは、最高のキャスティングである。視聴率が今ひとつふるわないことをこの主役のキャスティングのせいにして土曜ドラマの墓掘り人のように騒ぐ記事を見かけたが、これだけの上質なドラマが大衆によさをわかってもらえず苦戦している状況にあって鋭利なペンの武力供与をもって支援するのではなく、むしろその試みを可能にしている貴重な場を潰すほうに煽るなど、あまりに罪深いことである。
かつて1970年代くらいまでは、作家や論客は大衆をリードすることが役割だという自明の意識と矜持が共有されていたが、大衆がSNSというメディアを手にしてしまった今、作家も論客も大衆にまざって大衆に媚び、同じ高みで大衆のそこそこの欲望に応えることで受けをとり、保身に汲々とするという構図が一般化してしまった。「64」ってキャストも個性派だし、ストーリー展開もカタルシスがないし、なんだかモヤモヤしてわかりにくいドラマだと思ってますよね、と大衆に媚びるばかりで、このドラマの試みの高級さをもっともっと広く大衆に知らしめてやろうという一段高い文化的な侠気(おとこぎ)ある書き手がどこかにないものかと思う。
さて、脚本の大森寿美男といえば、2014年の村上龍原作のNHKドラマ『55歳からのハローライフ』もシビアな人間観察が目を離せなかったし、監督も兼ねた東映映画『アゲイン 28年目の甲子園』も辛口のアングルからじわじわと心あたたまる情感へと導くホームドラマの佳篇で、そこへこの力作『64』とあいかわらずの密度の濃い作品の連投ぶりに驚嘆するかりだ。演出の井上剛は『あまちゃん』のメイン演出家としても定評のあるディレクターだが、一転『64』では極めてクールで臨場感のある視点と小気味よい編集でまた全然違う一面を堪能させてくれて、マルチな職人肌で唸らせる。また、『クライマーズ・ハイ』のもうひとりの盛り上げ役だった大友良英の音楽は、今回も絶妙なアプローチで作品に硬質な知性を醸していた。










