エビデンスへの過剰な期待、過剰な敵視
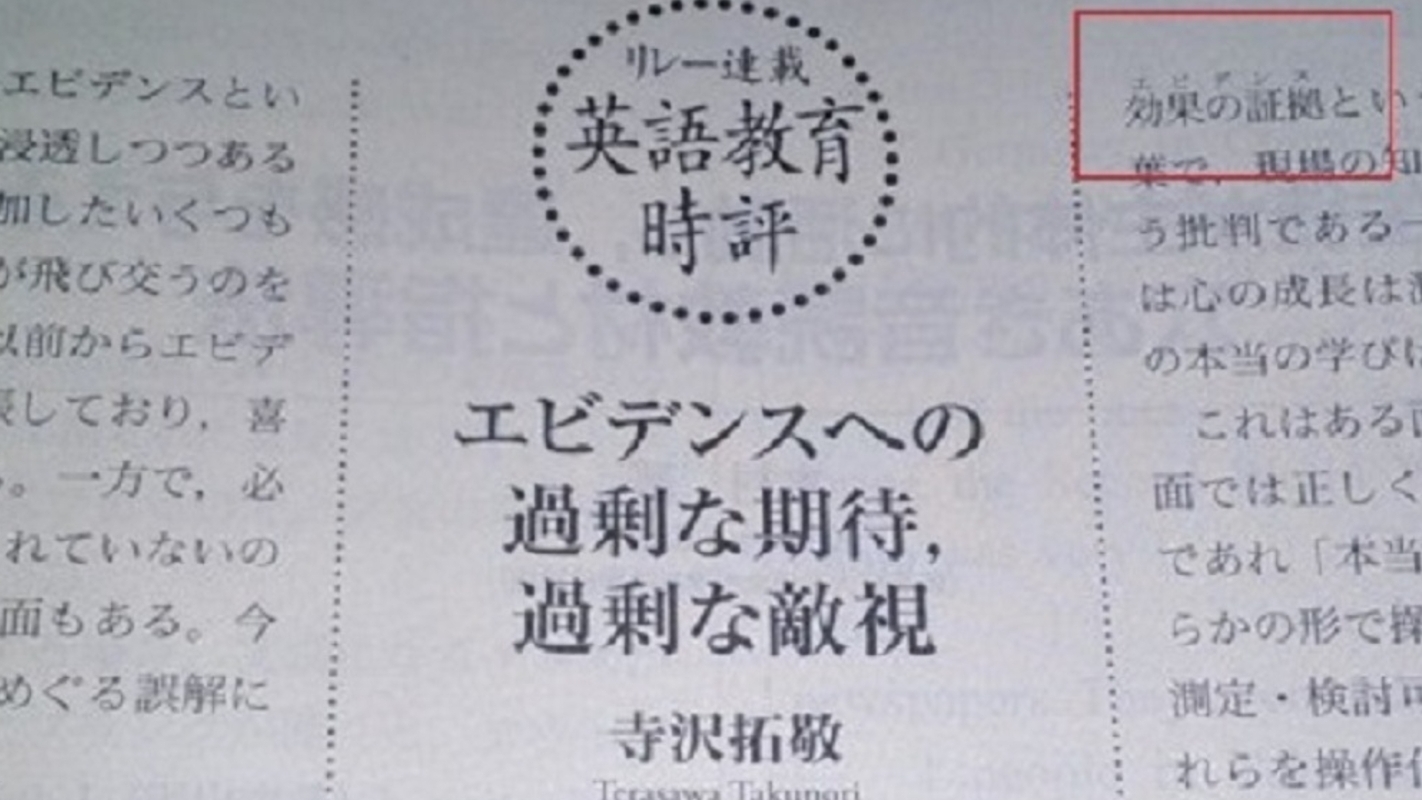
『英語教育』(大修館書店)11月号の英語教育時評に「エビデンスへの過剰な期待、過剰な敵視」というコラムを寄稿しました。1ヶ月が経過したので下書きを転載します。
なお、読者の便宜を考えて、キーワードのいくつかにリンクを挿入しています。
エビデンスへの過剰な期待、過剰な敵視
『英語教育』2017年11月号
寺沢拓敬
英語教育界でもエビデンスという言葉がじわじわ浸透しつつあるようだ。今夏に参加したいくつもの学会でこの言葉が飛び交うのを聞いた。私自身、以前からエビデンスの重要性を主張しており、喜ばしい動向ではある。一方で、必ずしも正確に理解されていないのではないかと不安な面もある。今回は、エビデンスをめぐる誤解について論じてみたい。
専門用語の「エビデンス」
この言葉は、元々、エビデンスベースト医療(通称EBM)で使われ始めたことを知っている人は多いだろう。ただ、その独得の意味に注意が必要だ。日常語の「根拠」のような緩やかな意味ではなく、それよりはるかに限定された使われ方をしているからである。
専門用語としての「エビデンス」を定義するとすれば、「特定の介入(例、指導法)が特定の結果(例、英語力向上)を生むと想定されるとき、その因果関係(指導法→英語力)を実際に支持し、その点で意思決定に役立つ実証的証拠」となるだろう。
単なる「根拠」では置き換えられない独特な意味がある以上、「〈根拠〉でいいのにわざわざ横文字で格好つけている」というしばしば聞く批判は当を得ていない。この手の誤解を避けるために、私は、エビデンスに代えて「介入効果の証拠」と呼んだ方がよいと考えている。
過度の期待
効果の証拠(エビデンス)は、流行語の宿命として過剰に期待されている面がある。たしかに医療をはじめとした意思決定に関わる諸分野で、効果の証拠(エビデンス)の考え方は目覚ましい成果をあげている。だから、「英語教育にもエビデンスを!」という声があがるのは理解できる。だが、導入にはかなりの痛みを覚悟しなくてはならないだろう。
効果の証拠(エビデンス)に基づくアプローチでは、実験デザイン・調査デザインを非常に重視する。しかし、既存の英語教育研究(日本だけでなく海外の応用言語学・SLAも)では、どのようなリサーチデザインが因果効果の推計に必要かという点の議論は弱い。いきおい、一般的な基準からするとかなり質の低い効果の証拠(エビデンス)しか蓄積されていないのが現状である。
たとえば小学校英語をめぐる効果の証拠(エビデンス)について考えてみよう。文科省や英語教育学者はこれまで、小学校英語の効果を示すために、多数の実証研究・調査を行ってきた。しかし、そのほぼすべてが適切なリサーチデザインに基づいておらず、効果の証拠(エビデンス)の質は残念ながらかなり低い。(参考:「英語教育学における科学的エビデンスとは?小学校英語教育政策を事例として」)
効果の証拠(エビデンス)への全面的依拠は既存の英語教育研究のかなりの部分(特に基礎科学的研究や実験室場面での研究)を否定することになりかねない。私が相当の痛みを伴うと述べた所以である。
過度の敵視
他方、誤解に基づく不当な敵視もよくある。たとえば、効果の証拠(エビデンス)という科学・学問の言葉で、現場の知が抑圧されるという批判である――曰く、「数字では心の成長は測れない」「学習者の本当の学びはわからない」等。
これはある面では正しく、ある面では正しくない。「心の成長」であれ「本当の学び」であれ、何らかの形で操作化すれば問題なく測定・検討可能である。逆に、これらを操作化することは不可能だという立場をとるならば、どんな手法を使っても(たとえ質的研究であっても)検討できない。
たしかに、操作化は、現実を固定的に見ることである。この見方に対し、現実はもっとダイナミックなものだと現場の視点から異議を申し立てることは非常に意義がある。だが、その場合、「本当の学び」のような別の固定的な見方を対置することはできない。
そもそも効果の証拠(エビデンス)の考え方が目指すのは、現場への科学の押し付けではなく、現場の意思決定をより公平・民主的なものにすることだ。現に、EBMの背景には、経験や勘、権威の個人的意見に基づいていた従来の医療行為を、客観的・民主的なものに変革しようという目的があった。
考えて見れば、教育現場も一枚岩ではない。自分の経験に絶対の自信を持つベテラン教員もいれば、多数の信奉者を抱えるカリスマ教員もいる。効果の証拠(エビデンス)の考え方は、権威・政治力を持った教員も持っていない教員も――そして研究者も――同一の基準に基づいて平等に意見を交わせる点に意義があるのである。










