法務局の遺言書保管制度で守らなければいけない遺言書のルールとは?
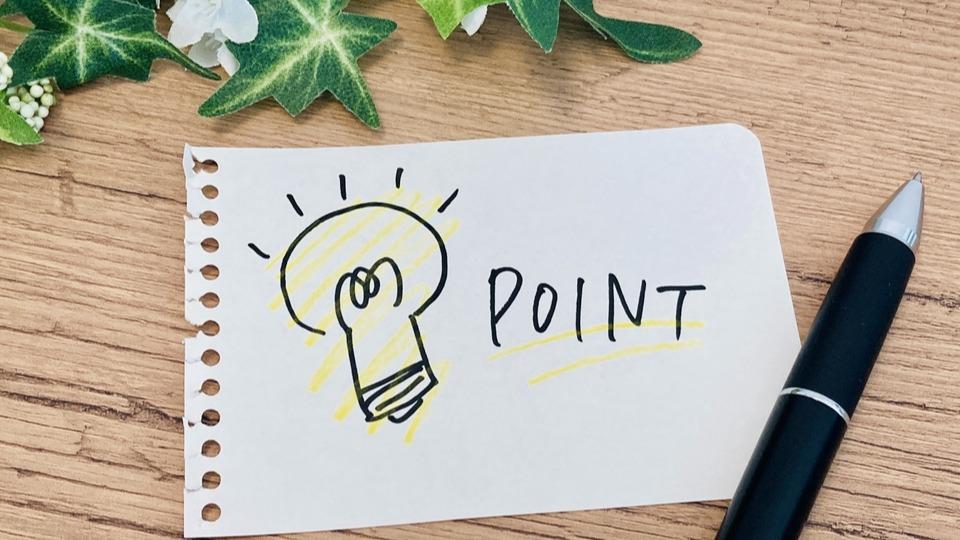
『遺言書って普通の便せんに書いてもいいの?』
『遺言書ってパソコンで書いてもいいの?』
いざ遺言書を書こうとすると、どう書いたら良いのか悩みますよね。法務局の遺言書保管制度を利用する場合、遺言書の書き方には法定の要件のほかに独自のルールがあります。
今回は、法務局の遺言書保管制度を利用したい方向けに、遺言書の書き方についてのルールをお伝えします。
そもそも法務局の遺言書保管制度とは

法務局の遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で預かり、遺言者が亡くなったときには、指定した相手に遺言書があることを通知してくれる便利なサービスです。
ただし、法務局の遺言書保管制度を利用して遺言書を預かってもらう場合、法定の要件を満たす必要があるのはもちろん、制度独自の様式を満たす必要があります。
スムーズに遺言書を預かってもらうために、どのような条件を満たせばよいのか見ていきましょう。
民法の要件に当てはまっていること

まず、遺言書は民法が定める形式的な要件を満たしている必要があります。
民法が定める自筆証書遺言の要件とは以下の3点です。
- 全文自筆で書く
- 日付、氏名を書く
- 押印をする
ちなみに、自筆証書遺言は、自筆で書くことが要件ですが、財産目録については、自筆でなくてもよいと認められています。
また、書き間違いがあった場合は、変更箇所がわかるように示した上で、訂正・追加した旨を記載して署名し、訂正・追加した箇所に押印すると定められています。
法務局で遺言書を預かる際、遺言書保管官が民法が定めている形式に合っているかの確認をします。
遺言書の体裁がルール通りに整っていること

次に、遺言書保管制度で決められている様式について見ていきましょう。
遺言書保管制度では、遺言書原本の保管とデータでの保管がしやすいよう、遺言書の様式が決められています。
- A4サイズの無色の用紙に書く
- 上部0.5cm、下部1cm、左2cm、右0.5cmの余白を確保する
- 用紙の片面のみに記載する
- 各ページにページ番号及び総ページ数を記載する
- ホチキスで綴じない
- 消えにくい筆記用具で書く
- 遺言者の氏名は本名を書く
財産目録として、不動産の登記事項証明書のコピーを添付するときは縮小コピーをして余白を広めにとると良いでしょう。
なお、不動産の登記事項証明書のコピーや通帳のコピーを財産目録とする場合には、そのすべてのページに署名、押印が必要です。押印は認印で大丈夫です。
ルールを無視すると最悪預かってもらえない可能性も

法務局の遺言書保管制度を利用するためには、遺言者が予め予約して法務局に行って手続きしなければいけません。
わざわざ時間をとって法務局に行ったのに、万が一遺言書を書き直す必要が生じてしまったらせっかくの頑張りが無駄になってしまいます。
法務局の遺言書保管制度を利用するときは事前に遺言書の書き方を確認して、スムーズに受け付けてもらえるようにしましょう。










