家庭菜園のクモは退治しないで!害虫対策になります【畑の益虫】
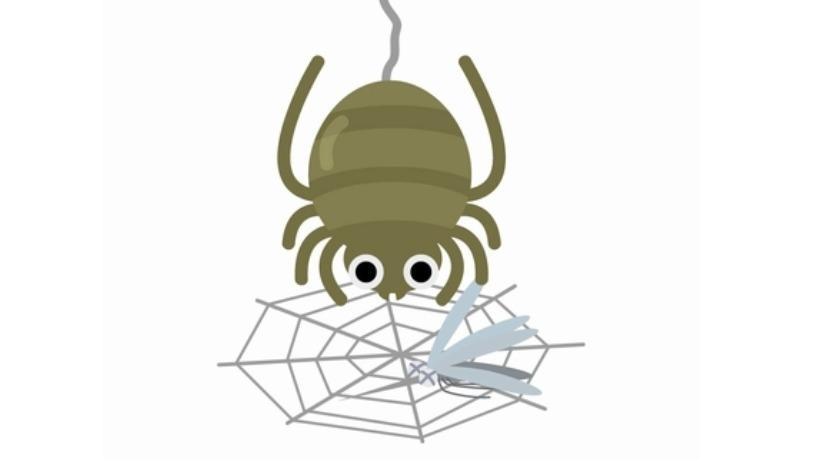
クモは畑の周囲では害虫を捕らえる益虫として活躍します。クモが苦手な人も多いですが、できるだけ退治せず畑で働いてもらいましょう。
網を張るタイプと、網を作らず歩き回るタイプのクモがいます。
この記事では、畑で見かける代表的なクモをご紹介します。
造網性のクモ・クモの巣は迷惑なときもあるけれど

クモと聞いて真っ先にイメージするのは網を張るクモ(造網性のクモ)ではないでしょうか。
造網性のクモは網にかかる様々な虫を食べます。コガネグモやジョロウグモといった大型のクモは、バッタやスズメバチなど大型の害虫にとっても天敵。時にはクモの巣にセミやトンボといった害虫ではない虫も捕らえられてしまうことがあるものの、全体的には害虫を増やさない働きをしています。
- コガネグモ:メスは最大3cmの大型のクモ(オスは1cm以下と小さい)。8本の足を2本ずつ揃えた体勢で網の中心に止まっているのが特徴。
- ジョロウグモ:非常に大きな黄色っぽい色の網を作る。メスは最大4cmにもなり、黄色と黒の模様がついているので威圧感がある(オスは半分程度のサイズ)。
- クサグモ:体長は1.5cm前後。植物の上に棚のような膜状の網を張る。その上に落ちてくる虫を捕食する。
家庭菜園でも通路など邪魔なところに作られたクモの巣は除去せざるを得ませんが、それ以外はできるだけそのままにしておきましょう。
徘徊性のクモは小さくてすばしこい

畑を歩き回るクモ(徘徊性のクモ)は巣を作らず、歩き回って餌を探しています。5mmから1cm以下と比較的小型で色合いも地味ですし、すぐに走り去るので、目にしてもあまり怖くは感じないかもしれません。
むしろ徘徊性のクモは目がとても良いので、大きな人間を見て怖がっているかも。姿を見かけてもそっとしておいてあげてください。
- ハエトリグモ:飛び跳ねるような動き。ハエやアリなどの昆虫を捕らえて食べる。
- ハナグモ:花の近くで待ち伏せし、花にやってくる虫を食べる。
- カニグモ:カニのような横歩きが特徴。
- ワカバグモ:黄緑色のきれいなクモ。葉の上で待ち伏せをする。
毒のあるクモはセアカゴケグモ
「クモは益虫だということがわかったけれど、毒のあるクモは危険じゃない?」と思いますよね。しかし日本に生息するほとんどのクモは人間に影響を与えるような毒を持っていません。

ただし、外来種の「セアカゴケグモ」は要注意です。体長1cmほどで丸い黒いおしりに赤い帯状の模様があるのが特徴。
畑のようなところより建造物の影や下を好むクモなので、家庭菜園ではほとんど見かけないかもしれませんが、覚えておきたいですね。
このクモはおとなしく攻撃性は弱いので、無理やり捕まえようとしない限り噛まれることはありません。しかし、もしセアカゴケグモに噛まれると赤く腫れ、重症化すると危険です。
参照:東京都環境局の「危険な外来生物」セアカゴケグモ のページ
まとめ
家庭菜園の周囲で見かけるクモは、畑の害虫を捕らえてくれる益虫です。できるだけ退治しないでそっと見守ってください。クモが多い畑は自然な環境が整った良い畑です。クモは迷惑な蚊や、カメムシ、スズメバチさえも捕らえてくれることがありますよ。
最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら著者のracssをフォローして他の記事もご覧ください。










