【光る君へ】藤原為時はどうやって自分を売り込んで、越前守になったのだろうか?
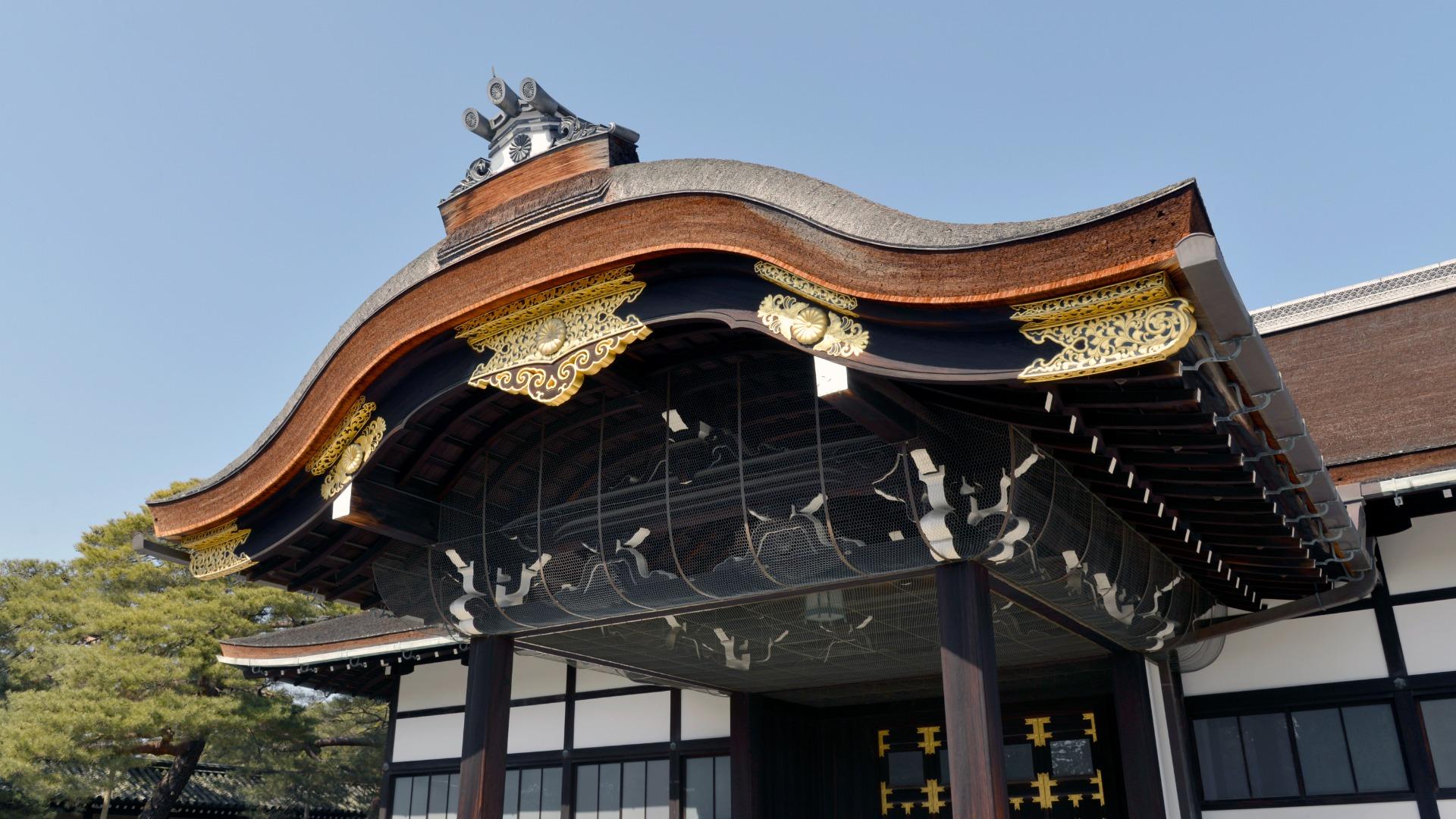
今回の大河ドラマ「光る君へ」では、藤原為時が10年にわたる就職活動を経て、ようやく越前守になった。まさしく「苦節10年」である。その間、為時は必死に就職活動をしていたのは当然のことだが、なぜうまくいったのだろうか。
当時、我が国の貴族はピンからキリまであった。御所の清涼殿南廂にある殿上間に昇殿することを許されたのは、基本的に五位以上の官人から選ばれた人たちで、彼らは殿上人と称された。一方で、昇殿を許されなかった人は、地下と呼ばれていた。為時は、長らく六位に留まっていたのである。
貴族は位階に対応して、職(中納言など)を与えられた。しかし、職には定員があるので、誰もが必ず任じられるわけではなかった。これを散位(位階があっても職がない状態)という。為時の場合は長らく職にありつけず、無職の時代が続いたのだ。
為時は学問に優れていたので、皇太子時代の花山天皇の御読書始で副侍読を担当した。それが機縁となり、花山天皇が即位すると、為時は式部丞、六位蔵人に任じられた。しかし、寛和2年(986)に花山天皇が退位すると、為時も同時に職を失ったのである。
そこで、為時は申文を作成し、自らを売り込んだのである。そもそも申文は、政策の提案や国司の報告を行うものだったが、やがて廃れていった。
その後、申文は官位の申請などが主たる目的となり、太政官や天皇に上申されたのである。貴族は申文に古典を引用しつつ、叙位任官に関わる先例などを列記し、自らを売り込んだ。ただし、文章が不得意な者は、代筆を依頼したという。
為時も必死の思いで、申文を作成して一条天皇の女官に託したという。そこには漢詩が書かれており、自身が苦学したにもかかわらず、職にありつけない嘆きを吐露する内容が書かれていた。その漢詩は、藤原道長の目に留まったというのである。その甲斐があって、為時は越前守になったのである。
当初、為時は淡路守に決まっていたが、宋からやって来た商人が北陸方面に滞在していたので、宋人と交渉できる者が国司になる必要が生じていた。そこで、道長は越前守に決まっていた源国盛に代えて、漢文に優れた為時を起用したといわれている。
為時にとってはすばらしい出来事だったが、事実上、更迭された国盛にとっては悲劇だった。あまりのことに、国盛は病気に罹ってしまい、その後しばらくして亡くなったという。










