インボイス制度がもたらした“実害” 蔓延する法違反の事例と当事者のリアルな声
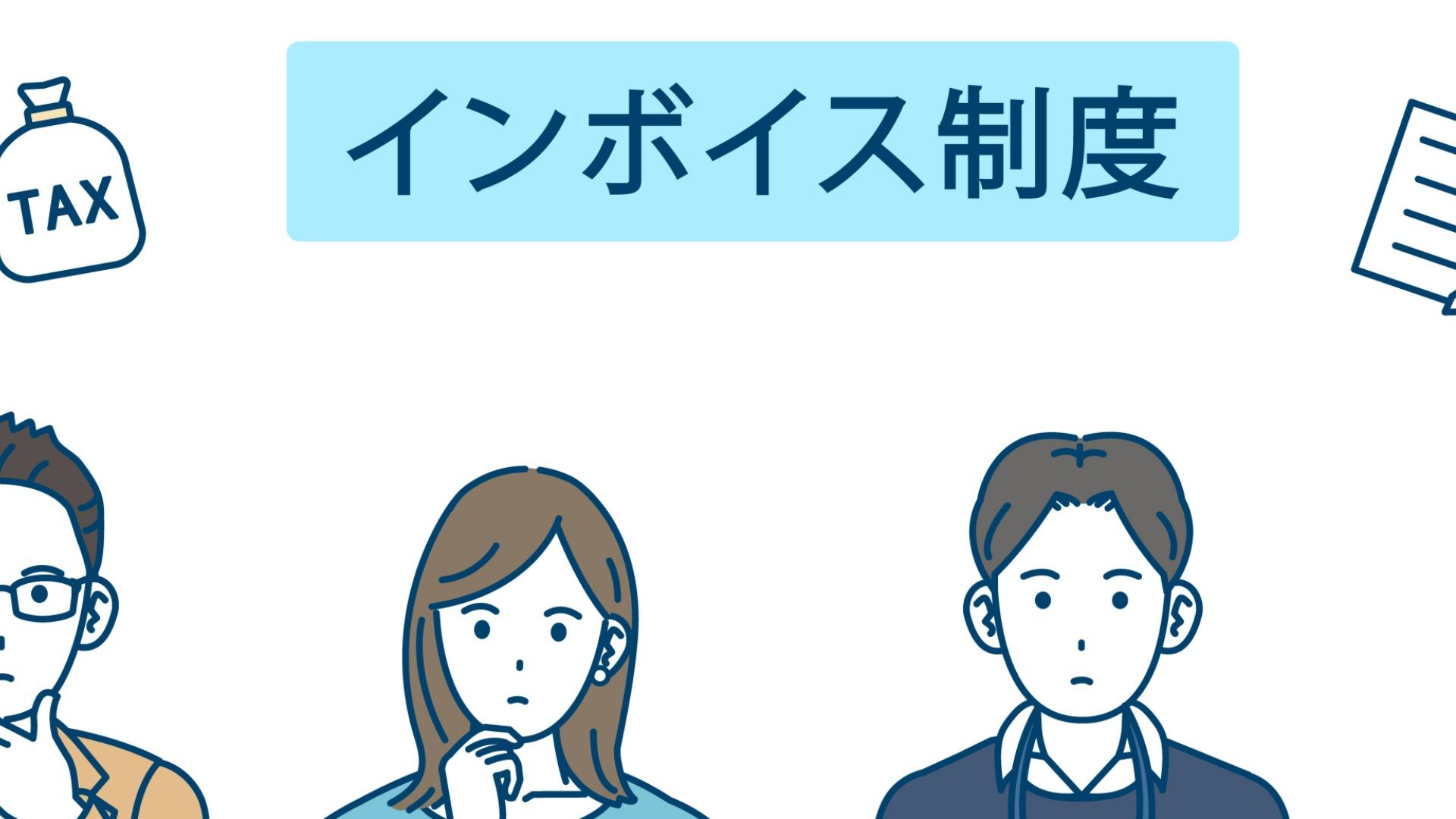
10月1日に消費税インボイス制度が開始されてから1か月が経ち、その実害が浮き彫りになってきている。
13日(月)、9月末に54万筆超のインボイス反対署名を岸田首相に届けた「インボイス制度を考えるフリーランスの会」(通称:「STOP!インボイス」)が、制度開始1か月を機に実施した緊急意識調査の結果を報告する記者会見を開催した。
緊急意識調査は、Webアンケートツールを用いたオンライン調査の方法で実施され、募集期間わずか11日の間に約3000件の回答が寄せられたという。回答の大部分がネガティブな回答であり、インボイス制度の不具合に対する早急な対応の必要性が浮き彫りになった。

※ なお、同調査は、フリーランスだけではなく、会社員、経営者なども含む「インボイス制度の影響を受ける方」を対象に実施されている。
免税事業者であったフリーランスへのインボイス制度の影響
まずは、インボイス制度が始まったことにより、フリーランスなどの小規模事業者にどのような影響が出ているのかについて、改めて確認しておこう。
以前から、年間の売上高が1,000万円以下の事業者の場合、消費税の納税が免除される制度の適用を受けることができた。売上高が1000万円であれば、事業者は100万円の消費税を納税する必要がある一方で、990万円であれば99万円の消費税を支払う必要はないということだ。このこと自体は、インボイス制度が始まってからも変わらない。免税事業者のままでいれば、消費税を納める必要はない。
しかし、インボイス制度が始まってからは、フリーランスが免税事業者のままでいると、フリーランスに仕事を発注している側(以下「発注者」という)に影響が出るようになる。

発注者は、自社が納める消費税を計算する際、売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を差し引いて、納税額を算出する。この消費税の原則を「仕入税額控除」という。
これまで、発注者は、免税事業者と取引をする場合であっても、仕入れの事実が記載された請求書と帳簿を保存すれば仕入税額控除の適用を受けることができ、納税額を抑えることができた。
ところが、インボイス制度が始まってからは、そうはいかなくなった。仕入税額控除を行うためには、適格証明書(インボイス)の保存が必要になったからだ。
インボイスを発行できるのは課税事業者だけなので、免税事業者のフリーランスと取引をした発注者は仕入税額控除をすることができない。このため、発注者の納める消費税の額はその分高くなってしまう。
こうして、発注者側としては、なんとか自身の税負担を抑えようと、免税事業者のフリーランスに対して課税事業者となることを要求してししまいがちになる。あるいは、実際に、免税事業者との取引を避ける発注者も現れる。
さらには、フリーランス側が免税事業者のままでいることを選択するのであれば、自社の消費税の負担が増える分、フリーランスに支払う報酬を引き下げようとする発注者も現れているのである。
苦しい二択を迫られるフリーランス
フリーランス側からすれば、免税事業者のままでいれば、インボイス制度が始まっても新たな税負担を負わなくて済むのであるが、免税事業者のままでいると取引先から敬遠されてしまうかもしれない。ましてや、長年世話になっている取引先からインボイスを発行してほしいと要請されてしまうと、断るのは容易ではない。
取引の機会を失うリスクを承知の上で免税事業者のままでいるか、課税事業者になって消費税を納付するか。どちらを選んでも損をする、苦しい二択を迫られているというわけだ。
緊急意識調査の結果によると、インボイス発行事業者として登録した(しようと考える)理由(複数回答)については、「強制があったわけではないが、登録しなければ仕事が継続できなさそうだと感じるから」が39.5%となった。
この設問の回答者にはもともと課税事業者であった人なども含まれているから(「すでに課税事業者だったので登録した」が45.2%)、免税事業者だけでアンケートを取れば、その割合はかなり高くなると思われる。

「インボイス制度を考えるフリーランスの会」には、次のような声も寄せられているという。
フリーランスのSEです。「登録は強制しないが、登録しないなら契約は継続しない」と元請けから言われ、事実上の強制だと困惑しました。年末までの契約なので年明けからはどうなるのか不安です。〔50代/東京都〕
企画・制作の仕事です。プライベートでも仲の良い社長から「未登録の相手とは今後、取引をしない」と言われた。免税事業者との取引は複雑すぎて経理が対応できないとのことで、交渉の余地はなかった。激変緩和措置がむしろ取引排除を促進していると感じた。〔40代/東京都〕
コロナ禍で受注が減り、やっとコロナ禍以前の売上の80%ほどに回復したが、まだ登録していないと説明したところ「未登録のままだと他の取引先に発注するようになる」と言われ、価格交渉にも応じて貰えない。〔40代/神奈川県〕
課税事業者にならなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法又は下請法に抵触する可能性が高い。上記の調査結果でも、「登録しなければ仕事をもらえないと取引先に言われたから」が14.1%となっており、法律違反に当たる行為が少なくないことが窺える。
一方的な取引価格の引き下げ
インボイス発行事業者として登録しないことを選択した場合に、一方的に取引価格を引き下げられるケースも見られる。
所属している芸能事務所に「インボイス登録をしてもらわないと仕入税額控除が受けられないから、出演料の手数料を1割多く徴収する」と一方的に書面通知され、「経過措置期間は80%の控除が受けられるため優越的地位の濫用による不当な値下げである」と指摘するも話し合いに応じて貰えていない。〔30代/東京都〕
インボイス制度が始まり、仕入税額控除ができなくなったことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、交渉を行った上で、双方が納得し、新たな取引価格を設定した場合には、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、法的な問題は生じない。
しかし、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げるなどと一方的に通告するような行為は、独占禁止法上又は下請法上、問題となり得る。
取引からの排除
免税事業者のままでいることを伝えたら、仕事をもらえなくなってしまったという声もある。
消費税分の報酬を下げられたり、免税事業者でいる意思を告げたら次の話が来なくなったりと、すでに不安。少しずつ仕事をつなげていった身としては、積み上げたものが崩されていくような気持ちになっています。〔30代/福岡県〕
インボイス未登録を理由に取引先から「人件費削減」の名目で業務量を半分以下にされてしまった。現在は子が小さいため、就職活動も十分に出来ない。保育園の入園も業務量が安定しない為に見通しが立たず、八方塞がりな状態にある。〔30代/新潟県〕
インボイス制度の開始を契機として一方的に取引を停止されてしまった場合でも、取引を停止した他の理由があるとでっち上げられてしまえば、法的に争うのは難しい。
緊急意識調査では、回答者の12.9%が「インボイス未登録を理由に、取引ができないと言われた/すでに取引排除にあっている」と回答している。

“実害”の実態を広く知らしめることが重要
実際に制度が始まり、かねてより懸念されていた事態が現実のものになっている。ここに紹介した事例は氷山の一角にすぎないであろう。
こうした“実害”の実態を広く知らしめ、窮地に立たされている人々の声を政治に反映させられるような社会的な動きを作っていくことが重要だ。
今回の記者会見では、財務省・国税庁・公正取引委員会・中小企業庁に要請書が手交され、改めて制度の中止、廃止の訴えがなされた。
「インボイス制度を考えるフリーランスの会」は、「STOP!インボイス陳情請願採択への道プロジェクト」を進めており、現時点では、全国の約370自治体においてインボイス反対の意見書が採択されているという。
また、現在56万筆超が集まっているインボイス反対署名を100万筆に上積みして、インボイス制度中止の意思を改めて政府に届けるプロジェクトも継続しているという。
この問題に継続的な関心が集まることを期待したい。
〔参考〕「インボイス制度を考えるフリーランスの会」(通称:「STOP!インボイス」)
無料労働相談窓口
(いわゆる「偽装フリーランス」の働き方をされている方からの相談も受け付けています。)
03-6699-9359(平日17時~21時 日祝13時~17時 水曜・土曜日定休)
メール:soudan@npoposse.jp
Instagram:@npo_posse
*筆者が代表を務めるNPO法人。労働問題を専門とする研究者、弁護士、行政関係者等が運営しています。訓練を受けたスタッフが労働法・労働契約法など各種の法律や、労働組合・行政等の専門機関の「使い方」をサポートします。
03-6804-7650
info@sougou-u.jp
*個別の労働事件に対応している労働組合です。誰でも一人から加入することができます。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。










