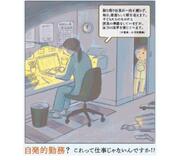「はて?」給特法廃止で予想される最悪の事態とは?
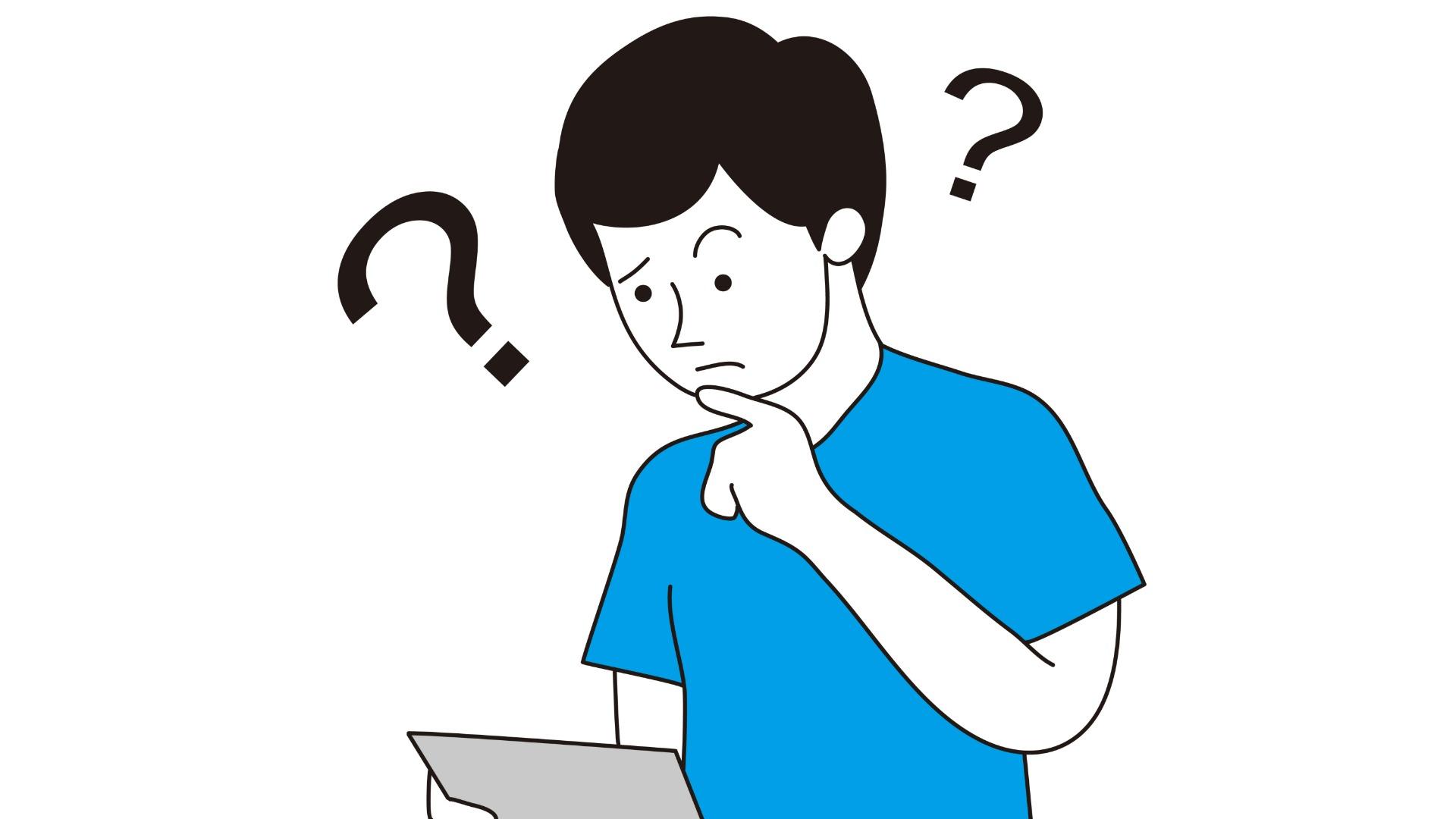
公立学校教員を「定額働かせ放題」にしている給特法の改正が議論される中、給特法を廃止したらかえって状況が悪化するのではないかと、最悪の事態を危惧するとのご意見を目にしました。
そのようなご意見を拝見した労働法実務に関わる弁護士(私)の感想は、「はて?」(NHK朝ドラ「虎に翼」の寅子風:朝も早い教員の皆さんも録画などでぜひ観てください)でありました。
このようなご意見は、給特法が廃止され労基法が適用されても、教員の長時間勤務が改善されず、労基法の労働時間規制の法の趣旨が一切実現しないことを前提にしているようなのです。
最悪の事態とは?
そのご意見とは、①教員の長時間勤務が改善されず、②教員給与が下がるか、③残業代が支払われない、という事態が起きるのではというものでした。
給特法を廃止したら長時間労働が放置され、給与が下がり、残業代も払われないというのですから、たしかに、それは最悪の事態です。
とはいえ、公務員法・労働法の仕組みから、法的にそのような事態が生じ得るのか、そのような事態が生じることを前提に法改正を議論すべきなのかは大いに疑問です。
「はて?」 労基法はそんなに役立たずの軽いもの?
「はて?」 違法状態の放置を前提に制度設計を論じて良いの?
(「はて?」のダブル)
というわけで、少しこのような言説について、法的・労働法的な解説をしたいと思います。
給特法の仕組み
給特法は、長時間労働が問題となる公立教員に対し、原則である労基法が定める残業代等(注1)の長時間労働抑制のための仕組みの多くを適用除外としています。
要するに、給特法は、公立教員から労基法という労働者が本来持っている長時間労働抑止の「武器」を奪っている例外的な法律というわけです。
ですから、給特法が廃止されても、法的空白は生まれません。私学・国立の教員、さらには他の一般職の公務員と同様に、原則通り労基法が適用されるだけです(公務員は労基法適用外というのは、よくある誤解)。
だから、給特法が廃止されても①教員の長時間勤務が改善されないというのは、労基法は長時間労働抑止の役に立たないという主張に他ならないわけですが、それはあまりにも乱暴でしょう。
日本は過労死(karōshi)という言葉を生んでしまった、世界的にみても労働時間が長い社会であり、現在も是正が必要な状況です。ですが、長時間労働の解消に向けて、労使はもちろん、行政(厚労省・総務省など)も一緒に、地道な努力と是正がなされてきました。近年の「働き方改革」の取り組みはその典型であり、そのような努力を法的にこれを支えている中核が労基法であって、しかも、長時間労働抑止に向けて改正され労基法の規制自体も強化されてもいるのです。
①教員の長時間労働は改善されない=労基法は役立たず?
しかも、法体系に即して考察すれば、労基法は単なる法令の一つではなく、憲法27条2項に由来する重要な法律です。憲法27条2項が「法律」で定めるとした「勤労条件に関する基準」を定めたのが労基法なのです。
日本国憲法第27条2項
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
だから、労基法は役立たずと主張することは、憲法に由来する法体系を役立たずであると否定する主張に等しいわけです。
労基法が適用されても長時間労働が解消されないという言説は、憲法改正をも視野に入れねば成り立たぬ、大胆かつ乱暴なご意見なのです。
以下述べますが、労基法は特効薬ではないかもしれませんが、決して役立たずではないのです。
労基法が定める長時間労働抑止の仕組み
給特法廃止が議論されるとき、(おそらく意図的に)労基法の定める残業抑制の仕組みがあたかも残業代だけであるかのように議論されます。(さらには、労基法の残業代制度の趣旨が残業抑制のためであることすら踏まえずに議論されます)。
ですが、労基法が定める本来の労働時間規制の仕組みは、下記図のように、ⅰ使用者による厳格な労働時間把握がなされることを前提に、ⅱ罰則付き上限規制(36協定)と、ⅲ残業代がその仕組みの中核となります。
そして、原則として労働者がもつ3つの武器を全て適用除外としているのが給特法で有り、憲法上の権利を制約する例外的な状況といえるのですが。

まず、ⅰ使用者による厳格な労働時間の把握がなされることが、全ての長時間労働抑制策の出発点です。そもそも、厳格な労働時間の把握がなければ、勤務の実情が把握できないので実効的な労働時間削減策も対策が立てようがなく(上限規制が導入できないのは必然)、労働時間把握を放棄してしまうのは労働法・労働安全衛生の観点からもあり得ないことです。
先ごろ中教審の特別部会が出した「審議のまとめ」では、公立学校教員は「一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務の特殊性は、現在においても変わるものではないため、勤務時間外についてのみ、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる」(49頁)とし、使用者による厳格な労働時間把握を放棄していますが、そこが何より問題なのです。なお、ここで厳格な労働時間の把握を否定する根拠として用いられる教師の「職務の特殊性」を定めるのが給特法(1条)です。
そして、「審議のまとめ」は、労働時間把握が「適当ではない」との前提にたつので、ⅱ36協定による罰則付きの残業上限規制が適用されない仕組み、ⅲ残業代支払による仕組みも維持するという結論になってしまいます。
実際には、教師に限らず多くの労働者は、程度の差こそあれ、自主的で自律的な判断に基づく業務を遂行しているし、指揮命令に基づく業務も行っています。
とりわけ、同じ教員なのに給特法適用外であって厳格な労働時間管理が求められる国立・私学の教員はもちろん、医師・公認会計士・大学教員など高度専門職とも法的差異をもうける理由とはなりません。
給特法を廃止してⅰ厳格な労働時間把握が実現すれば、現在適用されていないⅱ36協定による罰則付きの残業上限規制が適用されない仕組みが公立教員にも導入されることになりますが、これは長時間労働抑止に対して十分に効果を発揮し得る仕組みです。
ⅱ36協定とは
「定額働かせ放題」を生み出している給特法下の運用とは異なり、労基法の世界では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働者を働かせることはできないのが原則です。例外として残業をさせるには、労基法36条が定める36協定の締結が必要となります。
36協定とは、例外的に労働者を時間外労働や休日労働をさせる場合に、使用者が労働者側と結ぶ合意です。36協定の締結主体は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数の代表者であり、使用者は労働者側にこの36協定を結んでもらわないと一切の残業をさせてはならないのです。
なお、現在の公立学校教員は、「自主的活動」であるとして時間外労働が労働とみなされず、持ち帰り残業も在校等時間としても把握されていませんが、その法的根拠は給特法1条(職務の特殊性)にあるので、給特法が廃止されたら、このような運用も改定されることになります(実は、給特法の最大の問題はこの部分ですが、本稿の主題からずれるので割愛)。給特法が廃止されたら、持ち帰り残業でも残業=労働であるという、テレワークが普及した教員外の社会の常識を踏まえた法解釈がなされることになります。

控えめに言って、36協定のもつ本来の威力は絶大です。管理職が現場の教員集団の声を無視して残業を押しつけるような事態を防ぐため(例えば、押しつけが問題となる部活指導・縮小廃止が検討される学校行事の実施の有無)、学校単位で締結する36協定は強力な効果を発揮し得るものです(注2)。36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」も決める必要があるので、業務削減の内容も正面から学校単位で議論ができ、管理職の対応が納得できなければ労働者側が締結を拒否する権限もあります。
しかも、36協定があっても月45時間を超える時間外労働は原則として認められず、「臨時的な特別の事情」(部活指導や学校行事は「臨時的な特別の事情」ではありません)がなければ、これを超える時間外労働はできません。
さらに、「臨時的な特別の事情」があるとして36協定を締結しても、残業できる上限時間が法律で定まっており、罰則付で遵守が求められます(「働き方改革」が進む中、労基法の規制内容も大幅に強化)。

このように、公立学校教員も、給特法で奪われた36協定という「武器」を回復すれば、労働者側(管理職ではない現場の教職員側)が、集団として管理職に対峙し、学校の実状を踏まえた業務削減・効率化、人員確保を求めていけるのです。
納得できない管理職の方針に対しては、36協定を結ばねばよいのです。現在頻発する学校単位で管理職が現場の教員の声を無視して過大な業務を押しつける(人員確保はしないのに)という事態に対して、36協定は大きな効果を発揮し得るのは明白です。
他方で、このようにみていくと、実は36協定が、文科省・教育委員会・学校管理職による教育現場に対する上からの指導を強化したい方々、教員の主体性が奪われた今の学校の労務管理を維持したい方々からは、労働者側(教員側)の力を強めてしまう絶対に認めたくない代物であるとも言えるでしょう。
ⅲ残業代支払による仕組み
労基法が定める残業代の制度(労基法37条)の趣旨は、残業時間の抑制にあります。残業代制度は、使用者に割増賃金を支払わせることで、使用者に対してコスト意識を与え、時短に取り組ませる仕組みであって、お金の問題ではなく労働時間の問題なのです。
残業代の仕組みは、日本独自のものではなく、世界的にみても標準的な長時間労働抑止の制度です。日本でも、残業代支払いによるコスト削減の意識は、多くの職場で長時間労働抑止に役立っています。これを役立たずというのは、あまりに乱暴な議論ですし、③残業代が支払われない事態を前提に議論するのは、憲法に由来し罰則付きの労基法のシステムを馬鹿にした立論です。
命と健康の問題であることの認識の甘さ
給特法維持論の最大の問題は、給特法廃止=労基法適用の問題が、残業代という金ではなく、命と健康の問題であることの認識の甘さでしょう。
2022年度の精神疾患による病気休職者数は過去最多だった前年度より642人増の6539人(2022年度・公立学校教職員の人事行政状況調査)と、教員の働き方改革が提唱される中、事態は悪化しています。
精神疾患による病気休職者の全てが長時間労働の問題を抱えているとは思いませんが、その多くは長時間労働が要因であろうと推測されます。
1年度中に6539名もの精神疾患による病気休職者をだし、それでもなお抜本的な改革(しかも、本来適用されるべき原則=労基法を適用するだけ)すら拒否するなど、労働者(教員)の命と健康の問題を余りに軽く考えすぎています。大切な教員の命と健康をないがしろにされているのです(ここは、「はて?」ではなく「ブチギレ」でお願いします!)
給特法の問題を、財源問題に矮小化し給特法擁護論を展開する意見は、労働者の命と健康を害し続けてなお、労働時間を削減するつもりがないのでしょう。どんなに尊い仕事でも、労働者の命と健康の方が大切だからこそ、憲法に由来する労基法が存在するのに、基本が理解されていないのは、法律家としてはとても残念です。
②教員給与を下げることはできるのか?
給特法廃止によって、2兆円とも指摘される残業代の支出を強いられることを前提に、教員の給与引き下げが起きるという指摘がなされており、これが最悪の事態だと危惧されているようです。
まず、上記の通り労基法が機能すれば、現在の長時間労働が放置(=労基法が役立たず)されて、何ら残業が減らない前提での多額の予算措置が必要という見解は、その議論の前提自体が誤っています。労基法舐めすぎです。
そのうえで、地方公務員の給与は簡単に下げられません。
公立学校教員の給与など勤務条件は、条例主義(地方公務員法24条5項、地方自治法204条3項)の原則により、条例で定まります。要するに、最終的には地域住民の意思で決定されるのです。各自治体において、「残業時間を減らせない(=行政のおサボり)&残業代払えないから、給与を減額します」など馬鹿げた理由に地域住民が賛同し、条例改正が実現されてしまわない限り、教員の給与引き下げは不可能です。自治体の首長やら教育委員会やらが、思いつきで簡単に給与引き下げなどできないのです。
しかも、条例で引き下げるとしても、条例が制定できるのは「法律の範囲内」(憲法94条)であり、法律(条例より上位の法規範)によって条例制定権には限界があって、上記のような狙いでの給与引き下げは不可能です。
地方公務員法24条4項により、地方公務員である教員の給与についても、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとし(均衡の原則)、教育公務員特例法13条1項は、教員の給与はこれらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるとしています。
しかも、公立学校教員の給与に関連して、人材確保法という法律があります。この法律は、教員の給与を一般の公務員より優遇することにより、教員に優れた人材を確保し、もって義務教育水準の維持向上を図ることを目的とするものです。
ですから、一般の地方公務員(=残業代支払い義務あり)より劣位に扱い、教員は残業代払えないから条例で給与引き下げます等という安易な条例改正は、地方公務員法の均衡の原則・人材確保法の趣旨に反し「法律の範囲」外であって、そのような条例制定はできません。
なお、人事委員会は、地方公共団体の議会及び長に対して、教員の給与が社会一般の情勢に適応するように勧告する権限が付与されているので(地公法14条2項)、残業代が払えないから給与を減額する等という条例が制定されてしまったとしても、人事委員会の勧告による是正の機会もあります。
給特法廃止でも、給与はむしろ上げる(回復する)べき!!
給特法廃止で残業代が支払われるのであれば、給特法による教職調整額が廃止される可能性はあるでしょう。ですが、その場合でも給与引き下げとなり教員の魅力を失わせぬように給与を引き下げぬ対処が必要だし、法令上もそれが求められています。
人材確保法は、教員の給与を一般の公務員より優遇することにより、教員に優れた人材を確保し義務教育水準の維持向上を図ることを目的とする法律であり、「今後とも必要な法律であると考えられる」(文科省ホームページ)とされています。
この人材確保法の趣旨を実現するためには、給与月額の引き上げや、人事院による第2次改善勧告により創設された義務教育等教員特別手当の引き上げなどによって、給与減額が生じないような対応が同時になされるべきでしょう。教育が大事だと思うなら、教職の魅力向上が必要だと思うなら、むしろ教員の給与は引き上げねばなりません。
そもそも、歴史的経緯をみれば、公立学校教員の給与は、人材確保法による三次にわたる計画的改善により昭和48年度から53年度までに合計25%引き上げの予算措置がとられてきました。しかし、その後、平成18年6月2日施行の行革推進法等によって、教育職員の人材確保に関する特別措置法の廃止を含めた見直しその他、公立学校の教職員の給与の在り方に関する検討を行い、既に引き下げがなされてきたのです。
これにより、教職の魅力向上のため定められた人材確保法の趣旨が骨抜きにされてしまい(注3) 、教員の待遇面での優遇措置が削減されてしまっているのが実状です。
ですから、このような優遇措置削減による待遇切り下げの政策が誤っていたのであって、教員の給与を上げるのは何も特別待遇ではなく、むしろ、不合理に切り下げられた分、元通りの状態に回復させるのだという指摘が正確でしょう 。
③給特法廃止でも残業代が支払われない事態が放置されること
給特法が廃止され(労基法が適用されても)、残業代が支払われない事態が放置されることを前提に、給特法廃止で事態が悪化するという意見があります。
しかし、このような前提を踏まえた議論は、例えるならば、「窃盗罪があっても、万引きはなくならないから、窃盗罪は意味が無い」というのと同レベルの、低次元かつ野蛮な意見です。
文科省・地方自治体・教育委員会・学校は、いずれも行政機関です。行政活動は、行政機関独自の判断で行われてはならず、国民の代表者で構成された立法府の制定する法律に従って行わなければならないという大原則(法律による行政)があります(憲法第66条3項、第73条1号、第74条)。
憲法27条2項に由来し、命と健康の問題に関わる長時間労働抑止を趣旨とする労基法37条が遵守されずに行政運営が放置されるであろうことを前提に、行政機関やそれに関わる専門職により誤った法的見解が流布されるなど、あってはならない野蛮な事態です。
行政機関や行政官は、よってたつべき法律を守らないことを前提にした心配をする暇があったら、どうやったら法令を遵守させられるのか真摯に検討すべきです。
万が一でも行政官が本当にこのような意見に賛同しているのであれば、控えめにいって行政官失格です。ぜひ、このような事態が生じることを文科省が正面から容認できるはずがありませんので(法令違反を放置する前提で政策立案をするなど論外)、心ある国会議員の皆さんには、ぜひ国会審議で文科大臣や文科省の幹部からこのような言説を正面から否定する国会答弁をとっていただきたいと思います。
さいごに
もちろん、給特法が廃止されて労基法が適用されても、教員の長時間労働が直ちに改善されることはなかろうと思います(特効薬ではない)。
事実、私学教員や国立大学の附属であれ、民間企業であれ、公務員の一般職であれ、労基法が適用される職場でも長時間労働が完全に解消した訳ではありません。今でも、法規制の網をくぐり抜ける=違法行為を試みる使用者は後を絶ちません。
だからといって、労基法を適用しても意味がない、役立たずだという発想は論理が飛躍し過ぎです。労基法が適用されても直ちに長時間労働が解消しないからといって、労基法が長時間労働是正の役に立たない訳ではなく、労基法という「武器」を活用し、長時間労働是正に向けた取り組みがなされ得る状態になっているのです。
ですから、公立学校教員についても、むしろどうやってその労基法という「武器」を、長時間労働で疲弊しきった教員職場で活かせるのか知恵を絞るのが、労使の現場に関わる当事者、学識者、行政運営に関わる人間の使命ではないでしょうか。
労基法1条2項は、こんな大切なことを規定しています。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
とはいえ、それでもなお、そんな綺麗事を並べ立てても理想論じゃ社会は動かないんだ、財務省を動かせるはずがないだろ!とお怒りの方もいらっしゃるでしょう。
そんなあなたには、虎と翼でも寅子(主人公)が読み上げた、この素晴らしい憲法の条文を贈り、本稿を終えます。
諦めず頑張りましょう。
日本国憲法 第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
(注1) 給特法維持論者は、給特法を残業代の問題であると限定して論じがちですが、これは問題の本質を見誤ります。残業代は、給特法により適用が排除されている労基法の残業抑制の仕組みの一つに過ぎず、もう一つの中核は36協定の労使自治による事業場単位での時間外労働抑制の仕組みです(労基法36条)。
たとえば、自動車運送事業(特に、物流関係)や医療界で大問題となっている「2024年問題」は、こちらの36協定による厳格な残業抑制が遅ればせながら(しかも他の業界よりも緩やかに)導入されたことについて、物流や医療関係がたち行かなくなるのではとの危惧から指摘されて起きている問題です。
公立学校教員は、給特法により自動車運送事業や医療界よりもさらに遅れ、未だに36協定の適用が排除され蚊帳の外に置かれているのです。
(注2) 学校で働く職員でも、事務職員・学校栄養職員・現業職員等は給特法が適用されないため、残業には、原則通り労基法が定める36協定が必要となります。日教組が実施した「2022年 学校現場の働き方改革に関する意識調査」によれば、88.1%の学校で36協定が締結されており、学校職場に36協定が馴染まないというのは、実態を踏まえぬ空論といえます。
(注3) 2005年に平均で1万4686円支給されていた義務教育等教員特別手当が2010年には8522円となり、2015年には5619円へと3分の1まで縮小しているとの分析もあります(上林陽治「教員給与は適正に優遇されているのか~教員の働き方改革の論じ方~」自治総研497号111頁(2020年)123頁)
(注4)給特法全般の問題などは、以下の過去のYahoo!の過去記事などをご参照ください。
「公立教員から労基法を奪う給特法の廃止を!」(2024年4月21日)
教員「定額働かせ放題」をうむ給特法・「よくある誤解」をQ&Aで解説(2024年5月12日)
給特法は「高プロ」よりヤバい「定額働かせ放題」です!(2024年5月26日)