それって共感ではなく暗示ですよ! 多様性の時代に絶対にやってはいけない「暗示質問」
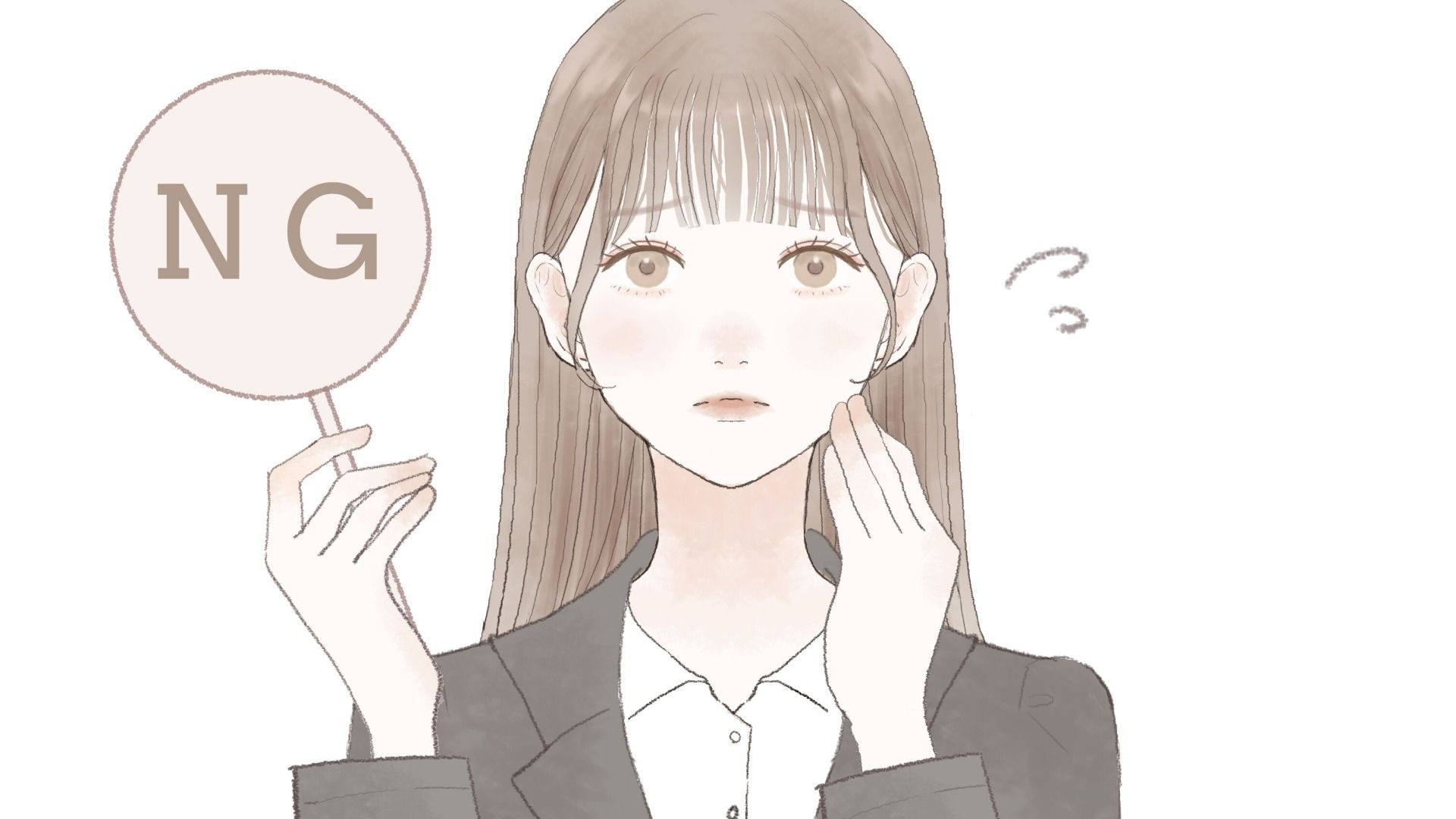
■それって共感ではなく暗示ですよ!
残業している3人の部下たちに近寄り、上司が差し入れのドーナッツを差し出した。
「残業、大変か?」
そう声をかけると、3人とも深く頭を下げ、お礼を言った。
「疲れたら、甘いものが欲しくなるだろ?」
上司は優しく微笑みかけ、さらにこう問いかけた。
「入社してまだ3か月の君たちにとって、遅くまで仕事をするのはキツいだろう。残業を楽しくやるコツを教えてやろうか?」
それを聞いた部下Aさんは「ぜひ!」と答え、Bさんは「ありがとうございます」と無表情で言い、Cさんは「はあ」とイラついた返事をした。
さて、この上司の問いかけに対し、三者三様の反応を見せたのはなぜか?
理由は、この上司に「大人の共感力」がないからだ。
大人の共感力とは、自分の感情をわきに置いた共感だ。
大人と子どもの違いは、自分の感情を優先させるかどうかでわかる。お腹が空いてもお昼休みまではランチを我慢するし、苦手な人を前にしても笑顔を作る。それが大人だ。
だから共感するときも、まずは自分の感情をいったん別のところに置いておくことが大事だ。
冒頭の新人3人が残業をしている間、それぞれどんな感情を持っていたか。
「ぜひ!」と答えたAさんは、もともと残業が大変だと思っていた。「はあ」と答えたCさんは、反対に残業することが嬉しかった。
だから上司から「残業は、大変か?」と声をかけられると、Aさんは「声をかけてくれて嬉しい。この人はわかってくれている」と思う。
しかしCさんは反対だ。「ようやく仕事を任されたんだから嬉しくてしょうがないのに、この上司はわかってないな」と思う。
問題はBさんだ。「ありがとうございます」とだけ言ったBさんは、残業に関して何とも思っていない。だから、
「残業は、大変か?」
と尋ねられると、
「残業って、大変なんだ」
という「残業=大変」という公式が頭に刷り込まれていく。したがって、この上司の働きかけは「共感」ではなく「暗示」になっているのである。
■「暗示質問」の正体
自分のことを「共感力がある」と思い込んでいる人は、やたらと感情を押し付けようとする。
「営業の仕事はキツいか?」
「社長と話すときは緊張するだろ?」
「残業は大変か?」
「はじめての出張だけど大丈夫?」
これらはすべて「暗示質問」だ。決して共感ではない。
「営業=キツい」
「社長との会話=緊張する」
「残業=大変」
「はじめての出張=大丈夫じゃない」
という先入観があるから、このような質問をするのだ。
多くの人はだいたいこう考える。
だから君もそう思ってるだろ?
わかるわかる。
私は君の気持がよくわかっている。
――と決めつけて質問しているのだ。
相手がたまたま同じ感情を持っていたら、「わかってくれている」と思われるだろうが、そうでなかったら「わかってない」と反感を買うか、暗示をかけることになる。
■そもそも「共感」とは何か?
共感とは「感情を共にする」ことだ。相手の感情を確認する前から決めつけてはならない。
30年近く前、私が勤めていた会社に「残業=大変」などという先入観を持つ人は少なかったと思う。それどころか、夜10時近くまでオフィスに残っていると、
「お! こんな時間まで残業なんて、ようやく一人前になったな!」
と上司から言われた。同じように思っていた同期が多く、
「はい! ようやく仕事を任せてもらえるようになりました」
「残業いっぱいやって、お金を稼ぎます!」
と返事をしていた。私は変わり者だったので、こういう上司には返事もしなかった。
「夜遅くまで残業しないと一人前に見られないなんて、何かがおかしい」
と思っていたからだ。
大人の共感力とは、自分の感情はわきに置いて、相手の感情を正しく受け止めることだ。とくに組織で働く人は気を付けたい。なぜなら感情は個人のものだからだ。現在は多様性の時代であり、よけいに決めつけた物言いはよくないだろう。
「残業は、大変か?」
のように、質問の中に自分の「感情」や「価値観」を入れてクローズドクエスチョンするのはやめよう。
「残業は、どう?」
とシンプルに、オープンクエスチョンすればいいのだ。
私は32年以上前から、知的障がい者のボランティア活動をしている。この32年間で、数えきれないほど言われてきたのが、この質問だ。
「日ごろから忙しいのに週末にボランティアだなんて、本当にスゴイね。何があなたをそこまで突き動かすの?」
雑誌や新聞社の記者にも、このようにインタビューされることがある。そして、この質問をされるたびに私は「わかってないな」と思う。
なぜなら、私自身は「スゴイ」とも思わないし、何か崇高な信念があり、その信念に突き動かされてボランティアをしているわけでもないからだ。
これまでに1000人以上のボランティアと知り合ってきたが、ボランティアをする理由は、人それぞれ違う。
強い使命感をもってボランティア活動をしている人もいれば、楽しいからやっている人もいる。
だから、こういう質問をされ続けると、
「ボランティアをやっている=スゴイ」
「ボランティアをやっている人=強い信念がある人」
という先入観ができあがっていく。まさに暗示なのだ。
こういう暗示が世間一般でされているから、私たちが「一緒にボランティアやりませんか?」と誰かを誘っても、
「私にはそんなスゴイことはできない」
「そこまでの使命感はないので」
と断られてしまう。このような固定観念は、いまだに多くの人が持っていて、30年以上ボランティアをやってきて残念に思うことの一つだ。
■「感情の代理人」とは?
勝手にできあがった先入観で、相手の感情を決めつけるどころか、その場にいない人の感情を身勝手に代弁する人も多い。
「あの人のことは私がよくわかってる。こうしたら絶対に喜ぶ」
「彼女はそんなことでは喜ばない。こうしたほうがいいんだ」
私はこういう人を「感情の代理人」と呼んでいる。
有名な調査結果をご存じだろうか。
結婚祝いのプレゼントを、友人たちで相談して決めてプレゼントするのと、本人に「どんなプレゼントがいい?」と質問して決めるのとでは、どちらのほうが満足度が高くなるのか。
答えは後者だ。本人の望むものをプレゼントするほうが満足されるのである。
あたりまえと言えばあたりまえの話だ。しかし実際は「本人に聞いたらむしろ失礼じゃないか」「きっと忙しいし、こっちで決めたほうがいいよ」と決めつける人も多い。
■厄介な組織の中の「感情の代理人」
私どもコンサルタントは、ほぼ毎日のようにこの「感情の代理人」たちと直面している。おそらく15年以上「絶対達成」をテーマにコンサルティングをしてきたからだろう。
この「絶対達成」という表現はパワーワードだ。この名称を使いはじめてから、セミナーや講演依頼が大きく増え、事業そのものも順調に成長している。
しかしパワーワードだからこそ悩みも尽きない。「絶対達成」という言葉に惹かれる人もいるし、反対に忌み嫌う人もいる。
「絶対達成」に共感してくれる人の代表格は、経営者だ。
「やっぱり目標を立てた以上、絶対達成してもらわないといけない。達成するかどうかは別にして、それぐらいのマインドでやらないとダメだ」
と言ってくれる社長は多い。いっぽう、強く反感を持つ人の代表格はミドルマネジャーだ(現場の当事者ではない!)。
「今の時代、絶対達成なんて社長が言いだしたら、若い子は逃げ出しちゃいますよ」
「そうです。最近の若い人はこらえ性がないんですから」
と、部長、課長たちが反発するのだ。興味深いのは、自分たちは共感すると主張することだ。
・私たちは絶対達成に共感する
・若い子たちは絶対達成に共感しない
と言い張る。まさに「感情の代理人」を演じているのである。
■当事者に対する質問の仕方
当然、私たちコンサルタントは冷静に受け止める。なぜなら「事実」ではないからだ。
「とりあえず、営業の方々とコミュニケーションをとってみますね」
と腰を上げる。
「本人たちに聞かなくてもわかりますよ」
「そうです。外部のコンサルタントに何がわかるんですか。私たちのことは、私たちがいちばんわかってるんです」
このように反発されても気にしない。結婚祝いのプレゼントを選んでいるわけではない。経営の方向性を決める重大な決断がかかっているのだから、当事者抜きで意思決定はできない。
感情は個人のものだ。個人と向き合い、その人の心の動きを察知しないと、
「今の若い子に絶対達成なんて言ったら、ビックリしますよ」
という表現をまともに受け取ることなんてできない。
それでは、現場の営業の方々と接するとき、私たちはどんな問いかけをするか。それを紹介しよう。
「今後の経営方針として、営業目標の絶対達成を掲げたら協力していただけますか?」
こういった質問をする。もちろん、これも暗示質問のように思えるかもしれない。だが「経営方針が掲げられたら従業員は協力するもの」という会社組織の原理原則が前提になっている。だから問題はない。
■知っておきたい!3通りの反応
すると、だいたい3通りの反応を受け取るものだ。
①「絶対達成と言われるとプレッシャーがかかります」
②「あ、そうなんですね。わかりました」
③「ようやくそうしてくれるんですか。目標があったら達成するのは当たり前なので嬉しいです。達成できなければそれでもいい、というこれまでの経営姿勢はおかしいと思ってました」
当然、結婚祝いのプレゼントについて尋ねているわけではない。目的は共感ではなく、経営方針に対して協力してくれることだ。ここでは終わらない。
②と③の人は問題ないだろう。しかし①の人に、
「そうは言っても経営方針なんだから、多少のプレッシャーはガマンしてもらえませんか?」
と誘導すべきではない。質問しながら相手の表情や声のトーンを洞察し、相手の感情を読み取っていく。
「絶対達成なんて社長に言われると、プレッシャーを感じるんですか?」
「そりゃあ、感じますね。どうして突然、そんなこと言い始めたのかわかりません」
「これまでは、目標を達成しなくてもいいと言われてたんですか?」
「いや、そんなことは言いませんよ」
質問を繰り返しながら、相手の表情や仕草を観察する。そして、
(本当にストレスを感じていそうだな)
と思えば、
「わかりました」
と言って、いったん引き下がり、関係者と対策を練る。しかし、
(プレッシャーがかかると言いながらも、それほど強くはなさそうだな)
と受け止めたら、具体的な施策について感想を聞く。
「私たちの仮説では、アプローチするお客様の量を20パーセント増やし、半年ぐらいかけて提案のフォーマットを修正し続ければ、達成は見えてくると思っています。いかがでしょうか?」
使うのはオープンクエスチョンだ。
「~それでもプレッシャーを感じますか?」
とクローズドクエスチョンで問いかけたら暗示質問になってしまう。というか、あからさまな誘導だろう。
もし相手が「はい」と答えたとしても、「言わされた」という気持ちがこびりついてしまう。だからオープンクエスチョンで、相手の意向を尋ねる。
「それだけなんですか?」
「提案ポテンシャルのあるお客様に、丁寧に提案していくことが重要ですが、それほど大変だとは思わないんですか?」
「これまで、どのように目標達成していったらいいのか、わからなかったので」
「どのように目標を達成したらいいかわからないことが、プレッシャーを感じる要因を作っていたということですか?」
「そうです」
相手の顔がスッキリしていれば、その感情を受け止めたらいい。
10人の営業のうち、1人がかなりのプレッシャーを感じているのなら、その方のケアが必要だと社長に報告する。
そのうえで今後の方向性を決めるのだ。少なからず「感情の代理人」のようになっている部長、課長の
「絶対達成なんて言ったら、若い子は全員、ものすごいプレッシャーを感じてしまう。わが社から若い子が一人もいなくなってしまう」
といった極端な意見に向き合う必要はなくなる。
大事なことは、本人の感情だ。自分の感情はわきに置いて、相手の感情をともにしないと、だいたいが「暗示」になる。
共感とは、感情を共にすることだ。こちらの感情を刷り込むことではない。多様性の時代だからこそ、「感情の代理人」になりたがる人は気を付けたい。










